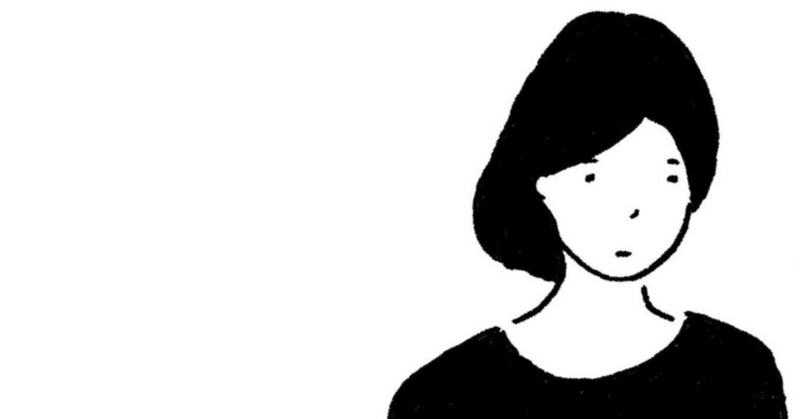
蘇州に住むあの子。
蘇州に住むあの子が日本に帰ってきた。
いつもの髪型に、飾らない姿、シンプルな服。重そうなリュックとバッグを持っていた。
「全然重くないねん」と言っていたけど、持ってみると重かった。いつもそうやってなんでも平気な彼女。
「ひさしぶり!◯◯くんは(私の子どもの名前)大きくなった?」と変わらない明るさ、そして子どもの名前も覚えてくれている。そして何故か「なんか背高くなった?」と言ってくれた。(もちろん背は伸びていないのだけれど。)
「美味しいパンか和食かカフェ」と事前にリクエストがあったので、京都の町屋をリノベーションした美味しいパン屋さんのカフェを予約していた。メニューはいくつもあったのに、2人ともサーモンときのこのホットサンドを頼んだ。
チーズがのびて、バターの味が染み込んでいて、美味しかった。

お互いの近況を報告して、中国の話を聞いた。彼女は中国で毎日頑張っているけれど、日本語が恋しいらしい。カタコトの日本語にも辟易しているんだとか。
日常に溢れる言語は、無意識的に認識されることはなく、常に読解しなければいけないというストレスがあるらしい。それでも頑張る彼女は強い。
「もう今の働き方を知ってしまったから、前の会社には戻れないわ」と言った。
彼女とは5年ほど前に出会った。私が働いていた部署に転勤してきた同期だった。一緒に働く同期だから、彼女が来る日まで緊張していたけれど、そんな緊張は不要だったと出会った瞬間に分かった。
力を抜いていて、ブレない彼女だった。だから誰のこともジャッジしない強さを持っていた。人に興味もなく、だれのことも悪く言わなかった。
媚びを売ることなく、もくもくと仕事をしていた。なのにゴルフが上手いので、知らぬ間にお偉い人たちとも仲良くしていた。その器用さが羨ましかった。
彼女は中国語や中国が好きなようで(アメリカドラマをきっかけに、アメリカの文化に染まってきた私からすると驚きだった。)会社の制度を通して中国で働きたいと、ずっと言っていた。
しばらくして会社から返ってきた返答は「女の子だから叶えてあげられない」だった。
私は許せなかった。でも化石のように固まってしまった組織、私たちができることは諦めることだった。
そんなこともあったから、この会社のおかしいところについて話し合い、共感し合った。こんなこと考えてたんや!1人じゃなかった!と私は純粋に嬉しかった。そして彼女の夢が会社のせいで中断させられているなんて、馬鹿馬鹿しいと苛立った。
そしたら次の日彼女に「ちょっとこっち来てくれへん」と呼ばれた。なにかと思ってついていくと1枚の切り取ったノートを見せられた。
「昨日話した内容をもう一度家に帰って考えてん。やっぱりおかしいと思う」と言いながら、見せてくれた。なんでこの会社がおかしいのか、を分解して考えた内容がびっしりと書き込まれていて、彼女の表情は至極真面目だった。
私も転職を考えていたあとだったので互いに「転職をするか」という結論に至った私たち。
彼女は数日後、本当に上司に辞めることを伝え、半年後には本当に辞めていった。
1年後に会ったとき、彼女は中国行きの切符を手にしていた。「中国で働くことになった」とケロっと言った。
そんな彼女は今日もケロっとしていた。いつも「何もすごくないよ」と言う。私から見ると、人生ずっとブレていなくて、誰かに消費されることなく生きていて、めちゃくちゃかっこいい。それを彼女は「自分のことばかり考えて、自分勝手すぎて自分が心配になる」と言っていた。心配はしなくていいよ。
そして一緒に本屋さんに行って、互いに好きな本を買った。
私はずっと買おうと思っていた本を買った。実はこの本は記念になる日に買おうと数年前から決めていて、ネットでは買っていなかった。
全く計画していなかったのに、彼女といっしょに本屋さんに来たという特別な日に買えるんだと、急に降ってきた特別な日。嬉しかった。

それを正直に伝えると「ありがとう」と言ってくれた。私のほうが「ありがとう」
そして少し歩いて、さよならした。久しぶりに会ったのに、週末よく会う地元の友だちみたいだ。
「頑張ろうね」と言い合って、彼女は京都駅に向かった。進みはじめた電車の中から彼女が一瞬見えた。なんだか少し切なくなった。
私も頑張らなければいけないなあ、と。でも頑張らなくても、力を抜いて毎日を過ごせばいいと、彼女の姿が言ってくれた気がした。
そんな、蘇州に住むあの子。ラブレターのようになったけれど、また会おうね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
