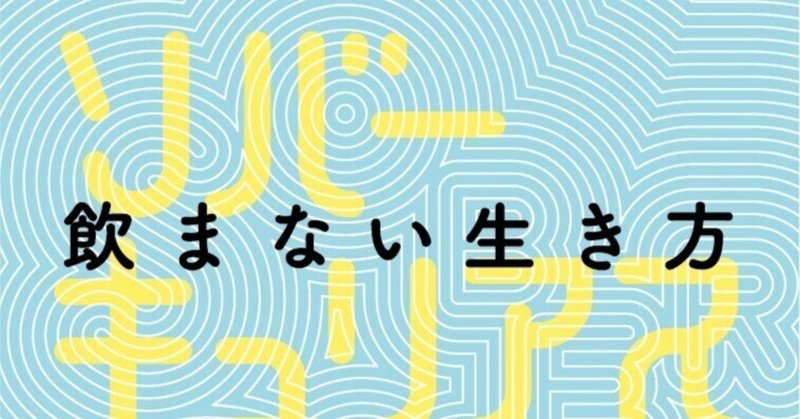
お酒を飲まないことこそかっこいい? ~『飲まない生き方 ソバーキュリアス』~
どんな本?
かつてアルコール依存症になりかけていた筆者が、お酒を飲まない生き方「ソバーキュリアス」をいかに作り上げ、実践していくかをたどる内容。元々、ソバーキュリアスという言葉の背景にある若者の思想を知りたくて手に取ったが、どちらかというとお酒を飲まない生き方をするための実践の書のため、マーケティング目的で興味を持った人はこの書評を読んでもらえれば十分だと思う。
どんな人に向いている?
上述した通り、若者を理解するという目的には向いておらず、お酒を断つ生き方をしたい人のための本になっているため、注意が必要。
学びはなに?
元々お酒が欠かせない生活を送っていた人が、我慢ではなくポジティブにお酒を断つにはどうすればよいかを筆者の経験を交えながら語る内容が大半。
その中からマーケティングに役立ちそうな箇所を以下に挙げる。
①ソバーキュリアスはあくまでアメリカの文化
日本でも若者の酒離れが叫ばれているため、アメリカを中心に広がっているソバーキュリアスという考え方に興味を持つ人も多いと思う。
しかし、アメリカと日本では飲酒に関する背景が異なる。
例えば、アメリカでシェアを急激に伸ばしている低アルコール飲料の分野。
日本で低アルコールといえば、度数0.5%のビアリーや2%程度のほろ酔いを想起する人が多いかもしれない。
しかし、アメリカにおける「人気の低アルコール飲料」とは、
5%程度のハードセルツァーを指すことが多い。日本で度数5%のフルーツ系アルコールといえば、チューハイがすでにメジャーな存在になっている。
本書には筆者の赤裸々な飲酒エピソードが多く紹介されるが、そこで飲まれている酒の多くがウイスキーやワイン、度数の高いショートカクテルなのだ。
アメリカでは日本よりも遥かに度数の高い酒を消費する傾向にあり、結果的に人口に占めるアルコール依存症患者の比率が日本の3倍以上に達している。
このような状況では日本よりも酒を飲むことのデメリットが若者世代に強く認識され、カウンターとしてのソバーキュリアスという考え方が生まれやすい土壌にあると思われる。
日米の違いを考慮すれば、アメリカで流行っているハードセルツァーをそのまま持ち込んでも、チューハイやサワーとの差別化に苦労するであろうことがわかる。
②お酒を進め続ける文化は健全なのか
日米の飲酒環境が異なる一方、飲酒を奨励する文化の健全でない側面が顕在化していることは否めない。
筆者は飲酒の問題が深刻になっている原因を、外向的な性格を良しとする文化にあるとしている。内向的な人が、他人に対して明るくふるまうためのアイテムとして酒が認識され、SNSの普及によってさらにその傾向が強まったというのだ。
確かに、我々の社会は不思議なほど飲酒を是としており、お酒を飲まない人へ風当りが強い。飲めることはクールで、飲まないということは何となく決まりの悪さを感じさせる。このような同調圧力による反発と、健康を求めるトレンドが重なり、ソバーキュリアスという大きな流れを生んでいる。
マーケターとしてどう思った?
まず、日本におけるソバーキュリアスはアメリカと異なる形で現れるだろう。アルコール依存症は日本でも深刻な問題としてあるが、アメリカとは規模も捉えられ方も異なる。泥酔するまで飲むようなパーティ文化のカウンターとしてではなく、より目的に対して効率的に生きたいという”タイパ”を求めるトレンドと合流するのではないか。
アメリカのソバーキュリアスはヨガや瞑想と結びつくスピリチュアルな側面があるが、日本では若くして成功したいという起業家カルチャーと結びつくような気がする。成功の証として酒を求めるのではなく、さらなる成功のために常に頭を明晰に保ち、タイムパフォーマンスを高めたいという欲求だ。
それは、運動や睡眠と比べて即効性のある疲労回復術としてサウナが流行しているように。
このようなトレンドが想定される中で、アサヒのスマドリをはじめとしたノンアル推進運動は的を射ているのだろうか?個人的には、少し否定的である。なぜなら、日本でもアメリカでもソバーキュリアス的な動きというのは、「アルコールが"なくても"楽しめる」ではなく「アルコールが"ないほうが"楽しめる」という主張として現れるからだ。
ノンアル推進の動きは、そもそも酒などないほうが楽しいと主張している人たちに、酒の代替手段を提供しているようにしか見えない。酒類業界は、依存症の問題や過度な同調圧力には配慮しつつ、ソバーキュリアス的なムーブメントに対しては、ソフトドリンクのブランドで乗っかったほうが良いのではないかと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
