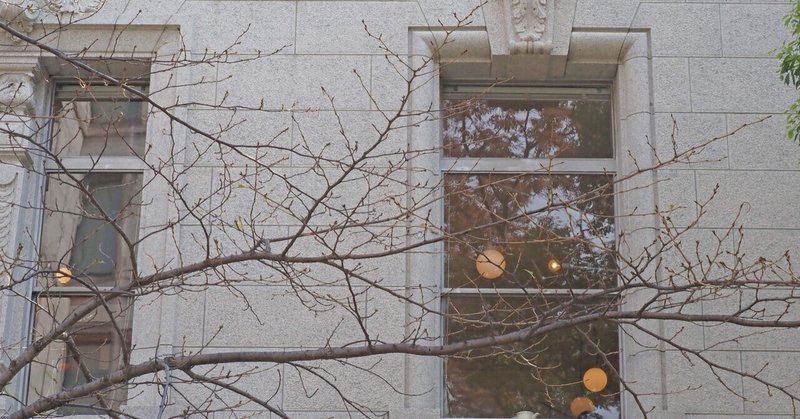
新しい奏法に出会って③
私が学んだ奏法を簡単に説明すると、響きが豊かになるだけでなく音色のバリエーションも増えて尚且つ身体に負担がないという利点があります。
「響」というのはペダルをいれて音を響かせるという意味での響きだけでなく、ノンレガートやスタッカート、トリル、音価が短い音も含めで「響き」と言っています。
奏法を変えるので弾き方を変えるわけですが
指、手、手首、腕、身体の使い方全てが変わっただけでなく、耳の使い方も根本的に変わりました。
今思えば、当時の私は「どのようにして音楽を作るのか」に注力し、自分の音を聴いているつもりでも聴けていなかったように思います。音の長さや強弱は聴いていても音色について考える時間は少なかったです。
先生からは、聴音をする時のように耳を使ってはダメ、お風呂に浸かっている時のようにリラックスして、響きを浴びているような感覚だと教わりました。
聴くというより感じるという感覚が近いと思います。肌で音を感じるのです。
ということで、奏法を変える始めのステップとして、身体の使い方と同時に耳を育てる、良い響きとそうでない響きを聴き分けるという訓練が必要になってくるわけです。
これは本当に雲を掴むような作業です。
私はこの時期、アルゲリッチ、ソコロフ、ポゴレリッチ、スルタノフ、ヴィルサラーゼ等の音源を聴いては、良い響きをイメージしていました。
響きの違いがよくわからないと足止めを喰らっている人は
①とにかく先入観なく、先生の響きをよく聴くこと、そして頭と身体と心をオープンにすること
②リラックスすること
③同じ系統の奏法のピアニストだけの音源を聴くこと(一定期間だけでいいので情報を絞った方が賢明です)
④一回のレッスンで得られるものがなくても落ち込まない事(笑)時間がかかる事であることを覚悟すること。
⑤こう弾きたいとか、今までこうやって弾いてきたとか過去の奏法はとりあえず一旦全て忘れて、違和感を感じることでも受け入れるという意識でいること。
これらのことを気をつけていると響きの違いがわかってくるんじゃないかと思います。
奏法を変える時って、新しいことを取り入れていくわけですから、違和感や抵抗を感じる人も一定数いると思うんです。でもそういう抵抗って一過性のものなので、耳が育ってきて、先生が明らかに横で良い響きで弾いていたら、抵抗も疑いも違和感も一発で無くなります(笑)
あとは美しい景色を観たり美味しいものを食べたり、ピアノ曲以外の作品に触れたり、旅行に行ったり、自分が好きなことをして感性を磨いていけば耳も育ちます。
そうしていくうちに、面白いことに受け入れられる音楽や演奏家の許容範囲が広がってくるんです。
結果的に、気づきが増えてますます音楽に惹きつけられるというわけです。
お試しあれ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
