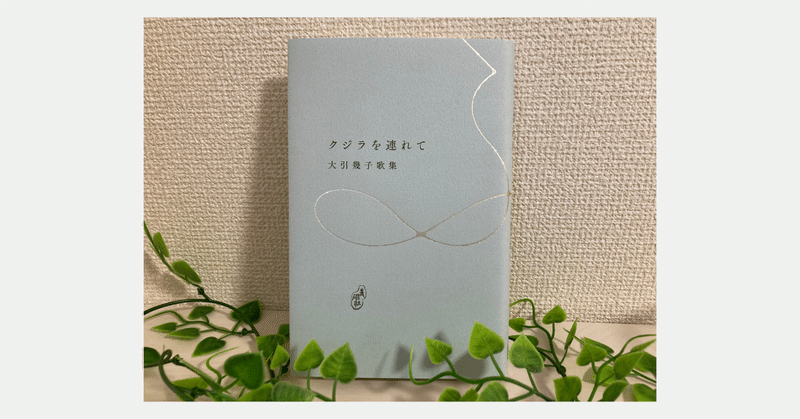
【書評】『クジラを連れて』大引幾子歌集(公開記事)
「ひかりの洪水」の向こうで
海蛇座碧空の裏に飼いいたり時に銀灰の鱗光らせ
便箋の静脈透けて舞い落ちる間も底知れぬ夜への投函
大引幾子さんの第一歌集『クジラを連れて』。
穏やかなブルーの表紙を開くと、まず目に留まるのは童話の世界も思わせる詩情豊かな歌だ。
真昼の海蛇座が空の裏側で鱗を光らせる様子。暗いポストの内部を想像させる「夜への投函」という結句。
いずれも作者の美意識が強く出ており、ぐっと惹きつけられる。
はつ夏のひかりの底に子を抱けば吾子は雫のごとき果実よ
三歳は二歳よりややせつなくてシロツメクサの白・雲の白
主体は愛する人と出会い、結婚し、やがて出産を経験する。
この歌集には子を詠んだ歌が多数あるが、そこにはやはり優しくほのぼのとした詩情が色濃くある。
一首目、産まれた我が子を腕に抱くと、赤ん坊は「雫のごとき果実」であると言う。雫も比喩であり、果実もまた比喩だ。
二重の比喩を用いることで、丸々とした乳児の体型や瑞々しい質感を強くイメージさせる。
二首目の「せつなさ」は日常的に歌を作る者ならではの感覚ではないだろうか。
二歳と三歳のせつなさ加減の違いは、シロツメクサと雲の白の違いのようなもの。その喩えは不思議な懐かしさを伴っている。
このような柔らかな歌群に、歌集後半は生々しい教師の職業詠が混ざり、読者は驚きながらもその変遷に引き込まれてゆく。
(死にたい)と(死ぬ)のはるかな隔たりをふいと跨いでしまいぬ君は
やめさせることが担任の手腕だと聞かされている生活指導会議
ガラス戸の割れ目から入れる封筒の学校の名が不意に目を打つ
自死してしまった生徒への思いを綴る連作や、教育現場ですら本音と建前があることを思い知らされる歌。
高校を辞める生徒の自宅に退学届を持っていく場面。
これらの歌は事実を差し出すだけで読者に作者の心情をありありと伝える。
教師という仕事と子育ての両立の過酷さを窺わせる歌もあり、徐々にリアルで硬質な歌の割合が増えてゆく。
どうしても直して来ぬと言うユキの傷んだ金髪なでてやるなり
作者の教師としての在り方が存分に伝わる一首。荒れる生徒にも真摯に向き合い、金色に染められた頭髪を撫でてやる。
そうやって一人一人に積極的に関わっていく。大引さんは歌の中でも生徒達を優しく包み込むようだ。
この歌集には作者の二十代から四十代半ばまでの作品が収められている。
絵でも音楽でも、長く作品を生み出し続けていると作風に変化があって当然だ。
自らの境遇、出会ったものや人、その時々で語りたいこと。
様々な要素が折り重なって「今」の作品が生まれる。
この歌集では、それは「柔らかさから硬さへ」という形で表れているように思う。
少女とは楽器であるか片脚を立てて銀色のペディキュアを塗る
もう九月 クジラを連れて散歩する陽気な君に会えるだろうか
そうした変化の中で、それでも作者は短歌という詩形の強さを信じる。
厳しい現実の歌と鮮やかなポエジーが共存するとき、そこに新たな視点が生まれることを、信じる。
両腕に出席簿かたく抱きながら渡り廊下はひかりの洪水
日差しが洪水のように溢れる渡り廊下を、出席簿と共に己の矜持も胸に抱えて歩む。その明暗の美しさと、凛とした主体の佇まい。
「ひかりの洪水」の向こうで大引さんの歌が今後どのような変化を辿るのか、楽しみだ。
(2023/9 青磁社)
(「塔」2024年2月号に寄稿した歌集評を公開しました)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
