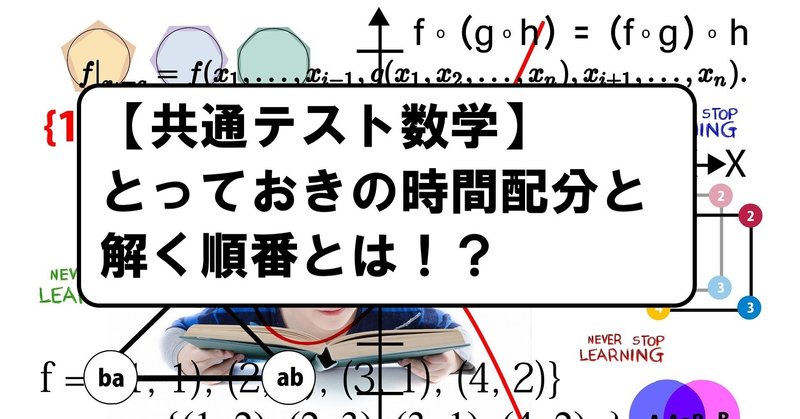
【共通テスト数学】試験本番で焦らない時間配分と解く順番!
予備校で講師&学習アドバイザーをしている冒険者です。教育系ブロガーとして冒険者ブログを運営しています。
今回は「共通テスト数学のとっておきの時間配分と解く順番!」ということで、記事を書いていきます。
大学受験を目指す高校生で、共通テスト数学に苦戦している人は多いです。しかも、時間との闘いの中で、自分の実力を出し切る難しさは、共通テスト模試などで経験しているはずです。
ですから、今回の記事を読んで、どうやって時間内に実力通りの結果を残すか!ということを学んで頂き、本番でしっかりと良い点数をたたき出してほしいです。
今回もnoteは簡単に、詳細はブログで!という流れでいきます。
noteでは「時間配分」に絞って書いています。「時間配分」も「解く順番」も予備校の知識を教えてほしい!という人は、ブログの方へいってください!
では、さっそくいってみましょう!
【共通テスト数学】とっておきの時間配分を教えます!
では、共通テスト数学のとっておきの時間配分と解く順番について解説していきます。
まずは結論からまとめます。
共通テスト数学の時間配分のコツ
①わからない問題が出たら飛ばす
②選択問題は決めておく
③完答を目指さない
この3つです。しかし、ここで1つ注意点をお伝えします。
試験時間を大問の数で割ると、大問1問あたり12分~15分です。
ただ、数学の問題はその大問によって、その時間内では解けない問題や、意外と早く解けてしまったりするケースがあるため「これくらいの目安で!」というのがありません。
とにかく上記の3つについて覚えておきましょう!では、1つ1つ詳細を書いていきます。
わからない問題が出たら飛ばす
まずは、わからない問題が出たら飛ばす、という方法です。
ブログではもっと詳細に書いていますが、ここでは簡単に理由だけお伝えします。
解けそうで解けない問題、これが一番厄介な問題で、そこに時間を割いていると解けるはずの問題も解けず、焦ってしまうからですね。
とにかく、「これは時間かかるな」「ちょっと解けそうにないな」という判断をすぐにして、ドンドン解き進めていきましょう!
選択問題は決めておく
数学にはⅠAにもⅡBにも選択問題があります。3つから2つ選ぶ、という感じです。
そのため、共通テスト数学は的を絞り、予め解く問題を決めておくのが良いです。選ぶ時間のロスと、迷いが生じてしまう為、脳が疲労します。
とくに数学ⅠAは「確率・整数・図形」の中から、選択する単元を対策しておくことをお勧めします!
しかし!これは「文系用」のテクニックで、理系はこれを使ってはいけません!理由は「選択問題も含めて、重要単元ばかり。そして、国公立2次試験や私大でも頻出の単元もあるから」です。
気をつけてください。
数学は完答を目指さない
そして最後に、共通テスト数学は完答を目指さないことです。
時間内にどれだけ点数を獲得できるか、これが勝負になります。つまり、100点を狙っている人以外は全部解けなくていい、ということです。
つまづいた時点で次の大問に移り、最後まで解き終えてから解けそうな問題を考えていく方が効果的に点数を確保できます。
満点を目指さなくても、志望校には合格できますよ!
【共通テスト数学】とっておきの時間配分と解く順番 まとめ
いかがでしたでしょうか?
noteでは「時間配分」に焦点を絞ってお伝えしました。ブログの方では「解く順番」も解説しています。
共通テストは数学だけではなく、英語も国語も時間との闘いです。時間配分と解く順番は、作戦として考えていないと、当日に痛い目をみることになります。
特に計算が遅いと思っている人は、時間配分と解く順番で、どこでどう稼ぐか?を考えて当日に臨んでください!
受験生の皆様、健闘をお祈りいたします。
最後までご覧いただきましてありがとうございました!
合わせて読みたい記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
