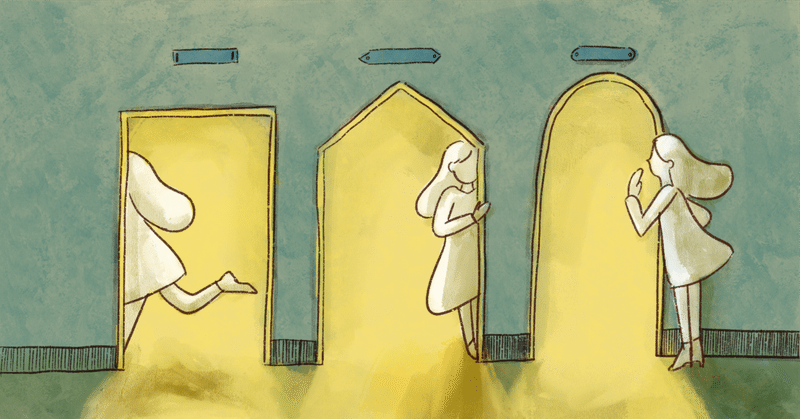
どんな顔をしていたらいいかわからないときに思うこと
たとえば、スマホの待ち受け画面に通知されるオンラインニュースで、「ガザ地区で爆弾大量投下」のタイトルと「日本シリーズ 阪神が先制」のタイトルが並んで表示されていても、その現実を受け止められているとき。
たとえば、子どもの貧困や教育格差の是正みたいな社会課題に取り組んでいる団体にクラファンで寄付はするのに、自分の子どもの小学校の学区が、荒れていると噂の学区とは別で、ほっとしたとき。
たとえば、発達特性のある子どもを持つ保護者同士の集まりに参加したり、相談に乗ったり、運営のサポートをしたりはするのに、タウン誌の取材が来るから集合写真を撮ろう、といわれると参加を迷ってしまうとき。
つまり、それなりに親切で道徳的だと思って生きている自分が、
実は厚顔で、自分勝手で、偽善的で、本音と建て前を使い分けていることに気づいてしまったとき。
そんなときには、どんな顔をしていたらいいのか、
どんな顔をして生きていったらいいのか、いまだによくわからなくなる。
世界が平和であるように、誰もが健やかで自分らしい暮らしができるように、と心の底から祈る気持ちは本当なのに、
戦争や災害はどこかひとごとで、
自分の身近に面倒なことや災いが降りかからなければいいと思っていて、
けっきょく、自分が他者からどう思われるかを気にしている。
おとなになったら、自然と自分の言動にうそがなくなっていくのかと思っていた。その場で、その社会で、自分自身に対しても、ふさわしい顔ができるようになるのかなって。
いまさらだけど、そんなわけない。
***
宮沢賢治の『農民芸術概論 綱要』のなかに、
世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はありえない
自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する
という一説がある。
この詩に出会う前から、しばらくのあいだ、
「自分の意識を、自分自身から、どれだけ拡張できるのか。例えば、家族に、組織に、地域社会に、国に、世界のすべてのひとたちに、生きものすべてに。」
ということを考えていて、なかなか難しいなと思っていた。
家族はいいとして、百歩譲って組織もいいとして(つなぎとめているものは利害関係とか、ビジョンとか、そういうものかもしれないけど)、地域社会あたりから、「わたしたち」という主語に身体感覚が伴いづらくなる気がして。
身体感覚が伴わなければ、それは道徳意識や集団のなかの一般常識としてきれいな言葉をならべるだけになってしまう。
「それはなんとかしないと」「わたしはまずこれをしてみる」という行動にはつながらない。
どんな行動にも所作にもつながらない思想は、たわごとと同じだと思う。
たわごとは言いたくない。
でも、意識の拡張は難しい。
しかし、自然と身体感覚が伴うほど地縁血縁利害が濃い地域コミュニティに属するなんてのは、想像しただけでぞっとしてしまう。
できれば、あっさりした都市的核家族・地域社会のなかで、なににもしばられずに意識を拡張して、気の合う仲間と暮らしや営みを続けたい。
わたしは、そんな自分勝手な人間なのだ。
何度生まれ変わってもナイチンゲールやガンジーにはなれない(何者かになりたいと思っているわけではないけど)。
そんななかでこの詩を読んだので、
無理にきまっとるやないかーい!
と思った。だって、
「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はありえない」
「自我の意識は個人から集団社会宇宙と次第に進化する」
これに身体感覚が伴う人間がいるのか?
1926年にこの感覚を持っていて、それを言葉で、しかも詩というかたちで表現した凄み。
そして、それが当時の社会にはほとんど理解されなかったという現実。
ところでこの感覚は、内田樹が言うところの、『私の変容態』にもつながる。
あらゆる人間はかつて幼児であり、いずれ老人になり、高い確率で病人となり、心身に傷を負う。
だから、集団のすべての構成員は時間差をともなった「私の変容態」である。
それゆえに集団において他者を支援するということは、「そうであった私、そうなるはずの私、そうであったかもしれない私」を支援することに他ならない。
過去の自分、未来の自分、多元宇宙における自分を支援できることを喜びとすること。
そのような想像力を用いることのできない人間には共同体を形成することはできない。
内田樹は、では、どんな共同体なら成り立つのか、という問いに対して、
「教育のための共同体、医療や介護のための共同体、それから宗教の共同体くらいでしょうか。」
と答えたらしい。
そして、これら三つの共同体には共通した特徴があって、それは、
「構成員のうち、もっとも非力なものを統合の軸にしているということ」
なのではないか、とのこと。言い得て妙である。
たしかに、わたしも、自分が育て辛い繊細な子どもを育てているから、同じような保護者さんにはできるかぎりのサポートをしたいと思うし、自分の親が老いてきたことを実感しているから、近所のおじいちゃん・おばあちゃんに自然に親切にできるようになった。
自分の手足がのびる範囲。きっと、半径数十メートルほどの意識。
***
厚顔で、自分勝手で、偽善的で、本音と建て前を使い分ける人間なりに、どこまで意識を拡張できるのか。
おとなになったわたしは、それを問い続けていけばいいのかもしれない。
そうしたら、おばあちゃんになるくらいまでには、透明で熱い人間になっているのかもしれないし、もしなれなかったとしても、それはそれでいいのだろう。
最後に。
宮沢賢治の『農民芸術概論 綱要』のなかで、
まづもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばらう
が、とてもすきです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
