
【取材記事】気候変動アクションを自走するNFTプロダクトをリリース。ウェルビーイングの象徴である「ミツバチ」×「アート」が生み出す画期的なweb3アート
ミツバチがもつ独自の社会性から着想を得て、養蜂と緑化活動を通じたサスティナブルな活動に取り組むBeeslow。ワンコインから都市の緑化支援を始められるサービス「Beeslow Club」を運営するほか、そこで集めた資金を活用したビルオーナー向けの緑化サービスを展開しています。
今回はあらたな取り組みとして独自のNFTコレクションをリリース。NFTアートを販売し、その収益を通じて都市緑化などリアルフィールドでの環境アクションにつなげます。今回は株式会社Beeslow代表取締役社長・船山遥平さんと、現代アーティスト・團上祐志さんをお迎えし、NFTコレクションの内容や取り組みに込めた思いについて伺いました。
【お話を伺った方】

船山 遥平(ふなやま・ようへい)様
慶應大学卒業後、大手エンターテインメント会社勤務、旅館業で起業。多様な価値観に触れる中で「⾷」と「環境」が⼈間の意識を⼤きく左右することに気付き、志をともにする養蜂家やアーティストとBeeslow社を設⽴。「Think bee, live slow.」をスローガンに、ミツバチ目線からの学びを、アート、国際支援などの形にし、地球環境と社会の多様性を考える契機を提供する。
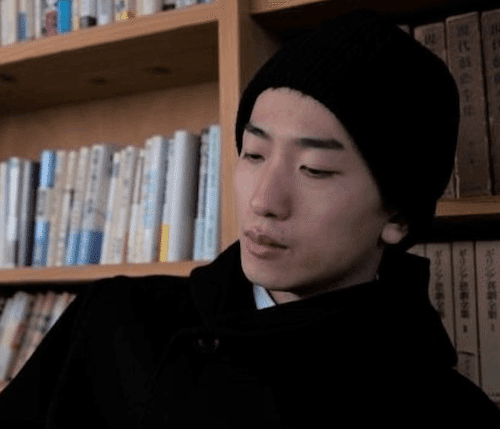
團上 祐志(だんがみ・ゆうし)様
1995年生まれ、愛媛県松山市出身。武蔵野美術大学油絵科油絵専攻卒業。クマ財団2期クリエイター。在学中にアメリカに渡り、ニューヨークやロサンゼルス、デンバーのギャラリーでの展示と、活動の幅を広げる。愛媛県大洲の古民家に国内外のアーティストを呼び込むというアーティスト・イン・レジデンスを軸に事業を展開。西日本豪雨で浸水した木材を使用したテーブル「two-by-two」の製作、雲孫財団糸島雲孫ハウスでの制作活動を通じ、油彩からミツロウと銅板、光へと移行し、題材としてNFT、環境問題に取り組む一般社団法人Beeslowのアートプロデュース、など、領域横断的な制作を行う。
■社会の発展とウェルビーイングを両立するミツバチ社会に学ぶ

mySDG編集部:「ミツバチ目線」で環境問題や社会の多様性に取り組むという視点が非常にユニークだと感じました。なぜ「ミツバチ」に着目されたのでしょうか?
船山さん:歴史上、ミツバチが住める環境というのは人間にとっても豊かな場所であり、ウェルビーイングの象徴であったと思います。しかし、今まさにそういった所が地球上から急速に減っています。私たちがミツバチから学ぶべきことは、社会の発展がウェルビーイングと分断されていないことです。ミツバチと共生することで、その気付きを得られると信じる、さまざまなバックグラウンドを持つメンバーと日々環境を創っています。
mySDG編集部:船山さん自身は、これまでエンタメ関係など、別のフィールドでお仕事に従事されてきた中で、全くの異業種となる「ミツバチ」を基軸に蜂蜜の販売などの事業を起業されたのはどういったきっかけからですか?
船山さん:当時、従事していたエンタメ業界では、タレントである人間を商品として扱う面もあり、私も寝る間を惜しんでマネジメントしなければならず、双方が疲弊していました。理想的な働く人間の関係性や社会を構想する中で、ミツバチが持つ健全さに魅力を感じました。ミツバチは食料としての花蜜(エネルギー)、繁殖に必要な花粉(タンパク質)を取り入れ、集めたプロポリスや生成した蜜蝋で巣を作り、繁殖します。私はこの様子から、ミツバチは自然環境から必要なものを必要な量だけ取り入れ、必要なものだけを作る生物だと考えました。また、病気を罹患したミツバチは巣を出ていきます。自分が巣を抜け出すことで、社会(コロニー)全体の健康を保とうとしているのだと私は解釈しています。このようなミツバチの生き様が健全であり、過分な生産と消費を重ねて環境問題に直面した人間が見習えることが大いにあると感じ、蜂蜜の販売にとどまらない事業を始めるに至りました。
mySDG編集部:蜂蜜の販売以外の事業とは、どのようなものでしょうか?
船山さん:都市空間にミツバチのいるガーデンを増やす事業「Beeslow Garden」を行っています。ミツバチは花の蜜や花粉を集める過程で植物の受粉を助ける「花粉媒介者」として、健全な生態系を支えてくれる存在です。日本に多く見られる慣行農業は、出荷したい単一作物以外の種や虫を排除することで、一定の収量を確保するものですが、長い時間軸で見ると、病害や収量の極度な減少といった問題を引き起こします。一方、生物多様性の豊かな場所では持続的な生産が可能になるのですが、「花粉媒介者」であるミツバチの営みによって生物多様性に貢献するということに気づいたんです。また、あえて都市空間にガーデンを作るのにも大きな理由があります。人間が生活する社会の中にミツバチの社会も共存させることで、都市空間に暮らす人々が日常的にミツバチを観察し、自らの生き方や人間の社会を省みる機会を提供したいという思いを我々は持っています。
■ミツロウを用いたリアルアートからNFTアートを制作。NFT保有者でコミュニティを形成し、主体的に環境問題に取り組む土壌をつくる

mySDG編集部:今回初となるNFTコレクションをリリースされるそうですが、具体的な内容を教えてください。
船山さん:今回のNFTプロジェクトは、気候変動に対するオルタナティブ・ファイナンスを目的としたweb3アートプロジェクトです。NFTコレクションとして、アーティストの團上祐志さんが手がけるアートピースを販売します。團上さんはミツロウを用いたアート作品を主に製作されていて、今回は「働き蜂」「オス蜂」「女王蜂」の3種類の蜂をモチーフにデジタルアートを制作していただきました。このNFTは気候変動や環境問題に対するアクションの証明となりますので、購入者はSNS等にアイコンを使用して、自らの姿勢を表明できます。
mySDG編集部:ちなみにNFTの収益はどのように使われるのでしょうか?
船山さん:収益の主な使途は、当社が運営するビルの屋上緑化サービス「Beeslow Garden」のハーブ苗や土などの購入費に充てるほか、NFTに関わったクリエイターやNFT保有者を中心としたコミュニティに還元されます。コミュニティに還元された資金は、メンバーの報酬や環境保全のための新たなプロジェクトの投資に利用される予定です。
コミュニティ内では、参加者自身が新たなプロジェクトが提案でき、NFT保有者による投票で意思決定される仕組みになっています。コミュニティを通じて、人々が主体的に環境問題に取り組める土壌をつくることが狙いでもあります。
mySDG編集部:今回NFTとしてアートを販売するということですが、ミツバチとアートの結びつきはどういった点にあるのでしょうか?
船山さん:ミツバチの巣から採取できるミツロウは、近代以前は画材として使われていた歴史があります。それ以外にも「都市養蜂でできたミツロウ」に着目したんです。自然の恵みではありながら、アート的。そこが非常にコンセプチュアルなんじゃないかと。
團上さん:そもそもミツバチは、ヨーロッパにおいても社会主義国においても東洋においても、常に哲学の対象でした。彼らの不思議な生態——いわゆる彼らがもつ独自の社会性であったり、数学的な処理で巣作りしたり、これまでもアートのモチーフとして扱われてきました。そのため、ミツバチをアートの文脈に引き入れるのは、そんなに難しいことではないと思いました。
mySDG編集部:今回はご自身のアート作品をNFTとして販売されるという点はいかがですか?
團上さん: 今回、コミュニティを通じて自発的に環境アクションできる設計を作ることは、極めて今やるべきweb3のアウトプットだと思っています。蜜蝋画のリアルアートからNFTアートを制作・販売し、その金額はクリエイターに分散され、なおかつコミュニティにもちゃんとプール再投資される仕組みです。環境に対して投資した人間同士がつながって共通口座があるという状態が生まれるので、今後もう少しアップデートした場作りができるのではないかと思います。よりビジネス的な話をすると、カーボンオフセットのような構造を、アートというちょっとお祭り的なことをしつつ、形成できるのではないかと考えているところです。
■ミツバチがもつ「真社会性」を軸に作品を制作。アートを通して都市と自然の新たな可能性を表現

mySDG編集部:作品について、教えていただくことはできますか?
團上さん:作品はミツロウで描かれていて、今回は人工顔料を使ってはいるのですが、使っていない部分もあるんです。花粉なども顔料になりうるので。そういうものを使って、まずは女王蜂に見立てて、リアルアートを作っていきます。一つひとつメッセージを込めているのですが、例えば都市と農村というような、いわゆる都市の中に新しい自然を作り出すという新しいオルタナティブな場所を作っていくことをテーマに取り組んでいます。
web3ではまさにDNAという表現を使うんですが、リアルアートの画像のデータを分割し、プログラミングによって1万通りのアートピースを作っていきます。NFTアートではいわゆる働き蜂や雄蜂という巣の中にいる蜂を表しつつ、その中の社会性をトンチをきかせて制作しているというようなことですね。
mySDG編集部:ミツバチの社会性とは、いったいどんなものなのでしょうか?
團上さん:ミツバチは、eusocial(真社会性)と呼ばれる人間とは異なる社会性を持っています。私は、ミツバチがもつ真社会性を、社会を維持するために、非常に柔軟に役割分業を行い、高い環境適応能力を発揮するためのプロトコルと捉えています。予測不可能な自然環境の中で、見事な役割分担を用いて健全なカタチで一つの社会を皆で運営する——。そういったミツバチがもつ真社会性を軸に作品を制作してみようと思いました。
もう一つは、新しい都市と自然についてです。人間生活と自然環境は、それぞれ遠い場所にあるように思われています。ミツバチは、それをつなぐエージェントとしてものすごく機能しているんです。都市でミツバチを飼うことによってミツロウや蜂蜜がとれて、新しい都市と自然の調和の可能性を見せてくれるだろうと。そういった理念も込めて作品を描いています。
■自然との結びつきを感じられる「場」をリアルとバーチャルで提供。人々がもつ豊かさをアートとともに有機的につなげていく

mySDG編集部:今回のリリースに対する周りからの反応はいかがでしたか?
團上さん:暗号資産系の企業からは、いわゆるweb3が求めている新しいファイナンシャルの世界というような、これまでの環境投資とは違うパターンだと認識していただいたようです。また、NFTアートの所有価値として、コミュニティでの投票権と環境投資としての活用可能性を訴求できたことは、NFTアートとコミュニティの設計において、先進的な取り組みになる予感がしています。
ある種、現時点でのNFTの盛り上がりを無視したようなプロジェクトだと思っております。ブロックチェーンとアートプロジェクトがどのように関係を結べるかを考えています。実際、競争するようなプロジェクトではないね、と周りからも言われています。あとは世論がどれだけくっついてくるかというところですね。
mySDG編集部:團上さんはアート業界で活動されていますが、どのように評価されていますか?
團上さん:社会のあるべき方向性を描き、実装することこそが、今後のアートのあるべき姿だと思っています。
mySDG編集部:非常に新しい取り組みであるがゆえに、賛否あって当然なのかもしれません。最後にBeeslowとして今後の展望を教えてください。
船山さん:まずは、都市で自然とのつながりを感じられるような場所を作ることですね。ビルの屋上、個人宅から公園のようなパブリックな場まで展開していきます。また、オンラインでの繋がりも含めて、環境アクションに取り組むプロジェクトを強く推進していくコミュニティを育んでいきます。これらの取り組み自体がアートとして人の意識を変容させていくことを期待しています。
この取り組みが参考になりましたら、ぜひいいね・シェア拡散で応援をお願いいたします🙌
mySDGへの取材依頼・お問い合わせは mysdg.media@bajji.life までお気軽にご連絡ください。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
