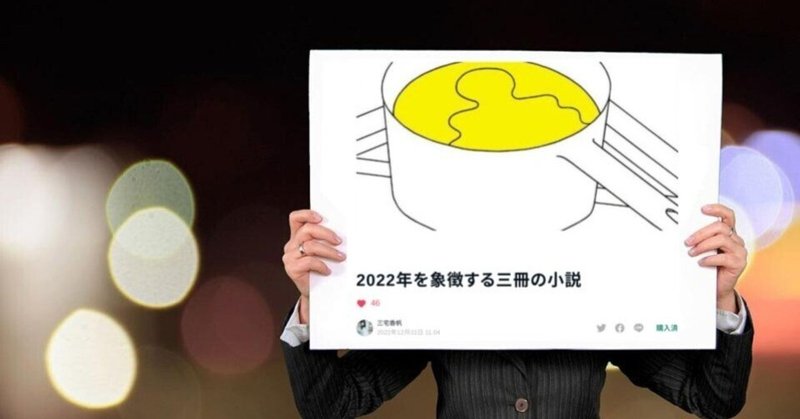
小説が何倍も面白くなる視点【小説の楽しみ方が手に入る記事を紹介します】
これを知っていたら、小説が何倍も面白くなる。
今回はその視点を発見した記事を紹介します。
こういう心を揺さぶられる記事を見つけたら、おもわずそれを人に紹介したくなりますね♪
*紹介する記事
書評家で何冊もの書籍も出している作家の三宅香帆さんの年末の記事「2022年を象徴する三冊の小説」です。
(有料記事ですが無料の部分だけでも十分に楽しめます!)
小説にとって大事なもの = 「今っぽさ」
note本文からの引用です。
私は小説に「今っぽさ」というのは意外と大切だと思っていて、小説というのは基本的に時代のマイノリティの感覚を掬い上げるものだと思い込んでいるからだ。それは属性としてのマイノリティという意味ではなくて、感覚としてのマイノリティのことだ。
面白い小説には「今っぽさ」がある。
読書が何倍も面白くなる視点
「今っぽさ」を出発点に、そこから考える読書が何倍も面白くなる視点は次の3つ。
視点①小説から「今っぽさ」を見つけよう
面白い小説には「今っぽさ」がある。
読んでいる小説からその「今っぽさ」を感じてみる。
視点②「今っぽさ」は口に出せない感覚
じゃあ、「今っぽさ」って何?
それは感じてはいるけど口に出さない感覚、マイノリティの感覚。
読んでいる小説からその「口に出さない感覚」を感じてみる。
視点③共感を超えていく「今っぽさ」
口には出さない感覚、口には出せない感覚。
その感覚が読んでいる本の中で言葉で表現された時、思わず心が揺さぶられる。
それは本と読み手との間だけことじゃなくて、その背後にある社会というもっと大きな存在と、その言葉で繋がった気がするからだ。共感を超えたこの貫通する感じ。これが「今っぽさ」なのかもしれない。
まだ言語化されていないリアル
確実に“ある”と感じているけど、言葉になっていない感覚。
まだ言語化されていないリアル。
だから口に出せない。
なんとなく言葉にできているけど、それが他者や社会でどう受け取られて、消費されていくのか?それがまだわからない感覚。
だから口に出せない。
その感覚を最初に言葉する、物語にするのが小説。
だから”小さく説く”だ。
物語が読み手の頭の中に入っていく。
社会の中に少しづつ溶け込んでリアルになっていく。
最初は小さく説いたものが読み手を通じて大きく説かれていく。
これがあの貫通する感じなんじゃないだろうか?
小説面白いですよ!
1月19日は第168回芥川賞の発表。
その発表前に候補作を全部読んで、受賞作を予想していきます♪
*芥川賞候補作全部読むチャレンジ中
*プロフィール記事
AIを使えばクリエイターになれる。 AIを使って、クリエイティブができる、小説が書ける時代の文芸誌をつくっていきたい。noteで小説を書いたり、読んだりしながら、つくり手によるつくり手のための文芸誌「ヴォト(VUOTO)」の創刊を目指しています。
