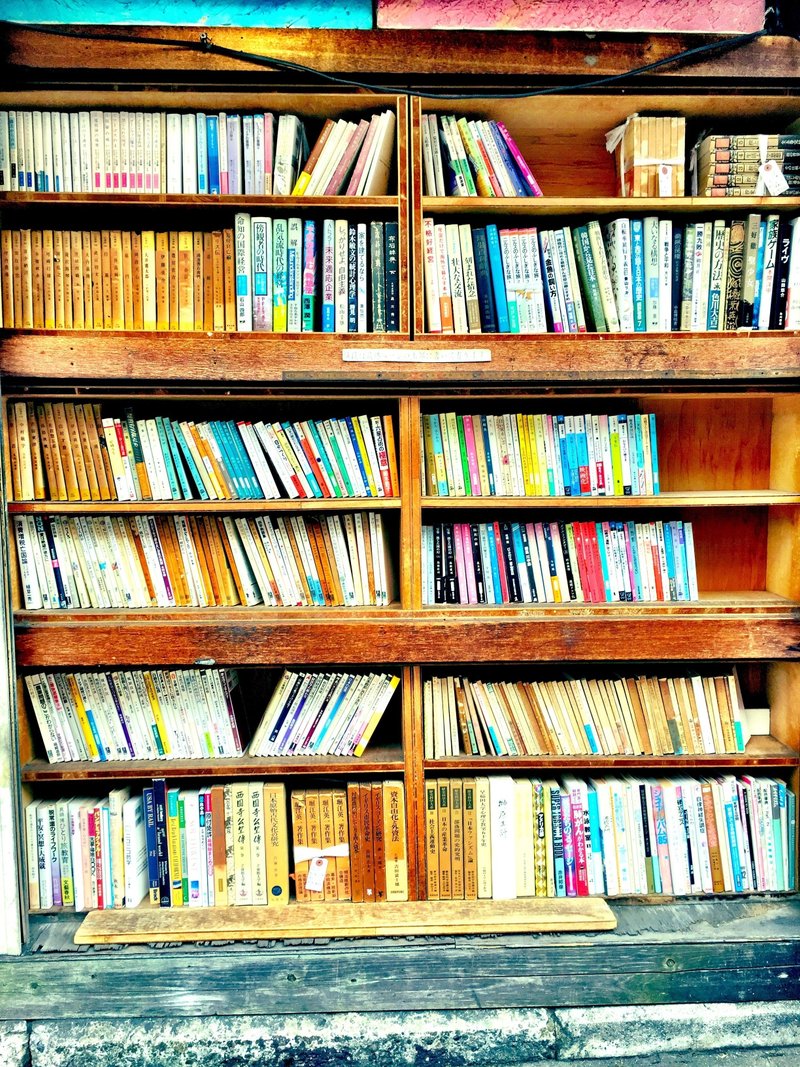
- 運営しているクリエイター
2018年4月の記事一覧
お金は本来繁殖力が強い
私は印刷所のために背負った借金をだんだんに返し始めた。着るものは質素なものに限り、遊び場所には絶対に顔を出さなかった。釣りにも漁にも決して行かなかった。…商売相応に手堅くやっていることを人に見せるために、方々の店で買った紙を手押車につんで、自分で往来を引いて帰ることも度々あった。
〜フランクリン著「フランクリン自伝」〜
アメリカ資本主義の育ての親であったフランクリンの自伝は、世界中の人々に勇気を
戦国武将の守銭奴ぶり
経済雑誌といえば利欲一点張りの我利我利記事ばかり。それをおもしろく、わかりやすく、楽しく読ませたい。
「経済マガジン」第一巻第一号=ダイヤモンド社
ダイヤモンド社の創業者で、有名な経済ジャーナリストでもあった石山賢吉が創刊した「経済マガジン」に、「戦国武将の守銭奴ぶり」と題する次のような読み物がある。
「人類の金銀に対する欲望は永遠である。丹碧燦然たる奈良朝の文化も、兵乱に明け、兵乱に暮れた弱
銭なき男は帆のなき舟のごとし
金が敵(かたき)
なかなか巡り合わない。金儲けは難しいと、敵にかけた意味と、大金を持ったために害を招くの意味にも使われる。不和や反目の生ずるのもみな金のためである。金と女がかたき
〜守随憲治監修「故事ことわざ事典」〜
「銭なき男は帆のなき舟のごとし」
男はお金がないと動きがとれない。
イギリスのことわざには、
「金なき健康は半病人なり」とある。
ロシアの文豪ドストエフスキーは嘆いている。
「
一番大切なものは金である
後世へわれわれの遺すもののなかに
まず第一番に大切なものがある。
なんであるかというと金です。
われわれが死ぬときに
遺産金を社会に遺して逝く、
己の子供に遺して逝くばかりではなく、
社会に遺して逝くと言うことです。
〜内村鑑三「後世への最大遺物」〜
内村鑑三は若い日、
「億万の富を日本に遺して、日本を救いたい」
と考えをもっていたそうです。
日清戦争勃発の中、
「われわれの今日の実際
学校では教えない歴史を知ると見えるもの
平清盛は瀬戸内海を制した。
平氏の繁栄は、武力によるもの。
学校の教科書には、
そのような背景しか書かれていない。
しかも、1時間程度で軽く流して終わり。
しかし、
父 忠盛が行なっていた宋との貿易。
それを大きくした清盛の日宋貿易。
貿易から得た莫大な利益。
その財力があったからこそ、
朝廷に媚びずに権勢をふるえた。
織田信長もしかり。
なぜ、強かったのか?
貿易による利益を独占していたから

