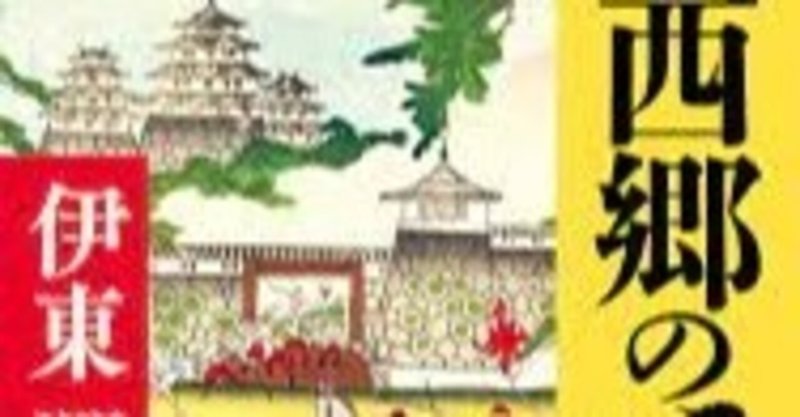
書評 西郷の首 伊東 潤 幕末、加賀家の二人の足軽が活躍する話し。幕末における侍の立ち位置が良く描かれています。

武士の中でも足軽は軽輩だ。
そんな足軽の二人が主人公。
島田一郎と千田文次郎は仲良しだ。
時代は幕末、前田家は新政府軍に加担する。
前半の戦争の場面とかは軽く、あまり楽しくないが、二人の生き方が分岐するあたりからが楽しい。
前半に、こんな言葉が出てくる。
「人は死に方ではない。それまで、いかに生きたかだ」
すごく印象に残った。
この作品のモチーフはここかもしれない。
前半で恩人とも言える勤王の志士が胴を切られて処刑される。
その人の彼らに残した言葉がいい。
「もちろん君も力尽きるかもしれない。それでも、君の屍を乗り越えていく者が出てくれば、君の死は無駄ではなかったことになる」 「それが志士なのですね」 「そうだ。屍になる覚悟のある者だけが志士と呼ばれる」 ようやく志士の何たるかが、一郎にも分かってきた。 「私はやります。必ずやこの国のために屍となります」
先輩の武士としての潔い死に様を見て
二人は感化されたのだと思います。
文次郎は戊辰戦争で義理の兄を失くし、病で妻を失くして一人となり
軍に入る、そこで真面目に頑張る。
一方、一郎のほうは、この国を良くしたいと思い自由民権運動に身を投じていく
明治時代になり、藩がなくなり武士も特権を失う。
不平士族たちが各地で反乱する。
明治の初期は前時代の不良債権である武士をどう処するのかという時期でもあった。
西郷が起こした西南戦争。
文次郎は政府軍として西郷たちと戦う。
心のどこかでシンパシーを感じつつ、それでも戦う。
そして、彼は、たまたま西郷の首無し死体を見つけ
西郷の首を探すことになる。そして、彼は西郷の首を見つけた。
それは武士の時代の終焉の瞬間だった。
─西郷さん、運命というのは皮肉ですな。 たった一度だけの出会いだったが、まさかあの時、分営の旗手を務めていた男が己の首を見つけることになるとは、西郷は考えもしなかったに違いない。 だが、もしも西郷の霊魂がいたとしたら、折田邸の庭で飯を食う将兵の中に、かつて話をしたことのある男を見出し、自らの所在を伝えたのかもしれない。 こんな形でしか再会できなかったことが、文次郎には口惜しかった。 ──だがわしは軍人だ。軍人は政府の命に従うだけだ。
そんな彼は故郷に戻り親友の一郎と再会するが西郷を神のように慕っていた一郎は激怒する。
「おぬしは西郷さんを賊だと申すか。西郷さんは私利私欲で起ったと思っておるのか!」 「それは──」 文次郎が言葉に詰まると、一郎が畳み掛けた。 「やむにやまれぬ思いから起ったのだろう。それをおぬしら政府の犬どもは、功を挙げて出世したいがために討ったのだ。これほどの非道があろうか」
ここで二人の道は明確に分離した。
西郷さんが死んだことで、武家の世は終わった。
それでも一郎は抗う。納得できない。
一郎は東京に出て仲間とともに西郷を殺した時の権力者大久保利通を暗殺する。
西郷の敵討ちだ。
逮捕された彼が名言を吐く
この時、「ほかに同志の者がおるか」という問いに対し、一郎は後世にまで残る名言を吐く。 「国民三千万のうち、官吏を除いたほかは皆、同志に候」
一郎の同士の長の辞世の句もいい
死するとも我真心は生るかに 思ふが如く事遂げにけり (たとえわが身は死しても、われらの志は生きていくかと思えるほど、事はうまくいった)
文次郎はこう決意する。
─軍人としてこの国を守ること。それが西郷先生の首を見つけた者の責務だ。 文次郎が西郷の首を見つけたことで、時代は大きな区切りを迎えた。一部の者はそれに抗ったが、大半の者は武士の時代の終わりを覚り、新たな道を模索し始めた。
武士の世界が終わった新時代。
西郷の首を見つけた文次郎は、軍人として生涯、この国を守った。
そして、大久保を殺した一郎は、最後まで武家社会という小さな箱庭の中から外にでられず
大局で物事を見ることができなかったのかもしれない。
大久保が親友の西郷を犠牲にしてまでやろうとしたこと
武士社会の終焉を演じて見せた西郷の最後の戦さの意味
西郷の決意。
まるで出来レースのように思える歴史の一幕。
しかし、西郷が死に、大久保が暗殺されたことで
前時代の不良債権である武士は完全に、その意味を失い。
日本は新しい局面を迎えるのでした。
二人の生きざま、武士としての矜持
色々と考えさせられるいい作品でした。
2022 1 10
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
