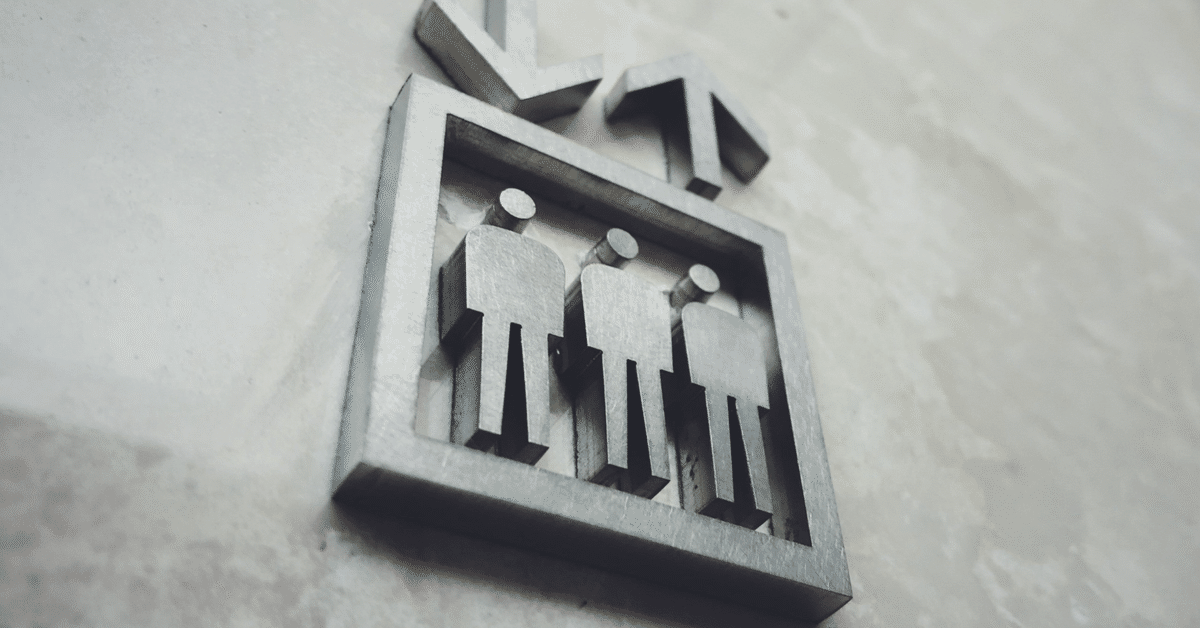
ひきこもり歴13年から今にいたるまで⑪
夕方、食堂へ向かうために自室を出る。
ひきこもっていた実家を出てから、毎日の食事は施設内の食堂を利用していた。
とくに食堂で食べなければいけないという制限はなく、外食も自由だったし弁当やお惣菜を買って自室で食べることもできた。
けれど、経験がほとんどない当時の自分に外食はハードルが高かったし、食堂の方が安く済むし、知っている人しかいないという安心感からほぼ毎日食堂を利用していた。
ただ、そうはいっても、自室から食堂に向かうときは多少の緊張はあったけれど。
エレベーターホールの前で立ち止まり、今どこにエレベーターがあるのか確認する。
2機あるエレベーターのうち1つは上の階で止まったままになっている。
それはいつもの光景だった。
一機が止まっている分、もう片方はせわしなく動いていて、私がいる6階に到着するのには時間がかかりそうだ。
「Uさん間に合うかな」と思いながら、自分は階段で食堂のある2階まで降りる。
食堂の窓から見える大きな川沿いの遊歩道に観光地らしいきらびやかな街灯がともりだすころ、ラストオーダーぎりぎりの時間でUさんが入ってくる。
いつも、ほとんど食べ終わって、食堂を後にしようかと思っている私とは入れ違うような形だ。
その施設の食堂は閉まるのがとても早くて、夜の7時頃には終わっていた。
「ご飯ありますか―」
からっと乾いて抜けるようなUさんの関西弁が人の出入りのピークをとうに過ぎてがらんとした食堂に響く。
普段はしゃべっているところをほとんど見ないが、厨房のスタッフにご飯を注文するときはその声を聞くことができた。
「間に合ってよかった」と少しほっとする私。
Uさんは自閉スペクトラム症でこだわりがあり、エレベーターに乗って行先のボタンを押すまでかなりの時間がかかった。
毎日、納得がいくまで、自動でしまってしまうエレベーターの扉と格闘していたのだ。
エレベーターが1機使えなくなることを多少不便だなと思いつつも、こだわりのきつさを知っているから自分でどうにかできたら世話無いよねとUさんに心の中でかげながら共感していた。
施設側も大きな支障がなかったからかもしれないが、Uさんのこだわりを咎めることはなかった。
私が利用していた施設ではひきこもり歴13年の自分ですら存在感がかすんでしまうほど、キャラクターが豊かな人たちがたくさんいた。
施設にきた当初、1人エレベーターに乗っていたとき、くまのプーさんみたいに赤いTシャツをきて、恰幅のよいロマンスグレーの短髪の男性が乗ってきた。
雪駄をひきずってゆっくりと歩き、瞼はほとんど閉じられていて寝ているのかなとも思えるくらい。
エレベーターの中で、となりに立つ彼を横目でみると物が置けるのではないかとおもうくらいお腹が出ている。
彼はこちらを気にしているようすは微塵もない。
なんだかバス停でトトロの横にたっているサツキになったような気分だった。
プーさんやトトロをほうふつとさせるMさんはエントランスの売店にあるアイスクリームが入ってあるボックスをじっとながめていたり、エントランスに置かれていた椅子で眠っていたり(目をとじていただけで起きていたのかもしれない)していた。
そんなMさんがデイケアのプログラムで卓球をするときは別人のように、目をみひらき強烈なサーブを打ったときは驚きだった。
今振り返ってみると、実家から出て初めて過ごす場所がそこでよかったと思う。
そこでは、ひきこもりだった自分を否定されるということがなかった。
言いかえると自分がマイノリティだと意識させられる場面が少なかった。
だから、大気圏に降る隕石のように地上に降りる前に燃え尽きてしまうようなことがなかったのかもしれない。
実家を出てからすぐのころは、とにかく社会になじまなければ、適応しなければと緊張しっぱなしだった。
普通でいなければという呪縛が強くあって、常に気を張って一日の終わりはくたくたになっていた。
例えば、子どものとき以来の買い物では、レジで支払いをするとき、自分が入国検査を受けるパスポートを偽造した不法入国者にでもなったような気分だった。
すばやくそこを通過したいため、小銭ではなく紙幣で支払いをすませた。
財布の小銭入れはすぐにパンパンになった。
また、「ポイントカードをつくりますか」ときかれても「いいえ」と断った。
必要事項を記入する際などに、戸惑ったりしたら怪しまれる気がしたからだった。
また、市役所にいったり、郵便局へいったり、乗り物を含めた公共機関を利用することに強い苦手意識があった。
そこでは当たり前、普通であること、常識を有していることが強く望まれる気がしたからだ。
そういった公的な場所に行くというのは、当時の自分にとっては大イベントで、なにかのついでにこなすみたいなのりで行えるものではなかった。
次の日に大事な試合を控えているスポーツ選手ばりに自分のコンディションを一生懸命整えていたように思う。
当時の自分は普通の人やマジョリティの人に対する幻想を抱いていた。
その幻想と自分を比較して自分のことを自分で貶めてもいた。
普通の人は、人づきあいの場面でこんなふうに悩まない、こんなふうに落ち込んだりしない、こんなふうに緊張もしないのだろうと、普通の人を完ぺきな人として想定していた。
そんなだから、自分に対する評価は常に減点方式で、点が減らされないようにいつも緊張していたのだった。
それでもデイケアやまわりにいた人たちと過ごすことで普通でなければという呪縛がほんの少しだけれど緩んでいったようにも思う。
言い方がすごく難しいのだけれど、その施設にいる人たちは、私が思い描く普通の人からは少し離れたところにいる人たちだった。
私はどこか普通であることが幸せの前提条件のように捉えていたけれど、そんなことはなかった。
彼らは普通にこだわっていた自分よりも、よっぽど自然に笑っていたし、堂々としているように私には見えた。
けれどやはりどうしても普通にこだわっていしまっている自分がいて、彼らに憧れる反面、彼らから距離をとろうとしてしまう自分もいたのも事実だった。
そんなふうだから、どこにいてもどこか肩身が狭いような感覚があった。
普通にもなれないし、彼らみたいにも笑えない。
自分の立ち位置がとても中途半端で、どこにも所属できていないような心細さが常にあったと思う。
普通なんてない。
きっとそうなんだろうとは頭ではわかっているつもりだった。
それでも、「普通」は砂漠の中の蜃気楼みたいに渇きをいやしてくれるオアシスを私のまえにちらつかせ続けていた。「普通」を求めれば求めるほどに砂漠の真ん中に迷い込むようでもあった。
宮崎にいた頃の自分を振り返ると、アクセルとブレーキを同時に踏み込んでいるような状態だったのだと思う。
社会で生きるなら適応しなきゃいけない。適応するとは普通に近づくこと、そんなふうに思っていた。
でも、適応しようと思うことは適応できていない自分を否定し続けることのように感じられた。
否定し続けた先に何が残るのだろうか。
そんな疑問や葛藤を抱きながらも、日々の生活や目の前のタスクをこなすことに手一杯で立ち止まる暇がなかった。
宮崎に来てから数か月後の秋ごろに通信制の高校に入学したり、学校の先生の紹介で市が行う学習支援を利用させてもらったり、自動車免許取得のために自動車学校に通ったりと目まぐるしい日々を過ごした。
よくもわるくもそこには流れができていた。
それはひきこもっていたあの部屋、停滞、断絶を絵に描いたようなあの場所にはなかったものだ。
流れにのるのはある意味では楽でもあった。
タスクをこなす達成感のようなものもあったのも事実だ。
向かう先はこっちの方向で良いのだろうかという戸惑いつつも、方向の正否はわからないけれど進んでいる、動いているという感覚にどこか安心や期待を持っていた。
とにかく動き続けたら、今抱えているモヤモヤも、もう少ししたら解消されるかもしれない。
そんなふうに考えて気を紛らわせた。
とにかく行けるところまでいくしかない。
そう自分にそう言い聞かせていた。
夕食の時間。
フッと深呼吸とため息の中間みたいな息を吐いて、自室の扉を開ける。
廊下をぬけてエレベーターホールで立ち止まる。
いつものように見上げる。
エレベーターは上の階で止まっている。
誰にというわけでもなく、今日のメニューはなんだろうね、と問いかける。
おいしいものだと良いね。
私は階段で2階まで降りていく。
ひきこもり歴13年から今にいたるまで⑪
終わり
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
