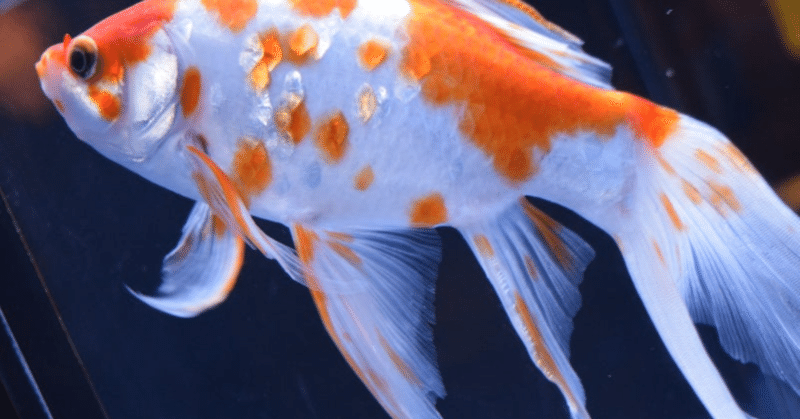2022年7月の記事一覧
そして、戦争が終わる
「戦争と愛は似ている」
「どこが?」
「いつもこの世界のどこかで、戦争をしているし、いつもこの世界のどこかで、愛が交わされている」
彼女は臨時ニュースで終戦を知った。国中のテレビがひとりの男の顔を映し出していた。男は言った。「戦争は終わりました」気だるい午後。
彼女は思った。終わったんだ。戦争は終わった。とはいえ、戦争は彼女の生活になんの変化も与えなていなかったのだ。戦争中も、彼女はそれまでと
きみは炭酸が飲めない
燦々と照りつける太陽、青く晴れ渡った空、モクモクと湧き立つ入道雲、「あちー」って暑いのわかりきってるのに言う感じ、プールの匂い、奥歯にしみるガリガリ君、あとで気だるくなるのがわかってるのに入らずにいられない海、頭がキーンとなるかき氷、なにかが起こる予感だけはするお祭り、浴衣、縁日、ドキドキワクワク花火大会。夏だ。心躍る夏。楽しいことめじろ押しの予感しかしない。
よろしい。留保が必要だ。
もし
わたしは死んだことがない
休日の朝、彼女は遅く起きてきた。前までなら、休日であっても早起きしてきていた彼女だけれど、ここのところは仕事がなかなかに忙しいらしく、昼近くまで寝ていることが多くなった。ぼくもそれについてはとやかく言わない。とやかく言える立場でもない。
「世界が」と、まだ寝起きで寝ぼけまなこの彼女はつぶやいた。「滅んでしまったの?」
「え?」ぼくは読んでいた新聞から顔を上げ、彼女を見た。ぼんやりと窓の方を見てい