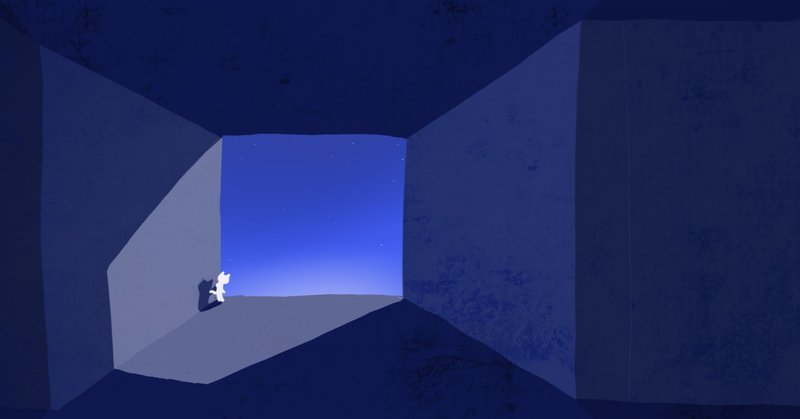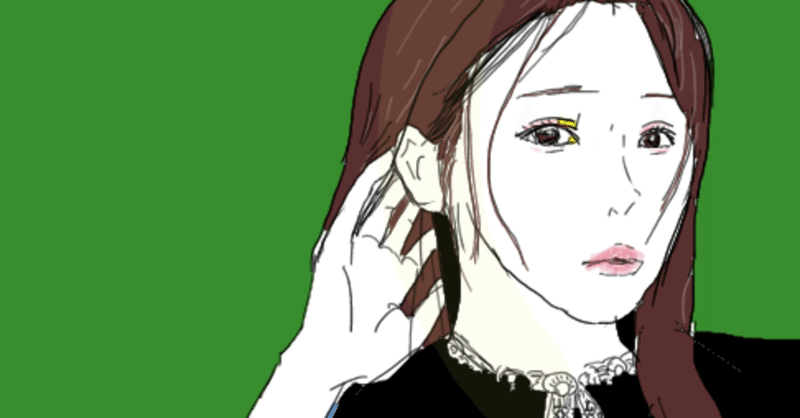2020年9月の記事一覧
ぼくらはどこにも行けない
昔、猫も杓子もタクシーに乗るものだから、タクシーがなかなか捕まらないという時代があった。もちろん、電車やバスという公共交通機関が存在しなかったわけではない。それはちゃんと存在したし、いまと変わらずに動いていた。電車やバスの交通網の整っているのになぜタクシーかと言うと、そういった公共の移動手段が終わってしまうまで飲んでいるだけ、世の中の多くの人の羽振りが良かったからで、そこでタクシーで帰ろうと考え
もっとみるわたしたちは愛を知らない
彼女のことを人に話すとき、わたしが彼女のことを「姉」と言うのは、ただなんとなくその方がわたしにとってしっくりくるからというだけで、実際のところ、わたしと彼女は双子であり、生年月日はまったく一緒、現実として産声を上げたのはせいぜい数十分の差でしかないだろうし、それだってわたしと彼女のどっちが先にこの世に出て来たのか、正直なところわからない。わたしたちは一卵性双生児で、姿かたちはまったく一緒、親でも
もっとみる誰も泣かないし、誰も笑わない
雪が降っていた。音も立てずにそれは白く積もっていった。積もった雪は溶けることなく積もり続けた。季節外れの雪。もしかしたら、それは雪ではなくて灰なのかもしれない。すべて死に絶えてしまったかのように静かだった。事実、町は死に絶えたも同然だった。いや、町はいままさに死のうとしているのだ。
男は扉を閉め、鍵穴に鍵を差し込もうとして苦笑いした。もう二度と戻って来ないところの戸締まりを気にかけるなんて馬鹿
そして、世界は滅亡する
すべては終わってしまった。ふたりの奮闘努力の甲斐もなく、世界は滅亡することが決定した。彼らになら、それを回避に導くことが可能だったのだが、残念ながらそう上手く事は運ばなかったのだ。映画や小説のように、タイムリミットぎりぎりで助かるなんてのは現実にはなかなか無いことだ。そう都合よくはいかない。電車の扉が目の前で閉まった経験を持つ人は多いだろう。まあ、世の中そんなものだ。そして、決定は決定である。変
もっとみるTHE WORLD IS MINE
男は死に瀕していた。それは男自身にもわかっていた。男は荒く、しかし弱い呼吸をしていた。足掻くことすらできなかった。どうにか生にしがみつこうとしたかったが、その力自体が、男の身体の中には残されていなかった。それは徐々に熱を失おうとしていた。ただの物体になろうとしていた。
男の傍らに悪魔が現れた。悪魔は男の耳元に口を寄せた。
「お前は死ぬだろう」悪魔は言った。
「だろうな」と男は答えた。
「お前の