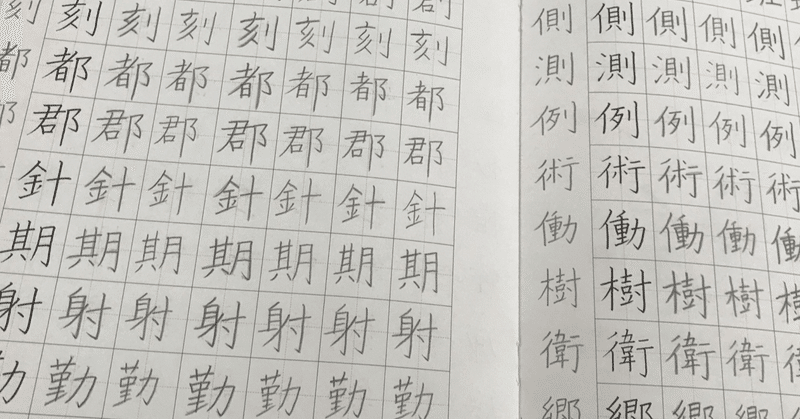
「せいsfれじおっrの権を他人に握らせるな!」
こんばんは、しめじです。
こういうのをきっかけに、もっと「言葉の読み方」にライトが当たるといいなあと思います。
この記事では、「せいさい」は慣用的な読み方としてという前提付きで許容されてもよいのでは、という形でプロの説明が引用されています。
私も同感です。基本的には生ー殺の対義ペアで熟語になっているので、あくまで「せいさつ」が本来かなあ、と思います。
ただ、「じゅうふく」や「そうきゅう」のように、慣用的な読み方が急速に普及している例も今現在に存在しますし、「でつぞう(捏造)」「しょうこう(消耗)」のように、本来の読み方が完全に失われているケースも多々存在します。
その点、たしかによく言われるように「言葉は生き物」なのだろうと思いますが、だから無反省に、無節操に「本来」が失われて良いものでもない、とも思います。
理由は、言語がそもそも同じ言語文化に属する人の間でのコミュニケーションを担保する道具だから。
つまり、ころころ変わって「通じない人」と「通じる人」の分化が進むのは、言語の持つ本来の役割を考えれば望ましくはない、ということです。
そして、今は大量の言語情報が飛び交う時代。
さらに、SNSによって、言語知識が乏しい人もそうでない人も、同じ規模で自分の発した言葉を流通させることができます。
加えて、これはあくまで私の肌感覚ですが、新しい言葉や言語表現の隆盛と消滅のサイクルは、インターネットメディアの普及によって、著しく加速しています。
ノーブレーキで言語変化を是としてしまうのは、ちょっと危ないのかな、と思います。
世代を大きくまたいだコミュニケーションが、行えるけど行わないことと、行えないから行わないことは、別です。
そのあたりは、私達みたいな職業の人間が、新しく手に入れた感情に名前をつけるという、若者のみずみずしい行為はちゃんと尊重しつつも、世代間の言語的断絶は産まないようにブレーキを掛けていかなきゃ行かないんだろうと思います。(それは、語彙レベルではなく、作法のレベルで)
「微動だ」って何よ。
こういう、「正しい日本語」の話になると、よく話題にあがるものの中に、
間、髪を入れず
とか、
怒髪 天を衝く
とかがあります。
(ちなみに、「雨垂石を穿つ」を、「雨垂石」という石だと思っていた、という人にもあったことがあります。なるほど。)
要するに、「切り方がわからない」ということなんだと思うんですが。
発音とかを聞く限り、結構切れ目を勘違いしている人が多いのではないか、と思うことばがもう一つあります。
「微動だにしない」
これを、「微動だ」にしない、と思しき言い方をする人がそこそこ居るように思います。
正しく単語ごとにわけると、「微動 だに し ない」ですね。
この「だに」は、文語で「〜でさえ」というような意味があります。
つまり、「微かな動きさえしない」わけですから、「全く動かない」という意味になるわけです。
口喧しく思われそうだから、ちょっと言いにくい。
こういうふうに、言い方が引っかかることって職業柄どうしても多いわけですが、実はちょっと言いにくいな、って思っています。
なんだか、口喧しく思われそうだからです。
いわゆる、「言葉遣い警察」みたいな感じに思われても嫌だな、と。
ただ、最近、流石に指摘してしまった出来事が。
先日、入試の準備で、担当者で集まって出願者名簿の点検をしていました。
その中で、エクセルのデータ入力ミスと思しき、別の受験生のセルに同じ住所が入ってしまっている箇所が。
その報告を受けた校長が、
「そうきゅうにじゅうふくが無いか確認してください」と。
流石に言ってしまいました。
ま、そういうこともあります。
では、今夜はこの辺で。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
