
祖母のおかしみ
母方の祖母は、なんかおかしみのある人間だ。
年末年始などで、実家に人が集まり、リビングがいつもより賑やかになると、私はそっとリビングからカウンターキッチンに移動して、母が料理をしている後ろの椅子のみんなの死角で、特に手伝いもせず座っているのだが、数分後、おばあちゃんもちょっといたずらっ子のような笑みを浮かべてカウンターキッチンにやってきた。
そして、「逃げてきた」と言って、そこでじっとしていた。
逃げてきた二人を知らないうちに匿うことになっている母の背中を見ながら、自分と祖母の共通点に少しおかしくなった。
8年くらい前までは、私の中でおばあちゃんはおばあちゃんだった。
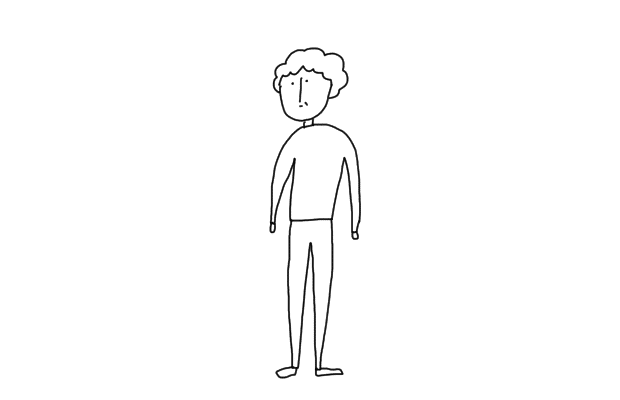
絵本に出てくるような、ある日おばあさんが、のおばあさん。が、自分のおばあちゃん。という認識。
たまに会って、笑顔で話しかけてくれる、よく知らない人物という印象だった。
だからたまにお小遣いをもらって、母から「おばあちゃんにありがとうの電話しなさい」と言われても、かける勇気が出るまでに時間がかかったし、かけても、特に話すことがなく、「ありがとう」「いいえ〜また来てね」「うん」くらいの、定型文を話すだけで、これで本当にいいんだろうかと思っていた。これで正解なんだろうか…?みんなはおばあちゃんと何を話しているんだろう…?と不安であった。
謎の多い人物ではあったが、うっすらと、なんかおかしみのある人物なのでは…?とは、小さい頃から思っていた。
おばあちゃんは読書家で、小学生だった私にたくさん本を貸してくれたが、その貸してくれる本が、
女性弁護士が活躍する海外ミステリー「天使の自立」(人が拷問されたりする)
とか、
解離性同一性障害を持った実在する人物の話「24人のビリー・ミリガン」(人が虐待されたりする)
とかなどであった。
初手で小学生に貸す…?
どっちも上下巻あったし。
よく読み切ったと思う。
貸してくれた中で、一番衝撃だったのは「本当は恐ろしいグリム童話」という本だ。
タイトルにあるとおり、本当に恐ろしく、最悪な気分になったのを覚えている。
「これ面白かったで。」と言って貸してくれたのも覚えている。
最後まで読んでない。
私はこの本で初めて「グロ」というジャンルに触れた。
グロはおばあちゃんが教えてくれた。
これも私が小学三年生くらいの頃、その当時は鹿児島に住んでいたおばあちゃんに、姉と二人で会いに行った。
私は初日から、食事の際、全員分の味噌汁をつぐことを率先して行っていた。
母から、おばあちゃんの手伝いをしなさいと言われていたし、帰ったときに姉に「手伝ってなかったで。」と告げ口されることを避けるため、味噌汁をつぐという簡単な仕事で手伝いポイントを稼いでいたのだ。
二日目くらいだろうか、朝の味噌汁をついでいると、おばあちゃんがやってきて「味噌汁はおばあちゃんが、つごか。」と言った。
私はついでいた味噌汁のお椀が手から取り上げられていくのを見ながら、「なんで?」と言った。今日は特に、我ながらきれいにつげた味噌汁であったので、不満な疑問であった。

おばあちゃんは、おたまも取り上げながら「ももちゃんの味噌汁は汁が多い。」と言った。
私は相当にびっくりした。目が本当に丸くなった。
まさかのダメ出しである。
二日目で。早。
私はびっくりしながらも、なぜかダメ出しをされたことに焦りながら、「だって、味噌汁やん!!!汁やから、汁多いのは当たり前や!」と叫んだ。
おばあちゃんはただ子供が無邪気に叫んでいるだけ。というような平和な顔で笑いながら、「汁ばーっかりや。」と追い打ちをかけ、味噌汁をつぎ続けた。
私は丸くした目を戻す冷静さもなく、手ぶらでテーブルに戻りながら、自分が小学三年生であることを確認せずにはいられなかった。
小学三年生の自分の手伝いは全て手放しで称賛されるものと思っていたからだ。祖母なら余計にだ。
祖母は孫に優しいんじゃなかったか?と、考えながら、具がいっぱいの味噌汁が運ばれてくるのを見届けて、祖母は孫に優しいというのは違う場合もある。ということを学んだ瞬間だった。
このように、私はちょこちょこ別角度から祖母にショックとおかしみを教えられていた。
そんなおばあちゃんが、8年ほど前に私の心のなかで「おばあさん」から「こたけ」(祖母の名前)になる出来事があった。
それは私が京都での一人暮らし生活をやめて大阪に戻り、お金がすっかんぴんの中、失業保険で暮らしているという寒々しい頃。
そんな、からっ風に吹かれているような私の様子を聞いた、当時鹿児島に住んでいたおばあちゃんが、「暇なんやったら1ヶ月くらい鹿児島来たら?」と言ってくれた。
私は緊張2:楽しみ98の気持ちで鹿児島に行った。
おばあちゃんの鹿児島の家は、「ぼくの夏休み2」を再現したような幸福度で存在していた。
大きな一軒家。目の前に畑。畳の部屋。土間。
縁側でスイカを食べた後、猫と昼寝をする時間。
おばあちゃんと私は、話したい時に話し、話さない時には話さなかった。
おばあちゃんは私に手伝いをしろと言わなかったけど、私がやりたいと言ったことはさせてくれた。
そんなのんびりした日々の中で、「服を作りたいな」という思いがふと立ち上がってきた。
京都の一人暮らし生活で枯れていた心に、久しぶりに宿った芽であった。
服を作ったことはもちろん無い。作り方も知らない。ミシンは小学生以来触っていない。そんな状態であったが、おばあちゃんに「服作ってみたい。」と言ってみた。
おばあちゃんは、ふ〜ん。というテンションで、「どんなの」と聞いた。
私は色鉛筆で描いた完成図を見せた。
それを見たおばあちゃんは、「ここからだったらどこどこで生地が買える」「バスに乗ってから電車に乗ったら着く◯◯というお店」「お店に着いたら店員さんに、ワンピース作りたいんですけど、どれくらいの長さを買ったらいいか、と聞くこと」など簡潔な説明とメモをくれて、簡潔なお小遣いをくれた。
そして、それ以外は何もせずにいてくれた。
私が銀色の布を無事に買って帰ってきた日の夜。
私の服作りの話から、おばあちゃんが昔、編み物をしていたことを話してくれた。
わざわざバスで都会の梅田まで出て、編み物教室に通っていたらしい。
私はその話を聞きながら、今の私と同じ歳くらいのおばあちゃんが、手提げカバンから編み物の棒をのぞかせながらバスに揺られる姿を想像した。
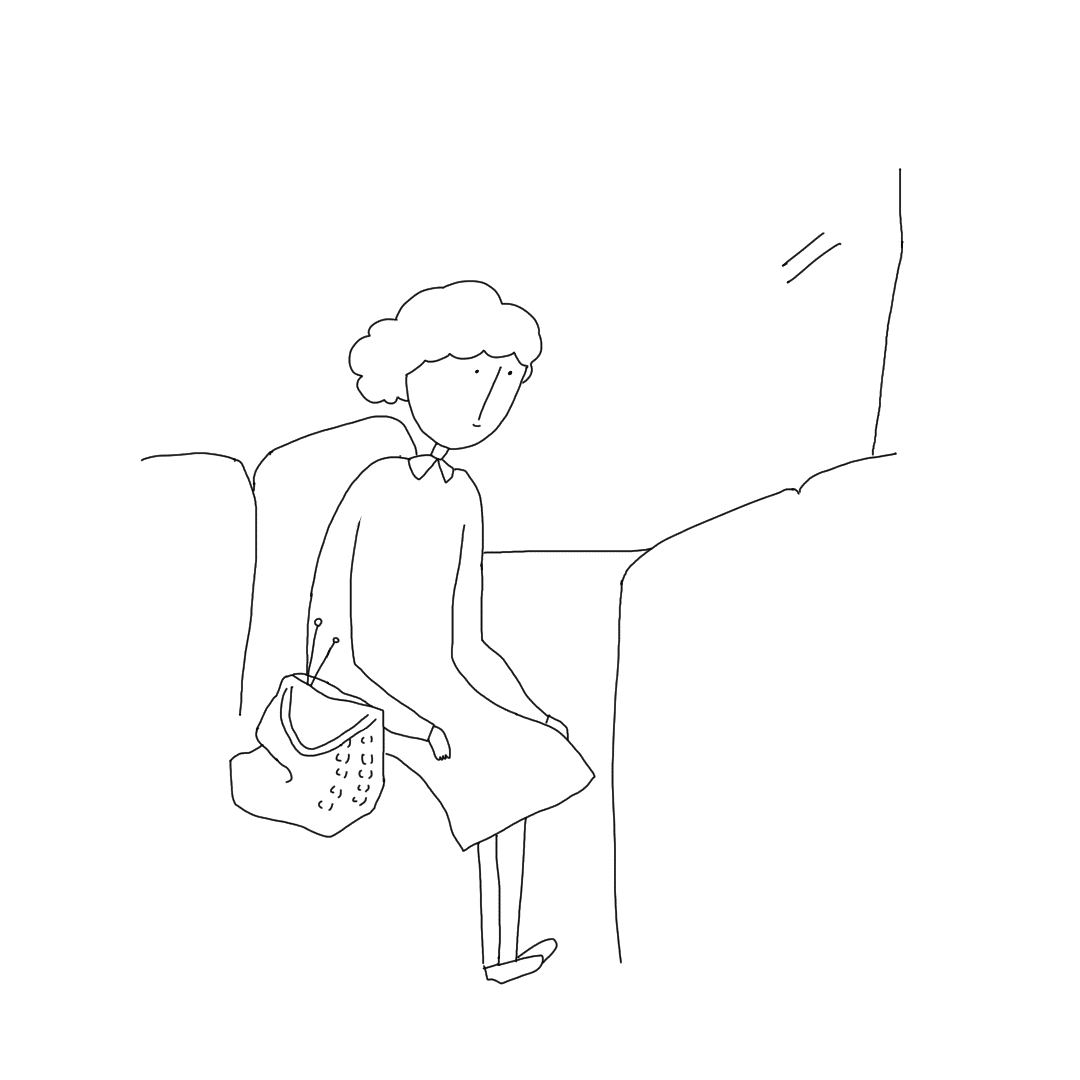
何年か通ったその教室の卒業制作かなにかで、毛糸で一から全身分の服を編んで、それを、作った本人が着てランウェイを歩く。という、楽しそうすぎる発表会があったらしい。
「本っっ当に恥ずかしかったで。」と、恥ずかしがり屋のおばあちゃんは笑って言っていた。
鹿児島から大阪に戻ったあと、毛糸の卒業制作のことをお母さんに聞くと、なんと、おばあちゃんはその作品で賞をもらっていたらしい。
一番の自慢どころを孫に言わずにいられるとは…と、改めておばあちゃんには感心させられる。
最近ふと、そのことを思い出したので、おばあちゃんに会った時に聞いてみた。
「おばあちゃん毛糸で賞取ったんやろ。」
「そうやで。」
「…。(すげぇ…)」
「でもな、その日授賞式もあったんやけどな、私そんな賞取るなんか思ってなかったからそのまま帰ってもうてん笑」
私はまたも驚かされたことに驚きながら、主役のいない授賞式と、そんなことも知らず今日の夕飯のことなどを考えながら家路についていたであろう当時のおばあちゃんのことを想像した。
現在のおばあちゃんを見ると、なにも気にせずいつもどおり飄々と笑っていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
