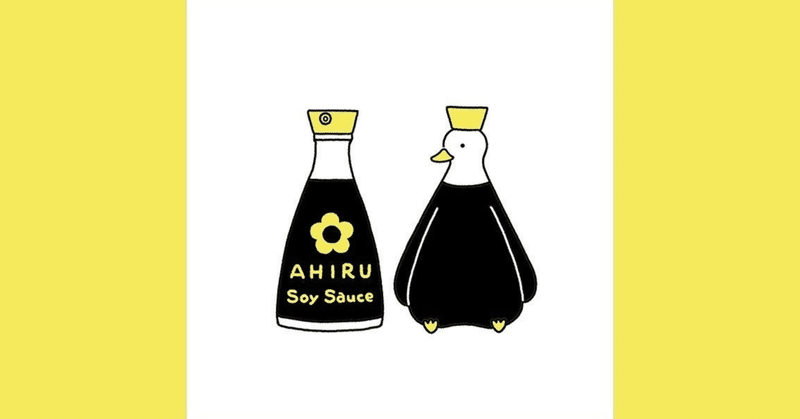
カナダで醤油を仕込んでみて
丸大豆醤油。
1990年。キッコーマンから特選丸大豆しょうゆが発売された。
わざわざ”丸大豆”と強調するその理由をつい最近まで知らなかった。
醤油の転換点は第二次世界大戦。
戦後生まれの私は、丸大豆醤油を味わうことなく育った。長年、実家で愛用している醤油は、脱脂加工大豆を使った製法のもの。丸大豆ではない。人工的な甘みも強め。その味に慣れ親しんでいるせいで、昔ながらの手法で丁寧に作られた醤油は「塩辛い」といって昭和一ケタ生まれの父でさえも嫌う。
***
2016年。発酵食品作りに目覚めた私は、長年実家に配達してくださっている造り醤油屋さんに足を運んだ。そして、天然醸造している醤油蔵を案内していただく。
昔ながらの大きな木桶に仕込まれ、静かに熟成を待つ。この立派な木桶は、今では手に入りにくく、修理出来る職人さんもいない。
見学した後でいろんな種類の醤油を味見させてもらった。初めてのことで、どれが美味いとか好みだとかよくわからなかった。一緒に行った母は「諸味の味がする!」と懐かしそうにしていた。
伝統的な作り方の醤油は諸味の味がしっかりとしていて味わい深く、人工的な甘みはない。だけど、その中にある天然の旨味が現代人にウケない。値段もさることながら、福岡では甘い醤油でないと売れない。
「醤油の味を決めるのは消費者だから」と職人さんは苦笑いしていた。
***
大豆、塩、水のみで仕込んだ豆味噌作りに大失敗して以来、豆麹作りは諦めていた。ふと、今年になって醤油用の麹で再チャレンジしてみたいという気持ちが湧いてきた。
茹でた大豆、砕いて炒った麦と醤油用の麹菌。麦が茹でた丸大豆の余分な水分を吸収していく。仕込んでから48時間後、緑色の胞子をつけた自家製醤油麹が出来上がった。

これを塩水とあわせて醤油に仕上げていく。

米麹も加えて自然な甘みがでないかの実験中
1年経過後に搾れば自家製醤油の出来上がり!
醤油ほど日本人の生活に入り込んだ調味料はない。にもかかわらず、それそのもののことをよく知らなかった。
自作してわかったことは、醤油麹に対して塩水の量が少ないということ。丸大豆と丸麦のエキスを凝縮して出来上がった液体は旨みの塊だということ。海塩を効かせることでミネラルも加わり保存性も上がる。減塩では無理。
丸大豆醤油とは、本来ハレの日に使う贅沢な調味料。
三十年の時を経て腑に落ちた。
サポートしていただきありがとうございます。そのお気持ちが投稿を続けるモチベーションになります。大事に使わせていただきます。 コメントはいつでもお気軽にどうぞ!
