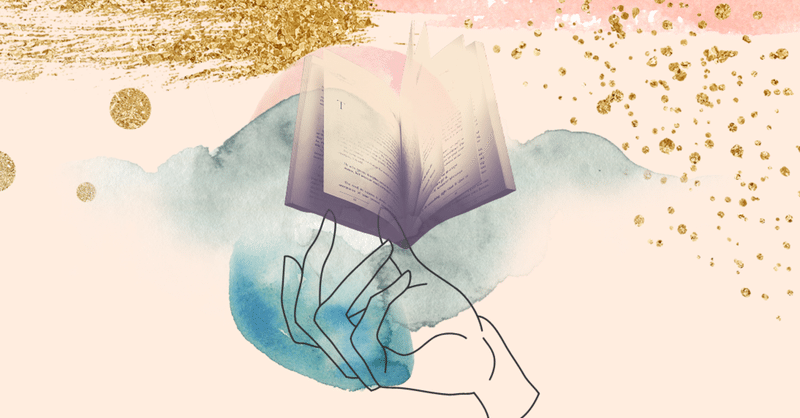
エッセイストのエッセンス #1
【この投稿の目的】
名乗ったからには勉強したいということで、少しずつ、エッセイを読んでいくメモ。不定期シリーズ化予定。
小川洋子・河合隼雄 『生きるとは、自分の物語をつくること』
えっ・・すでにタイトルが結論・・という感じもあります。表紙もとても落ち着いていて、経験したことはないけれど、精神内科のクリニックの待合室はこんな感じなのかなぁと思ってしまいました。
作品は、共著者どうしの対談を記したものでした。編集されて、ある意味では磨かれた言葉遣いになっていますが、どちらの方も、とても知識が深く、雑談に混じるお互いへの敬意が、とても心地よく感じる作品でした。巻末には「少し長すぎるあとがき」と題した、小川洋子による対談の回想録が記載されていました。
少し、印象深い発言を置いておきます。
本来ならば、ある程度の文脈を得なければ、発言の意図が伝わりにくいとわかっているのですが、平たく言って、臨床心理学者と小説家がお互いの仕事の内容を対談している、そんな対談の中で発せられた言葉です。
河合
自分の意図を超えた面白さが上手い具合に入ってこそ、良い作品になるんやと思います。思ってる通りに書けてもオモロないでしょう。(p21)
ふむふむ、僕も感じていますが、テーマを意識して書くよりも、まずは書きたいエピソードを書き出していくと、なんだか自分でも予想していなかった展開になることがあります。
自分の中に、こんな考えが、こんな言葉がいたのか、と発見するような瞬間を何度も経験してきましたし、そういう経験を経た文章は、気に入っているものが多い気がします。
河合
それしかないっていうのは駄目なんです。そして、それはもう、すごく微妙なことなんです。(p51)
反応の種類がひとつでは、とても危ない。そして、種類が多くても、何を選ぶか、判断基準もとても微妙だということです。
なんとなく、この頃の日本語で、この限定した使い方が流行っているのか、語意を強める意味合いで使われることが多くて、僕は落ち着きません。
「推ししか勝たん」
「感謝しかない」
「新しい会長は○○さんしかいない」
ほんとうは違う、と個人的には思うのです。もっと複雑な感情もあって然るべきだし、いくつも候補があることは恥ずかしいことではないと、ぼんやり考えてしまいます。
なぜそんな表現が広がってしまったのかなぁと不安です。近視眼的というか、短絡的というか。
多くの選択肢を得ること、そしてその判断基準のようなものは、経験すると分かるのかもしれませんが、時間がかかりますし、かける必要もあるでしょう。そのためには、“それしかない”を疑うことを忘れないようにしたいと思うのです。
小川
矛盾との折り合いのつけ方にこそ、その人の個性が発揮される。
河合
そしてその時には、自然科学じゃなくて、物語だとしか言いようがない。
小川
そこで個人を支えるのが物語なんですね。
河合
ええ。自然科学の成果はたとえば数式になったりして、みんなに通用するように均一に供給できる。そして、それで個が生きるから、物語になるんだっていうのが、僕の考え方です。(p106)
個と物語の関わりを、見事に描写されていて、何度も読み返しました。現実逃避に必要だから物語を得るのではなくて、むしろ現実に生きるための物語を拠り所にする。
エッセイがある意味では物語であることを考えたとき、大前提として「生きなきゃ駄目」なんだなと。個性を物語化する時には、死は一つの結末として用意されているものであり、死から先への物語はあり得ないということになります。
作中に「ヴェルテルは死んだけれどゲーテは長生きした」という示唆的な発言があります。とても高度な冗談という向きもありますが、個としての自分と物語、その境目が見えなくなると、自らの命を落としてしまう原因になってしまう、と危惧している部分でもあります。
河合は、小説家は物語を書いても何も起こらないけれど、臨床心理士は目の前にいる人への言葉かけを間違えると死んでしまうかも知れない。それでも、生きていくための物語を見つけてもらうための努力をするのだと言うのです。
自らの物語を見つける・・これは、おそらく自分のやりたいことだとか夢だとか将来のこともあるとは思うのですが、むしろ過去をしっかりと見つめ直すことで、今の自分の場所やこの先進んでいくであろう道が見えてくるのだと言うことなのかなと思って読みました。
エッセイは物語です。でも、それが本当に自分の物語と言えるのか、もっと自分の中にある感情とか言葉とかを深く掘ってみたい意欲が出てきました。そして、読んでくださった方が、物語として楽しんでくれるような、そんな工夫ももっと勉強しなくちゃなぁと思ったのでした。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました! サポートは、子どもたちのおやつ代に充てます。 創作大賞2024への応募作品はこちらから!なにとぞ! https://note.com/monbon/n/n6c2960e1d348
