
小説 「長い旅路」 38(最終話)
38.旅の果て
俺は、再び檜村さんの世話になって、玄さんの勤務先で働くことが正式に決まった。身分としては前職と同じ「福祉サービスの利用者」ではあるが、れっきとした雇用契約を結んでいる。
ここも椎茸の栽培工場だが、前のところとは設備が全く違う。あちらは窓の無い地下室で栽培が行われ、収穫物はエレベーターで上層階に運ばれてパック詰めされていた。ここは、郊外にある広い敷地に専用のハウスが10棟も並び、その中に山ほど菌床が並んでいる。ハウスで収穫された椎茸は人力で作業小屋まで運ばれ、パックや袋に詰められる。工場というより、農場だ。
利用者への指導の仕方も、まるで違った。あちらでは、新人はまずパック詰めとシール貼りを教わる。菌床のある階層で働けるのは、ごく限られた『エリート』だけだった。しかし、ここでは応募前に5日間の体験実習があり、その時点で真っ先にハウスへ案内され、膨大な量の椎茸の収穫と運搬で初日が終わった。2日目以降も、ハウス内での水仕事に終始し、出荷に向けたパック詰めに関わったのは最終日だけだった。
現場で菌床から生えている椎茸が、どのように収穫され、運ばれ、選別されて冷蔵され、商品となっていくのか……一連の流れを見ることができ、すごく解りやすかった。また、収穫だけではない菌床そのものの管理方法については、その時初めて知った。
働いている人々も、明らかに労働意欲に溢れていた。独り言が止まらない人や、極端に怒りっぽいような人も中には居るが、それでも皆が真面目に、そして誇りを持って職務に勤しんでいるのが伝わってきた。中でも特に印象的だったのが、片麻痺の人達が平然と「肉体労働」をこなしている姿だった。収穫物を満載した、誰もが両手で持つような重いカゴを、彼らは悠々と片手で持ち、台車の上に積み上げ、作業所へ運んでいく。床掃除の際も箒や水切りを難なく使いこなし、また、彼らは然るべき装具があれば、走ることさえ出来るのだ。(前の作業所なら、片麻痺に限らず身体障害のある人は座り仕事しか与えられていなかった。)
ここでは業務そのものが「作業療法」を兼ねているのではないかと思った。
勤務初日から、俺は「玄ちゃんが連れてきた後輩」として温かく迎えられた。体験時にも顔を合わせていた人達なので、さほど緊張はしなかった。特に、50〜60代と思われる人達とは、安心して話せた。
俺の苗字が体験時とは違うことについて、やはり初めは「結婚したの!?」と驚かれたが、俺は「父親が変わりました」と答えた。先輩方はそれを聴いて訝しむことは一切なく、さほど珍しくはない「母親の再婚に伴う改姓」と解釈したようだった。妙な勘繰りをしてくる人は1人も居なかった。
実は、体験時には既に養子縁組の手続きは済んでいて、戸籍上の氏名は「小野田 和真」だった。しかし、実際に就職できるか定かではない上に、唯一の知人である玄さんにもそのことを伝えていなかったため、俺は無粋な詮索を恐れて「体験中だけは旧姓を名乗りたい」と願い出たのだった。(体験中は賃金が発生しないためか、会社側はあっさりと要求を受け入れてくれた。)
朝礼の後、小野田 和真としての初仕事は、収穫だった。園芸用の鋏と、虫眼鏡のような形をした、収穫すべき大きさを示す針金で作った輪を携え、数人の同僚と共に、指定されたハウスへ向かう。
この会社では指導員(通称・職員)にだけ男女共通の制服があり、利用者に支給されるのは社名が入った帽子のみだ。(よく目立つオレンジ色で、後ろ半分がメッシュになっているキャップだ。)それさえ被っておけば、あとは何を着用しても良い。作業内容に応じて、エプロンを着けたり、合羽を着たり、履き物を何度も替えたりすることが想定されるため、そのような規定になっているのだが、中には個人的にこだわりのある服装のまま、頑なに着替えない人も居る。それも含めて「自由」である。
椎茸の生育状況に合わせた空調は、人間には少し寒い。俺は、この場所で着るために買ったウィンドブレーカーと、マフラー代わりのタオルで寒さを凌ぎながら、黙々と椎茸の軸を切り続けた。笠が針金の輪より大きければ軸を根元から切り、S字フックで棚に引っ掛けた手提げカゴへ入れる……そのカゴが一杯になれば、台車に載せてある運搬用のトレーへ移しに行く。そのトレーが積み上がり、140cmくらいにまで到達したら、作業場に運び、入れ換えに空のトレーを持ってくる。
それが、延々と繰り返される。
始業から1時間近く経った頃、視界がみるみるうちに白くなり、ほのかに灯油の匂いがし始めた。とはいえ、決して危険な状況ではない。誰かが、高圧洗浄機で菌床の洗浄を始めたのだ。冷温下で熱湯が噴射されるため、ハウス全体が真っ白になるほどの蒸気が発生するのである。
これが始まると、一転してハウス内は暖かくなる。この「温度変化」も、椎茸の成長に欠かせない「刺激」となる。
今日の洗浄担当者は、漁師が着るような青色の厚い合羽に身を包んだ玄さんだった。菌床は一つの棚に150個近くは並んでいるはずだが、彼の、見るからに洗練された動きによって、カビに侵されていたものが皆みるみるうちに綺麗になっていく。思わず見入ってしまう。
俺は昔、似たような機械で、廃鶏を出し終えて空になった鶏舎を洗っていた。その作業の基礎を教えてくれた人は……もちろん、亡き恩師・隆一さんである。
遠き日の思い出が蘇り、涙が滲む。
俺が手を止めて突っ立っていることに気付いた玄さんが、銃器のような先端部(通称・ガン)を素早く操作し、噴き出す湯を止めた。
「どうしたの?……通りたい?」
「い、いいえ……!ただ、あの……見学を……!」
洗浄機の電源は入ったままなので、近くまで行けば かなりの音がする。俺の声は、彼に届いただろうか?
「洗浄に興味があるの?」
「む、昔!こういうの……やって、ました……!」
「良いねぇ!!即戦力だ!」
この状況下でも、会話が成立した。
そのやりとりが、短い休憩時間の間に職員へ伝わり、俺はその日の午後から、洗浄に挑戦することになった。あくまでも短時間の「挑戦」なので、服は替えない。濡れることは避けられない作業ではあるが……着替えなら持参している。
濃紺で統一された作業着と帽子、そして背中に大きく社名の入ったオレンジ色の上着が、職員達の「正装」だった。その格好の若い男性職員から、高圧洗浄機の使い方と洗浄の仕方・目的を教わった。明らかに歳下と思われる彼は懇切丁寧に実演をしてみせながら、必要に応じてB5サイズくらいのホワイトボードに手順や留意点を書き起こしてくれた。俺はそれを「ありがたい」と感じると同時に「当たり前だろう」とも思った。前職での馬鹿馬鹿しい日々が、少し頭をよぎった。
満を持して、俺がガンを手に取り、熱湯の噴射と菌床の洗浄を始めると、職員の彼は「さすが経験者!」と声をあげ、朗らかに笑った。そして、しばらく見守った後、問題無さそうだと判断したのか、俺に、1棚分が終わったら声をかけに来るようにと筆談で指示して、その場を離れた。
俺は、そのハウス内で独りになった。
本体の形は全く違うが、洗浄機は洗浄機だ。ガンの扱い方は、体が覚えている。
熱湯の噴射によって表面に生えていた青カビ・白カビは順調に剥がれ落ち、水分を吸った菌床は黒く染まっていく。この黒い色が重要で、洗い方が甘ければ、すぐに乾いて褐色に戻ってしまう。それでは菌床内部が温まらない。菌床は洗浄後2日間冷水に浸けるのだが、内部が温かい状態のものを冷やすからこそ、意味があるのだ。表面のカビさえ落ちれば良いわけではない。
小さな生き物を一頭一頭、洗って、温めてやるような気持ちで……丹念にガン先端のノズルを動かしていると、遠い昔の光景が、次々と脳裏に蘇ってきた。
隆一さんのもとで仕事の基礎を学び、高圧洗浄機に限らず、刈払機や丸鋸など、様々な機械の使い方や整備を教わっていた頃……日々、胸が高鳴って止まなかった頃の、大切な思い出だ。決して消えることは無い。……彼が、天に召されようとも。俺がこの世に在る限り、彼の教えは、必ず活きる。
活かしてみせる。
約束の1棚分を終えても、俺は職員のところへ行かなかった。隆一さんへの報告が先だった。
「俺……俺、出来ました!もう一度!」
ノズルからの噴射をやめても、ガンを掴んだまま、気がつくと叫んでいた。
「貴方から教わったこと……体が覚えています!!」
顔を含む、ほとんど全身がびしょ濡れだ。帽子のつばから、湯が滴り落ちてくる。
視界が、ぼやける。
「貴方は!……間違いなく、あそこに居ました!!」
頬や額を伝ってくる水は、まるで海辺のような匂いがする。やがて、鼻が詰まってくる。……理由は解っている。
「そして、俺は!確かに貴方の部下でした!!」
応えは無いが、それでもいい。俺がこの場で口に出したことが【事実】である……それだけで、充分だ。
あそこは、正に地獄のような場所であった。だが、やはりどうしても彼との記憶だけは尊いのだ。
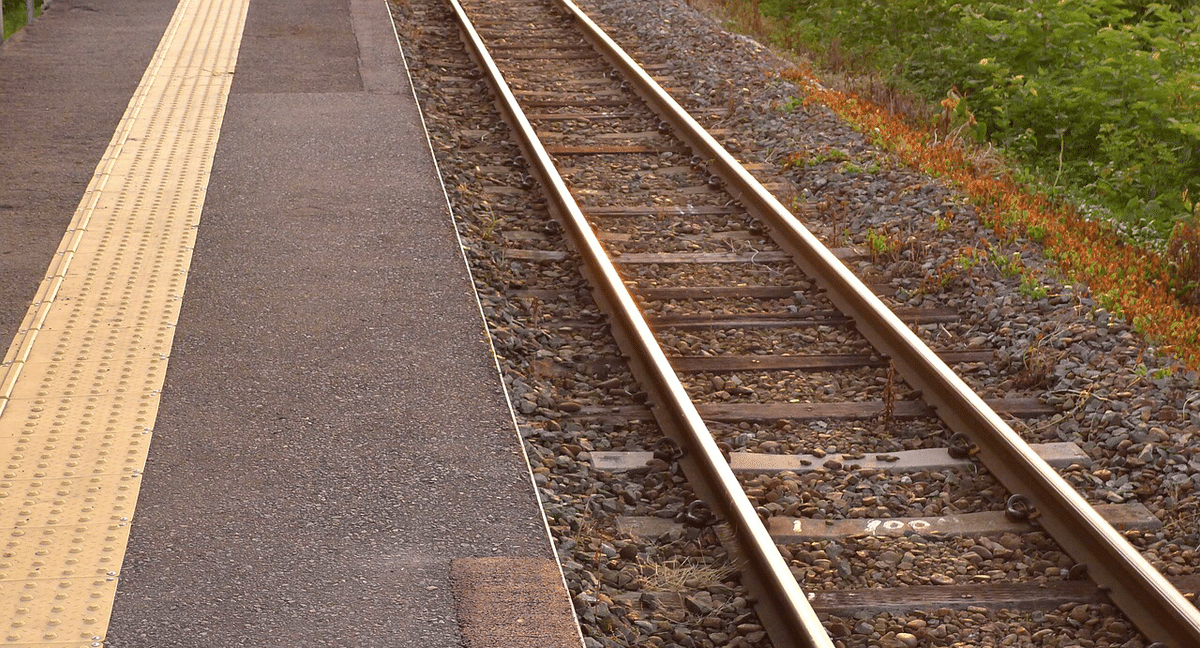
無事に初日の業務が終わり、俺は同じ電車に乗って帰る玄さんと共に、駅のホームでベンチに座っていた。彼は「小腹が空いた」と言って、前日にスーパーで買ったという大きな おにぎりを食べ始め、俺は その様子を眺めつつ、恒毅さんに「今から帰る」という旨のLINEを送っていた。
ふと、玄さんが言った。
「和真くんも、意外に大きな声を出すんだねぇ」
「え?あ、はい。た、た、たまには……」
洗浄機の側で声を張った時のことだろう。
「先生か……誰かに、報告をしていたでしょう?」
そう言われた瞬間、頭が真っ白になりそうだった。
(あれを、聴かれていたのか!!?)
ハウスの外にまで漏れるほどの声量だったとは、自覚していなかった。だとすれば、何人に聞かれていただろう!?
俺が羞恥心に駆られ狼狽えていると、玄さんはおにぎりを片手に、少し慌てたように上体を泳がせた。
「いや、別に……おかしくはないと思うよ。僕も、家でなら、よくやるから。……天国にいる先生に、つい話しかけちゃうんだ」
彼は空いていた手で頭を掻きながらそう言った後、すぐに「あ、吉岡先生じゃないよ?別の人!」と補足した。
彼が言っている行動は、きっと遺影や仏壇の前でのみ行われることであって、常識の範囲内なのだろう。彼は、俺のように故人の【声】までは聴いていないだろう。
玄さんは、俺の狼狽ぶりを気にしない。
「僕に『働き方』を教えてくれた先生。もう……20年くらい前に、亡くなったんだけど。ほとんど毎日、話しかけてる気がする。お供えもするし」
義理堅く、信心深い、素晴らしい人ではないか。
「和真くんにも、大好きな先生が居たんだね」
この俺を奇異の目で見ない彼の存在は、本当にありがたい。
何も応えられずにいると、唐突に、男性の叫び声らしきものが聞こえた。ひったくりか、それとも喧嘩でも始まったのかと、緊張しつつ そちらを見ると、リュックを背負った男性が、頭を掻きむしりながら誰も居ない空間に向かって叫んでいた。誰かと通話ができるような機器は見当たらない。そして、何かに対して激怒しているらしい彼は、まだ名前は憶えていないが、同じ作業所で働く仲間だというのは判った。やがて、彼は俺でも聴き取れるほどの大声で段取りに対する不満を叫びながら、俺達の前を足早に通り過ぎ、階段を降りていった。
俺は彼のことが心配だったが、玄さんは落ち着き払っている。
「……大丈夫だよ。ああいう人も居るから。少しくらい大きな声を出したって、誰も気にしないさ」
素晴らしい職場に巡り逢えた。
玄さんとは途中の駅で別れ、俺は無事に家まで帰り着いた。真っ先に洗濯機のある脱衣所へ行き、リュックの中でビニール袋に入れて帰ってきた ずぶ濡れの作業着を放り込む。今日のように、ハウス内で濡れた菌床に触れていた時間が長い日は、持ち帰った服から木酢液のような匂いがする。(きちんとした消臭効果のある洗剤で洗えば消える。)
洗濯機を回し始めたらリビングに向かう。その際には必ず台所の入り口近くを通るので、恒毅さんが奥に居るかを見る。
俺の初出勤に合わせて休みを取ってくれた彼は、予想通り台所に居て、洗ったばかりのフライパンを火にかけて乾かしていた。そして、俺に気付くなり「おかえり!」と声をあげ、こちらへ来いと言わんばかりに手招きをした。
素直にそちらへ行くと、調理台の上に、何やら高級感漂う鶏卵用の紙パックが置かれていることに気が付いた。
「見て、和真!ほら、烏骨鶏の卵!!」
彼はパックのラベルに印刷された文字を指でなぞってから、慎重に開封して蓋を開けた。
淡いベージュ色の殻をした小さな卵が8個、姿を現わした。紛うことなき烏骨鶏卵だ。
「これ、すごく高いやつです……!」
俺がそう言うと、彼は得意げに胸を張った。
「可愛い『息子』の、就職祝いだからね!!奮発したよ!!」
彼は縁組を機に、嬉々として「父親ぶる」ようになった。しかし、2人きりの時にやるそれは、幼児の「おままごと」に近い戯れなのだ。(逆に、病院等で「養父です」と名乗り出る時は、至って大真面目な面持ちと心境である。年齢差を理由に訝しがられても、動じない。)
「今日は、これでオムレツを作るよ!」
「お願いします」
俺の応えに、彼は途端にむすっとして「いつまで敬語なんだ、此奴は」と言い、決して痛くはない力加減で俺の頬をつねった。(こんなことは、よくある。)
解放されてから、俺は「このほうが精神的に安定します」と答えた。彼は、いかにも芝居っぽく「ならば仕方ない」と言って、大事な卵のうちの一つをボウルに割り入れた。
濃いオレンジ色の、見事な卵黄だ。烏骨鶏卵は、卵自体は一般的な鶏卵よりも小さいのだが、逆に卵黄は大きい。
「おぉー」
彼が小さな歓声をあげる。
俺は、調理の邪魔にならないよう寝室へ引っ込む。通勤着から部屋着へ着替えたい、というのもある。

夕食の時間だ。いつものように、2人並んで食卓につく。俺が左側、彼が右側だ。食事中に正面となる位置にテレビがあって、必ず字幕付きで視聴する。音量は彼の好みに合わせる。
2人揃って「いただきます」を言い、迷わずメインディッシュから食べ始める。
彼が作るオムレツは、いつだって美味い。きちんと濡れ布巾を用意して、ほとんどプロと変わらない手順と速さで作るためか、焦げるということが無い。だが、今日のは卵からして素晴らしいのだから、美味くないわけがない。
美味いものを食べながら、信頼できるパートナーと、何の気兼ねもなく話をして、自由に喜怒哀楽を表現する。そんな時間が、幸せだ。
かつての俺は「大切な人のために生命を賭すこと」を、勇ましい、讃えるべき事だと思っていた。だが、今は「大切な人と、共に生きる」という喜びを、何よりも大切に感じている。
随分と遠回りをしたが、俺は、人として当たり前の暮らしを、やっと始められた。
この幸せが、一日も長く続くよう……祈ると共に、自分にできることを、探し続けたい。
【完】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
