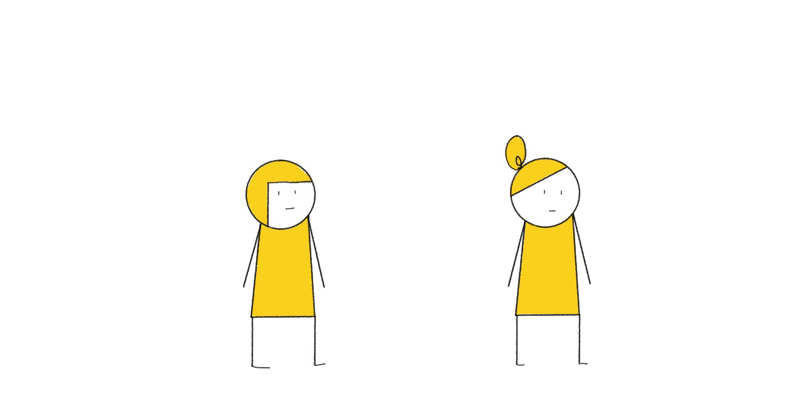
「つきあいづらい人」だと気づいてみると
先日、本を読んでいたら「つきあいづらい人」にはこんな傾向があるよ、と書いてあった。
ちなみに次のような傾向ですって👇
・実は何かしらコンプレックスを抱えている
・人とコミュニケーションをとるのが苦手
・伝える能力がない(ことを自分でもわかっている)ので、伝わらないとつい、自分自身の不甲斐なさを相手に対する怒りに置き換えてしまう
・自己表現が得意ではない
・怖そうに見えて、意外に脆い
本はコチラ👇
著者の印南さんが知り合いの女性から「職場の先輩が怖い」という話を受けて、「つきあいづらい人」ってどこの職場にもいるよね、と書かれていて、あぁ・・わかる・・と共感。
そして「つきあいづらい人」の傾向を読みながら、あれ?私もしかして全部当てはまってるのでは??と気づいて、ちょっとうろたえた。
自分が「つきあいづらい人」だと薄々ながら気づいてはいたのだけど、印南さんの本を読み、特に気になったのが
・伝える能力がない(ことを自分でもわかっている)ので、伝わらないとつい、自分自身の不甲斐なさを相手に対する怒りに置き換えてしまう
この部分。
自分自身の不甲斐なさを、相手に対する怒りに置き換えてたんだ!!
そうか、相手に対する怒りは、自分自身の不甲斐なさを隠すためだったのか!!と衝撃を受けた。
伝えることが下手なことは自覚していたのだけど、悪くない相手に自分の身勝手さで怒りをぶつけていたという事実に気がついてみると、まさしくその通りな状況を何度も経験していたことを思い出して悶絶するかと思った。
伝え方が悪いのは自分なのに、伝わらないことで怒るなんて、怒りをぶつけられたほうは理不尽な思いを抱いていたに違いない。
特に夫には理不尽な怒りを日々ぶつけまくっていると思うので、本当に申し訳ないことをしたと謝りたい。ごめん。
*
そんな最近の読書は『不安なモンロー、捨てられないウォーホル』。
マリリン・モンローは境界性パーソナリティー障害だったのではないか。
アインシュタインは自閉症スペクトラムだったのではないか。
過去の偉人たちにも「生きづらさ」があり、その「生きづらさ」を現代の医学で考えてみると、「うつ病」「不安症」「依存症」などに当てはまる、といった内容の本だった。
しかし障害についてはまだ未知の部分もあるため、偉人たちが本当にその障害を抱えていたのかは謎。
自分で「依存症です」と宣言している人もいるけれど、現在でも過去でも、そうやって自分のことを理解できている人のほうが稀なんだろうなと思ったりした。
マリリン・モンローは生存中に、医師から診断をくだされている他の病名があるけれど、それは間違いだったのではないかと本にはあって、しかし現代であっても診断名は医師によって違うというのが私個人の見解としてある。
診断名よりも、まず本人にとってどんな治療がベストなのか、それを探ることが大事なんだろうなと思ってみたものの、しかし病院はそうやって個人に寄り添ってくれる場所なのか、私にはわからない。
医師による、という身も蓋もない感想が出たので本を閉じた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
