
学生時代に学んだ、建築設計の基礎
建築設計を仕事にするにあたって、今も実務で生きていることを思い返してみました。mocAでの設計で重要と考えていることの共有をしつつ、建築設計を目指す人にとっても参考になるところがあれば幸いです。
私が、学生時代に学んで良かったと思っていること、そして今も実務の根底にあることは、以下の4つです。
■ 学生時代に学んだ、建築設計の基礎
① コンセプトとカタチを一致させる重要さ
② 「アフォーダンス」という力の存在
③ 都市のイメージ (5つの街の要素)
④ 感動を生む五感を刺激する体験
逆に、会社で学んだ大きなものは以下の4つです。
■ 会社で学んだ、建築設計の基礎
Ⓐ コストを収める設計、対費用効果の高い設計
Ⓑ 建築法規の読み方、運用の仕方と、協議の仕方
Ⓒ モノの納まり
Ⓓ CAD・BIMの操作
大項目だけ見て気づく方もいらっしゃるかもしれませんが、学生時代に学ぶことは概念・理念的なことが多いです。社会人になると、日々の業務に忙殺されて、概念・理念・哲学的なことを一から考え直す時間を持てる人はなかなか少ないと思います。
つまり、学生時代に学ぶこと・考えることは、社会に出てからの基盤となるので、建築設計者・デザイナーにとってはとてつもなく重要な時期です。
学生時代に考えたことや、感動した体験をもとに、将来どういうものを目指したいのか蓄積していき、それを社会に出てから、現実世界に受け入れられる形で発揮するという2段階のステージが必要だと思っています。
もちろん、社会人になってから設計を目指す人もいて、中にはすごい実力を発揮する方もいらっしゃると思いますが、建築学科の課題に打ち込む学生の熱量はすさまじいので、それを超える熱量をもって日々の業務にあたりつつ、深堀りをしていくのはとてつもないエネルギーになることでしょう。
では、さっそくですが、本記事では①~④について書いていきたいと思います。
① コンセプトとカタチを一致させることの重要さ
「デザインでプロが心掛けていること」の記事でも取り上げましたが、私が学生時代に学んだ一番重要だと思うことは「① コンセプトとカタチを一致させることの重要さ」です。
別記事でも書いているのに、ここでもか!というのは理由があり、本当に重要と考えていることだからということと、実際、私も学生の時には、教授から口が酸っぱくなるほど、何度も叱られ、教えを頂いたことだからです。
これができないとデザイナーと名乗るには恥ずかしい、とまで言っても良いと思っています。

建築設計やプロダクトデザイナーは、もろに3次元のカタチを扱う職業です。2次元のデザインには2次元ならではのスキルや特徴があると思いますが、3次元のデザインは、立体的な形が持つ効果や意味、人への影響を理解した上で、コンセプトをカタチに置き換えるスキルが必須です。
大袈裟で単純な例でいうと、説明では「ゆったりと落ち着ける空間をつくりました」と言っているのに、使っている素材は「粗目の岩の自然素材」ばかりで、やわらかい素材が何もない、みたいなことですが、それだけ聞くと「そんなことする人いないのでは?」と思うかもしれませんが、実際には頻繁に目にする現象です。
当人によくよく聞いてみると、「いや、今回は岩の素材を使ってみたかったんです」と主観的な希望からカタチを作っているだけで、コンセプトに合致したものになっていない。着眼点や(無意識の)センスがよくても、プレゼンテーションにおいては、人に共感を得られるものになっていない、となるわけです。
すべての選択に対して、理屈付けを言葉でしないとだめだ、とまでは言いませんが(実際、それはとても難しいこともある)、大枠の道筋はコンセプトとカタチが一致してないと、「これは何ですか?」と聞かれたときに、トンチンカンな答えをしてしまい、共感を得ることができないデザイナーになってしまう、というわけです。
② 「アフォーダンス」という力の存在
では、説明とカタチを一致させるって、どうすればいいのか。
ひとつの回答が「アフォーダンスを知れば、どうカタチをつくればいいのかわかってくる」のですが、学生の時、初めてアフォーダンスを知った時は、目からウロコでした。
ギブソンという人が提唱した造語で、私の解釈で一言で言いかえると、「アフォーダンス」=「モノが人の行動・認知に与える潜在的な力」です。
事例を見てみましょう。
<1> タイルとタイルの目地
人は、目地に傘を立て掛けられると認知することがしばしば。=目地がアフォーダンスを持っていると言えます。

別の事例として、デザイナーの深澤直人さんは、アフォーダンスに着目して、下のような傘もデザインしています。傘の取ってに少し窪みがあるだけで、袋をひっかけられる、ひっかけたくなるミニマムなデザインです。

<2> ドアの押しプレート・押し棒・引き棒
ドアの押しプレート(下図左)は、押したい、押せる、と思いますよね。つまり、そのカタチが「押せるという認知」を誘発していると言えます。一方で、実は押し棒(下図右)は、それだけだと押すのか、手前に引くのか、右に引くのかわからないカタチです。そのため、「PUSH」や「PULL」をサインで併記するのが親切なデザインと言えます。

<3> 牛乳パックを捨て置きたくなる手摺の天端
手摺の天端は、牛乳パックを捨ておくために作られたものではありませんが、道にモノを捨てるとき、唐突に道路に投げ捨てるよりも、なんとなく、置ける場所につい置いてしまいますよね。(もちろんポイ捨て自体ダメですが)

このように、上記①②③はアフォーダンスのほんのシンプルな事例ですが、行動を誘発するカタチの持つ潜在的な力(アフォーダンス)は多岐にわたり、環境から人は常に様々なアフォーダンスをうけながら生きています。
全てを言語化するのは難しいですが、アフォーダンスを積極的に理解し、できるだけ意図的にデザインすると、深澤直人さんのデザインのように、洗練されたデザインになっていくと私は考えています。
③ 都市のイメージ (5つの街の要素)
学生時代に学んで今も生きる知識の3つ目は、「都市のイメージ」という本に書かれた内容で、人が認知する都市は、大きく分けて5つの要素から成るというものです。
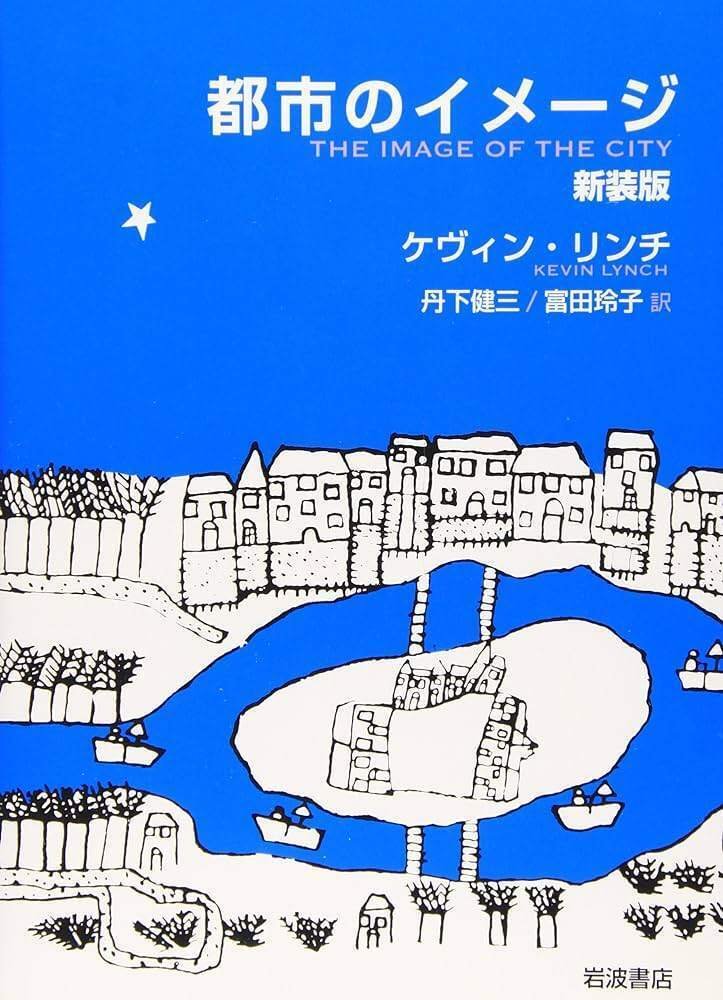
<1> パス →通り
<2> ランドマーク →目印
<3> ディストリクト →地域
<4> ノード →交差点など
<5> エッジ →川、土手・崖、高速道路など
なんのこっちゃ、と思うかもしれませんが
これを意識して街を眺めると、好きな街、魅力的なな街は、5つの要素の配置バランスが最高に良い、みたいなことがわかってきて、都市計画や街づくりに関わる人にとっては、必携書籍なんです。
例えば京都は、碁盤の目状の通り(パス)にはそれぞれ名前がつけられており、交差点(ノード)も通り✖️通りの名前でわかりやすく、また、交差点は建物が頑張って印象的なつくりになっている場所が多いです。時折スパイスのようにランドマークが散らばって、歩いていて飽きない。鴨川(エッジ)がいい具合に密集を回避して、街に濃淡を与えて、魅力的な街になっている。
などなど、生活するだけであれば、あえてそう難しく考える必要はないかもしれませんが、都市計画に関わる人にとっては、どうやって魅力的な街づくりをすれば良いか考える際の大きなヒントになります。
他にも、カナダのバンクーバーは比較的新しくつくられた街ですが、条例などの規制によって、意識的に5つの要素が配置された街づくりをしていました。意図的につくった通りに、狙い通りに人が歩いて動くのを見ると、基盤って大事だなと実感させられます。
④ 感動を生む五感を刺激する体験
最後に、学生の時に学んでよかったと思うことは、学生の時しかできない空間の実体験です。
社会人になってからも物理的には体験できるんですが、思い返しても今とは感受性が違う、と思います。あの時経験したからこそ、それが今も生きているのだと思います。
実際に訪れて感動した空間として、すぐにぱっと思い浮かぶ5つの空間を紹介します。
<1> ヨーロッパ諸国の教会

<2> トルコのカッパドキアの洞窟と岩肌



<3> ローマのパンテオン

<4> 京都 圓通寺の借景

<5> フィレンツェの屋根

私が5つの空間から学んだことは、
A 曲線美(アーチ・ドーム・自然造形)に人は惹かれる
B 水平垂直以外のカタチは、身体感覚を刺激する
C 圧倒的なスケール感、スケール感のメリハリに感動する
D 反復(リピート)による量感に感動する
E 全体として統一されていることに惹かれる
F 奥行き感(レイヤー・重層)を感じられるものに惹かれる
そして、これらの魅力を、現代建築に落とし込んだ最も良い例が、伊東豊雄さんの多摩美術大学の図書館だと思います。現代建築で自然と同じレベルで感動した現代建築は、これ以上ないかもしれません。同様に、SANAAの21世紀美術館も、上記の魅力で構成される建築だと思いました。
多摩美術大学の図書館 designed by 伊藤豊雄

人の行動に影響させる潜在的な力のことをアフォーダンスと呼んでいましたが、アフォーダンスは建築計画学のほんの一部でして、上記A~Fのように、心理的な影響を与える空間構成だったり、平面計画(ゾーニング)が人の行動与える影響だったり、人が複雑に世界を認知しているからこそ、空間やカタチも考え甲斐がある世界が広がっていると思います。
そう考えると、今後、VRなどのバーチャルな世界と現実が交わることで認知の幅が広がり、さらに新しい空間のあり方も出てくるかもしれませんね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
お問合せ
記事中の不明点がありましたら、お気軽にご連絡ください。
okamoto@mocadesignoffice.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
