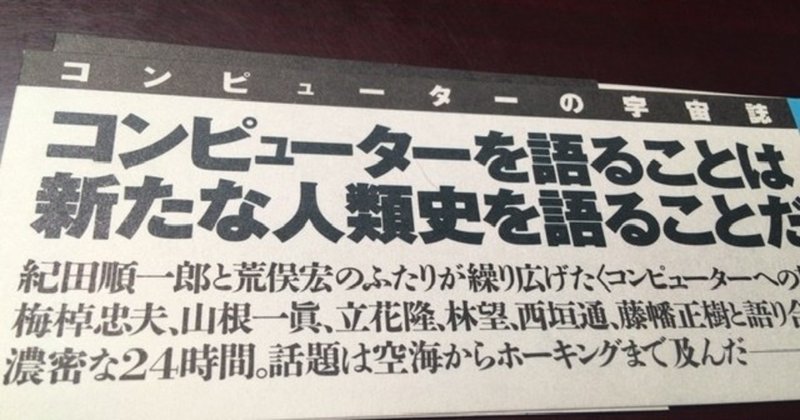
サブカル大蔵経351紀田順一郎/荒俣宏『コンピューターの宇宙誌』(ジャストシステム)
本書の登場人物たちをデジタル省大臣や有識者にしたらいいのにとこのご時世に再読してまず浮かびました。
〈ジャストシステム〉は出版もしていた。現代にもつながりのある本だ。登場人物のアップ写真が狂っていてすごい。本書も、紀田&荒俣の師弟コンビが、梅棹に会いに行って、この本は生まれたのだろう。


いわゆるデータと称して本や新聞をせっせと写している人がいますけれど、それはナンセンスです。そんなもの書いても何にもなりません。それより大事なのは、頭の中にパッとひらめいたことを定着させることです。/分類したら絶対ダメだ(笑)分類をやり始めたら収拾がつかなくなります。/分類と言うのは難しい。基本的に分類できないですね。(梅棹忠夫)p.34
せっせと書写している今の自分を否定しながら気にかけてくれている感じて嬉しい。分類ができない。つまり、分けられない時代。科学から博物へ戻り、智慧の世界か。

外国文献の索引の根源はやはりバイブルだと思うんですよ。牧師さんがお説教する場合も何章何節と明示しますね。ところが日本の仏教の経典はどこに何が書いてあるかわからないし、わからなくても意に介さないんですよね。その辺の風土の違いがどうしてもあると思います。p.43(紀田)
〈索引の思想〉を持たない日本。百人一首とか百鬼夜行とか、日本語や図象は索引しづらいかも。法話の時に、引用した言葉の典拠を伝えると、逆にあまり細かく言わない方がいいと、諭されたこともあります。どちらも一理あって興味深いです。
パソコンといった新しいツールが登場したために、博物学が持っていた方法論が見直されてきたんですね。(荒俣)p.114
データベースと博物学。
テープを聴き直すのは、時間がかかって困る。メモは一度相手の話を聞き、それを整理すると言う知的作業終えたものだから、情報の凝縮度が高い。(荒俣)p.129
今の自分がしていることは、まさにこのことなのかもしれません。
ものというのは、いくらどれほどの注意力を込めてにらんでも何もわからない。けれども、二つを並べて比べてみると、ちょっとした努力でものの本質がわかってくることが知れる。(林)p.165
本質のために比較する
日本では仏教を大衆化するためにテキストから離れ、西洋ではプロテスタント以来、テキストにもう一回即したというちがいは大きいですね。(荒俣)p.174
プロテスタントの聖書主義と仏教法話の味わい。語りの近似と違うんだなあ。牧師さんはあまり味わいしないのかも。僧侶は逆に好き勝手いい過ぎてるのかも。
丸暗記はそらんじる、心を空にする。メモリはフランス語のメモリエ、心を満たす。西洋と東洋で発想まるで違う(紀田)p.195
空の思想。密の思想。
空海は全てを集めましたが、すべてがわかったことにはなりませんでした。真言宗的叡智。「空を見ていると気持ちがいいね」すべてを知るということは、すべてを知らないというところに戻ってくる。ライプニッツはすべてを集めれば最初がわかる。西洋は完全を想定、日本では完全を考えていない。それがコンピュータに対する態度にも出てくると思います。(荒俣)p.202
ライプニッツと空海の情報編集。
アメリカでは、パソコンネットワークは、反権力という要素もかなりあります。(西垣透)p.205
ネトウヨにもつながる。
本を買って読みます。
