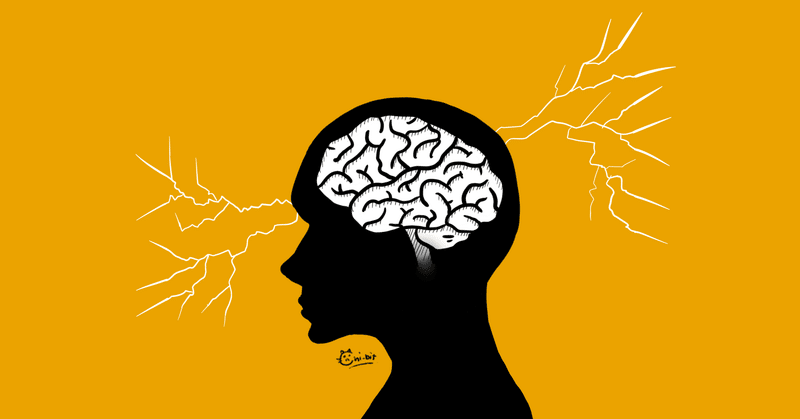
先の見えない不安を乗り切ろう!理論編
先が見えるという安心感
私たちは日々、人生の節目節目を頭の中に描きながら生きている。
妊娠している女性は9か月先を、大学生は4年後にくる就職の日を、大人はローンが払い終わるXデーを、どこか頭の片隅に置いている。
この「先を見据えて生きる」というのが重要な能力の1つであることは間違いない。この能力を使った方が物事は確実に上手くまわる。
「先を見据える」というのは、当然ながら「先が見渡せる」ことが前提となる。「一寸先は闇」という表現にもあるように、見えないことは私たちに恐怖心を与える。
そのことを痛感したのは、前回日本に帰国した時のある体験だった。
幼少期に頻繁に訪れた広島の宮島で大聖堂のお戒壇めぐりをした。本堂の地下、自分の指先も見えない真っ暗闇の中を手探りで歩いていくというものだ。
計ほんの10分もかからなかっただろうに「早く出口に着いてくれー」と祈るような気持ちで、一瞬たりとも足を床から離すことなく、一ミリ一ミリ、左右の壁を両手で確認しながら進んだのを覚えている。
まったくもっておかしな話だ。
お坊さんが足元にわざわざつまづくようなものを置くわけがない。わざわざ段差を付けるなんてこともあり得ない。それでも、段差に脚のスネをぶつけたら痛いだろうなという怖さが頭をよぎる。蜘蛛の巣にうっかり触れてしまうかもしれない。日本は世界一清潔な国なはず。本堂の地下だって絶対今朝清掃されたはずなのに。
頭ではわかっていても、腹の奥底に潜む不信がにょきっと顔を出してきて、引っ込まない。先が見えない時、思考は助けにならないのだと知った。
なぜ、先が見えないとこんなにも不安になるのか
私たち人間は、この世に生まれた瞬間、母親の子宮の中という、自分の力で呼吸することも食べることも必要ない、何もかもが満たされた天国から、人生という海に投げ込まれる。
それは今まで体験したことのない、空腹、眠さ、自分ではコントロールのしようがない感情の嵐が吹き荒れる太平洋みたいなものだろう。
そんな日々を、差し伸べられる救いの手によって生き延びていく。
果てしなく続くように思える空腹が満たされ、
寝落ちしてしまったら親が自分を担いでベッドへ運んでくれる。
そして、なんだかむしゃくしゃして泣きわめいてる時、親が辛抱強く耳を傾け、「そっか、悔しかったんだね、よしよし」と、訳のわからなかった感情を噛み砕き、その感情に名前をつけて消化しやすい形にして返してくれる。これがイギリス人精神分析家ウィルフレッド・ビオン(W. Bion)のいうところのアルファ要素だ。
その時、子供は「そうか、このよくわからなかった感情は悔しさだったんだ」とわかる。もう一度同じ気持ちを味わった時、それが悔しさなんだと自分でわかるようになる。そして、少しづつ自分で自分を慰められるようになる。
この外から与えられる「枠」が安心感を与えてくれる。
話を元に戻すと、先が見えるというのも、ある程度外から枠のようなものが与えられることだと言える。
道はすでに整頓されているし、道の先にゴールがあることはわかっている。
だから、走りやすい。その枠の中で安心して「先」へ向かって走れる。
逆をいうと、この枠がなくなった時、先が見えない時、私たちは大聖堂のお戒壇めぐり同様、赤ん坊の時に体験したような真っ暗闇の海に再び引き戻されるのだ。
これが、私たちが先が見えない状況で感じる不安ではないだろうか。
枠だらけの社会で我らが失うもの
この「枠」は我らにとってすでになくてはならないものとなった。
その象徴たるものとして、現代社会で何もかもが「可視化」される傾向にあることが浮かぶ。
だらだらと文字がひたすら並べられた文書は敬遠される。ストラクチャーがはっきりとし、チャートなどがついた記事は読み手が付きやすい。
セラピーにおいても、図にしてメカニズムを可視化し、セラピーの後に宿題を出し、確実に目に見える具体的なものを渡してくれる認知行動心理学は人気だ。
一方で、可視化しない、わかりやすくない、見えない精神分析的心理療法はウケない。
チャートも何も使わず、セラピストと対話をするだけという(感じがする)のは、患者さんにとってあまりにも不可視なのだ。一体今何をしているのかが掴みにくい。だから不安になる。
ただ、何もかもがわかりやすく可視化された「枠」だらけの社会に生きることによって我々が失うものがある。
そのひとつが、イギリス人精神分析家ドナルド・ウィニコット(D. Winnicott)がいうところのネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)ってやつだ。それは何かというと、
答えが出ない、先が見えない、はっきりしない状況を耐えることができる力
日本人は「耐える」のが得意だと私は思ってきた。本当にそのなのかわからない。何かに耐えて病気になるのは、コーピング (対処)できていると言えない。病気になることなく心のバランスを崩すことなく、先が見えない状況に耐えられる、これがネガティブ・ケイパビリティ。
では、これを持つ人と持たない人の差は何か?
ここで幼少期の親との関係まで言及するとさらに長文になってしまうので、個人レベルの話に限定する。
ネガティブ・ケイパビリティを助けるのは、自分で自分に枠を作ってあげるような、混沌とした情報や感情の嵐の中で、それを分類し、整理し、わかりやすくし、消化しやすくする力だと思う。つまり、赤ん坊に対して親が代わりにしてくれたことを自分で自分にしてあげる能力だ。
可視化やサービスが極限まで進んだ社会では、システムがこの役割を引き受ける。だから、個人の力は必要なくなる。
誤解をさけるために書くと、可視化やサービスが必ずしも悪いというわけではない。しかし、私たちは今、先が見えなくなったり、システムが機能しなくなることが、いとも簡単に起こりうると改めて知った。
だから、ここで一歩戻って、暗闇を歩くときのように、自分の足元に意識を集中させ、昔懐かしの人間の底力を再発掘する必要があるのではないかと思う。
理論的なことを長々と書いてしまった。次回は不安に効く今すぐできるセッションを紹介したいと思う。
最後まで読んでくださってありがとうございます。面白いと思ったらフォローしてくれると励みになります。ダンケシェーン。
サポートをよろしくお願いします。頂戴したサポートは、より面白い記事が書けるように、皆様のお役に立てるようになるため、主に本の費用に当てさせていただきます。
