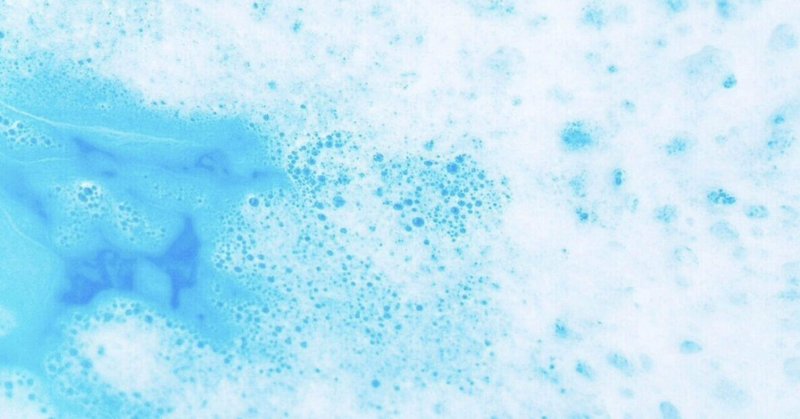
【#3】my rainy days/短編小説
一
向こうで君がホームランを打った音が聴こえて、カキーンと云うこだまを聴いていた。
「あ、いま赤星先生ホームラン打ったね」
と言った友達Aに対して僕は微笑って
「そうだね」
と相槌を打って伸びをした。
球技大会の日、僕達のクラスは初戦敗退して午前中からやることが無くなって欠伸を堪えていた。僕と友達AとBは校庭の鉄棒の前に屯って三角座りをしている二人を横目に、僕は地面に寝転んで頭の後ろで腕を組んでいた。そんな時、赤星先生が打った球が僕の青空を捉えていた視界に、白昼の流れ星みたいに大きな軌道を描いて流れていったのだった。
「先輩達がキャーキャー言ってるよ」
「うるさいなぁ」
と僕の味方をしてくれている友達AとBに対して、僕は鼻で笑った。
「これでもっとファンが増えるね」
と僕は言って、二十五歳にして男子高校生達の群衆の中をニヤけて満塁を踏みながら走っていく、その赤星先生と云うこの頃僕の世界の結晶になっている人物を眺めては、嘆息を漏らした。
赤星先生は完璧だった。元警察官で、そして今は教師で昔高校野球をしていて今は野球部の顧問をしていて、自信があって軸があってしっかりしていて度胸があって、完璧な中身を持ちながら、ガタイが良くて格好良くてイケメンで余裕があって、彼は校内の女子からの人気者だった。
彼が元バンドマンでドラムをしていたと云うことを授業で話すとそれが女子達のその日一日の主な話題となり、彼の元カノの名前が知られた日には同じ名前の女子を羨ましいと拝みに行く女子が絶えなかった。それぐらい、赤星先生は皆の注目の的だった。
彼の車の助手席ではなく後部座席に乗ったとき、彼はエルレの曲を掛けた。僕が幼い頃に解散したそのバンドは、邦ロックの世界では伝説みたいになっていて、バンドマンの大阪の彼氏の影響で邦ロックを聴き出した僕が、最近聴いていたバンドだった。
「エルレガーデンやん」
と僕が言うと赤星先生は
「知ってるん?」
と吃驚していた、それから共通の趣味が多かったり僕の好きな小説を彼が好きだったこともあり、意気投合した。
二
三年生の派手な女子達が赤星先生を囲っていて、友達AとBがそのハーレム状態に引いているのを見て、
「まぁ赤星くんの連絡先知ってるの僕だけだけどね〜」
と戯けて見せた。帰りの会が終わると僕は生徒会長をしていた男友達と談笑しながら、指定された掃除場所に行く、その時に三階のトイレ前を必然的に通るので、三階のトイレ掃除を担当している赤星先生と必然的にすれ違うのだ。僕はすれ違う度に赤星先生と何気ない談笑をして仲良くなった。
「この学校に来てまだ一ヶ月だけど名前と顔覚えたのお前だけだわー」
と他クラスの授業後に廊下で溜め息を零した先生に対して
「なんかあったら言ってよ、助けるから」
と僕は励ました。
全クラスの交流会も兼ねて名古屋への校外学習があったとき、クラスの担任もしていない赤星くんがピンチヒッターとして呼ばれた。彼は先生達からも期待されるくらい人気だった。
学年でカースト一位の四人組の中に居た僕は、ノリで赤星先生を誘って五人で集合写真を撮った。僕らは果てしなく自由で、高校二年生の身分ながら一時間の自由時間でタクシーに乗って何処までも冒険しようとして名古屋で有名な高級デパートまで行って、平日の昼から制服姿でウインドーショッピングをした。発想がもう陽キャだったと思う。
校外学習が終わって、休み時間に職員室に行った僕は赤星先生を呼び出した。集合写真を送りたいから連絡先を交換して欲しいと言った僕は、部活の顧問の先生とも連絡先を交換しているからと云う理由で説得して、なんとか連絡先を交換して貰った。
三
僕が気が付くと、赤星先生はベランダで煙草を吸っていた。窓をノックして彼が僕に気が付いて窓を開けると、彼は履いていたスリッパの片方を僕に貸してくれた。僕がベランダに出ると夜の景色が広がっていて、夜空は最高密度の黒色を保ちながらその中に大きな月だけが、街のネオンより明るく光彩を放ちながらポツンと浮かんでいた。
「吸うか?」
と吸いかけの煙草を僕に差し出した先生は苦笑いしていて、僕は返答に困った。
「いや、いい」
と断って僕はベランダから見える景色を見ていた。その時君が吸っていたメビウスのブルーベリーのオプションの煙草はその後の僕の人生を狂わすことになる、とは知らずに僕は唯その煙草の匂いを嗅いでいた。
無言で何も考えずに呆けていると、赤星先生は無言で僕の頭を撫でた。左を向くと、吸い殻を片手に前を見据えている彼の横顔が自然と月明かりに照らされていて、僕はその時初めて月が綺麗ですねの概念を知った。月が綺麗なんじゃなくて、月を見ている君の横顔が綺麗だったのだ。彼は相変わらず、零戦のパイロットのような面持ちで、険しい表情をしていた。
朝になり、また学校で会うのだけれどお別れして、帰りに自動販売機で僕はいろはすの水を買い、彼はコーラを買った。
「コーラ好きなの」
と聴くと彼は
「飲み物はコーラしか買わない」
と言ってお釣りを受け取っていた。
四
放課後、学年の人気者の友達Cに促され、僕は高校の近くの自動販売機で買ったコーラを赤星先生に渡しに行くことになった。職員室に行くと、赤星先生は野球部の練習で校庭に出ていて居ないと云うことだったので、筆箱から油性マジックを取り出しコーラのペットボトルに
『好きです(ハート)』
と書いて差し入れですと他の先生に渡して赤星先生のデスクに置いて貰った。コーラを飲むとペットボトルが透けて、油性マジックで書いた文字が浮き上がるのだ。
下駄箱で、退屈そうな友達Cを宥めながら正面玄関に出ると、スコールが降っていた。それは通り雨にしては粒が大きすぎて運動部の不幸を思った。そんな中、こちらに駆けてくる人影があって、頭を覆っていた腕を退かして僕達の姿を認めたとき、それが赤星先生だと悟った。
「大丈夫?」と僕が訊ねると、泥だらけのユニフォームをびしょびしょに濡らした彼は仄かに微笑った。
「……あ、職員室の机の上にコーラ置いといたから!」
と僕が勇気を振り絞って伝えると
「おぉ、サンキュ」
と彼は喜んで、気をつけてなと僕達を見送った。友達Cはニヤニヤしながら僕を肘で小突いていて、僕は頬を伝う雨が赤く熱くなった僕の頬を冷ましてくれるのが有り難かった。
それから些細な出来事で、僕達二人は七年間音信不通になるのだが、それはまた、別のお話——。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
