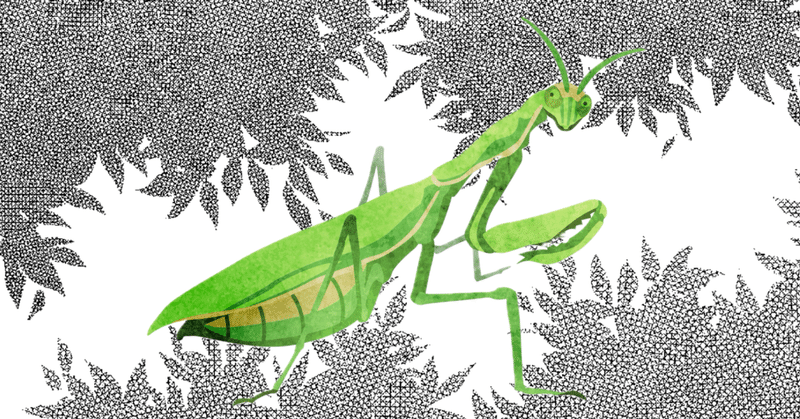
畑のお客さま。
二年生になってもうすぐ二ヶ月になる。新しいクラスにも、けっこう慣れた。なかよしののんちゃんとも同じクラスになので、つくしは毎日学校に行くのが楽しくてしかたがない。ある日、担任の先生が、
「そろそろ、宿題で日記を書かせようと思います」
といった。国語が大好きな先生は、子どもたちに作文を書かせるのも好きなのだ。
「えー!」
「いやだあ」
子どもたちが大きな声で反対した。先生は教室中を見わたしたあとニッコリ笑って、
「そんなに心配しなくてもだいじょうぶ。週に一回だけだから」
と言った。これからは毎週、月曜日に日記を出さなくちゃいけないらしい。
「お休みの日に身の回りで起きたことを、なんでもいいから書いてみてください」
放課後、つくしはのんちゃんと待ち合わせして商店街の文房具屋さんに出かけた。日記帳を買うためだ。
「ああ、ゆううつ」
つくしは、一年生の夏休みの絵日記のことを思い出していた。あれは本当に大変だった。お父さんもお母さんも、いつも通り仕事があるので、つくしは毎日学童保育に通っていた。そこで宿題をやって、マンガを読んで、友だちとトランプしたり、お絵かきをしたり、あばれたり。そして夕方には家に帰ってテレビを見る。同じことのくりかえしだから絵日記に書くことが見つからなかった。
お母さんは、
「同じことを書いたっていいのよ」
と言ったけど、そんなわけにはいかない。かっこうわるい気がしていやだったのだ。海に行ったとか、映画をみたとか、旅行に行ったとか、なにか特別なことを書くのが夏休みの絵日記のはずだと思っていた。それなのに、学童、家、学童、家のくりかえし。夏休みの終わりの三日間で、半分泣きながら、お母さんにも手伝ってもらって仕上げたのだった。
「考えただけで、むねがムカムカしてくる」
つくしがそう言うと、のんちゃんは、
「わたしは、ワンダフルのことでも書こうかな」
と、のんびり口調で言った。
「いいなあ、のんちゃんは。自分ちの犬のことなら、たくさん書けそうだもんね」
「うん。毎日ワンダフルと遊んでも、ちっともあきないし。書きたいこともいっぱいある」
のんちゃんは笑った。
文房具屋さんのたなには、何種類かの日記帳がならんでいた。お店のおばさんにたずねると、二年生の日記ならこれよと教えてくれた。
「三年生になったら、もっと行数の多いノートになるのよ」
つくしはパラパラとノートをめくってみた。
「うわ、こんなにたくさん書かなくちゃいけないの?」
一年生用の日記のように、上半分が絵のための空白にはなっていない日記帳は、ページいっぱい長い列があるだけ。これを全部、自分の字でうめなくちゃいけないなんて。つくしは頭はクラクラしてきた。
夜、お母さんに日記の話をすると、
「あらら、大変ね」
と面白がっているような反応だ。お父さんはノートを見て、
「こりゃ、こりゃあ」
と、片手でペタッと自分のひたいをたたいて見せた。
「一年間続いたら、将来は新聞記者かなんかに、なれるかもしれんぞ」
そんな風におだてられてもやる気は出てこない。書く材料さえれば、何とかなるかもしれないんだけど。そう思っていると、お母さんが週末にうら庭の畑の草取りをしてほしいと言い出した。
「梅雨に入る前に、夏の野菜の苗をいろいろ植えたいのよ。トマトときゅうりと、なすびも。夏野菜カレーの材料になるし。つくしも好きでしょ?」
「ええ、でも、わたしは食べる担当だけでいいよ」
「畑の草取りを手伝いましたって、日記に書けるじゃない。日記のネタだと思えばいいよ」
「地味なネタだなあ」
「うちにはそういうネタしかないの。あきらめなさい」
お母さんが、うら庭の手入れをするつもりなら、きっとお父さんも手伝わされるだろうし、家族でどこかにお出かけなんて予定も入らないだろうなと、つくしは思った。書くことが見つからなくてなやみ続けるより、書けるなにかがある方がマシかも。
「わかった、手伝うよ」
つくしは小さくため息をついた。
土曜日、学校は休みだというのに、つくしは朝早くから起こされた。
「つくし、起きなさい。草取りが待ってるよ」
「まだ八時すぎだよ。今日一日時間はあるんだから。昼からやるよ」
「何言ってるの。外はこんないい天気だし。昼間は暑くて外仕事なんてやってられないわよ。朝のすずしいうちに草をとって、畑を耕してしまわないと」
お母さんはやる気まんまんだ。今日と明日で、畑を耕して、肥料をまいて、来週には苗を植えつけるらしい。
「お父さんは、平日仕事で夜がおそいから、もうちょっと寝かせておいてあげたいのよ。つくしは先に始めておいて」
「いいなあ、わたしもやる」
妹の雪乃は、草取りを遊びとかんちがいしているようだ。
「雪乃はまだいいの。あとでお母さんといっしょにやろうね」
虫よけスプレーを手足にふりかけてもらって、大人用の大きな麦わらぼうしをかぶったつくしは、黄色い長ぐつをはいてうら庭に出た。自分の家の庭なのに、ふだん行くことはない。玄関からまっすぐ門を出て、学校に行くだけだから。長くつでカッポカッポと音を立てながら歩いていくと、庭には草がぼうぼうに生えていた。
「なんだこりゃ」
畑は一面みどり色、ほぼ雑草王国だ。後ろからスリッパをつっかけて、お母さんが追いかけて来た。
「ものおきの中に、バケツとかスコップとか入っているから。草の上の方だけとってもダメなのよ。根っこが残っていると、あとからまた生えてくるから。しっかり草取りしてね」
「はあい」
庭の真ん中あたりにしゃがみこんで、つくしは草取りを始めた。数日前に雨が降ったので、土の表面はまだ少ししめっている。それでもスコップを思いっきり差し込まないと、土の中までほりおこせない。かたいかたい。心の中でブツブツ言いながら、いつの間にか、つくしは草をほりおこすことに集中していた。ザクッ、ザクッ、ザクッ、ザクッ。土の中には、太い根っこがはりめぐらされている。土の表面をやわらかくほぐして、根もとをぎゅっと指先でつまんで、「エイヤッ」と力を込めてひっぱる。スポッと抜けると気持ちがいい。両手につけた軍手は、またたくまに土で茶色く汚れた。
ザクッ、ザクッ、ザクッ、ザクッ。
スポッ。
ザクッ、ザクッ、ザクッ、ザクッ。
スポッ。
しばらくすると、ぬいた草の小さな山があちこちに出来てきた。たまったらバケツに集めて、庭のはしっこまで持っていく。顔を地面にちかづけて作業していると、土のにおいがまわりにふわっと広がった。ほこりっぽいような、なつかしいようなにおい。やや大きめのクロアリが、あわてふためいてにげていく。土の中からひっぱり出されたミミズは、くねくねとねじれておどっているみたいに見えた。
雑草は少しずつ、少しずつ取りのぞかれ、だんだん畑はきれいになっていった。なんかすごいぞ、わたし。つくしがそう思っていると、
「まだまだ、へたっぴだな」
足元から声がした。カマキリだった。みどり色の小さなカマキリが、りょううでのカマをむねの前にちょこんとかまえて、つくしを見ていた。
「おまえ、草ぬき、はじめてなのか?」
カマキリが顔をななめにかたむけて、つくしにたずねた。
「はじめてじゃないよ。久しぶりなだけ」
カマキリの聞き方がえらそうなので、つくしはムッとした。
「おまえのぬき方、ダメだな。ここからちょっと先のばあさんなんてな、こしが曲がってても、そりゃあていねいに草をむしるぞ」
「どこのおばあさん?」
「ここから三けん先の家の、ばあさんだ」
ああ、さかもとさんのことだ。さかもとのおばあちゃんは一人暮らしをしていて、買い物は手押し車を使っている。あのおばあさん、畑仕事もしてるんだ。つくしはそんなこと、知らなかった。
「あのばあさんの畑じゃ、きっとおいしい野菜がとれるぞ」
カマキリは、右にゆれ、左にゆれながら、そう言った。
「どうして分かるのよ?」
つくしが食ってかかるように言うと、
「はたけの土を大事にしているからさ」
当たり前のことを聞くなと言わんばかりに、カマキリが答えた。
「土は、植物たちのねどこなんだ。土を大事にしている畑では、野菜はのびのび育つ」
「わたしだって、おいしい野菜がとれるようにと思って、せっせと雑草ぬいてるよ」
つくしは、ほっぺをふくらませた。
「うそをつけ。おまえはただ、草を引きぬくのを楽しんでるだけだ」
カマキリがぴしゃりと言った。
「いい土になれ、いい土になれって気持ちがないとダメなんだ」
休みの日に、朝から一人で庭の手伝いをがんばっているのに。こんな小さなカマキリにしかられることなんて、何一つしていないのに。つくしは腹が立って仕方がなかった。
「よう、何してるんだい?」
別の声が聞こえて、つくしとカマキリがふりかえると、ちょうどトンボがとんできたところだった。
「ほう、子どもが畑で草ぬきなんて、感心だな」
トンボは、しばらく空中にじっととどまるように浮かんでいた。それからひょいと、つくしのかぶっている麦わらぼうしの上にとまった。
「トンボ君、あんまりこの子をちやほやしない方がいいよ」
カマキリが、きつい調子で言った。
「お手伝いしてるってだけで大きな顔する、なまいきな子どもなんだ」
トンボは、カマキリの意見を聞いて、ふふんと鼻で笑った。
「なあに、子どものうちは周りがほめてやって、もっとがんばろうと思わせてやればいいじゃないか」
トンボはつくしのことを、それなりに認めてくれているようだ。
「オレたちの、もっと昔のご祖先さまたちがこの辺りをとび回っていた時代には、子どもといえども田んぼの仕事は、なんでも手伝っていたと聞いている。ところが近頃は、田んぼってものが姿を消してしまって。子どもたちはヒマな時間を勉強しろだの外で遊べだの、あれこれ言われているらしいぜ」
トンボは、人間のことをよく知っているようだった。つくしは目玉をキョロキョロ上に向けて、頭の上からふってくるトンボの話に耳をかたむけた。
「こんな小さな畑の草むしりだとしても、この子にとって、そりゃあ大事なお手伝いなんだから、オレたちがおうえんしてやればいいじゃないか」
カマキリは、だまってカマをむねの前にかまえたまま、また右に、左にゆれていた。
「おやおや、よそ者が、勝手なことばかり言ってるよ」
今度はおばあさんのようなダミ声が、物干しざおのあたりからひびいてきた。みんながいっせいにそちらをみると、物干しざおのつつの入り口に、茶色のかたまりが見えた。カエルだった。
「この子はいつも家の手伝いなんか、やっちゃいないよ」
カエルに言われて、つくしはドキンとした。それは本当のことだ。
「この庭に毎日やってくるのは、この子の母親だけだよ」
カエルはつくしの家のうら庭で長く暮らしているらしい。
「母親は、いつもせんたくものを干したり、畑を耕したり、いそがしそうに行ったり来たりしているよ」
ほかのみんなは、だまりこんでしまった。
「あんたたちがやって来て、いらぬ口をはさむものだから、草ぬきの作業がほったらかしになってるじゃないか。さあ、さっさと続きを始めな」
カエルがそう言うと、トンボはサッと麦わらぼうしの上からとび立って、どこかに行ってしまい、カマキリは、小さくぴょんぴょんとはねて、草むらの中に消えていった。カエルは、物干しざおの奥の方に、引っ込んでしまった。つくしは、また一人になって草ぬきを始めた。
ザクッ、ザクッ、ザクッ、ザクッ。
スポッ。
ザクッ、ザクッ、ザクッ、ザクッ。
スポッ。
なあんだ。草を一本、一本、ぬきながら、つくしは思った。
「だれもわたしのことなんて見てないと思っていたのに。生き物たちにしっかり見られてたんだ」
そう思うと、つくしは背筋をしゃんと伸ばしたい気持ちになった。
「これを日記に書いても、きっと作り話だと思われちゃうな」
つくしは少しガッカリした。
「でも、いいや。日記のネタになる以上に面白かったから」
この夏は、お母さんの野菜作りのお手伝いもやってみようとつくしは思った。わたしが手伝ったら、去年よりもっとおいしい野菜ができるはず。そう思うとワクワクした。
昼ごはんの後、今度はお父さんがうら庭に出て作業をする番だ。
「つくしはどうした?午前中、一人で草ぬきがんばったんだろ?」
リビングにつくしの姿は見えない。お父さんがお母さんにたずねた。
「うん、そう。すごくがんばってくれたの」
お母さんが昼ごはんの後片づけをしながら、ふふふと笑った。
「がんばりすぎて、疲れたみたい。昼前にカルピスを一気にのみほして、そのまま部屋でねてるわ、ごはんも食べないで」
「そうか、そうか。じゃあ、次はオレの番だな」
お父さんは、ジャージ姿で頭をタオルでまいてから、りょうてを前後左右にふりまわし、やる気をアピールした。それから、
「まあ、今日の夜はつくしは日記を書けそうだな」
と言って、よっこらしょと玄関を出ていった。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。サポートしていただけるなら、執筆費用に充てさせていただきます。皆さまの応援が励みになります。宜しくお願いいたします。
