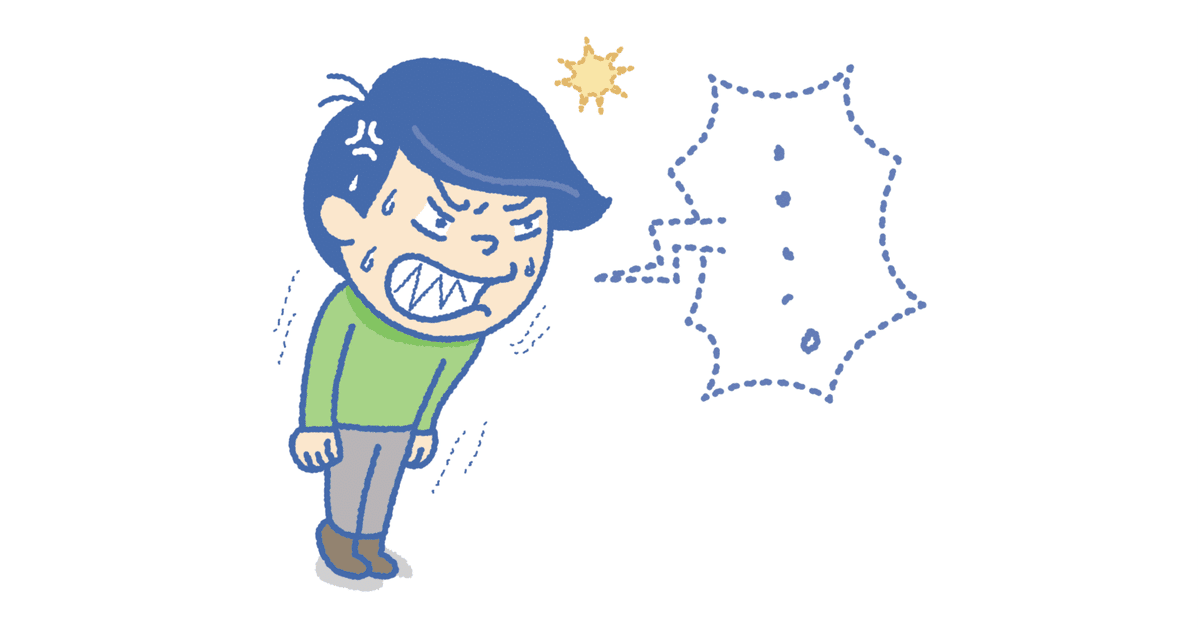
『叱る』の生む最悪の依存性
先日、投稿したコチラの記事へ
ステキなコメントをいただきました。
投稿した記事はコチラ☟
上記の記事では、
「あやとりりい」さんの記事を拝読し
わたしの体験談をお話しさせていただきました。
その中で、”攻撃的な上司”から
自分が受けた言葉によって自己肯定感が下がり、
大事な家族に当たってしまう
という最悪の事態が生まれました。
上記の体験に多数の方から
コメントいただきました。
コメントいただいた皆様、
本当にありがとうございます!
皆様の温かいお言葉は、
わたしの心の支えとして
大切に受け取らせていただきます。
また、
素晴らしいコメントをいただく中で
「はるかぜるりい」さんから
下記のコメントをいただきました。
楽なんですよね。
(相手を貶める言葉によって)
”自分が努力しなくてよいストレス解消法”って。
まるで丹精込めて育てられた花壇の花を
片っ端から蹴散らしていくかのような。
ですが人と関係を構築するのは大変でも、
壊れるのは一瞬です。
村中直人氏の「叱る依存が止まらない」
という本を読んで、こういう人の
ことが少しわかったような感覚になりました。
コメントより引用
なるほど…
「相手へ攻撃的な言葉を使う」とは
いわば、自分が努力しなくてよい
お手軽なストレス解消法なのだという点。
続けて、文章には
「叱る依存が止まらない」という本を
ご紹介されています。
さっそく、検索して
kindleで購入。
読んでみました。
攻撃的な上司は、なぜ攻撃的なのか。
攻撃的な言葉は、どうして
お手軽なストレス解消法になりえるのか。
今回の記事では
「叱る依存が止まらない」を読んだ
わたしの所感を共有させてください。
「わたしには無縁だ」と思っている方。
とても危ないですよ。
けして他人事ではありません。
だれでも
「叱る依存」にハマってしまう環境が
用意されているからです。
さらに最悪なのは、「叱る依存」を認識せずに
周囲に当たり散らかしていつの間にか独りぼっち
というケースに陥ること。
そうならないためにも
今回の記事で「叱る依存」について
考えを深めていただければ幸いです。
では、いってみましょう。

✔叱りたくなる

なぜ、
相手を叱りたくなるのでしょうか。
理由はひとつ。
「相手に変わってほしいため」です。
もっと詳しく解説すると…
「自分の求める理想像に変化してほしい」
ために相手を叱ります。
そして、
「叱る」という行為に発展する場面には
かならず”権力の行使”が背景にあります。
権力の行使とは、権利を持つ人が
実際に権利を実行することです。
上に立つ人がいて、下に座る人がいて
はじめて「叱る」は成立します。
たとえば、
会社でいう上司や部下の関係性。
家族でいう親と子。
先輩や後輩。
そういった権力の行使の名のもと
生まれる関係性によって、
「叱る」は実行されます。
「相手に分かってほしい」
「これが正しいと理解してほしい」
「それは損だよと気づいてほしい」
”相手に変わってほしい”という考えが
根本にあってこそ
「叱る」をひとつの手段として選択します。
ただ…
同時に「叱る」によって快楽を得て
気持ち良さを感じて依存する人もいます。
そう、
「叱る依存」です。
✔目的がズレる瞬間

「叱る」の目的は
相手にかわってほしいことです。
叱って、相手が理解して
正しい道へ進むからこそ
「叱ってよかった」となるはずです。
ただ、往々にして
「叱る」行為は相手よりも
”自分のため”に実行する行為に近い。
なぜなら、「叱る」ことで
2つの報酬を得ているからです。
1つは、自己効力感です。
自己効力感とは、自分で物事を決定し
実行する感覚のこと。
人は何事においても
「自分で主導権を握りたい」と考える生き物です。
それは、
人を行動させることにもつうじます。
つまり、「叱る」ことで
相手を自分の意のままに操る感覚を得て
「生きている」と快感を得ています。
2つ目は、処罰感情を生むです。
「叱る」とは、
「相手が一方的に悪いことをした」
「間違った行為を正すため」という感覚で
起こりうる行為です。
だからこそ、
「悪は成敗せねば」という感情によって
自分の中の正義を正当化させる。
そして、
その正当性によっておこなわれた処罰は
あなたへ「気持ちいい」感覚を得させます。
1、自己効力感
2、処罰感情を生む
「叱る」ことは、
上記の二つの報酬を与えて
あなたへ最高の快楽を得られます。
それは
「相手を変えなきゃ」と思っていたことが
いつのまにか「この快楽を得なきゃ」へと
目的意識を変化させます。
そして、
気づけば快楽の渦に巻き込まれ
”依存”というカタチで、
「叱りたい」「もっと叱らないと」
と本来の目的からズレるハメに…
✔”攻撃的な上司”の場合

過剰に「叱る」を多用すると
依存性を発揮します。
また、依存性という側面から
依存性を生む理由からも
「叱る」へアプローチ可能です。
「どういうこと?」と思う方へ。
アルコール依存症や
ギャンブル依存。
薬物依存にハマる人は、
例外なく「叱る」にも依存するのです。
『依存症』と名のつくものに染まる人は、
相応に理由を持ちます。
その理由の多くは、
”現実からの一時的逃避”です。
「忙しい毎日」「とれない疲れ」「社会的な孤立」
「慢性的なストレスから解放されたい」
「苦痛から脱却したい」と考える人は、
依存症に手を染めます。
わたしの体験談にある攻撃的な上司も
そういった”現実からの逃避”から生まれた
言動や行動だったのではと考えます。
「おれはこんなもんじゃない」と
現実から目をそむけるために
相手にたいして
パワハラまがいの言葉を投げつけて
ストレスを解消する。
権力の行使によって
あたかも自分の正当性を掲げる。
正義の執行官として
「お前は間違っている」と正す。
そして、カンタンに相手は
自分の言う分を聞いたように感じて
とても心地よい気持ちに浸れる。
まさに
「叱る依存」と同じ。
「叱る」ことは目的のズレによって
叱る依存へ発展しましたが…
パワハラの場合、
自分の現実逃避のための手段として
相手を利用する行為。
これほどお手軽に
「おれって最強!」を実感できる方法は
存在しません。
本来は、努力を重ねて結果につなげて
はじめて「自分はがんばった」と
実感するもの。
それを他者を貶める行為だけで
楽に得られるのだから
タチが悪いですね。
ラクでカンタンでお手軽。
攻撃的な上司は、
パワハラという依存から
一生、抜け出せないでしょう。
* * * * *

「叱ってはいけないのですね。
では、褒めるように努めます」
と考えた方へ。
いえいえ、叱るのも
相手のために必要な行為です。
大事なのは
「叱る依存」へ発展させないこと。
つまり、
「叱る」に自分がコントロールされることなく
正しい目的を達成させればよいのです。
そのためには、ときには
「褒める」行為も必要でしょう。
そして、
相手との信頼関係を築くことも忘れずに。
ただ、一方的に
自分の主張ばかりを伝えていては、
いつまでたっても相手は受け身で
あなたの考えに賛同しません。
相手が何を考えているのか。
聞く耳を立てて、
コミュニケーションを取るべきです。
だれでも心は弱いもの。
だったら、ひとりで強がるよりも
周囲と共有して
互いに手を取り合ったほうが
最高の人間関係を作れると考えます。
そうした生まれた関係性は
あなたをより一層、強くしてくれます。
「叱る依存」からバイバイ🤗
では、また。
失礼します。
サポートしていただければ、あなたの習慣活動を全力で応援します!!
