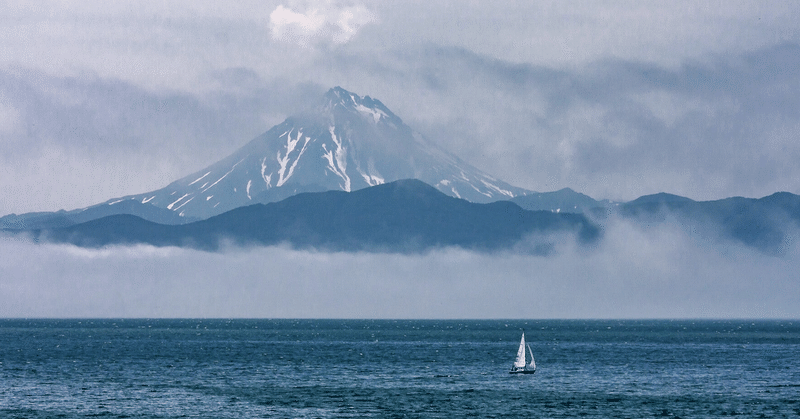
音を聴くということ。
気づけばもう10月。しかも半ばに差し掛かっている!
最初の記事から後は色々ありました。簡単にまとめ。
8月の終わりは今後弾く曲たちの勉強や、9月はじめのオーケストラの楽譜の準備。準備とは具体的に、コンサートマスターの仕事のひとつである弓順番付けですが、これが意外に時間が掛かります。
弓順番はアップ(弓を上方向に走らせる)とダウン(下方向へ)の2種類だけですが、フレーズやアーティキュレーションを含めて考えるので組み合わせには無限の可能性があります。音楽の方向性なども決めてしまう大切なもので、リハーサル中に指揮者が自分の思うように変えたり、また指揮者がすでに自分で弓順を決めた独自の楽譜を持ってくる場合もあります。(このときは私たちのお仕事が少しラクになります..というのはここだけの話。)
9月頭は友人の開催する室内楽のフェスティバルに出演。
ラヴェルとドビュッシーの弦楽四重奏曲、ラヴェルのデュオ・ソナタ、エイミー・ビーチ(20世紀はじめのアメリカ女流作曲家、アメリカ人女性で初めて交響曲出版をしたそうな)のフルート五重奏曲などを素晴らしい演奏家たちと一緒に演奏できました。
私にとって今シーズン最初のベルギー国立管の演奏会は、無声トーキー映画の付属音楽の生演奏&上映プロジェクトでした。Elena-Kats Cherninさんというオーストラリア人の女流作曲家で、なんとこの上映のためにはるばるオーストラリアからいらっしゃったとのこと。音楽はよかったし、いい企画でしたがここでは割愛。
先週は金曜と日曜の2回公演で、ショスタコーヴィチの交響曲第8番を演奏しました。
1943年に書かれたこの曲は、前作の7番のような勇壮さ(勝利のテーマや戦力高揚のためのマーチなど)とは一転、恐れ、悲痛な叫びや哀惜に満ちた音楽で、当時のソヴィエトの人々が直面していた厳しい現実―飢えと制裁―を音で表したような、壮大な音絵巻。
その中にもトランペットによる華やかな、迫力あるギャロップがあったり、終楽章である第5楽章はのどかなファゴットのハ長調のテーマにはじまり、終盤ではかすかな希望をのぞかせる。多面的で、圧倒的な構成の名曲です。
リハーサルにはそれなりの準備をしてから臨むわけですが、今回の演奏にあたって、80年代頃でしょうか、日本で制作されたドキュメンタリーを見ました。ショスタコーヴィチがどのようにスターリン政権下ソヴィエトで音楽活動をとおして生き抜き、密かに抵抗していたかを主に伝えるものでしたが、当時のレニングラードの飢饉や制裁の映像がそのまま残っていて、ドキュメンタリー内で使用されていました。それはあまりにも衝撃的で…事実としてはあったことを知っていても、しょせんは何十年もまえにどこか遠い世界の出来事「であった」というくらいの認識なのであって、映像をみてようやく想像にも生々しさが伴ってくるものです。
第7番「レニングラード」の初演についての部分がとくに印象に残っています。
(第8番の書かれた前年にあたる)1942年8月、レニングラードはドイツ軍に包囲されており、兵糧攻めのために毎日のように餓死者が絶えなかった。(そのアーカイヴ映像も映されていました…ふらふらと歩きながら、ふいにつまずいて倒れ、そのまま起き上がらないひと。大通りの至る所でひとが倒れている。)
そんな中の第7番初演。生き残ったオーケストラ団員だけででも演奏しようと、指揮者エリヤスベルグのもとに集まった演奏者たちはみな骨と皮同然に痩せこけていて、ヴァイオリン奏者は半数に、オーボエもファゴットも一名ずつしかいない。そんな状況での演奏会に大勢が詰めかける。
その演奏会で観客のひとりだったという女性。「こういう曲に出会う瞬間のために、生きてきたのです。―聴衆たちはみな、これが生涯最後の機会かもしれないと思っていたのです」
その日演奏したオーボエ奏者。「食べ物がないかわりに、私たちには音楽がごちそうでした」
明日は自分も死ぬかもしれない、という状況下で聴き、演奏する音楽。
背後に迫る死を意識するがゆえに得られる一瞬間の輝きを、有り難がるべきだとは決して思いません。
けれど、こういう思いで音楽と接することが、現代では(少なくとも日本やベルギーなどでは)少なくなっていると感じています。現代の私たちはほとんどいつでも聴きたいものをイヤフォンやストリーミングで聴けて、街中は音であふれかえっている。
でも私たちが演奏する大半の音楽は今とは全く異なる重みをもってこの世に生み出され、人々の耳に触れてきたのです。音楽というものが「ごちそう」だった。教会で公的コンサートが催され始めた17世紀頃も、ひとびとは何を聴くかよりも、「音楽を聴くこと」そのものを目的に集まって演奏を楽しんでいたものです。
音楽に、また耳に触れる音そのものに、裸の心を震わせられるという感覚に、現代人の多くはとても鈍くなっていると思う。私も含めて。
こういう些末なようでいて欠かせない、小さな意識は日常のいろいろにかき消され、どうしても忘れがちですが、音楽を提供する私たち演奏家はことあるごとに思い出す努力だけでも必要ではないかと思います。
以上の話はショスタコーヴィチに限った話ではありませんが、そう思って彼の交響曲第8番の冒頭(ヴァイオリンによる悲痛なモノローグ)を弾くと、ただでさえ壮絶な音楽の、それを構成する一つ一つの音のかぎりない重みを感じずに音を出すわけにはいきませんでした。
加えて昨今の緊迫した社会状況。繰り返してはならない過去から、さんざん痛い目に遭って学んでいるはずなのに。人間の脆さと、愚かさ。
そのようにして1週間、リハーサルと二回のコンサートを行い、入魂してこの交響曲に向き合いました。
少し休んだので、来週のヴィヴァルディ四季やベートーヴェン英雄など、諸々の準備中です。
ぶつんと切れるような終わり方ですみませんが、今回はこの辺で。お読みくださりありがとうございます!
赤間 美沙子 (note特別プロフィール)2021年よりベルギー国立管弦楽団コンサートマスター。ゲスト・コンサートマスターとして、またソロや室内楽でもヨーロッパ各地で演奏する。特に室内楽はライフワーク。サロン・ド・プロヴァンス室内楽音楽祭(フランス)では音楽監督のエリック・ルサージュ、エマニュエル・パユら敬愛する方々と共演し、彼らの尽きない好奇心と向学心に大いに刺激を受ける。東京音楽コンクール第3位、アンリ・マルトー国際コンクール第2位及びモーツアルト演奏特別賞、ロン・ティボー・クレスパン国際コンクールにてブーレーズ作品演奏特別賞など。ソリストとして新日本フィルハーモニー管弦楽団、フランス国立音楽院オーケストラ等と共演。東京都出身。桐朋学園大学音楽学部を経て、パリ国立高等音楽院首席卒業。同音楽院アーティストディプロマ、ケルン音楽大学Konzertexamen課程修了。桐朋での師、景山誠治先生には音楽の面白さと奥深さを、パリでの師、ロラン・ドガレイユ先生(元パリ管コンマス)にはコンサートマスターとしてだけではなく人間としての在り方を、そしてケルンでの師、ミハエラ・マルティン先生にはどう音を聴き音と向き合うかということ、音楽家としてのマインドを学んだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
