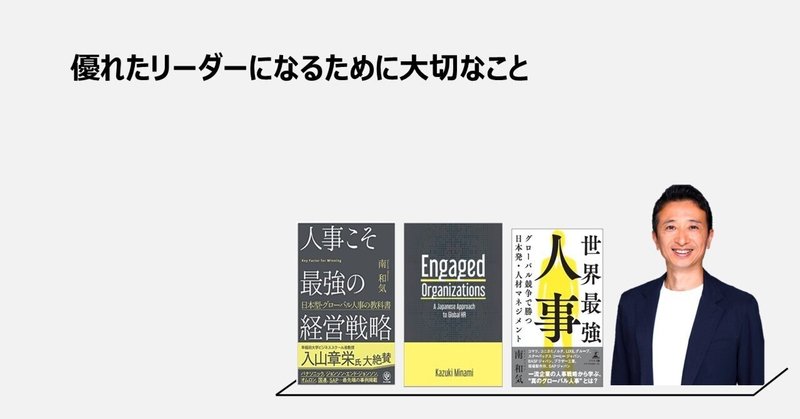
優れたリーダーになるために大切なこと
昨年の4月、「日本電産の永守重信氏が77歳でCEOに復帰」
という発表がありました。永守氏が偉大な経営者なのは疑う余地がありませんが、後進に道を譲る必要性は永守氏本人が一番理解しているはずです。にもかかわらず、なかなか人材を育成しきれていない――。
この状況は、日本電産に限らず、他にも多くの日本の大企業に当てはまります。偉大な創業者が高齢になり、または20年を超えるような在任期間を経てもなお、いまだに後継者を育成できない、後進に道を譲れないでいる。それが日本の現状です。
「人材育成に力を入れている」と表明している企業がほとんどであるにも関わらず、なぜこのような状況になっているのでしょうか。
今回は、世界が実践する「リーダーの育て方」を解説します。
優れたリーダーが大切にしていること
私は、国内外を問わず、多くの経営者やリーダーたちと、人事として、時にコンサルタントとしてともに仕事をしてきましたが、どのリーダーにも、最初に必ず同じ質問をします。
「リーダーとして、あなたが最も大切にしていることは何ですか?」
このとき、海外の優れたリーダーから返ってくる共通の答えがあります。
それは、「後継者を育てること」。
また、リーダー育成にまつわる有名な言葉にこのようなものがあります。
「リーダーになる前の成功とは、自分自身を成長させることである。リーダーになったならば、成功とは他人を育てることである」
そう、優れたリーダーとは、人を育てることができるリーダーなのです。
「自分自身がパフォーマンスを発揮することが大切だ」「プレイングマネージャーはどうしたらいいのか」と感じる人も多いと思います。しかし、リーダーになるということは、組織を預かり、メンバーを預かるということで、どちらにしても一人でどんなに頑張ってもチーム全体の目標を達成できるわけではありません。

「名選手、名監督にあらず」という言葉もありますが、名選手でなかったとしても、メンバーを育て、モチベーションを高めることで、組織全体のパフォーマンスを上げられるリーダーが実際には優れたリーダーであり、組織の目標を継続的に達成していけます。
日本企業では、個人として成績の良いトップパフォーマーがリーダーになることが多いと思います。もちろんそれが悪いわけではなく、リーダーとしてお手本を見せることができる面もあるでしょう。しかし、全員がトップパフォーマーと同じことはできません。トップパフォーマーが必ずしもリーダーとしては機能しないこともよくあります。
世界と日本とのリーダー育成の差
世界的な企業のリーダーたちは、自分たちの後継者を育て、確実に次の世代へのバトンを渡しています。
▶-----------------------------------------------------
・マイクロソフトのビル・ゲイツは44歳でCEOを譲る
・アルファベット(グーグル)のラリー・ペイジは46歳でCEOを譲る
・アリババのジャック・マーは49歳でCEOを譲る
-----------------------------------------------------◀

このように世界を代表する大企業の創業者ですら、早いタイミングで後進に後を託しています。なぜこのようなことが可能なのか。それは、トップから企業全体を通じてリーダー育成に本気で取り組み、実践しているからです。
一方で、日本のリーダー育成の現状に目を向けてみると、次のような結果が示されています。
▶-----------------------------------------------------
・管理職(課長)に登用される平均年齢は47歳
・部長登用の平均年齢は49歳から52歳
・社長の平均年齢は2015年に60歳、2020年は62歳に高齢化
-----------------------------------------------------◀
管理職になるのがキャリアの終盤で、経営者になるのは定年間近です。つまり、世界に比べて、日本はリーダーを育てることに圧倒的に時間がかかりすぎています。経験豊富であることはマイナスではないですが、企業のほとんどは、新たな成長事業やイノベーションを必要としています。現場で起きているニーズや顧客の温度感と、経営者やリーダーの世代とにあまりにも距離があることは大きな課題となります。だからこそ世界では、現場と経営者の距離が遠くならないように、次世代の人材を育成し続けることに全力で取り組んでいます。
ロールモデルを追いかけるリーダー育成は時代遅れ
日本の人材育成は基本的に「背中を見て学ぶ」というのが主流の考え方でした。これを「行動理論」といいますが、経営者、創業者、または特定のリーダーの姿を「ロールモデル」と呼んで、そのスタイルや考え方を全員が目指すという育て方です。
しかし、いかに優れたカリスマ経営者であっても、決して万能ではないですし、現任の経営者が育ってきた時代背景と、今の環境は大きく変化しています。にもかかわらず、一つの見本と比較し続けて「まだ育っていない」と、いつまでも後継者に道を譲れない状態に陥っている――これが人材育成のスピードが遅くなる要因です。
皆さんのキャリアで、素晴らしい上司だったなと思う人を何人か思い浮かべてみてください。直接の上司ではなくても、直接かかわった人であれば構いません。
おそらく、さまざまなリーダーの顔が浮かんだと思います。新人のとき、中堅のとき……時期によって異なるタイプの上司の顔が思い浮かんだ人もいるでしょう。
私もまったく同じです。自身の状態、立場、また自分との関係によって、上司として素晴らしいと感じるリーダー像は都度変わってくるものです。
つまり、これだけ「変化の時代だ」と言われ、人や状況によって思い浮かべる優れたリーダー像が異なるのであれば、1つのロールモデルによるリーダーシップスタイルで誰に対してもどんなときも通用するということは、現実的にはあり得ないのです。

これから目指すべきリーダー像
これからのリーダーは、相手や状況に合わせてリーダーシップスタイルを使い分けることが必要になります。これを「条件適合理論」と言います。この理論についてはまた詳しく書いていければと思いますが、まずは、一つのリーダーシップ論やロールモデルに頼りすぎないように気を付けてみてください。
もし自分が素晴らしいと思うリーダーに出会えば、「なぜ素晴らしいと感じるのか、どういう人に対して素晴らしいのか」を考えてみることが大切です。どんなに素晴らしいと感じたリーダーの言動も、相手や状況が変われば、必ずしも良いとは限りません。いろんなリーダーの素晴らしいところを見つけて分析することで、少しずつ自分のなかにリーダーシップのスタイルのパターンを蓄積しましょう。
リーダーシップスキルとは、「人を育て、動かすスキル」です。「相手や状況に合わせて使い分ける」という意識をもつことが、優れたリーダーになっていくための近道となります。ぜひ実践してみてください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
