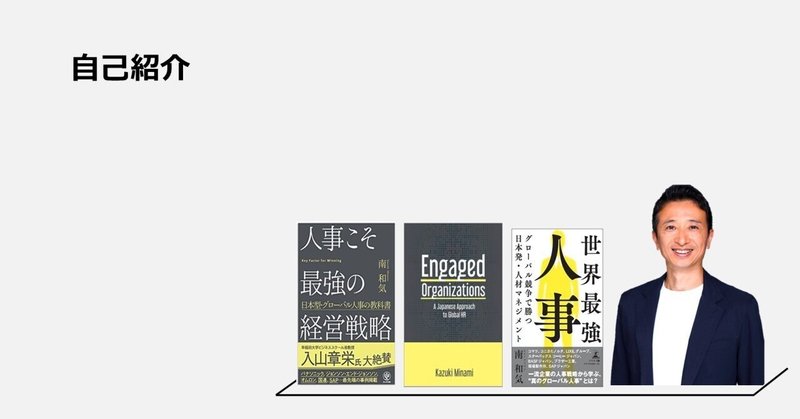
「自己紹介」―これまでのキャリアの歩み
これまで日本企業、ドイツ企業、アメリカ企業を経て、部下も上司も外国人という環境や、日本企業の人事役員として、株主、経営者、社員、組合などあらゆるステークホルダーと向き合う経験をかさねてきました。ただ、私も20代は人事とは全く違う職種で、まさか自分が人事の仕事をするとは思ってもいませんでした。
今回は私のキャリアの変遷と、それぞれの選択をするときにどんなことを考えていたかを振返りながら、皆さんにとってのキャリアづくりのヒントにしていただければと思います。
最初のキャリア「ITエンジニア」
私は、今でこそ人事の世界でいろんな仕事をしていますが、新卒入社したのは、オラクルというアメリカのIT企業で、ITエンジニアとしてキャリアを始めました。
大学までド文系だったため、入社当時は同期の会話にもついていけないような状態で、ITとプログラミングの勉強漬けの毎日でした。まさに、オフィスに寝袋を持ち込むような状態で、平日も週末もなく勉強し続ける。という日々でしたが、2年ほどたつと、エンジニアの仕事が意外と向いていると感じるようになってきて、自分なりに仕事に自信を持てるようになっていました。
しかし3年目の夏、アメリカ本社に出張し、本社のエンジニアと仕事をする機会があり、彼らのプログラムを見せてもらって話しを聞いたのですが、会議が終わるころには「これは何年かかっても彼らには絶対に勝てるわけがない」と確信させられました。ほぼ同年齢のアメリカのエンジニアたちのスキルは、少し会議しただけでも分かるほど、途方もなく高いレベルで、日本ではそれなりに頑張っていたつもりの当時の私は、世界とのあまりのレベルの差に、悔しいという気持ちを通り越して、これはこの仕事ではとても食ってはいけない。と心から思いました。
そして帰国してすぐに異動の希望を伝えたのです。当時は挫折のように感じていましたが、結果としては井の中の蛙になることなく、自分の価値を客観的に見ることの大切さを教えられた経験でした。
その後、エンジニアからマーケティングに異動してビジネスや数字の大切さを基礎から学びましたが、「IT業界に身を置く以上は、一度コンサルティングの現場を経験したい」という思いを強くするようになり、声をかけていただいたドイツのIT企業であるSAPに人事コンサルタントとして転職しました。
これが、人事の世界との出会いとなります。特に人事領域のコンサルタントを希望していたわけではありませんが、オラクル時代にマーケターとして人事システム製品を担当していたことがSAPの目に留まったこともあり、事業開発の責任を担いながら、人事コンサルタントとしての入社でした。
SAPでの最初のミッションは、当時沈んでいた人事コンサルティング事業の立て直しでした。ところが、コンサルティングの現場経験はまったくない中で、SAPに入社したその日、私を採用してくれた上司は「ごめん。俺も異動になった。あとは頼む」と言い残して去っていきました。
そこからは新人のときと全く同じで、毎日人事の勉強に明け暮れましたが、今回は中途入社だったため、最初から結果を残すことも求められ必死でした。SAPに入社したころは英語も全くできませんでしたが、しばらくすると上司も部下も外人というグローバル組織になり、毎日6時に英語のレッスンを受け、8時からのグローバルチームとの電話会議を終えたあと出社するという毎日で、苦しく孤独な闘いでしたが、徐々にチームとの信頼関係がつくられ、チームメンバーと顧客に支えられて、幸い日本の事業は大きく成長しました。

世界における日本人の存在感のなさ
その後、アジア地域の責任者となり世界の多くのクライアントを経験し、SAP社内の人事部門も経験したなかで、私はひとつ大きなことに気づきました。それが今でも、人事として仕事を続けるモチベーションになっています。
「日本人は世界でも信じられないくらい優秀だ。しかし、その能力は世界を舞台にほとんど発揮できていない」
SAPの10万人の社員の中で、日本人はわずか1%。当時100人ほどのグローバルマネジメントミーティングに出席している日本人は私だけ(アジアの他の国からは複数人いる)で、世界における日本人は究極のマイノリティでした。
他の外資企業でも状況は大きく変わらず、結局主要なグローバル企業にとって日本市場はそれなりの規模があるにもかかわらず、重要な意思決定に日本人はほとんど関わっていません。
私の書籍でも常に述べているのですが、これまでさまざまな国のリーダーたちと仕事をしてきた経験から確信しているのは、一人ひとりの能力でいえば、日本人は世界No.1といえるほど優秀であり、勤勉ということ。しかし、海外の人材に比べると、専門性が磨かれず、一つの会社の社内事情に詳しい、似たような人材ばかり育っています。
このままでは、グローバル競争の激化とともに、日本企業は、海外企業に飲み込まれていってしまう――。
そうした思いが強くなるとともに、「日本企業に貢献したい」という思いで、ご縁のあった江崎グリコに人事役員として入社し、経営戦略の策定と人事改革を進めました。
「一人ずつに向き合って話す」ことの大切さ
このとき私がもっとも頭を悩ませたのは、「社員に改革の意味と目的を理解してもらう」こと。
経営戦略や事業変革を進めるために、人事がいくら制度・プログラムを整備しても、未来を作るのは社員自身です。社員がその気になってくれなければ結果はでません。
しかし、会社が大きくなればなるほど、社員一人ひとりは、会社の経営状態や経営戦略の全体像が見えなくなっていきます。そうすると、「なぜ自分が今、変わる必要があるのか?」ということに腹落ち感がないのです。
特に、私のように外部から採用された人間が変革を推進していくと、社員から、「なぜ人事制度を大きく変える必要があるのか」、「会社の良い文化がなくなるのではないか」といった声があがるのは当然です。自分たちが変わる必要性も、具体的にどう変わればよいのかも、イメージがはっきりしないからです。
多くの日本人は、自分の能力を自分の成長や価値を上げるためにどう使うのかがわからない状態のまま、会社によっていろんな仕事を与えられ、ジョブローテーションを繰り返しています。たしかに、若いうちはこの方法で視野も広がり、できることも増えます。しかし、気づいたときには、「いろんなことが少しずつできる人」が会社に溢れています。そうなると、より若い世代、場合によってはテクノロジーによって仕事は代替されてしまうのです。
そこで私は、毎週いろんな職場の社員に3人ずつ集まってもらい、会社の未来と個人の未来について直接じっくり話す時間を持ち、会社の変化によって、一人ひとりの人生やキャリアにとって何が起きるか、そして、一人ひとりのキャリアをどう考えるのかを対話し続けました。
歩む道は人によって違います。だからこそ、「一人ずつに向き合って話す」という地道な時間の積み重ねが、変革が支持され早く進めることができた変化点になったと感じています。
これからは、社員のキャリアを考えるのは会社ではなく、社員自身になります。
しかし、これまで自分でキャリアの地図を描いたことがない多くの人たちに、いきなり白紙のキャンバスを渡しても描けるものではありません。自分を客観的に見ること自体、簡単なことではないからこそ、多くの人がキャリアに悩むことになります。

キャリアは偶然の機会が重なってつくられる
いま私は、大企業からスタートアップまでいろんな企業とお付き合いをしています。各社の社員の皆さんとお話することも多くありますが、皆さん本当にキャリアに悩んでいます。またこれまでも社員からキャリアに関する悩みや質問をたくさん聞いてきました。
「自分が何をやりたいのかわからない」
「自分が最終的に何を目指すべきかわからない」
悩んだり、不安になったりする気持ちはとてもよくわかります。ただ、キャリアの道は、自分で選んでいるようで実はほとんどの場合、他人によってつくられます。自分で自分の道を選べる人は、よほど才能と結果に恵まれた一部の天才だけです。
自分にとって最適な仕事は、自分が決めるのではなく、他人によって与えられた機会のなかで結果を出していくことで、また次のチャンスが巡ってくる。このようにしてキャリアは自然と作られていきます。
私も、何度も挫折や失敗をしながら、目の前の仕事に集中してきた結果、いろんな人との出会いがあって、偶然、人事の世界で仕事をすることになりました。今も人事の仕事が自分のゴールなのかどうかはわかりません。でも、それで良いと思っています。まずは今、目の前の仕事に全力で取り組んで、結果を出しながら成長し続けることで、また次の道が見えてきます。
もしキャリアに悩んでいる方がいらっしゃれば、まずは目の前の仕事で結果をだすことに集中してみてください。そして、自分の強みをつくることを考えてください。あまり遠い未来を見る必要はありませんし、人と比べる必要もありませんし、自分のペースで構わないので、まず一歩、一歩を大事にしてください。そうすると次のチャンスが向こうからやってきます。
キャリアのつくり方については、あらためて詳しく書いていきたいと思いますが、私のこれまでの経験が少しでも皆さんのキャリアづくりのヒントになれば嬉しく思います!
次回の予告
4月を迎えて、あらたなキャリアにチャレンジする方や、リーダーとなっていく方も多いと思います。次回は、良いリーダーとなっていくために大切なことを人事の目線から書いていきたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
