
多摩デザイン大学 「デザインプロモーション」 秋元 淳さん
昨年通った多摩美術大学が、期間限定「多摩デザイン大学 / Tama Design University」を開校しているので、受講しています。
この問いを頭に置きつつ、学んでいこうと思います。
「我々は新しい世界をどうデザインできるのか?」
我々は今、環境をはじめとした様々な課題や、テクノロジーによる急減な変化と向き合っています。その状況の中でどうデザインするかの前に、何をデザインしていくべきなのかを問い直していくことが重要ではと考えました。
▼講義詳細
多摩美術大学が、誰もが参加できる“デザインの大学”を期間限定開校。50の新たなデザイン領域を知る、講義プログラム公開
東京ミッドタウン・デザインハブ第94回企画展「Tama Design University」12月1日(水)〜12月26日(日) 会期中は講義プログラムを毎日開催。聴講無料。
▼講義一覧HP

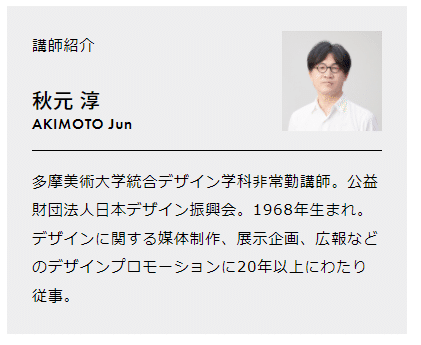
■テーマ
デザインプロモーション「社会にデザインの本質を伝えるには?」
デザインプロモーションの4つのポイント
について、順にご説明いただくスタイルでした。
1.一般性と専門性のバランス
デザインに関する意識調査から、デザインに対する認識を掘っていくと、
一般層と、デザインを仕事にしている方たち(デザイナー、デザインプロモーションなど関わりのある立場)で、下記のような認識の違いがあるそうです。
一般的には・・
造形、装飾、衣装、洒落、美術
専門的には・・
構想、計画、設計、実装、創造
確かに、一年前のわたしは、デザイン=形や色などがかっこいい家具、家電、などぐらいしか思いつきませんでした。
デザインの仕事に関わりがあるないで、こんなにも認識が全然違うものなのか、とも思いましたし、一つの言葉でここまで解釈が違うのもすごく珍しいんじゃないでしょうか。
たとえば、経営企画とかエンジニア、人事などだと仕事で関わっている、いないでそこまで認識にずれはない気がします。「デザイン」という言葉の解釈の幅は広いですね~
次に、デザインの「上乗せ」と「掛け合わせ」の話が続きます。
上乗せ
すでに十分デザインされてきた対象を、さらにデザインによって
価値を高める Ex)デザイン家電、デザインマンション、デザインホテル
掛け合わせ
これまでデザインされていない対象に、デザインの手法や効果を活かして
価値をもたらす Ex)デザイン思考、デザイン経営、行動デザイン
この二つのアプローチが併存している中で、いかにデザインを伝えていくのか。効果的なやりかたを開拓していくのか、を考えられているとのことでした。
まとめ
一般的なデザインに対する認識・理解と、デザインの専門層・プロフェッショナルのそれとの間には、明らかな差異がある。それは現在までのデザインと人々との関わりのあり方や、社会におけるデザインの扱われ方を鑑みれば避けられらないことであり、この差異の存在をつねに前提としながら「共通言語」を見い出していかなければならない。
どちらがいい悪いではなくて、解釈や認識にずれがあることを理解しながら、お互い会話していくべきだそうです。
2.デザインを万能薬にしない
次に「スタンフォード式人生デザイン講座」の本を元に、
デザイン=万能な課題解決の手法? と思っているかもしれないが、そうではないというお話をされます。
デザインに期待される3つの本質的要素
1. 人を軸に成立する「人間中心」の姿勢
2. 見えないことを具現化する「可視化」の効果
3. 一過性・一方的でない「継続性・互恵性」の形成
デザインに備わるこれらの要素が、課題の解決など社会が取り組むべきアクティビティに必要なものとして期待されている
→必ずしも手法としてのデザインが課題の解決を図れるわけではない。
デザインでなんでも解決できる!ではなくて、デザインのもつ大事な要素を活かしていく、そういうことが社会で求められている=社会課題の解決などに繋がっていくと思う。とおっしゃっていたのですが、この考え方も納得です。
まとめ
デザインは課題の解決や課題の発見に貢献できるが、社会にはデザインだけでは解決できない課題の方が圧倒的に多い。
デザインの力があればこれまで解決できなかったこと・果たせずにいたことが達成できるかのような、デザインが万能な処方箋であるような印象を与えてはならず、デザインができる事・しなければならない事を謙虚に示していくべき。
3.「デザインをする人」を伝える
今度はグッドデザイン賞を受賞した人の事例をもとに、デザイナーは様々なジャンルの方がいらっしゃるという話になります。
また、何かの調査で、デザイナーの人数は増えているけれども、デザイン事務所は減っているというお話があります。
これはどういうことかというと下記の変化があるそうです。
デザインをする人=専門職としてのデザイナーと言えなくなっている
デザイナー自身の属性やデザイナーに求められる能力も変化してきている
→デザインを担う人材の多様化
デザインを成り立たせている目的性・指向性の変化
=「デザインをする」人の意識とモチベーションの多様化が進んでおり、それをいかに的確に伝えることができるかが問われている。
まとめ
デザインの概念や定義や手法は、時代や状況の変化とともに変動する。
社会におけるデザインはつねに不定形・進化系であり、リジッドな扱いはできない。
それであれば、何よりもまず「私はデザインをしている」と考える当事者の意思と姿勢を伝えることを通じて、デザインが持つ力やその可能性=デザインの現在地を示せればよいのではないか。
4.+??
2020年度グッドデザイン金賞をとった台湾のPlan(教育環境のデザイン再構築 Design Movement on Campus)の紹介。
環境の在り方をリデザインしていくプロジェクトだそうですが、日本でいう文科省とプロモーション団体が一緒になって進めている事例だそうです。
特徴的なものは3つあり、
・行政とデザインプロモーションとの協業
・教育の現場という「社会の最前線」へのコミット
・プロモーター+プロフェッショナル+ユーザーの一体的な実践関係
デザインのプロモーション=社会へのデザインの浸透・定着に向けた実践事例として、先導的かつ実効的な取り組みである点で注目されたそうです。
また、プロと子供が一緒になってやっているのが大事なところともおっしゃっていました。
もう1件、おてらおやつクラブ(2018年度グッドデザイン大賞) の紹介。
デザインに期待される本質的要素が全部入っている、素晴らしい事例とのことです。
デザインとしての「おてらおやつクラブ」
人間の尊重▶何よりも貧困状態にある子どもと親のために
価値の可視化▶寺の機能と役割を今日的に再構築して提示
共創の仕組み▶共感と協業を促すコミュニケーションの構造化
体験の創出▶関わる人たちにもたらされる新たな体験
目的・理想の達成のため「デザインをする」意思のもと生まれた
「おてらおやつクラブ」を、いかにデザインとして伝えられるか?
最後は、
4=デザインプロモーションは、明るく・楽しく。希望を伝えて。
とのことで締めくくり。
■所感
「デザイン」という言葉に対する認識の違い、昨今のデザイン思考はなんでも解決できそうと思われているがそうではない、人にフォーカスする、広義のデザイナーが増えている状況、グッドデザイン賞の選び方など、長らくデザインに関わっているからからこそ見える景色が知れて勉強になりました。
いままでグッドデザイン賞の受賞対象を細かく見たことはなかったのですが、一度じっくり過去のものも含め見てみようと思いました!
最後までお読みいただき、ありがとうございます!スキ💛コメント、とても嬉しいです💛
