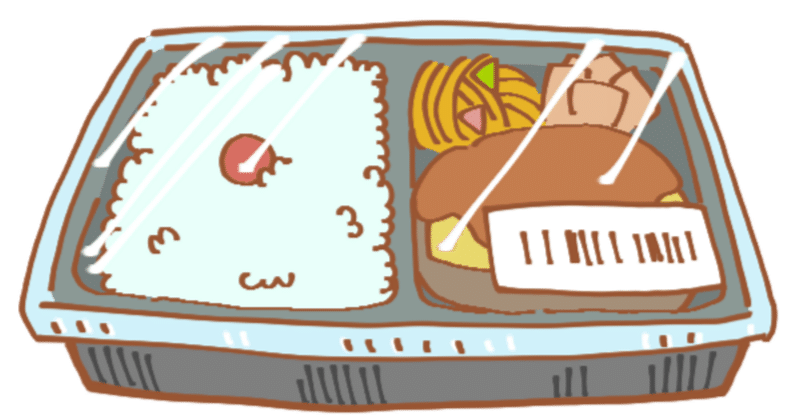
コンビニ弁当を縦に入れる
文学フリマ東京37にて寄稿したショートショートです。
初めてのバイトは夜の街のコンビニだった。レジに一人で立たされた初日、お弁当用のレジ袋の存在を知らなかったおれは、強面のおじさんのお弁当を縦にして入れた。
あの時おじさんとおれの間に流れた空気は、年月が経った今でも全く他に例えようのないもので、もはや唯一無二のフレーバーである。
もちろん、当時のおれは考えもなしにそうしたわけじゃない。もしお弁当を縦にすればお米が端に寄ってしまったり、付け合わせの具材が重力に負け、転げ落ちてしまうだろうとは、高校生のおれでも想像ができた。けれど一番大きいレジ袋をもってしてもお弁当は横向きに入ってくれそうになく、あれやこれやとトライアンドエラーを繰り返すおれを、まだかまだかと睨み続けてくるおじさんの眼力の方が大きな問題となってきていたので、おれはすぐにでも結論を出さざるを得なかった。
『おれがきっと知らないだけで、悲しきかな現在コンビニが提供するサービスでは、お弁当を横向きにいれる方法がないのだ。みんな縦向きにして持って帰る。それが世間一般が共有するコンビニの常識なのだろう』
心の内でそう合点すると、おれは参考書を買った時の本屋さんを思い出し、Mサイズのレジ袋を取り出して横向きに寝かせた。お弁当を持って横から丁寧に入れ、手を添えて縦向きに渡したところ、強面のおじさんは「おっおっおっおっおっ」と声をあげておれを止めた。「お前ェバカか」
夜の1時半。少しうなされ目を開ける。脳みそというものは不思議なもので、昔に起きた絶望的な失敗の記憶を就寝前に見せてくることがある。それは唐突であり、脈絡などまるでない。
脳の中でおじさんの言葉が自然と反芻する。お前ェバカか、お前ェバカか、お前ェバカか、お前ェバカか。
こうして思い出すと、あの「バカ」の「B」の破裂音はとてつもなく強かったように思う。この言葉と破裂音に、おれは当時とっても傷ついた。なぜなら、ゼロから自分なりに考え抜いた末にバカと言われ、そして後から思えばやったことが確かにバカだったからである。いや、でも、おれの根本はバカではない。たとえバカだったとしてもあんなに強い破裂音で言われる筋合いはない。驚かす上に悲しませるなんて卑怯だ。くやしい。
10年以上も前のことにも関わらず、今更気にするなんてあほらしいと思いつつも、その後もおじさんの声の反芻が続いたので、大人になったおれからあのおじさんへ何か一言言ってやろうと思った。
おれは再度布団に潜り込んだ。
目を閉じると、目の前にレジが現れる。下を向くと、フックにかかったレジ袋。おれの胸ポケットには顔つきの名札。そして顔を上げると目の前には人一人分とは思えない空気の圧があった。般若のような怒りの顔、そこから唾が飛んでくる。
「どういうつもりだお前!」
「すいませんすいません」
「わざとやってるんじゃないだろうなお前!」
「すいませんすいません」
「他の店員呼べ!」
「すいませんすいません」
記憶の中のかわいそうなおれ。完全に拳を振り上げきったおじさんと、防御一択になってしまった高校生のおれのやり取りがそこにはあった。これではあまりにも惨めなので、何か言ってやろうじゃないか。
「はい、おちついて!」
パァン、と手の平を叩き、おれはおじさんの眼前でねこだましを食らわした。
「わたくし、この晩、レジ独り立ち初日で、お弁当の袋の存在を知らなくてですね! これが全身全霊をもってした結果なのでありましてね!」おれはおじさんに負けじと大声を出してみる。
「これどうしてくれるんだ!」
「ほら、聞いて!聞いて!」おれは続けてパァン、パァン、と手を打った。
「最初は誰しも赤ちゃんでしょう!この日おれも店員の赤ちゃんだったんですね!」
「お前ェみたいないい加減な仕事をする奴が俺は一番嫌いなんだ!」
「くそ!」全然応えてくれないのでおれはおじさんを殴った。しかし、その後も記憶の中の彼は怒鳴り続けていた。
「なーにやってんだか」おれはレジから出てバックヤードに行くと、ブレーカーを落とした。真っ暗な店内の中、おれは雑誌コーナーの前に寝そべる。
どんなに言い返してもあの日のおじさんは変わらないのだ。
こんな器の小さなことやってないで、明日の仕事のために早く寝よう。このまま夢に落ちよう。そう思った。
瞬間、すうっと引っ張られるようにレジ前へと意識が巻き戻された。目の前を見ると、おれはまたお弁当を縦にしようとしている。おじさんは「おっおっおっおっおっ」と声を上げ、「お前ェバカか」と唾を飛ばした。
おれはため息をつく。無意識に記憶を反芻してしまっている。こうなってしまうとなかなか寝付けないのである。
しょうがなくぼんやりと眺めていると、「そんな、被害者のような顔をするな」とおじさんは言った。
「だって弁当を縦に入れるなんて頭がおかしいだろ。おれを怒鳴らせたのはお前なんだ」
おれは首を傾げる。おれの記憶にない会話が始まっているような気がする。
「だからって、怒鳴っていい権利なんてないでしょう」おれは試しにラリーを打ち返す。
「なんだと、お前ェ今なんて言った」
「だからってこんなまだ若い子を店内で怒鳴っていい権利なんてないでしょぉて言ったんです」
おじさんはあり得ないものを見たような顔をしていた。「なんだこれは」
おれは腕を組んで考える。これは夢にしちゃ相当変な夢だな。彼の言葉や表情はライブ感があり、まるで、今ここにいるリアルな人間のように見える。
しめた。これはおそらく、相当にリアルな明晰夢ではないか。
おれは、やったやったと言いながらレジを飛び出すと、おにぎりコーナーからおにぎりを持ってきて開封し、おじさんの顔に擦り付けた。
数粒の米は彼のまぶたに付き、また数粒は頬に残った。
「なっ、なっ、なっ、な」おじさんの顔色がみるみる怒りの赤色へと変わっていく。
「やはりリアルだ」ひとしきり手を叩いてゲラゲラと笑った後、おれは再度考えた。「うーん」胸に手を当てる。「リアルでいいけど、これはおれのやりたいことじゃない」
今度はお弁当コーナーに行き、いくつか重ねておじさんの前に戻ってくると、その全部をレジ袋へ縦に詰めた。数回振り回すとお弁当を取り出して、おじさんの前で食べた。
「ほうらごらんなさい!お弁当は縦にしてもうまい!ほうら、ほうら!結局味は変わらない!」
おじさんは呆然とおれを見ながら立ち尽くしていた。
「うーん」おれは胸に手を当てた。「これもちがう。自分を正当化しすぎている」
次におれはしゃんと立つと、腰を折り曲げてお辞儀をした。
「お客様、申し訳ございません。私、あの晩レジスターに一人で立つのが初めてだったもので、経験も浅く、お弁当のレジ袋の存在を知らず、その節は大変ご迷惑をおかけいたしました」
胸に手を当てる。「うん、やはり真摯にこれかなあ」
さておじさんの顔は、と顔を見上げた瞬間に怒声が響き、おれはおじさんに頬を殴られて後ろのタバコ棚にぶつかり崩れた。
「なんだってんだこれは!」
おじさんは顔についた米粒をはたき落としていた。
「ええっ」おれは地べたに尻餅をつきながらおどろいた。「ここはおれの夢なのに殴られた」
*
「それじゃあ、おじさんが、おれの記憶に入り込んでるってことですかね」おれはおじさんの両手と両足をビニール紐で縛り、その横でそっと体育座りしていた。
あの後、憤慨したおじさんがレジに入り込んで殴ろうとしてきたので、それはそれは大層な取っ組み合いになった。コーヒーメーカーは倒れ、レジ前のガムと電池は散乱し、最後には『ころしてやる』と叫んで文具コーナーにはさみを取りに走ったおじさんを、後ろからロックアイスで殴ったおれが幸いにも勝ったのだった。
「ここは、俺の記憶だ」おじさんはイライラした声で言った。
「はあ」おれは遠くを見ながら言った。「もしかすると、お互い同時に同じ出来事を思い出してるから、頭の中で繋がってるのかもなあ」
「阿呆か、俺ァそんなオカルト信じねえ」
「まあおれも、こんなの夢だと思ってます」
試しに一度目を覚そうかと思ったが、現実のおれの瞼はどうしても開かなかったので、やはりこれは夢かも知れなかった。
特に話題がなくなったおれは、少しもじもじして言った。「あの。おれがおじさんのお弁当を縦に入れたこと、覚えてます?」
「覚えてるからここにいんだろが」おじさんは紐をギチギチさせながら言った。
「そうか」確かに、と思った。「その節は、本当すいませんでした」
おじさんは舌打ちをすると「すいません、はもう何度も聞いたんだよ」と言った。おれはそれを聞いて、こいつなんかに謝るんじゃなかったと思った。
少し咳払いをして尋ねる。「しかしまた、なぜ10年以上も経った今、ここに」おれはおじさんの顔を覗きこむ。
「もしかしておれに怒鳴ったこと後悔してる、とか」
「違う」
「バカのBの破裂音を強く言いすぎたな、とか」
「なんだそれは」
「お弁当を縦に渡されたのがあまりにショックすぎた、とか」
「それは」おじさんはぽつりと言う。「半分当たりだな」
おじさんはその後しばらく黙り、数秒ののち、口を開いた。「この日はな、俺がおじさんになった日なんだよ」
おれはポカンとした。会った時からあなたはおじさんでしたけど。と言いたかったが、彼がそのまま続けて喋り出しそうだったのでこらえることにした。
「と、いうと?」
「お前、人はいつからおじさんだと考える」
おれは考えてみる。それは人それぞれではないか。「年齢では、ないとは思いますけど」
「お前は今おじさんか?」
「うーん、それはまあ、見る人によっちゃあ……」
「じゃあお前は今若者か?」
「それもまあ、見る人によっちゃあ……」
「俺はな、そのくらいの歳の頃からな、自分より若い奴がどんどんと青く見えて、存在が遠くなって行ったんだ。奴らがまるで世間知らずで、無知で、かつ宇宙人のようで、おれを舐めているように思えた」
「こわいですね」こういう風に急に喋りはじめるところもおじさんだな、と思った。
「その一方でな、俺は年齢と共に図々しくもなってきてたからな、ある時初めて、俺はドカンと店員に声を荒げた」
おれは自分を指差す。「あ、それ、おれだ」
「その時、なにかとんでもなく悪い奴を更生させてやったような、スッキリした気持ちになった。そんで店を出てちょっと歩いた後、ハッとした。ああ、俺は今この瞬間、おじさんになったんだってな」
「なるほど」そう言いつつ、おれはよくわからなかった。「それで、今もここを振り返ってるのは、おじさんになったことがショックだったからですか」
「いや、おじさんになった印象的な日ってなだけだ。後悔はしてない」おじさんはフンと鼻から息を出した。「今も結局、正義を大声で主張するのは気持ちがいい」
おれはそれを聞いて大層げんなりした。
「なんだよ、後悔してくれよなあ」
「あんな唾飛ばして怒鳴り散らかしたの謝ってほしかったなあ」「おれも悪いけどさあ」おれはぶつぶつ言いながら立ち上がって、酒類コーナーへと足を向けた。「酒でも飲まないとやってられないね」
おれは買い物カゴにいくつか缶酎ハイを入れながら言う。「何か飲みますかー?」
後方の這いつくばったおじさんから、飲めんのか? という声が聞こえた。
「さっき僕がお弁当食べた時にはなんとなく味がしたんで、酒もいけるでしょう。夢の中ですけど」おれは適当におじさんが好きそうなものを見繕う。
「はい、ワンカップ」
戻ってきたおれは、おじさんの腕のビニール紐を解き、ワンカップをその前に置いた。
「あのな、ワンカップはもっと、上の世代だろ」おじさんは顔を顰めてワンカップを持った。
「そうなんですか?」おれはレモンハイを啜った。
「それを一括りにされちゃおれは困る」そういいつつも、おじさんは啜るとカーッという顔をした。
「それもまたおじさんだなあ」おじさんをつまみにまたレモンハイを啜った。
時間が経つと、おれとおじさんは完全に出来上がっていた。目の前にはいくつもの缶と瓶が見える。
「わかるか? 俺はつまり正義で怒鳴ってるんだよ。謝罪を求めるな」おじさんは身振り手振りで熱弁する。
「おおいやだいやだ、相容れない相容れない」おれは首をねじれんばかりに横に振る。
「おまえいつまでも若者ぶるなよぉ」
「おれも、いつかはおじさんになる日が来ると?」
「くる。まちがいないね」
「いやぁおれはね、あなたみたいな怒鳴るおじさんにはならないと思いますね」「なにせシャイなので」おれの瞼はとても重かった。
「いいや、なる。おれァ、昔っから人に意見する性格だったから、刃剥き出しのおじさんになっただけ。おまえもどんなかたちであれ、おじさんになる。若者へのうらやましさややっかみをもったおじさんに、なっていくんだよ」おじさんの瞼はほとんど開いていなかった。
「そんなのボーロンだぁ」おれはゆらゆら揺れて床に酎ハイをこぼす。
「あんな、もし自分がおじさんになったかどうかをな、確かめたければな」おじさんはドシャ、と横に崩れてそのまま天井を見上げる。「お前ェが俺にやったことがァ、いいな」
「それは」おれもあぐらをかいたまま前にグシャ、と倒れ、おでこにタイルと酒の冷たさを感じた。「それは、なに」
「コンビニの店員にィ、弁当を縦にいれてもらえば、わかる」
「はははははは」
おじさんはいびきをかき始め、おれは床に向かってケタケタと笑う。
少しの間『お前ェバカかぁ!』とおじさんの真似をしているうちに、おれの視界は暗転していった。
意識の中のコンビニの中、おれとおじさんはまたも向かい合ってお酒を飲んでいた。
「この間、ついにお弁当を縦に入れられました」おれはレモンハイを啜った。
「それで、どうだった」おじさんはワンカップが気に入ったようだった。
おれは胸に手を当てて言った。「おれ、すこしだけおじさんになってました」
おじさんは嫌な笑い方をした。「そうかそうか」
おじさんは一呼吸置くと言った。「俺はな、このあいだ、爺ぃになった」
「えっ」おれは驚いた。「おじさんと、爺いは、違うんですか」
「違う」
「どう違うんですか」
「お前ェにはまだ早い」
「爺い度合いを測るためには、どうしたらいいんですか」
「お前ェにはまだ早い」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
