
ウッチ映画大学で一番初めに聞かれたこと、それは映画監督になるための最初の一歩でした。
そもそもウッチ映画大学って?
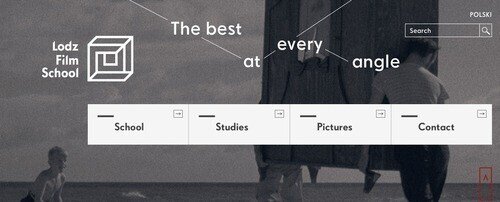
ロマン・ポランスキー『戦場のピアニスト』『ローズマリーの赤ちゃん』
アンジェ・イワイダ『灰とダイヤモンド』『カティンの森』
クシシュトフ・キェシロフスキー『デカローグ』『トリコロール/赤/青/白』
70年以上の歴史を持ち、数々の有名監督を輩出したポーランドの名門映画学校。
それがウッチ映画大学です。
近年では米ハリウッド・レポーター誌の「世界の映画学校ベスト25」でも選出され、ヨーロッパでも5本、カメラ科に関しては世界の5本の指に入るほどの高水準の設備、教育を備えた学校です。
現在も世界中から生徒が集まり、監督科、カメラ科は1/3以上が外国人生徒という国際色も大変豊かなことも特色です。
先攻は監督科、編集科、シナリオ科、カメラ科、アニメ科、プロデューサー科と映画に関する学科の他に俳優科、写真科があり、それぞれプロフェッショナルの育成のための独自のカリキュラムを備えております。
学生作品は年間国内外の250以上の映画祭にて受賞、ノミネートをしており、カンヌ、ベルリン、サンダンスなど名だたる映画祭での学生部門の常連となっております。
そんなウッチ映画大学、監督科1年生の最初の授業で問われる質問があります。
それが“Kim chcesz być?”
意味は “あなたは何者になりたいか?”
これを、ほぼ各授業の冒頭で連日問われます。
この質問の意味は映画監督として、回答者、質問者としての訓練も兼ねています。
授業中は“あなたは何になりたいか?”をきっかけに連想ゲームの様に質問者は質問をドンドンしていきます。
さらに、もう一つの目的は自分の目標をはっきりさせる事。
そして、現時点での自分との差を認識する事にあります。
大事なのは質問されたら考え込まない事。
なるべく早くに回答します。
”あなたは何になりたいか?”
”どんな?”
“どうしてなりたいのか?”
“どうやってなるのか?”
”なんのために?”
“誰の為に?”
①大事なのは質問者と回答者2名以上で行う事。
②質問は交互ではなく、1人が矢継ぎ早に質問していき、1人がそれに答えていきます。
③抽象的な質問はしない。
例えば「なぜ?」を連発する事。
「なぜ?」を聞く場合は必ず動詞もつける事。
「なぜするのか?」
「なぜとるのか?」
「なぜそう考えるのか?」
具体的な質問は映画監督に必要な観察力、具体的な指示能力を養うのに効果的です。
そして、実はこの質問の最も重要な意味は
”なんのために?”
“誰の為に?”
の回答にあります。
絶対に答えてはいけない、否定される答えがあります。
それは“自分の為に”
映画監督は”自分の為”に映画を撮ることはありえないのです。
それ以外なら何でも良いです。
お金のため。観客のため。名声のため。
しかし”自分のため”という曖昧な回答は即否定されます。
そして、撮っていけば分かりますが、これはプロとしての映画人ならありえない答えなのです。
試しにこの3つの回答
お金のため。観客のため。名声のため。
まん中の”観客の為”意外は一見、自分のエゴの様に感じますが違います。
この3つはいずれも達成されれば自分以外の別の人にも何らかのメリットを与える事になるからです。
お金のため。→作品が売れる→スタッフにもお金が入る
観客のため。→楽しんでもらえる→多くの人に見てもらえる→売れる→スタッフにも…
名声のため。→有名になる→スタッフもその名誉の恩恵を受けれる
映画は多くの資金、多くのスタッフを使って完成させます。
“自分のため”という回答は、自己完結であり、具体的な目標設定とはなり得ません。
多くの若い人が勘違いしがちですが”自分のため”の答えの先には何もありません。
何処までいっても、明確な答えも、行動の伴う結論も出てきません。
具体的な目標設定の無い人間に人は付いてきません。
映画監督はセンス、才能はもちろんの事、人を動かすということが最も重要な仕事の1つになります。
映画監督は常に“どうすれば人が動いてくれるのか”を考え実行し続けなければならないのです。
その為に“自分のため”という回答を捨てる事から始めなければなりません。
ここで見えて来るのが質問者としてのあり方。
このメソッドの重要な部分は回答者と質問者、両方の立場が監督に必要な能力を鍛える事になるという事です。
もし、回答者が質問に対して曖昧または自己愛的な回答をした場合、すぐさまそれを否定した上で、具体的な回答に導いていくのが質問者の役割なのです。
自分たちが納得できるまで毎日、15分、1週間も続ければ映画監督の自覚と共に質問者、回答者としても成長できます。
また、最初のうちはこの質問の様子を録画しておき、後に自己分析に当てるのも手です。
そして、常日頃から両方の立場を意識する事で、自然に自分自身に質問を出し、具体的な答えを導いた上で、的確な指示へとつなげられるようになります。
この訓練のおかげで、それまで犯しがちだった、曖昧な批判、抽象的な支持が無くなり、仕事上での指示、コミュケーションがかなりスムーズになりました。
この方法は映画監督以外の "何者になりたいか" というはっきりとしたビジョンを持つ全ての人に有効だと思います。
皆さんも、試してみては如何でしょうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
