
【研究ノート】ノスタルジーの解剖学(2)~1980年代とはどのような時代だったか~
1970年代記号論と文系エリートのユートピア
土地は言葉を生み、言葉は人間を生む。言葉も人も、一度生まれてそれで固定されるというものではなく、日々、その幻影のような形を変え、手触りを、匂いを、温度を変えつつ、徐々に同一性を確立させ、やがて原初の土地と何の関わりもない人々の耳目にも否定し切れない実在として映るようになるものではないかと思う。あたかも名前のない記憶が、時間の流れに対してささやかで粘り強い抵抗を水面下で続けているように。我々は通常、そのような過程や経緯を「関係」と呼ぶ。土地と言葉は心を通して関係する。その関係がまた、感情と感情、思念と思念、概念と概念の間を結びつけるのである。しかし、このことは忘れられた。土地と心の原初的なつながりが意味を生み出すという人間文化と精神的伝統の基本は、コミュニケーションを非時間的・非歴史的なものとして設定した記号論(Sémiologie)の隆盛以来、失われてしまったように思われる。
1960年代から1970年代にかけて、ソシュール(Ferdinand de Saussure, 1857-1913)やレヴィ・ストロース(Claude Lévi-Strauss, 1908-2009)に触発されたヨーロッパの文明批評家(エーコ、バルト、デリダ、グレマス、バンヴェニスト)は数々の「文化というシステムの理論」を作り出した。システムとは「意味体系」あるいは「コード」のことである。人と人、あるいは人とモノの間に、理想的には自然言語に似た記号を介したコミュニケーションが成り立つとき、そこには一貫したコードがあるとされた。記号論的文化論はこのコードの分析である。さて、1970年代、日本とアメリカの記号論者のバイブルとなったウンベルト・エーコ(Umberto Eco, 1932-2016)の『記号論』(A Theory of Semiotics, 1976年)は、ある時点で「意味」を「文化単位」と言い換え、「意味体系」を「意味場」と言い換えている。この「空間」とは観察と実験の空間と重なる。エーコが「意味」の研究についての基本的な考え方をまとめているところを引いてみよう。
a. 意味は文化的単位である。
b. これらの単位が分離できるのは、その文化の中にそれらの単位の解釈項の連鎖が現れているから。
c. ある文化における記号の研究は解釈項というものを位置や対立の体系の中で捉えることによってその価値を規定することを可能にする。
d. このような体系を措定することによって、いかにして意味が生じるかを説明できる。
e. この種の方法にしたがえば、さまざまの意味場とそれらを記号媒体の体系に結びつける規則を所有するロボットをつくることも理論的に可能となろう。
f. 普遍的意味体系を記述したようなものは存在しないから、意味場はある一群のメッセージを研究するという目的で有意義な対立関係を説明するのに有益な手段として措定されたものである。
太字筆者。)
「意味場」はやがて「意味空間」と言い換えられる。
「記号媒体の意味とは何か。意味体系の中で正確に規定された「空間」の中に措定された意味単位のことである。
これらは「純粋なコミュニケーション」のシチュエーションをモデライゼーションするためにエーコが便宜的に行った用語の変換である。しかし、そこで必然的に起こること、否、起こったことは、記号論的な「意味」生成の理論から時間性という「外部」が除外されたということだ。記号論が手本とした構造主義文化論にとっての最大の「外部」が歴史だったことは言うまでもない(ミシェル・フーコーの1963年『言葉と物』は非歴史主義のマニフェストであった)。そう考えれば、記号論はその土台から非歴史的な機構であることを志向していたと言ってもいいかもしれない。いきおい、記号論がその再構築を試みた「文化」という機構についてもまた、歴史的要因を排除したものの見方が適用されていたと考えられよう。
もちろん、1970年代記号論がコミュニケーションの図式から歴史的考察を排除したことの背景には、記号論者の「科学的」厳密性への志向があっただろう(実験科学は基本、実験室という密室で時間を限って、しかも繰り返し、行われる)。またそこに、超歴史的な「普遍言語」という西洋の伝統的な夢想の名残を聞き取ることも可能だろう。しかし、私自身は、何よりも戦後ヨーロッパの知識人が近現代の自国の歴史に覚えていた屈折した心情にその理由の大半は見出せると思う。
1960〜1970年代のヨーロッパには、植民主義から二度の世界大戦にいたる自国の歴史を感情抜きで直視することのできる知識人はいなかったはずだ。しかしそれでも、彼らには「現代」を解かなければならないという使命があった(サルトル以来、ヨーロッパの知識人の役目には「現代の解読」がある)。ソシュール言語学や構造主義的人類学が1960年代の新たな学術の希望として表れ、記号論がヨーロッパ・アカデミズムの未来とみなされるようになった事情は、背負いきれない過去の重さというファクターを考慮して考えなければならない。文化論が学問であり続けるためには、一旦歴史の法廷から離れた場所に置くことが必要だと、彼らには思われたのではないだろうか。
一方、ヨーロッパの構造主義と記号論とを誰よりも早く歓迎し、熱心に学習し、伝導に努めた日本の知識人たちは、果たしてヨーロッパの先生たちと同じような歴史への忌避感と暗い罪の意識を抱いていたのだろうか。
事実はむしろその逆だったと言わざるを得ない。
1970年代後半から1980年代初頭にかけて、日本の新興中流階級の感性は完全に過去から離れていたと言っていい。田中角栄(1918-1993)の土建政治は地方に長く前近代的な心性を蔓延らせたが、石油ショックとロッキードがそこからの解放をもたらした。このスキャンダルが解禁したものは、金権政治の闇だけではなかったに違いない。
1980年代に入って、日本の大衆は世界にも稀な情熱を持って、生活からあらゆる「古いもの」を排除し、「新しいもの」を追い求め始めた。企業と国民の水も漏らさぬ関係、毎年史上最高レベルを更新し続ける貿易黒字の数字がそこに追い風をかけた。1956年の「もはや戦後ではない」宣言から20年後、東京は「371に上る世界中の金融機関の駐在事務所」を集め、「超高層ビルが林立」する「ロンドンとニューヨークに次ぐ世界第三の国際金融センター」(朝日新聞、1987年1月22日朝刊、20面)となっていた。1987年1月に1ドル158円だった円は、同年12月のひと月で132円から121円へと跳ね上がった。そしてそれ以後、そのレベルは定着した。「日本がまだ貧しかった時代」は、若者の耳には遠い大陸の発展途上国の物語よりもエキゾチックに聴こえたものである。戦争の話題を持ち出していいのは年間の決まった時期、決まったフレームワークの中においてと限られており、また持ち出すことを許されているのも野坂昭如くらいのものだっただろう。それは端的に、野坂がエキゾチックな話題にふさわしいエキゾチックなパーソナリティーをメディアから与えられていたからに過ぎない。
つまり、ヨーロッパが歴史との折衝と相克の中でヒューマニズムの継続の方法を探っていたのと同じ頃、日本は軽々と歴史的煩悶を乗り越え、文化を自在に交易する未来をすぐそこに見ていたのである。歴史にとらわれて身動きが取れないヨーロッパの「後進性」を尻目に、広告産業と記号論に支配される消費社会を実現させつつあった。さらに言えば、ヨーロッパのエリートの特徴である経済へのコンプレックスは日本の選良にはなかった。1980年代、歴史を振り落とした日本のニューアカにとって「文化は経済、経済は文化」というスローガンは恥ずかしいものでも、堕落したものでもなく、むしろ日本が先鞭を切って世界に示すべき「先見の明」であった。
とは言え、古典的マルキストの柄谷行人や吉本隆明などは消費社会の到来については紋切り型の見解しか持っていなかったし、構造主義について日本の誰より知っていると言わんばかりの蓮實重彦にいたっては、高邁なフレンチ・エリートに自己投影するあまり、経済事象に文化の説明を見るなど想像もできないようだった。ここでも文化論者としての面目を躍如するのは、経済史の知見を備えた浅田彰であろうか。
彼が1989年に佐藤良明・巽孝之と繰り広げたトマス・ピンチョンについての会話には、アメリカ現代史についての概観が述べられているが、日本に十分当てはまる。
(浅田)時代論的なことをものすごく単純に割り切って言っちゃうと、こうなるんじゃないでしょうか。60年代というのは(...)科学技術の進歩と経済の高度成長、他方ではそれに対する反体制運動や前衛芸術運動が盛んだった。後者の側には、反科学の代表として、ドラッグ・カルチュアみたいなものをつけ加えておくこともできるかもしれない。そういうものが、60年代末から70年代はじめの爆発と挫折を経て、70年代以降、宙づりのエア・ポケッットみたいな状態に入っちゃったんですね。この状態は一般にポストモダンと言われますが、要するに、生産とテクノロジーよりは消費とセミオロジー[1]が前面に出て、消費社会の表層を空虚な記号の群れが覆う時代、「科学」の時代ではなく、「文化」の時代だったわけです。しかし、1980年代後半になると、そういうポストモダン的な記号のゲームが飽和してくる。(...)3〜4年前から急に、ハイテク、ハイテクと言われ出してまたまた時代の前面に踊り出してきたわけですね。(...)つまり、「文化」の時代においては野暮なものとして遠ざけられていた経済、とりわけ世界経済を貫く貨幣と資本のパワーみたいなものが、またまた前面に出てきたという感じがあるわけです。要するに、仮に消費社会の記号のゲームとしてのポストモダニズムというものがあるとすると、それがある程度飽和する一方で、それを突き抜けるようなテクノサイエンティフィックなパワーや、経済的・政治的・軍事的なパワーが、再び時代の表面に露呈しつつある。

1960年代=製造と技術の時代、70年代前半=石油ショックと反体制と反核の時代、70年代末から80年代前半=「文化」と記号消費の時代、80年代後半以降=マクロ経済と金融の時代という流れは、大まかに言って同時代の日本の大衆も経験した通りである。ただ、文化の表層性をより記号論の「非歴史性」と絡めて考えるとき、この図式もまた、エリートにしか関わらないということは明らかであるし、それは日本もアメリカも同じであろう。
ともあれ、日本人は歴史から解放された「文化」の可能性を、増殖する広告言語の中に見た。それは、少なくとも1980年代においては、西欧に対する日本の「文化的」優越を指し示していた。例えば、蓮實重彦が1977年の『反=日本語論』で日本語に与えた、きわめて「ポストモダン」な性質にもそれは明らかである。
蓮實によって、日本語は「意味と音声と表記法の自由な戯れを可能にした言語」、「無知と誤解から生じた豊かな(言葉の)増殖ぶり」を披露する言語、という特権的な立場を与えられた。そのような言語を継承した日本人は、ヨーロッパ近代の合理性を超えて未来に有効な「超現代」的論理を保有していることを示す義務がある、と蓮實は暗示する。我々は、ヨーロッパ的ヒューマニズムをはるかに凌駕するヒューマンで寛容な文化を育む能力を遺伝的に備えていることを証明すべきである、と。あらゆる外来の記号を、小賢しい吟味などせず、「言葉が言葉になろうとする子供の薄明の意識で」受け入れてきた日本語である。その存在は、1980年という「文化」の時代を前にして、新しい言語的創造のあり方を告げているのだ、と。そう、1980年代は学のない日本人が、日本語話者であるというだけで、西洋インテリを啓蒙する立場に立つことができる時代だ、という種類のメッセージが、この有名なエッセー集のいたるところに隠されている。
(日本語の)意味と音声との表記法との多様な戯れは(...)西欧形而上学の今日的崩壊過程へと向けるわれわれの視線を鍛えうる役割をも担っている(...)。
しかし、先に述べたように、蓮實の切々とした「西洋文明批判」は、その雄弁と比例するように表面的である。なぜなら、彼は根本的に規範と制度の従順な信奉者であるからだ。その証拠に彼の批判の方法自体がヨーロッパ記号論者の教えを忠実に踏襲したものにすぎない。『反=日本語論』が発する「異種表記混淆言語」礼賛のメッセージは、その理論的な支柱をエーコやバルトの記号論に負っている。そして、すでに見た通り、そうした記号論の特徴と成功の理由は、「意味生成」を「空間」の問題に帰し、「意味」から歴史性を剥奪したところにあった。それにより、1970年代の記号論は「記号」そのものには総じて深い内容はなく、基本、無色透明で無謬であるという幻想を生み出した。その頃、日本の大衆は未来を思考するあまり、現代史における主体の意識を持つという意味での歴史感覚を完全に捨て去っていた。彼らの目に、そうした無謬の「記号」の群れ――時に符牒、時に商標、時に情報として現れ、常に同質的な空間に並置され、それを受け取る消費者に統語法的な解析を要求しない—は、来るべき国際社会(日本が主導的役割を演じるべき国際社会)の通貨として映ったのだった。
1970年代の記号論は、林周二の「大衆の浪費を刺激する10の戦略」(『流通革命』、中公新書、1962年)の線に沿って、すでに軌道に乗っていた消費社会の要請に応えるものとして現れたのか。あるいは、記号論が言葉を消費物に変えていく中で、「文化」の意味合いも変わってきたのか。それはわからない。ともあれ、そうした記号論がなければ、蓮實の日本語論もなかったことは確かである。そして、いかに彼が日本語を例として「意味と音と形の戯れ」の言語学を「豊かで創造的な肯定の場[1]」と主張しようが、それが決して大衆のものにはなり得なかったことも。
エーコやバルトが唱え、蓮實が踏襲した無謬の記号のユートピアは、すでに歴史感覚を備え、言葉の深い意味を知り、欧語の統辞法を完全にマスターしたエリートたちのものであり、それ以外の人々の手に移ることはないものだった。やや唐突な比較と見えようが、ここで筆者が想像するデリダやエーコや蓮實重彦のような人たちは、あたかも『O嬢の物語』(Histoire d’O, 1954年)や映画『アイズ・ワイド・シャット』(Eyes Wide Shut, 1999年)に出てくる、仮面で顔を隠してダンジョンに集い、世間に知られてはならない背徳的な趣味に没頭する名士たちに似ているように思われる。彼らは自分達の昼間の身分を忘れて、歴史から自由になった無数の記号の果てしない戯れの中で、詩人ごっこに耽るのである。
しかし実際にこのようなユートピアに幼児レベルの頭脳しか持たない人間を集めた場合―例えば、同時期の東京の郊外で「深夜に学校に侵入して窓ガラスを壊して回っていた」中学生の群れなどを―、そこで生まれるのは文字通りの殺し合いであり、決して言語と人間精神の間の生産的で「文化的」で、ましてや「創造的」な関わりなどではあるまい。
それが証拠にとは言わないが、1980年代の日本では、記号の氾濫がかえって文化的な貧しさを作り出すという事態が起こった。それは、ポストモダンの最前線と任じていた日本の深部にポッカリと開いた暗部だった。煌びやかな記号の世界に遊んでいたエリートたちは、そのような状況を耳にするたび、なんとなく嫌な気持ちに駆られて、さらに日本から顔を背けたものだ。
記号論のポストモダン、言語不在のプレモダン、二つの世界
1980年代の日本には二つの隔絶された世界があった。
一つは、先に見たような、豊富な言語資産に飽いた人々が未来の「国際情報化社会」に向けて記号論との信用取引を進めていた世界。もう一つは言語不在の世界である。そこでは、1960年代までは僅かに残されていた文化的資産が急速に価値を失い、その空白に歴史性を剥奪された記号が雪崩のごとく流れ込み、「豊かさ」や「力」の幻影を作り上げていた。
1970年代後半より増大の一途をたどり、81年に統計上のピークを迎え、84年には政府が乗り出した「教育現場の荒廃」の問題はもちろん後者において起こったことだが、その根本的な理由は、二つの世界の隔絶にあったと思う。歴史性を自ら放棄した記号論が知的枠組みを作ったようなバブル前夜の日本の知性の「爛熟」、そのシニカルとも言える知的消費主義の主張、そういったものと、1970年代末から80年代半ばまで毎日のように新聞を騒がせた「校内暴力」と「刑法犯少年の増大」、そして「少年犯罪の凶悪化」現象、この二つを私は同じ問題の異なる顔だったと考える。どこか深いところで、「人と言葉の関係」が病的な変容を蒙っており、それは社会の上層において知的消費主義として現れたが、下層においては激しい暴力として姿を現したのだと。
学校、特に都市部の公立中学校を「戦場と化した」とされる、まだ10代前半でありながら筋金入りの暴力団員のような振る舞いを身につけていた少年たちの暴力の内容については、インターネットサイトEdupediaの記事「校内暴力とは何だったか」に詳述されている。その具体例はここで繰り返すに堪えないが、統計の数字だけを挙げておこう。昭和56年(1981年)の『警察白書』はこう伝える。
刑法犯で補導した少年の数は、(昭和)48年から増加傾向にあったが、55年(1980年)には戦後最高を記録した。特別法犯で補導した少年も同様に増加傾向を示している。また、触法少年は、52年から増加に転じ、55年は著しく増加した。(...)昭和55年の後半は、全国各地でいわゆる校内暴力事件が続発したが、特に中学生の教師に対する暴力事件が急増して、大きな社会問題となった 。

(出典:Wikipedia Commons)
一方、1985年版『児童心理学の進歩』に掲載された「校内暴力」に関する初めての学術的調査報告によれば、
警視庁が昭和48年(1973年)から取り始めた全国的統計によれば、それから10年後の昭和57年(1982年)にかけて、対教師暴力は、71件(中学58件、高校13件)から843件(中学825件、高校18件)とほぼ10倍強(補導人数も180人から1894人と約10倍)となり、特に中学生によるものの増加と、昭和56・57年における著しい騰勢とが特徴である。
内閣府が1984年に臨時教育審議会、いわゆる「臨教審」を組織してことに対処するまで、この疫病とも言える集団暴力の現象は、警察の管轄だったのである。1982年3月の卒業式には、全国の637の中・高校に警官が出動し、警戒にあたった。翌年、1983年3月には、全国800校が警官の出動要請を出した。同年4月の社会面タイトル。「非行——82%中学校長は悲観的」(1983年4月6日付)。
警察の所見、教師や親の苦悩については同時代から多くの資料が残っているが、少年自身の精神状態についてはさほど情報がない。そう考えれば、前出の『昭和56年警察白書』(実に宝のような資料集)に見つかる「最近の校内暴力の特徴」の一説は貴重である。
犯行の手段として、木刀、鉄パイプ、ヌンチャク、モデルガンを使用したり、脅迫の言辞も暴力団まがいであるなど、凶暴性が強まっている。
ここには、この時期の集団暴力現象の言語学的性質を解き明かす要素が詰まっている。そもそも暴力とは、人間が自分と言葉との関係を一時的にせよ、決定的にせよ、放棄することに始まる。しかるに、ここに見られる中学生の「コミュニケーション」パターンは、もともと言葉というものと何の関係も持ったことのない人間のそれと言わざるを得ない。思考のアーティキュレーション(接続)のインフラがないところに、武器でもなく、防御でもない道具が、自己アピールの記号としてのみ動員されているのだ。
この中学生とまったく同時期、おそらく彼の学校から10キロも離れていない首都圏内で、外側は似ても似つかないが、言葉との関係という意味ではよく似た現象が起こっていた。1980年の芥川賞受賞小説『なんとなく、クリスタル』の主人公、表参道に住む女子大生モデルの由利もまた、一般記号を身にまとい、それをコミュニケーションの道具としている。ただ、前述の中学生とは正反対に、由利はアーティキュレーションの達人である。「気分」をデザインするほどにまで。
クレージュの夏物セーターをクレージュのマークのついた紙袋に入れてもらう。そのスノッバリーを大切にしたかった。
甘いケーキにならエスプレッソもいいけど、たまにはフランス流に白ワインで食べてみる、そのきどりを大切にしたかった。
クラブのある日には、朝からフィラのテニス・ウェアを学校に着ていってしまう。普段はハマトラやスポーティでも、パーティにはグレースなワンピースを着て出てみる。その遊びを大切にしたかった。
(...) こういうバランス感覚を持った上で、私は生活を楽しんでみたかった。同じものを買うなら、気分がいい方を選んでみたかった。

1980年代を貫くのは、こうした「世代のずれ」をからかうようにあらゆる空間を埋め尽くすにいたった意味のない記号、閉鎖的なコミュニケーションの意識であると言えると思う。
与えられなかった土地の記憶(『東京漂流』)
人間活動の源泉が言語と切り離せないエネルギーにあるとすれば、言語学者ほど、土地の問題を考えなければならない存在はいない。なぜなら、心は土地を通してしか自己イメージを結ばず、自己イメージが結ばれない限り、あらゆる言辞は虚妄であるからだ。
その前提から、互いに背を背け合う二つの世界の共通の成立項として、人と土地の関係が失墜していたに違いない、という帰結は自然に演繹された。
そうした流れにしたがえば、1970年代を通して加熱した「マイホーム」ブーム、1980年代前半に始まる時価の急騰、そして1986年から1991年まで狂乱の様相を呈する土地バブル、そうした流れが消費社会を一方で広告の支配へ、他方で暴力の勝利へと導いたことは、自明のことに思われる。
しかし、不思議なことに夥しく渉猟した当時を扱う研究書や論文や記事には、この視点を掲げたものが一切なかった。
この問題意識をストレートに、時を待たず、諦めることなく、政治的に、芸術的に語り続けた人は、言語学者ではなく、写真家であった。新潮社の『FOCUS』の創立にも関わり、中年以上の日本人なら誰もが知っている多くの広告写真の版権者であり、昔も今も大著名人の一人でおられるらしい「藤原新也」氏の名前を、私は恥ずかしながら2022年まで知らなかった。何かの論文を参照していた時、そこに載っていた『東京漂流』から一節に衝撃を受けた折まで。以下の文章である。
このような私の揺れ動く旅の続く中で、あるとき私は、意識的に日本に自分の行動の中心軸を移したい、と思ったことがある。80年代に入ってからのことだ。私は日本とアジアを往復する長い時間の中で、つい数年前から、日本と日本人の関わる問題様式の軸が、微妙に変化してきたことを、感じ始めたのである。
それは60年、正確にはあの56年を発端とする「日本人と土地」「日本人と家」との確執から派生して、日本人のかかえこんだ大きな問題意識は、それから20年を経た現在、すでに自明のこととして、生きる上の前提条件にすぎなくなったこと.....つまり、それはなしくずしのまま、新しい時代の中で、古色めき、リアリティのない問題へと凍結されていった。
(...)
時代は非情である。20年間のその「人と家」「人と土地」の確執に、何ら回答を与えることなく、なしくずしに古色めかせ、追い打ちをかけるように、新しい次の様相を見せ始めた。
この20年間、決して「人間」を育てることがなかった「新しい日本の家と土地」と社会体制という負の母胎に生まれ育った新しい人間群像。それらの群れのまにまに、今日、無謬なる確執と中心(母胎)感覚のない狂妄が見え隠れし始めている。
この一節は言葉のない人にも、封印した記憶に閉じ込めた気持ちを噴き出させる。
その頃、同時代を見る写真家の目の俯瞰の高さと洞察の深さを評価できる比較言語学者・文化評論家はいなかった。今からでもいい。彼らは自分たちが文化の符牒に飽食した西洋ミドルクラスの「ポストモダン」という傲慢な幻想に幻惑され、足元の国語の問題を見失っていたこと、通常彼らに帰されるべき現代日本の文化的現状の診断を、マスメディアの一写真家が引き受けていたという学問の惨状を認めるべきであろう。
とは言え、以下の藤原の説にはいささか反論したい。
大雑把に見ると、この20年に日本人は二つの時代を持ったと思う。一つには60年代から70年代前半に至る「人間対風土の確執」の時代である。そして他の一つは70年代後半から80年代に至る「人間対人間の確執」の時代である。つまり前近代的な価値や方法を残した日本文化が瓦解される過程で、その風土の変化と人間の間に表れる矛盾を背負わされたのが前者であり、その風土を失い、競争社会のもと、自閉的な環境や家に育ち、社会管理され、記号化された人間同士の意思や感情の疎通が絶たれようとするのが後者、つまり80年代であるように思う。
1980年、荒れ狂っていた少年たちは、自分達をある「時代」の中に置いて考えていたのではないと思う。むしろ彼らは、奇妙なやり方で区画整備された「領土」に身を置いていたのだとは言えまいか。それが言語から与えられるべき時間的な想像力を奪われた子供にとって、最後の社会性の砦、動物としての生存を守る「聖域」であったのではないだろうか。だからこそ、いわゆる「ヤンキー」と言われる種族は、「地元」から離れないのではないか。
1980年代に日本の最も弱い部分が文化的貧困の状態になだれ込んだことの理由は、言葉が歴史性を、意味が社会性を失ったことである。反対に、コミュニケーションは空間化された。実際の空間というよりも、脳内の空間の中に閉じ込められたのではないかと思う。1980年代、日本にあったのは二つの時代ではなく二つの世界、目に見えない境界線に守られた「領土」だったのではないか。そして、そうした二つの世界が隔絶されていながら表裏一体を成していたこと、それこそが日本の悲劇ではないのか。
金属バットとコンクリ事件の記憶
藤原新也は、1980年代の病理を告知し、象徴する悲劇を、1980年11月に起こった事件に認めた。川崎で20歳の浪人生が起こした「金属バット両親撲殺事件」である。
彼はこの事件を通して戦後史批判を試みた。そのために、まず新興中流階級の成功の記号としての金属バットを撮ろうとした。その考えを述べた文章は、『東京漂流』でも最も広く知られたものの一つである。
もし、写真家としての私に、80年代の日本を一発ワンショットで撮れ、という乱暴な注文が与えられたとするなら、迷わずに、一柳展也が両親の額めがけて振り降ろした、あの金属バットを撮る。
撮影方法も、よく警察で発表される物的証拠写真のように暗いオドロオドロしいものではなく、たとえば雑誌『ポパイ』のあっけらかんとしたカタログ写真に載っているスポーツ用品のような撮り方をする。実際に私は、一柳展也の使った金属バットを、80年代の御神体のような感じで撮りたいと思っていた。
(...)
戦後36年の歳月をかけて造り上げた一つの城が、朝顔の露のように、あっけなく消え去ったこの戦後人生の構図。これは、戦後日本における時間の図表であるとともに、80年代日本家庭を俯瞰して描き出される、一家の隠された家相図でもある。(...)戦後の「家」と言うものの中から御神体とか神棚とかは消え去り、それに代わって一本の金属バットやテニスラケットが家の片隅に立てかけられたのである。私はその物(ブツ)を、80年代日本の家庭の反面御身体として撮影したかったのである。。
しかし、凶器が警察に押収されていたため、この願いは叶わなかった。そこで彼は一柳家の戸建そのものを撮ろうと思った。
私はその「事件の家」を撮る場合、その家を、惨劇の起こったイメージに沿って、例えば、鬱々とした雨雲の低く垂れ込めた日であるとか、嵐の吹き荒ぶ凄惨なイメージの日に撮ることは、その家の現実を表さないと考えていた。(...)
私が「事件の家」を撮る場合、方法として選んだのは、毎週金曜日の新聞の朝刊に折り込み広告として誰の家にも配達される、あのアート紙にカラーで印刷された「不動産屋建築広告」の写真の技法であった。
(...)
なんだこれは不動産屋の写真じゃないか、と言う言葉の背後には、何だ、これは、日本のどこにでもある、という思惑が読み取れる。さらに言えば、何だ、これは、私の常日頃み慣れた私の街や私の家や、その周辺の家と何ら違わないじゃないか、と言う意味に収斂できるはずだ。
私は、その意味に収斂させていくために、あのような不動産広告的写真技法にのっとって、「一柳家」を提出したのである
藤原新也が行ったことは、記号への歴史性の返還である。同時期、言語活動を生業とする東西のエリートが歴史性を否定するところに成り立つ記号論に魂を売っていた時に、この写真家は、大衆に向けて売り出された商品の合金の肌の下から、それを手にした人々、さらには彼らの父母の、祖父母の喜びと悲しみまでを読み取り、表現しようとした。商品経済が押し潰した「人間」の復権を、彼の持ちうる手段の中で試みたのである。これこそが批評であり、すべからく正統的に行われた批評がそうであるように、思考を通した言語の再創造であると思う。
藤原新也の写真を通した1980年代の闇へのアプローチは、言葉を通して、言葉との対話の中で、現実を深化させる方法を探している人間を皆、立ち止まらせ、深刻な方法論的懐疑に導くだろう。創造的活動とは、多言語の境界を交錯する「意味と音と形の戯れ」を弄んで、一人「詩」に似たものを彫塑していることばかりではないはずだ。
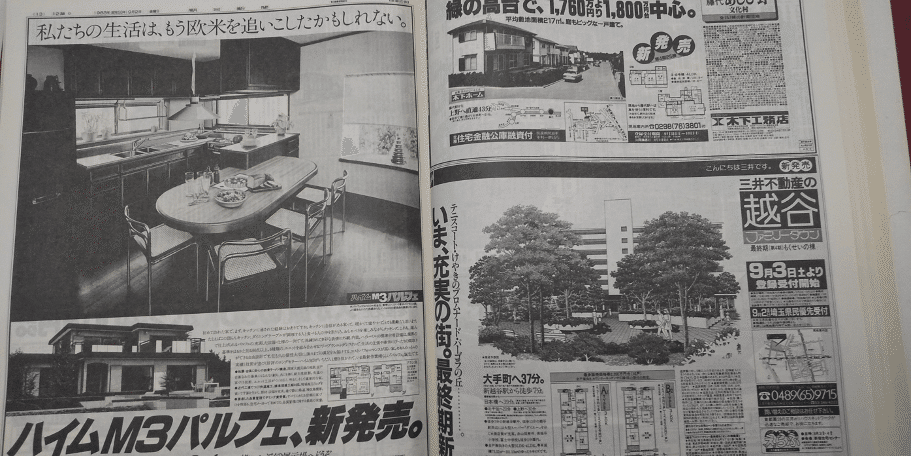
世代の違いからか、私は1988年末から1989年初めにかけて起こった事件がそれまでの20−30年の日本に起こっていた陰湿な言語統制を白日のもとに晒したと思っている。足立区綾瀬で16歳から18歳の不良グループが起こした「女子高生コンクリート詰め殺人事件」のことである。長く、「あの事件」という言い方でしか示すことができなかった事件だ。
犯人や被害者と同世代だったということもあるだろうが、この事件が私にとって決定的な文化史指標としての価値を持ったのは、それだけの理由ではない。藤原が70年代に行ったように、私自身90年代後半から2000年代前半まで10年以上日本を離れ、その視点から日本の現代現代文化史の指標を自分自身で作り上げざるを得なかったからでもある。そのまま日本にとどまっていた知識人にとって、90年代を禍々しく彩ったオーム真理教の事件、あるいは権力を掴んだフェミニズムにとっての尽きることのない現代史理論の源泉ともいうべき東電OL事件が、バブルの終焉における人間の孤立と分裂を際立った形で象徴する事件であったとすれば、そうしたジャーナリズム言説に覆い隠されてしまったような80年代の子供の暴力とその行き着いた先は、紛うことなき日本の記号論的「バブル」による人間性の目に見えない崩壊の象徴として映ったのである。
私が欧州への期限を決めない勉学の旅に出た頃、一般大衆はまだ世界中で強い円の効力の恩恵に預かっていた。しかし、遠くから見た「繚乱ニッポン」は実に暗い顔をしていた。日本の誇る「24時間闘える」企業戦士のみならず、欧米を遠征して前衛美学としての「ジャパネスク」の広報をしてまわる文化人・知識人・作家たちには、何かグロテスクな自己欺瞞があるように思われた。ポストモダンは前近代を乗り越えたのではなく、それを「見えないところに」追いやっただけであるとわかっていたからだ。記号が溢れ、意味も歴史的思考も決定的に欠如した環境において、言語そのもの、人間そのものを否定するに至った暗い目の刑法犯少年たちを忘れることはできなかったからだ。彼らは突然変異したミュータントではなく、むしろ日本社会の典型的な落伍者であり、日本の宿痾を負う人々であり、日本にしか生まれない怪物と思われたからだ。
海外にいる間に、次第に「コンクリ事件」はそれなしには1980年代を考えることはできないような象徴的な事件と思われるようになり、それゆえに1980年代を語ることがタブーとして心にのしかかるという苦しい状況が長く続いた。
荒川の渡しと二つの日本
事件の経過そのものについては、ここで一瞬でも振り返るつもりはない。ただ、藤原新也の問いかけを私も自分に投げかけてみたい。「もし、1980年代の日本を一発ワンショットで撮れ、という乱暴な注文が与えられたとするなら」、(写真家ではないが) 何を撮るだろうか、と。答えはわかっている。「女子高生コンクリート殺人事件の犯人、A、B、Cが、遺体を詰めたコンクリートのドラム缶を車に乗せて、荒川沿いに足立区から南下し、荒川の向こうの江東区の埋立地を目指して西に車を向けた時に見えた東京湾にかかる橋」を撮るだろう。
そう思わせたのは、事件直後に横川和夫が発表したルポルタージュに転記されていた調書の一文である。
昭和63年(1989年)1月5日夜8時ごろ、(被害者の遺体をドラム缶に入れた犯人A、B、Cは)ワゴン車で東京湾に向かった。海に捨てるつもりだったが、途中に怖くなり、江東区若洲海浜公園整備工場現場の空き地に捨てて、逃げ帰った。
何も怖いものはないはずだった野獣たちが、なぜここにきて「怖い」と思ったのだろう。何が怖いと思われたのだろう。足立区の片田舎の10代の少年にとって、港湾はあまりに巨大で荒々しかったからだろうか。太平洋を前に、3人は自分の惨めさを身に染みて感じたか。そのように想像することもできたが、その前にそれ以前の彼らの非行の足取りを地図上に追ってみることにした。いくら追っても、彼らは足立区に生まれて以来、決して荒川の西に出向いたことはないように思われた。少なくとも、東京の他の区で悪事を働いたことはない。あたかも東京の中心に何か彼らを弾き出すものがあったかのように、車で動くときも、自転車で移動するときも、彼らは常に足立区から東、あるいは北東の方向の埼玉や千葉に向かうのだった。
1988年8月、被害者の女子高生を拉致した3ヶ月前、免許を取ったばかりの主犯の「少年A」は、父親より車を買い与えられた。 車という移動手段は首都高のネットワークを彼らに開いた。1980年代は、工場地帯であった荒川と隅田川の東を新しい首都高のネットワークのジャンクションポイントとして開発した時代でもあったらしい。1982年、首都高速中央環状線(C2)が開通、1985年には三郷JCTが完成し、日暮里の北の小菅から足立区の北部を通って埼玉の三郷へ向かう首都高速6号三郷線が完成した。この線によって、少年たちの車はそのまま柏へ、流山へと常磐道に乗って向かうことができるようになったはずである。1988年11月初めには婦女暴行略取の目的で、3人の無為徒食の輩は車で徘徊していたのだが、近隣で無理やり車に乗せた若い女性に、こう言って脅したと言う。「このまま柏へ行くか、それとも栃木の山奥へ行くか」(東京高等裁判所刑事第10部(1991年7月12日)、控訴審判判決本文)。しかし、その行動半径の狭さを鑑みるに、脅された女性よりも、柏や栃木という「遠いところ」に行くことを最も怖がっていたのは、あらゆる捕食動物がそうであるように習慣性の生物であったこの3人であっただろう。

1980年代より続く首都高ネットワーク
綾瀬を拠点として、首都高中央環状線と首都高三郷線の周辺から付かず離れず動いたとき、その移動の基準は自ずと見えてくるであろう。3人の未成年犯罪者たちは、一度も荒川を西へ渡ったことがなかったのである。おそらく、ドラム缶を積んだワゴン車で葛飾区を南下し、いずれかの時点で西に曲がったとき、初めて「荒川の西」という未知の世界、これまで意識の外から締め出してきた「あちらの世界」へ渡ろうとしていることに気がついたのではないだろうか。
昭和最後の年が明けたばかりだった。昭和天皇の臨終は近づいていた。そのような時、東京葛飾の場末から乗り込む高速には、行き違う車はほとんどなかっただろう。道は真っ暗で、エアコンのない車の中は白い息が立ち込めていただろう。話す言葉もないまま、彼らは自分達の「領土」から離れなければ、この車に積んだ「死」からも逃れられないことを感じ、同時に、領土から離れることはすなわち彼ら自身の「死」を意味するのだという気持ちが高まるのを感じていただろう。
この事件が1980年代日本の亀裂を露見するのは、震える手でハンドルを握る「少年A」が左目の端に東京湾の果てしない広がりを目に捉えた時だったのではないかと考える。そして、この事件を語るにあたっては、この瞬間をどこまでも分析することで、ほんの一端でも、1980年代にその魂を返すことができるように思う。

1980年代、日本には二つの世界があった。そのはざまで失われた青春があった。なぜそのようなことが起こったのか、個人の運命を超えて、土地と言語の関わりからもう一度考えるべきではないだろうか。
(2022年9月あるシンクタンク雑誌に初公開ー再使用許可取得済)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
