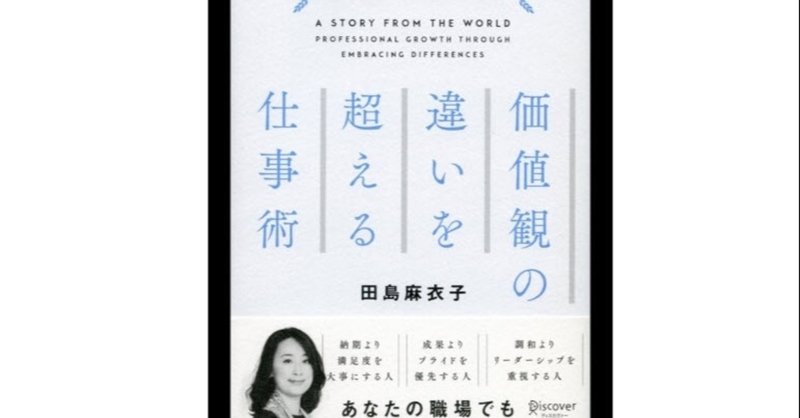
【書評】国連で学んだ 価値観の違いを超える仕事術 田島麻衣子
読書をしていて有益だと感じるのは、自分では決して経験できないような経験をしてきた人から、みっちりと話を聞けることだ。私はあまり外国人と接する機会がないので、外国人と日本人の違い、外国人から見た日本人について聞くと新鮮に感じる。
ゴールを大切にすること
パラパラ読みしていたのだが、繰り返し「ゴール」というキーワードが出てくることに気づき、1章に戻って読み始めた。どれだけ価値観が違ったり、個性があっても、共通のゴールがあれば、それなりに仲良くなり仕事を進めていけるというのがこの本のテーマになっている。
周りに合わせることを主軸にとらえてしまう日本人(私)は、目の前の相手に合わせることが目的になってしまい、やもすると会社の、プロジェクトのゴールから目をそらしてしまうことがあり得る。それでは意味がない。表面上、いくら仲良くできているようでも、チームとしては失敗なのだ。
本書の中では、アラブ人、イタリア人、アメリカ人が章ごとに登場する。筆者はもっとたくさんの人種と接しているだろうけれども、わかりやすくするために3人種に絞っている。前書きでも述べているように、これは人種のステレオタイプを強調するものではない。読み進めるとそのことが分かる。
アラブ人からは相手への気配りや尊重が学べるが、それはゴールを達成するという目的を持ったものなのだ。イタリア人の陽気な雰囲気づくり、誉め言葉もチームの雰囲気をよくしてゴールを達成するという目的を持ったものだ。アメリカ人はなんでも思ったことを言うように見えるかもしれないが、実はそうではなく、ゴールに合わせて自分を出したり控えたりしている。
外国人の働き方に照らしたときに、日本人がいかに「空気を読むこと」(周りに合わせること)を重視しているかを振り返ることができた。会社やチームがプロジェクトを行う時には、ただ仲良くするだけではなく、皆で前に進んでいかなければならない。そして、前に進もうとする推進力こそが、チームを一つにする力であることを学べる。
ゴールを達成するのに必要な性格を身に着ける
この本を読んで、私が思ったのがエゴグラムのAC・FCのことだ。ACは「従順な子供」をFCは「自由奔放な子供」を表す。私の場合だとACが高すぎるので、FCを高めるという行動処方になることが多いが、ただ単純にFCを高めるだけでは、問題は解決しない。
本書の中に登場するアメリカ人のように、なんでも思ったことをハキハキ言えるFCも大事だし、争いにならないように身を引くACも大事。大切なのは、それをふさわしい場所で表すA(成熟した大人)なのだ。
Aのコントロール力こそが、社会で働くためには必要だと分かる。外国人は日本人と違って自由だとか、遠慮しないというステレオタイプがあるけれど、大事なのは、ゴールのために必要な性格・人格を表すということだ。
パーソナリティの語源は「ペルソナ」(仮面)なのだから、性格というのも固定されたものではなく、必要な時にかぶる仮面(良い意味で)と考えると腑に落ちるものがある。
ただ自分を表現しよう!とか、もっと楽になろう!とか、素の自分、ありのままで、、と考えすぎると、仕事・プロジェクトを行う上では、大事なところがすっかり欠落した人になってしまうのかもしれないと気づかされた。豊富な国際経験を分かりやすく教えてくれた筆者に感謝!
エゴグラムに関して詳しくはこちら。
大人のADHDグレーゾーンの片隅でひっそりと生活しています。メンタルを強くするために、睡眠至上主義・糖質制限プロテイン生活で生きています。プチkindle作家です(出品一覧:https://amzn.to/3oOl8tq)
