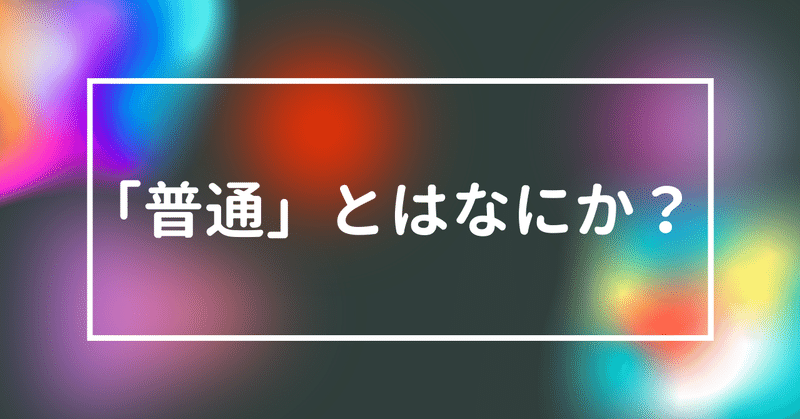
「普通」とはなにか?自分と他人の「普通」はなぜ違うのか
普通に勉強して、普通に働いて、普通に結婚して……
学生時代にそんな冗談をよく口にしていたが、はたして「普通」とはなんなのだろうか。多様性、アンコンシャス・バイアス、LGBTQなど、世界の「普通」は次々に変わっていく。
正直に白状してしまえば、僕自身は知識として頭に入れているつもりでも、心がまったく追いついていない状態にある。
同性愛やアセクシャルなど、長年付き合ってきた身近な人に打ち明けられたとき、心に1%のわだかまりもなく会話ができるのか不安である。動揺しないで平静を保ち、打ち明けてくれた友人の心を暗くしてしまうことはないだろうか。
特に変わっていないこと。ごくありふれたものであること。それがあたりまえであること。また、そのさま。
あたりまえってなんなのだろうか。よくよく考えてみたら大人になって「普通」という言葉と真剣に向き合ってこなかった。
変わりゆく世界の中で今一度、「普通」という意味を噛み砕いておくべきなんじゃないだろうか。
自分の中で「普通」を再定義することにした。
結論:普通とはそれぞれが持ったものさし
ここから僕が本やコラム、映画などを見て、「普通」について調べたことを書いていく。しかし、かなり長いので先に結論だけ述べておこう。
「普通」とはそれぞれが持っている基準を决めるものさしである
「普通」は自分を取り巻く環境で変化する
貧富の差がある子供の「普通」はまったく異なる
友人、学校、社会など、自分が身を置く環境で「普通」は変化する
時代やマジョリティによって「普通」は変容していく
1分前まで常識だったことが非常識になることもある
ここから調べたことや、結論に至った考えなど、現時点での自分が思う「普通」についてをつらつらと書いていきたいと思う。
「普通」を考えるキッカケになった「コンビニ人間」
「どうしたの、恵子?ああ、小鳥さん……!どこから飛んできたんだろう……かわいそうだね。お墓を作ってあげようか」
私の頭を撫でて優しく言った母に、私は、「これ食べよう」と言った。
「え?」
「お父さん、焼き鳥好きだから、今日、これを焼いて食べよう」
コンビニ人間の主人公である古倉恵子は「普通じゃない人」として描かれている。
他人の感情がわからず、善悪の判断がつかず、幼少期にはすでに自分自身が「普通ではない」ということに気づく。そこからは他人と一切関わらないと決めて学生時代を過ごす。
私はバックルームで見せられた見本のビデオや、トレーナーの見せてくれるお手本の真似をするのが得意だった。今まで、誰も私に、「これが普通の表情で、声の出し方だよ」と教えてくれたことはなかった
恵子は大学生になってコンビニでバイトをすることで、人と会話する術を初めて得ていく。コンビニは学校とは違い、すべての人間がマニュアル通りに働いている。陳列された商品と同じように、働く人間の行動も均一な世界なのである。
ただし、恵子は世間の人から見て「普通になった」わけではない。恵子の行動はすべてコンビニで働く人間を模倣しているだけだ。会話、仕草、洋服、髪型など、そこに自分の意思はない。「あの人ならこう言うだろう」というパターンを真似して、形だけを世界に馴染ませているような状態だ。
私の摂取する「世界」は入れ替わっているのだから。前に友達と会ったとき身体の中にあった水が、今はもうほとんどなくなっていて、違う水に入れ替わっているように、私を形成するものが変化している。
だから、コンビニで働く人間が入れ替われば恵子の性格も変わっていく。
世間から見たら「普通ではない」が、恵子にとっては人の行動をコピーして生きることこそが「周りに合わせて普通にする」ことなのである。
コンビニで働くことが世界との架け橋になった恵子は、大学1年生から30代半ばまでずっと同じ場所でバイトを続けていた。
そんな生活をしていると、やはり世間からは好奇の目を向けられる。そして「就職」や「結婚」の話題をもちかけられる。
しかし、他人に婚活の話を持ちかけられても、恵子にはなぜ結婚をすべきなのかがわからない。恵子の「普通」には「結婚」や「世間体」という概念がないのである。
「それって、やってみるといいことありますか?」
素朴に尋ねると、ミホの旦那さんが戸惑った表情になった。
「いや、早い方がいいでしょ。このままじゃ駄目だろうし、焦っているでしょ、正直?あんまり年齢いっちゃうとねえ、ほら、手遅れになるしさ」
「このままじゃ……あの、今のままじゃだめってことですか?それって、何でですか?」
純粋に聞いているだけなのに、ミホの旦那さんが小さな声で、「やべぇ」とつぶやくのが聞こえた。
友人たちの世界では「30歳を過ぎたら結婚するのが普通」であり、そこに疑問を持つ恵子は完全なる異物なのだ。
「このままじゃ……あの、今のままじゃだめってことですか?それって、何でですか?」
恵子の結婚に対する疑問は、僕自身が持つ「普通」を揺るがす一言でもあった。
「30歳になったら結婚する」ということを自然と受け入れている自分がいた。自分自身が「なんとなく世間体で結婚しなければならない年齢」という強迫観念にかられている事実が今ある。
なぜ、30を超えたら結婚することが自分の中の「普通」として脳にインプットされているのだろうか。
この「普通」の感覚は一体、誰のものなのだろうか。自分の中の常識は、誰が形成したものなのだろうか?
(ポップに「普通」を扱った作品としては『まともじゃないのは君も一緒』という映画がおすすめ)
「環境」によって変わる普通
まず、確認しておきたいのは「普通」という感覚は、環境や境遇によって大きく異なるということだ。
小学生になったころ、自分の家が貧乏ということに気づいた。よその家のお父さんは昼間は働いて家にいないこと、友だちの家のトイレは水が流れることを知った。「どうしてうちは普通じゃないんだろう」姉たちはそれぞれ自立し、そのころから母は夜も働くようになり、私はひとりで夜を過ごすようになった。
「自分がどんどんクスリをやってしまう状態のとき、お母さんが怒らないのは、やさしいところでいいところって思っていたけど、それは違うっていまは考えるようになった。ちゃんと怒ってくれたほうがよかった……」
少年院にいる子の大多数は虫歯である。なぜなら、「歯を磨く」という「日常生活の普通」が存在しないからだ。
こういった環境を考えると、今の自分が持っている「普通」という基準が、いかに安全な場所からでてくる言葉であることかというのを実感する。
僕は両親にも兄弟にも友人にも恵まれて育ってきた。自分の「普通」からすると、少年院に入る少女たちの「普通」は受け入れがたい現実だ。本心を包み隠さずに言えば「普通以下」だと言える。逆に彼女たちにとっては僕の生活は「普通」ではなく、「理想の生活」になるのかもしれない。(マズローの欲求5段階の話に近い)
世界の貧困などを映像で見たときに、映画や小説の世界のように認識してしまうことがある。日本で生きて、普通に食事ができて、普通に働いていて、普通にお酒を飲んで、普通にベットで寝ていると、他の世界の普通を心の片隅では信じられない部分がある。
自分とは程遠い世界にいる他人の「普通」は、「異常」とも言えるのかもしれない。
あなたが最も長く時を共にする5人の人間の平均が、”あなた” という存在だ。
自分自身の「普通」という基準は周りの人によって形成されていくというのは経験上でもよくわかる。
今、僕が働いている会社の人たちの考えが、自分自身の考えにもなっている部分は確実にあるだろう。高校生だった頃は、周りの友人達と同じ思考だったはずだ。新しいグループに入ることで、思想や思考が混ざっていき、自分という境界線がぼやけていく。「普通」という基準は周りにいる人によって簡単に変わっていく。
「時代」「マジョリティ」によって普通は変わる
多様性、アンコンシャス・バイアス、LGBTQ、SNSによる誹謗中傷……と、ここ数年で世界の常識が大きく変わっている。生きやすい人が増えてきて、世の中が良い方向に進んでいると信じたい。
中川家のドライブをテーマにした漫才でシートベルトをつける所作がなかったという理由で漫才が全てカットになったエピソードを語り、「異常な時代やで」と発言。
ただ、最初に述べたように、時世の変化に僕自身はまだまだついていけていない。今まで自分が「普通」だと思っていたことが、次の日には非常識になっていることがあるからだ。知識としては頭に入っているけれど、心が追いついていかない。世の中の人たちはみんな本当にこの変化についていけているのだろうか……
「たしかに、昔はふつうじゃなかったことも、時代がかわるとふつうになることはあるなぁ」
「みんながあたりまえにできることができないって意味だもん!」
「なるほど。じゃあ、ふつうってのは、みんなができることってことなのか」
「そうなるね。“ふつう”は、みんなにとっての“あたりまえ”って意味だよ」
大多数の人間が「普通」であると認識したときに、「例外」は初めて共通認識として「普通」になる。
駅前で一人で叫んでいる人がいても無視をするが、それが100人にもなれば足を止めることもあるかもしれない。むしろ意見に賛同して加わる人もでてくるはずだ。
意見に賛同してくれる2人目がいると、周りで見ている人の目が変わるという側面もあるが、精神的な支えとしての役割も大きいだろう。
1人だけが「普通」だと思っていたものは、賛同者ができることで共通認識となる。その人数が増えていくことでだんだんと世の中の「普通」になっていく。
逆に一部の偏った思想を持ってしまうことがあるのは、数人の強い「普通」が共感しあえているからなのだろう。
普通をなぜ強要してしまうのか
時代や環境によって「普通」が変わっていくと認識していても、身近な人間が「普通」という道から外れてしまうことを人は恐れる。そして、自分の中の「普通」を強要してしまう。
例えばこの記事で起きるような事象は、教師が持っている「普通」と生徒が持っている「普通」のギャップから生まれる問題なのだろう。
教師側の生きた時代や自分の苦労した経験などから「学生が茶髪であることは普通ではない」という認識になってしまっている。
ただ、他人に普通を強要するのは必ずしも悪意ではない。むしろ善意や慈愛で忠告する人の方が多いはずだ。
先ほどの教師の意見も100%の悪意ではなく、「社会にでたら苦労する」という経験則からくる忠告で発した可能性が高い。
また、親が自分の子どもへ「普通にして」と注意してしまうのは、世の中の常識から外れないように「普通」を教えているからだろう。
「角」の切除を施された人たちは、初めに感じていたはずの窮屈さも忘れ、「普通」であることをみずから望むようになり、周囲の人間や子どもたちにも同じ価値観を求めはじめます。「『角』の切除をして普通になることが大人になることなのだ」という洗脳が、こうして拡大していきます。
つまり、「普通」という言葉は、さらに「標準的な」「社会適応している」といった価値観をも含んでいるわけです。ある言葉が人を縛り付けたり固定したりするとき、言葉の何がその人を縛るのかというと、このように、その言葉にまとわりついている価値観や世界観のようなものが縛っているわけです
大人になると様々な失敗を経て、世の中の辛さや厳しさが身にしみてわかってくる。その辛さを知っているからこそ、子どもに「普通」を強要したくなる。苦労をしてほしくないからこそ「普通」でいてほしいのだ
学校が「普通」を強要される場として感じる人も多いかもしれない。サラリーマンを量産するための教育と揶揄されることもあるほどだ。
僕自身は学校を楽しんでいたタイプなので、正直言ってあまりこういった意見には賛同できない気持ちがある。学校には感謝しきれない出会いもたくさんあり、学べたことも多くあった。(大学に行って友だちができずに便所飯をするまでに人生が急落するのだが)
僕自身は「学校は楽しく学べる場所」としての「普通」を受け入れられている。
この経験を考えると、事象の外側にいるか内側にいるかという立ち位置によって「普通」に感じるかどうかが変化するのかもしれない。学校において内側にいる人間はマジョリティである。成功体験があることで自分の中の「普通」になっていくのだ。
普通であることは安心につながる
小説 『コンビニ人間』で描かれているように、学校や社会において「普通ではないこと」は疎ましく感じられ、静かに排除されていく。
どうやら「自分たちと少し違う人間がいる」という事だけで、大きな不安を生む時代になってしまっているようだ。学校におけるいじめの世界では、子どもたちは多様性(みんなと違う)の獲得とそれに伴う混乱を恐れているように見える。この混乱を避けるために彼らは常に「僕らはみんな一緒だよね」と確認し合って生きていかなければならないのだ。そして、バランスを崩す可能性のある要素は排除しなければならないのだ。
周りと同じにするというのは、敵を作らないことにつながり安心感が得られる。狩猟の時代から人間はグループに属して生きてきた。グループから外れることは死に直結する。周りに合わせるという行為は生き延びるための本能なのである。
僕自身も学生時代は常に怯えていたのを覚えている。友だちが多いからこそ周りに合わせるのに必死だった。仲間はずれにされるのが怖かった。マイノリティには絶対になりたくなかった。学生時代はマジョリティにいることこそが自分の「普通」だったからだ。
鶏には順位性という習性があり、厳しい縦社会があります。例えば100羽の群れの場合、1~100番まで順位が決まり、トップの鶏はほか全ての鶏をいじめ、2番目の鶏は下位の97羽をいじめます。
いじめは人間だけでなく、動物の世界によっても起きる。力を誇示することで縄張りを作り、自分のコントロールできる世界を広げているのだろう。
人間の究極の欲求は「安心感を得たい」ということです。住み慣れた世界では心配はありませんし、強い安心感があります。しかし、未知の世界ではそうはいきません。
自分の生きている常識の世界からちょっとでも逸脱したもの、コントロールのきかないものはみんな病気とされてしまう。そのような見方をされてしまったら、両者のコミュニケーションは成り立ちません
「普通」でいるということは、日常生活を自分のコントロール配下におけるということにもつながる。周り合わせることで攻撃されず、安全圏に自分の身をおくことができる。
冒頭で「普通に仕事して、普通に結婚して……」という話は、2つの側面からでてくる言葉なのかもしれない。
周りに自分が「普通」であることを誇示する
大きな夢などを語ってしまうと他人に「普通ではない」と認識される恐れがある。防衛行為
人生を自分のコントロールにおけるようにしておきたい
「普通」はトラブルが起きずに安全
普通ではないことが可視化される時代
「普通は安心する」という一方で、SNSによって「特別」が可視化されやすい時代にもなった。
YouTuberやTiktokerなどのインフルエンサーを筆頭に、好きなことで生きていけることを目指す若者が増えたように感じる。(正確には「夢を追う若者も可視化されてわかりやすくなった」と言うべきかもしれない)
体重150kgの癒し系キャラクターのじんじんと、クールな関西弁女子のタナカガによる夫婦漫才を彷彿させるやりとりが特徴となっている。
Z世代総合研究所(Z総研)による10代から20代の男女106人を対象に行った調査を基に発表した「Z世代が選ぶ2020年上半期トレンドランキング」では「流行ったインフルエンサー」のYouTube部門で1位となった
僕自身は30代であるため、今の10代の「普通」を知ることは難しい。
そこで、若者に人気があるYouTuberはどのような「普通」の感覚なのかを知るため、パパラピーズの著書や動画を見てみることにした。
小6で母親が失踪して、養護施設に入った。父親が仕事してて「世話できんから、兄弟3人が大きくなるまで、ごめんな」って。一般家庭から養護施設へ。そのときは、家庭の事情にコンプレックスがあって、友達にもあんまり言ってなかった。当時から「恥ずかしい人生はダメだ」と思ってたから。みんなと同じように見えるようにもがいてたなぁ。
「男が好き」っていうことを、胸を張って言えるようになったのは、上京がきっかけ。東京って生きやすいんですよ。俺の周りだけかもやけど、いろんなことを受け入れてくれる人が多い。それに、人が多くて生きる場所が多いから、「ここからはみ出たら終わり」っていう感覚がなくなる。
パパラピーズのじんじんは、環境によって幼少期の「普通」が左右されていた。『女子少年院の少女たち』の登場人物と「普通」の根源はおなじものがあるのかもしれない。
どんだけ仲良くても「誘われるの嫌かな?」とか考えてもーて人のこと誘えやんからはやくこの癖直してじんじんみたいに第三者から見て普通に引くぐらいがめつく生きてみたくもある。
ただ、二人が本で語っていたことは10代や20代の男女が抱える「普通の悩み」と変わらないように感じた。違うのはパパラピーズの2人が、若者にとって「特別な存在」であるかどうかだ。
「特別な存在」になると、「普通の言葉や行動」がすべて「特別」に変わる。
特別な存在になると「親の育て方」「幼少期の体験」「過去の発言」など、すべてに意味を持つようになる。変わったのは周りがその人たちを見る目だ。
▲一番再生数の高い企画
『ウーバーイーツで1日のご飯を相方と頼み合いしてみたwww』
約700万再生されている
また、パパラピーズの企画は特殊なものよりも、モッパンと呼ばれる食事動画が中心であり、それほど「特別なこと」はしていないように見えた。
これだけ聞くと「全然、すごくない人たちじゃん」と思うかもしれない。しかし、誰かの日常生活の一部として「普通にいる存在 」になれている時点で異常で偉業なことなのである。「あなたが出ている動画を誰かが好んで毎日見ている」ということが考えられるだろうか。ファンを1人つくということの難しさは計り知れないだろう。
2人は一般人に近い「普通」の考えを持っている部分もあるかもしれないが、努力やスキルは同じ年の若者よりも頭抜けているのだろう。むしろそのアンバランスな感覚こそがYouTuberとして成功するコツなのかもしれない。
SNS=世間という認識を持っていると、可視化された数値がすべてだと勘違いしてしまう。
世の中にはSNSでは可視化されないものがたくさんある。楽しく生きている人や尊敬できる人は、SNSではない場所に山ほどいる。派手に生きる人生ももちろん楽しいかもしれないが、毎日コツコツ努力を続けて幸せに生きている人間の方が世の中には多い。
SNSがすべてだと考えている人にとっては、「普通の人生」はつまらないように感じるかもしれない。彼らにとっては「数字を出すこと」が「普通の成功」であって、それ以外は失敗と認識しているからだ。
「普通」とはそれぞれが持っている「ものさし」
様々な観点で「普通」を調べてきたが、やはり定義をするのは難しい。というより出来ないと言った方が正しいだろう。
普通というのはそれぞれが個々で持っている基準であり、「ものさし」のようなものなのだ。
また、そのものさしは自分の考えだけで作ったものではないということも理解しなければならない。環境によって「普通」はすぐに変動する。それは他人のものさしだけではなく、自分自身も例外ではない。
「普通」というのは常識であり良識であり、今生きてきる環境を表す鏡のようなものなのだ。

人と人とが出会ったときに気が合うかどうかは、それぞれの「普通」がどれだけ重なっているのかが重要だ。
仲の良かった友人や夫婦が、ライフステージが変わることで気持ちが離れていくことがある。本人たちの取り巻く環境が変わり、それぞれの「普通」が変化したことによって心が離れていってしまうのだろう。

そして、それぞれの「普通」というのはさきほどの円の画像のように、単純なものではなく、もっと曖昧なものだ。年齢、環境、体調、気分、場所、天気……など様々な要因によって変わる。境界線は非常に曖昧で、ないようなものかもしれない。
そして、この記事自体も間違いなく僕のものさしで書かれている。記載してある参考資料も無作為に選んでいるようで、僕の「普通」を書くために無意識に選別しているのだろう。
普通の許容範囲を広げることが重要
普通というものさしは状況によって変わるし、世界のものさしもすぐにアップデートされていく。そして、その「普通」を决める世界とは、友人、会社、SNS、家族など環境によってすぐに変化する。むしろ、仲の良い友人グループに誰かが1人加わっただけで、「普通」はまったく違うものになるだろう。それほど「普通」は曖昧で変容しやすいものなのだ。
他人の「普通」を完全に理解することはできないが、少しずつ知っていくことはできる。誰か一人の「普通」がわかることで、違う世界の「普通」を許容できるようになっていくはずだ。
僕自身の現時点の「普通」への理解と結論は一旦ここまでである。今後も自分の中の「普通」をアップデートして拡大していくことで視野が広がり、頭と心の両者ともに「世界の普通」についていける日がくるかもしれない。
数年後にこの記事を自分で見たときに、「過去の自分は許容範囲が狭かったな」と思えている自分でありたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
