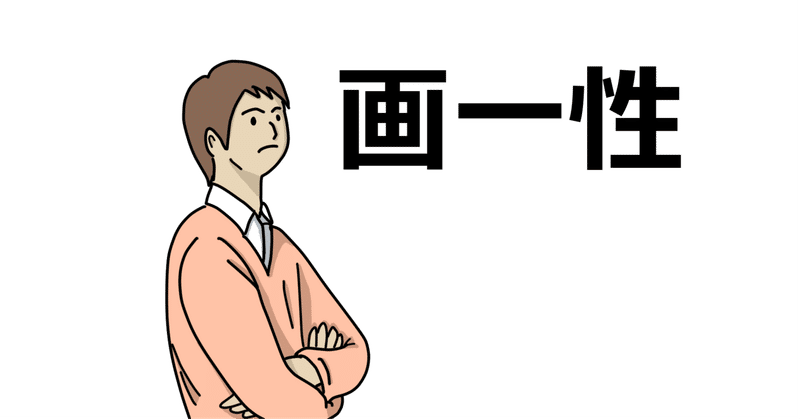
国による評価方法の画一化
学校における指導の全体的な潮流は「画一化」に進んでいます。例えば、国立教育政策研究所からは「指導と評価の一体化に関する参考資料」が出されました。これは、各教科での具体的な単元の場面を描き、そこでの評価の方法や観点などを細かく記述して説明しています。これはあくまで参考資料ですので、学習指導要領と異なり法的拘束力などの強制力はありませんが、国の機関が出している資料ということで、強制力は無くても影響力はあるはずです。
評価に関する方法を規定するということは、その指導内容にまで影響を及ぼします。例えば、「思考力判断力表現力等」を評価しなければならない場合、学習活動における「表現活動」の割合は増えてくることでしょう。例えば、体育科や音楽科や図画工作科などの「実技」がある科目では、この傾向は顕著です。学習のまとめとして「振り返りカード」などを、子供達に「書かせる」わけですが、「文章を書く」という活動には、かなりの程度「個人差」があることは否定できません。書くのが得意な子は、苦もなく自分の感じたことを言語化することができますが、書くのが苦手な子は、どの教科でも「自分の感じたことの言語化」を求められることになるので、「苦痛の時間」が増えてしまうことでしょう。しかし、「思考力も判断力」もそれ単体では「見ることも測ることもできない」以上、「表現してもらう」しかないわけで、これは評価をする上では仕方のないことになるのです。例えば、それまでは「文章は書けないけど、運動は抜群にできる」という子供は「体育で良い評価」をされていたかもしれませんが、現行の評価方法では「文章に表現できないから、良い評価はできない」と切り捨てられるかもしれません。逆に「運動は苦手だけど、自分の感じたことを上手に表現できる子」は、体育で良い評価をもらうこともあります。
問題は画一化にあります。画一して線引きをすれば、線の外側が生まれることになります。線引きには「曖昧さの排除」が含まれるわけですが、学習活動が「査定の場」ではないことを考えれば、その子の特性に応じた「曖昧さ」こそが「教育の質の担保」につながるはずですが、どうも国の方はそのように考えていないようです。
