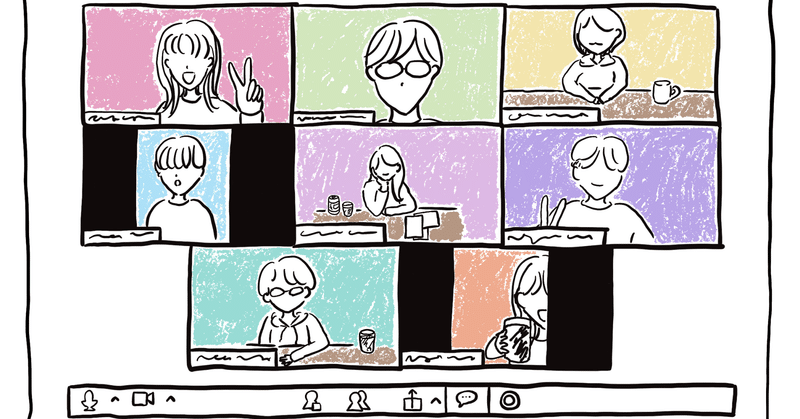
【テーマ:交通】政治を気軽に語るオンラインカフェ「コーヒー・ハウス」2021年5月26日の話題まとめ
政治への関心、知識がある人もない人も、気軽に話し合えるイベント「コーヒー・ハウス」。参加者の皆さんの関心ある話題、質問、意見、その他コメントなどをまとめます。(前回5/19の記事はこちら)
会話の流れを詳細にまとめた記録、正確な発言の記録ではありません。備忘録としてご覧ください。
テーマ:交通(公共交通機関・自転車・まちの道路事情 etc...)
今回は、「交通」をテーマに掲げてみました。参加者の興味関心などから、主に自転車政策について話し合う時間が多めになりました。
【話題】仙台市は本当に自転車の利活用を推進しているのか?
・仙台市も自転車の利活用を推進しているはずなのに、実際の街の状況をみていると、より自転車は不便に、自動車が便利になっていっている印象がある。
→自転車のマナーが悪いから取り締まりをしろという意見が多い
→マナーが悪い自転車ユーザーがいることは否定しないが、数ある交通手段の中で自転車だけが特筆しているのか?
→法律上、自転車は車道を通行しなければならないことになっているが、実際は危なくて走行できない道が多い(危ない理由:自動車による嫌がらせ、車線等が自転車を想定していない)。
・他都市の状況
→ブラジル・サンパウロでは、自転車を日常利用している人はあまり多くはない(とは言ってもそこそこいる)
→名古屋は、戦後の復興計画で幅広の道路が多い。歩道も広い。
→トヨタのお膝元が近いこともあるのか車の使い勝手が良い。駅ビルにでっかい駐車場があり中心部まで車で来る人も多い。
→車道に比べると歩道はすかすかで、自転車レーンも余裕がある(もちろん狭い道もある)。駐輪場は100円で値引き等はない。
・仙台で自転車を利用することについて、所感
→本日の参加者の9割以上が、日常的に自転車を使う機会があると回答(車を日常的に利用する人も、目的に合わせて自転車も利用する)。
→信号待ちが多いので、街を抜けるのが大変。
→一人の時は車道を走るが、家族と一緒のときは危ないので(自転車歩道通行可の)歩道をゆっくり走る。
→自転車は走りやすいと感じる。狭い橋とかを渡るときも歩道を走ってよいので(大橋や愛宕橋? ※結構歩道が狭いので、本来自転車通行可の歩道なのかは要確認)。
→自転車歩道通行可かの大きな通りでも突然歩道が途切れることがあるので、地下道や歩道橋しかない交差点は車道を走る。
→仙台市といってもどの辺りに住んでいるかでだいぶ印象が変わる。
→八幡町は走りにくい。歩道が狭く交通量も多い。
→学生なので八木山から青葉山まで自転車で移動するが、車道が狭い(車でもギリギリ)しカーブも多い。トラックの通行も多いので危険を感じる。
→自転車が車道を走る想定の道路なのに、構造が自転車を想定していなくて危険な道がある。
→国道45号線の苦竹インターチェンジ
→国道286号線の仙台南インターチェンジ付近
→隣の名取市に昨年「名取市サイクルスポーツセンター」がオープンしたが、仙台方面から自転車で向かおうとすると手前の閖上大橋を自転車で渡ることができない。
・公共交通機関との連携やシェアサービスについて
→地下鉄やバスへの輪行はできないのか?
→秋保へのバスによる輪行など実証実験が行われた例はあるが、恒常化はしていない。
→運賃はどうするか、混雑時はどうするかなど課題も多い。
→仙台にはDATE BIKEもある。シェアバイクでいいんじゃないかという感想。
→中心部に用があるときは自分の自転車は使わないでDATE BIKEを利用する。駐輪場が足りなすぎるのと、道路が整備されていなくてロードバイクでは走りにくいから。
【話題】道路交通法、交通ルールへの理解について
・警察官が道路交通法を把握しておらず、間違った指導をされる
→歩道がある道路の端の線「車道外側線」は、あくまで車両が歩道に近づきすぎないようにするための目安の線なのだが、自転車はこの車道外側線の外側を走るようにと指導されることがある。
→まして、歩道がない場合の「路側帯」は軽車両である自転車は通常通行することができないのだが、この路側帯を走行するように指導されることもある。
・警察官でもこの程度の認識なので、まして自動車ドライバーは道路交通法への理解が乏しい。走行して良い場所、走行すべき場所、などの解釈が人によってまちまち
→ルール通りに自転車で車道を走っているだけでクラクションを鳴らされたり幅寄せされたり、邪魔者扱いされる。→車道外側帯を走行することもあるが、(車道と比べて整備されておらず、凹凸などあることもあり)走りにくい。
→バイパスなど大きな通りを走行していると、急に車道外側帯が途切れたりする。そこでやむを得ず車道側に戻ると自動車に轢かれそうになったりするので、必ずしも車道外側帯が安全とは言えない。
→例えば、片側一車線の場合は自転車は車道の左端を走るのがルールだが、片側二車線以上の場合は左車線内であれば真ん中を走行しても法律違反ではない。
・「自転車はどこを走るべきか」という議論自体がナンセンスで、自転車専用レーンをつくって作ってしまう以上の解決策はない! という議論もネット上では交わされている
→みんなが法律をすべて理解するというのは無理。
→そもそも、全員が理解すべきというほど(道路交通法が)良く整備された法律とも思えない。
→歩行者はどこを歩けばいいかわかるし、自動車もどこを走行すればよいか(どこを走行してはいけないか)知っている。自転車だけがみんなの理解が不正確だから宙ぶらりんになる。
→つまり、「そこを走っている分には誰も文句を言わない」という道(走行レーン)が、自転車にも必要。
(話題)自転車ユーザーたちは、政治や行政への働き掛けを行っているのか?
・政治家とはそんなに簡単に知り合えない
→自転車に理解のある政治家となるとなおさら難しい?
・(仙台在住ではない方の意見)自分の住む市の自転車担当部局に意見を伝えたこともあったが……
→今思えばクレームを入れたような形になってしまいあんまりよろしくなかった。
→行政職員と信頼関係を作るところから始めなければならず、非常に時間がかかると感じた。
・交通事情を議論する団体は世界中見渡せばたくさんあるが、日本は市民運動をしようという空気が薄く、交通系となるとほとんどない印象
→仙台には「地域公共交通会議」という会があるが、行政職員のほか交通事業者や市民代表としての町内会長(年齢高め)などが主な構成メンバーで、自転車の利用促進については話題になりにくい。バス路線の本数を増やせとか、そういう話が多い印象。
・全国規模では「自転車活用推進研究会」という団体があり、ここが政策提言などを行ってくれているが、それでも道路交通法の矛盾を解消するには至っていない
・一部の自動車愛好家たちが議論していても「世論」とは思われていないのではないか
→自転車を趣味として愛好している人と、日常の移動手段として利用している人の間には溝があると思う。
→「自転車ツーキニスト」という単語もある。
→愛好家の方々の意見が、必ずしも自転車利用者全体にとって利があるようなものにはなっていないかもしれない。
→歩行者が普段、自分の「歩行する権利」を考えたり発言することがないのと同様に、自転車を利用している人たちの多くもわざわざ発言したりはしない。
(分科会の話題1)「住みよいまち」と交通手段
・地方で暮らすには車が必要。
→代替の交通手段では運賃や維持費がかかりすぎて成立しない。
→タクシーすらいない過疎地域では、白タクシーが規制緩和で認められている。
→名古屋大の教授の取り組みで、田舎にコミュニティバスを走らせようという活動をしている人がいる。
→仙台でもコミュニティバスの実証実験はやっていた。
→田舎で車を手放すのはハードルが高い。両親が75歳を迎える前に車に乗らないようにさせたかったが、それでは生活できない。
→交通量が多くない地域ならば、わざわざ自転車道を区別して設ける必要はなく、共存はしやすい。
・日本と海外では、交通手段について話題になるポイントが違う
→ブラジルの場合は、車を停車中に襲われないかとか、道路に穴が空いていて危ないとか、そういう話になる。
→都市間交通の事情が日本と全然違う。国土が広いのに、都市同士を結ぶ鉄道がない。全部ドラックだから輸送コストが高く「ブラジルコスト」と呼ばれる。これが経済が伸びない原因になっている。
→2014年リオオリンピックの際、サンパウロとリオデジャネイロ間に鉄道を作ろうという話があったが頓挫した。
→サンパウロは電車にもバスにも、時刻表がどこにも書いていない。ダイヤは決まっているはずなのだが、予定通り到着しないから?
→バスの運転手が道を知らなくて、乗客のおばあちゃんが道案内していた。
→日本は公共交通機関の運賃が(使い方によって)高い?
→イギリスの国鉄は、時間帯(ピークタイムとオフピーク)によって運賃が違う。また遅く着く電車の場合は半額ぐらい、極端に運賃が変わる。
→ロンドンでは一日の運賃が決まっていて、一定額以上払えば後は乗り放題になる(日本の「1日乗車券」とは違い自動的に精算される)。ただしベースの金額は高め。
【分科会話題2】仙台駅西口の周辺は、一般車が入れないようにしてもいいのでは?
・いわゆる「カーフリー化」。現実味は?
→仙台市はまだまだ車が多い印象だが、交通量のピークは超えていて最近は減少傾向にあるらしい。
・駅前には駐車場もたくさんあるので、車を減らそうという動きには反発も予想されるのでは。
→駐車場は確かに多いが、必ずしも儲かっているわけではない。
→平置きの駐車場は(次のビルが建設されるまでの)仮の事業。機械式の立体駐車場はメンテナンスコストがかなりかかっている。
→人の流れが生まれれば、土地ももっと有効利用される?
その後、河北新報さんから下記のような報道がありました。コーヒー・ハウスで出た意見とも近い部分があり、今後の動きにも注目したいですね。
仙台駅前「青葉通広場化」を検討 市と地権者ら、協議会が1日発足(2021年05月31日 06:00)
【分科会話題3】自動車ユーザーの方が、税金を多く払い道路の維持管理等に貢献している?
・受益者負担という観点では、自転車ユーザーの方があまり声高に主張しにくいのではないか?
→前提知識として、かつては「道路特定財源制度」という目的税があったが、廃止され今はガソリン税、自動車重量税などもすべて一般財源となっている。
→道路を傷めているのが何なのかを考慮すると、自動車は本来もっと税金を払わなければならない可能性もある。
→少し情報が古いが「自動車にいくらかかっているか」(上岡直見)という書籍もある。
→この本によると、自動車重量税やガソリン税だけでは道路の維持費はまかなえておらず、残り2/3程度は一般財源と財政投融資が投入されている
・「ドライバーが好き勝手運転できるように歩道等が整備されている」という見方をすれば、車道以外も自動車のために整備されている。
→極端な話、横断歩道や交差点でちゃんと車が停車してくれるなら、信号すらいらないが、実際はそうもいかない。
・大前提として、物流など様々な形で、私たちは車が安全に走ることができる道路の恩恵を受けている
→単純に交通手段としての自転車・歩行者vs車という話ではない。
・自動車産業は日本の基盤だから、自動車が使いにくくなっていくのは困る?
→海外で売れればよいのではないか。
→自動車の生産はすでに相当量が海外工場に移転しているので、産業基盤として昔のように見ることはできない。
終わりに
次週はフリーテーマです。
今後の「コーヒー・ハウス」についても、今回のようにまとめてログを残していきたいと考えています。
ぜひ皆様も気軽にイベントにご参加ください。内容に関する質問や感想も歓迎です。
イベントに関する情報はTwitterまたはFacebookで発信しています(Webサイトはリニューアル準備中です)。
NPO法人メディアージ Twitter
ポリスク-politics square- Facebookページ
NPO法人メディアージの、政治・選挙に関する情報発信や、対話の場作りのためのサポートを何卒よろしくお願いいたします!
