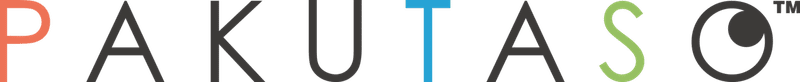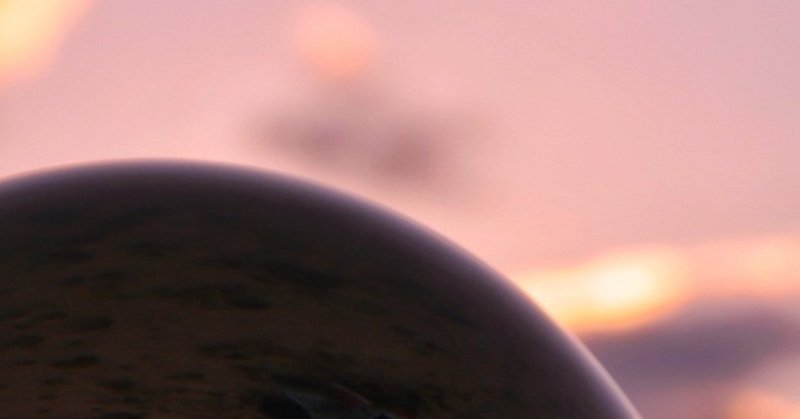
【短編小説】灼熱の風が吹くこの星で ⑩
【エピローグ】
ブザーがなり、辺りが暗闇に覆われる。
緞帳の下りる音が聞こえ、それが止まるのと同時に、消えていた明かりが会場全体を明るく照らし出した。
毎年、地の民と水の民が交流することになった記念日に開催される演劇、その第一幕が終わったのである。
静まり返っていた観客席が、ザワザワと騒がしくなり始める。
演劇について語り合う人達がいる。
喫煙所に向かう人達がいる。
たくさんの観客達が様々な様相を呈している。
そんな中、歴史学者である私はトイレに向かいながら、演劇の内容に関して自分なりの考察をしていた。
のちに、【生物学の祖】と呼ばれることになるレルフとミリスの両名だが、演劇とまったく同じような出会い方をしたと言われている。
二人によって、水の民と地の民は、お互いのことを詳しく知ろうとするようになった。
ただし水の民と地の民が同じ環境で暮らすようになるのは、さらに何十周期も先のことである。
当初はほとんどの者達が、共存を拒んでいたらしい。
しかしミリスが根気強く説得を続けたことで、まずは水の民の者達が、殺意衝動を克服する方法を実践し、地の民へ歩み寄ろうとした。
一方でこれまでずっと殺戮され続けてきた地の民は、なかなか水の民に近付こうとはしなかった。
それでも水の民の真摯な態度を前に、次第に考え方を軟化させていったそうである。
こうして徐々にではあるが、水の民と地の民の間で協力体制が築かれていった。
長いこと、この世界には二種類の知的生命体が存在していると思われていた。
地の民と、水の民である。
彼の者達は、どちらも親を持たない。
それ故、それぞれが大地から生まれると考えられていた。
しかし事実は違った。
地の民と水の民は、まったく同じ種族だったのである。
地の民がマルネ虫と呼んでいるモイ虫が進化した結果、幼虫期と成虫期、その両方が知性を持つに至った。
ところがサナギの時期、完全変態する際に、脳の大半までもが作り替えられてしまうため、成虫としての水の民は、幼虫である地の民の記憶を引き継がなかったのである。
結果、完全に別の存在として新たに誕生したかのように、錯覚してしまっていたのだ。
地の民が水の民に強い憧れを抱くのは当然だった。
何故なら水の民こそが、自分達が成長した将来の姿なのだから。
水の民が地の民を愛おしく思っていたのも当然だった。
何故なら地の民は、水の民が産み落とした卵から孵った子供達だったのだから。
最大の謎であった、水の民が地の民を殺そうとする理由。
これに関しては、共同研究グループが、共歴百三十周期にその原因物質を発見している。
地の民は生まれてからずっと特定のフェロモンを放ち続けており、そのフェロモンに反応することで、水の民は抑えられない殺意衝動を抱いてしまっていたのだ。
ちなみに現在では、水の民はそのフェロモンを感じ取る器官を取り除く手術が義務付けられている。
いったいどうして、同じ種族を殺してしまう機能を水の民が持っていたのか?
その理由は科学の進歩した現在でも、仮説の域からは出ていない。
ただ、おそらくは種の数を調整する目的があったのだろうと推測されている。
常に同じ面が太陽を向いているこの惑星には、赤熱の大海と呼ばれる溶岩の海が広がっており、限られた範囲しか生命体が存在できない。
そんな過酷な環境だったため、進化の過程で種の数を調整する機能が備わったのだろう。
私がトイレから座席へ戻ると、間もなく第二幕が始まる時間になっていた。
多くの人達が会場に戻り、演劇が再開されるのを待ち侘びている。
ブザーの音が鳴り響いた。
天井の明かりに合わせるように、ざわめきも消えていく。
そして緞帳がゆっくりと上がり始めた。
地の民の街が騒然としている。
自分達を殺戮する恐怖の対象でしかない水の民達が、何人も一斉に訪れたからだ。
街中が混乱に陥っていた。
ところが水の民は、地の民に危害を加えようとはしなかった。
脅える地の民に石を投げられても、罵詈雑言を浴びても、穏やかな表情のままだ。
全員が、フェロモンの知覚器官のあった首を傷付けていたからである。
やがて水の民の一団は、地の民の街にある出版社を訪れた。
恐怖に取り乱す出版社の社員達。
しかし水の民の者達が、冷静に説得を続けたことで、話だけは聞いてもらえる状況になった。
この時の交流により、かつてレルフと呼ばれていた少年から、水の民に関する原稿を渡されていた編集者のリルルは、書かれてある内容の全てが真実であることを知った。
歴史は動き出す。
進化の過程で備わった殺戮本能を克服する方法が見付かったことによって、地の民と水の民との間に、交流が生まれた。
両者の蓄えてきた知識が混ざり合い、世界が目覚ましい発展を遂げ始めたのだ。
ここまでは忠実な史実である。
だが、このあとのフィナーレは、演劇として盛り上げるために都合の良い脚色をしているのだと私は思っている。
それでも子供達は夢中で見入っているし、実際、この通りであって欲しい願う大人はとても多いはずだ。
レルフが赤熱の大海の近くでサナギになってから、一周期ほどが過ぎたある日のこと、水の民の街へ新たな少年が姿を現した。
彼は一冊の本を持っていた。
地の民の出版社が発表したばかりの新刊である。
ミリスが赤熱の大海へ行き、レルフの埋まっている穴の中に入れておいたのだ。
彼が水の民に成長したら、きっと持ってきてくれると信じて。
初めて目にする街を前に、どこへ行けば良いのか戸惑っている彼のもとへ、ミリスが涙を流しながら歩み寄っていく。
「ちゃんと大人になれたんだね。レルフ」
「レルフ?」
声をかけられた少年は首を傾げた。
「ひょっとして、それは僕の名前なのかな?」
「そうだよ。レルフ」
水の民になった時、地の民だった頃の記憶はほとんど失われている。
だからレルフは不思議そうな顔をしていた。
「どうしてキミは、僕の名前を知ってるの?」
するとミリスは小さく吹き出してから言った。
「だってわたし、前にあなたに会ってるもの」
「前に?」
「そうだよ」
レルフがキョトンとする。
そんな彼を、ミリスは優しく抱き締めた。
「久しぶりレルフ。これからまた、よろしくね」
この時の二人の姿は、世界の平和と進化を願う象徴となり、現在、我々の暮らしている街の中央に、立派な石像が設置されている。
―― 了 ――
創作活動にもっと集中していくための応援、どうぞよろしくお願いいたします😌💦