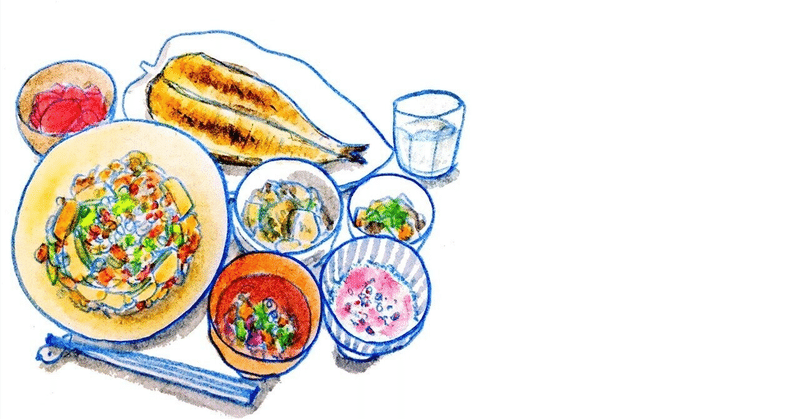
フードライターになってわかったこと
こんにちは、フードライター マッシ(@massi3112)です。
日本語が母国語ではない僕が、日本語と遊んで好きな分野で書き出したら、知らないうちにライターになっていたことについて書きたいと思う。
僕は子供の頃から、自分で考えたストーリーを言葉にして読んでもらうことが夢だった。いつかやりたいと思いながら、読書したり日本語力を高めたり好きなものを食べたりしている間に、いつの間にかこの夢が叶った。特別なことをしていないと思っていた僕は、ある日気が付いたことがあってこの記事にすぐ書き出した。
フードライターになるために、資格も学歴も必要ない。プロになる証拠は原稿料だと思っていたけど、実はそうではなかった。自分で書いた文章を多くの方に読んでもらった上で行動させたり、共通点を作って感動させたり、フードから生まれた信頼感が出たりすることで、言葉のプロに近付いていくと感じたのだ。原稿料をいただいても読者の心まで届かないと、書いた記事は最初で最後になる。
自分らしさを変えないことも大事。
書いた文章を読んでその書き方の特徴や魅力によってライターの名前がパッと思い浮かぶのが理想だ。そのため、周りのライターや作家を真似しない。参考にしたとしても、自分らしさを変えない。
自分からしか出せない表現、グルメよりストーリー性を優先、物語のように読めば読むほど続きを読みたくなる、引っ張り方はグルメではなくグルメをいただいて感動した気持ちから書く。
グルメについて書きたいと思っているあなたは、自分の前にあるグルメをネタにすることを避けてもらいたい。なぜかというと、グルメというのは食材や料理、飲食店だけではなく、食文化も食べた後の感動、食べた物の思い出、グルメの中にいる自分はどのぐらい変化があったのか、などの書き方もある。正直に言うと、この書き方にすると魅力や美味しさが伝わりやすい。
「グルメ=ネタ」ということ考え方を捨てた方が楽だ。現実をそのまま語ると、面白くない。誰のことも引っ張ることができない。
情報だけを書いてしまうことのデメリットは、自分のブランド力が落ちること。書いた文章より、現実の情報を取りたいだけになってしまう。要するに、カタログのように欲しいものを探してメモにしてからカタログを捨てる。捨てられてしまう。
僕にとっては当たり前だけど、もしかしたら多くの人にとっては当たり前ではないかもしれない。食材から調理された料理は「生き物」である。もっと深く考えると、この生き物は食べる人の人生3倍分の濃さがある。
農家さんなどの人、元気に育てられた食材、調理人
フードライターとして、この3つの人生を忘れないでほしい。
僕にとっての1番大事なことは、美味しいものに美味しいと言わないこと。意外と思われるかもしれないけど言いたいのは、その美味しさに驚いたこと、感動したこと、人生がどのくらい変わったことを中心にして、文章を書く。これが、きっと美味しいの言葉以上に伝わる。
去年KADOKAWAで出版したエッセイグルメや東京メトロのメディア、自分のnoteなどの記事は、いつもこの書き方で楽しく読者に読んでもらっている。読者に読み聞かせているわけではないけど、その文章を通してマッシが語りかけているような気持ちになったら嬉しい。
グルメを使って自分のネタにするのではなく、グルメという特別な仲間と2人で物語を書くことが大切。このポイントをしっかり守らないと読んだ後に何も残らない。ライターのこともすぐ忘れる。要するに、人気が出ない。
僕は毎日美味しいものを食べるときに、まるで初恋のような気分になりながら文章を書いてることに、最近気がついた。食べるのが好きだけど、自分のコンテンツのためにネタにしたいと思うと「アモーレ」の部分が一気になくなる。このバランスを取るのが難しいと思うけど、まずは記事のために食べるのではなく、食べてみたい気持ちを優先するのがオススメだ。
日本語で頑張って緊張しながら記事を書こうとしているイタリア人の僕が感じたことを、ここまで読んでいただいてありがとうございます。みなさんの意見なども知りたいから遠慮なく、コメントやシェアをお願いします。
ではでは、今日も美味しいものとデートをしていこう!
Massi
みなさんからいただいたサポートを、次の出版に向けてより役に立つエッセイを書くために活かしたいと思います。読んでいただくだけで大きな力になるので、いつも感謝しています。
