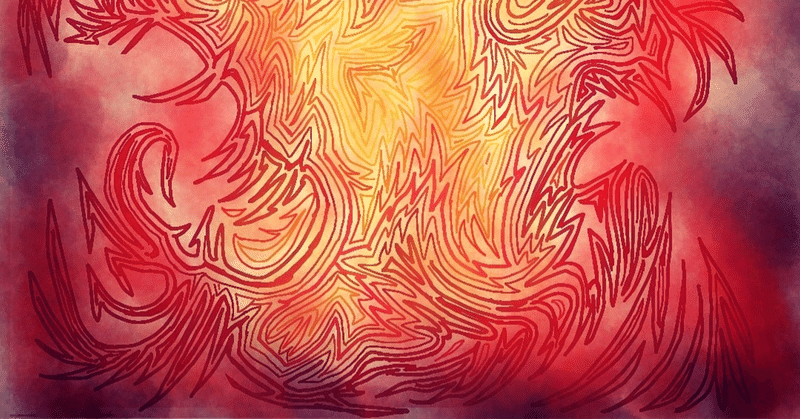
小声コラム#34 小説
ここ数日間、頭のなかにパチンコ玉くらいの鉛が埋まっているみたいだった。それを頭痛と呼ぶには、頭痛にわるい気がして、どう名付ければよいものか思い倦ねていた。鈍天とでも呼ぼうか。
本当の曇天は空模様であるが、言葉を掛けたレトリックは愚案だと、元上司の教えが脳裏にこびり付いていて、素直に浮かんだ言葉を扱うことが難しくなっていることに細やかな不自由を感じる。
意識が朦朧としていても記憶していた海馬が、自分を置いて先に行ってしまうような気がしてならない。
鉛を抱えた頭で小説を読んだ。そうでなくても思考や想像はいつも、それこそパチンコ玉を弾くように、散乱して収集できない僕にとって、鈍い頭で読む小説は非常に空虚で贅沢なものだった。
小説における良作の定義を知らない。著名な文学賞を受賞すること則ち良作と、至極単純なことのかもしれない。
僕は、読むことを逸らせる作品が良いものだと思っている。均一性などない個人の尺度だ。それが自然であるかの如く、文字の温度に共鳴して血流が荒々しくなる。目で追っているのか、構築された景色が先に過ぎてゆくのかわからなくなる。読み終えたあとに残る、涙になりそうな青黒い灰が堆積して、指先を痙攣させる。そんな作品を良作と決めている。
そして今回のそれは、鉛をブチ抜いて、夏を思わせる五月晴れに引き戻した。耳を塞ぎたかったが、不正確な鼓動に合わせられる音楽がなく、仕方なく日曜日の昼間に漂う愉快なジャズを聴きながら自転車を漕いだ。
虚しいのは頭は軽やかだったことだ。現実では、何も考えていない、何も感じていない、何も持ち合わせてはいない、それでも稼働する脳が羨ましい。僕はただ、背中に滲んだ汗が気持ち悪かった。
その夜は眠れない気がして、その日のことを思い出そうとした。そこで記憶は途絶えたまま、またひとつ、何かを失くした。
#34 小説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
