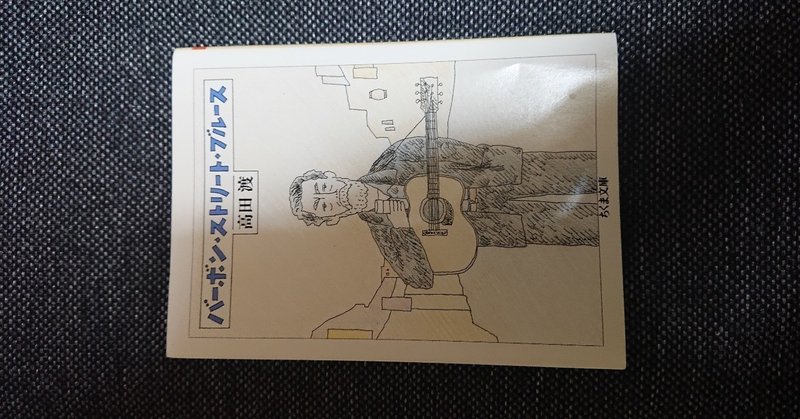2019年9月の記事一覧

一日一書評#29「6時27分発の電車に乗って、僕は本を読む/ジャン=ポール・ディディエローラン著・夏目大訳」(2017)
今回紹介するのは「6時27分の電車に乗って、僕は本を読む」という本だ。著者のジャン=ポール・ディディエローランはフランス在住の作家で、過去2回、短篇でヘミングウェイ賞を受賞している。本作は、著者の長編デビュー作となる。 主人公のギレン・ヴィニョールは、本を処分する断裁工場で働いている。本を死に追いやる毎日は、とても楽しいとはいえない。断裁機から救い上げた、断裁されなかったページを通勤電車で朗読し、成仏させるのが日課だ。読み上げるのは、物語も脈絡もないページたちだが、乗客は喜