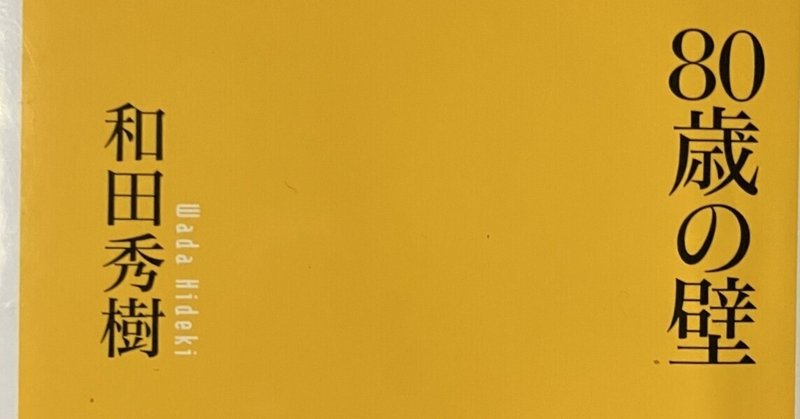
若さは宝と母が言ってた、和田秀樹医師の80歳の壁を読んで思うこと
多分若い人たちは全然年老いた時の事は考えていない、えかきのつまもそうでした
天才バカボンではないけれども、それでいいのだ~、これでいいのだ~と思う
この世の中には何がしあわせで、何が不幸せなのかという正解はない
前頭葉は人間の脳の中で一番大きな場所なのに実はほとんど使っていないと和田秀樹医師は言う
そもそも、日本人は前頭葉を使わない国民性だと言えます
学校にしても、会社にしても「言われた通りに動けばいい」と言う風潮があるから本当の意味での頭を使っていない
たとえば中学、高校の試験は知識重視
大学教育も本来は高校までに習ったことを疑ったり、議論したりする場なのに「教育の言うことが正しい」と教える
会社に入っても上意、下達で、考えて行動する人材は枠にはまらず嫌われる
前頭葉を鍛える機会が極端に少ない
そういう国民性だから、本を沢山読んでいる人が「頭がいい」と言われるわけ
本当は、本を読んで物知りになったうえで、その知識を加工したり、自分の意見をつくったりすることが大切なのに、それをしない
前列踏襲になりがちで、応用力や加工力が低くなってしまう

高齢者ではなく幸齢者と呼ぶのもおもしろい、高齢者専門の精神科医
ス~と読めちゃう単行本
ところどころ引き用させていただきます
*幸齢者になったら健康診断はしなくていい
*医療に頼るなかれ 医師には「健康」という視点がない
*病院に行かなくなったら死者数が少なくなったという事実
医者仲間をみんな敵に回しているかしら?
認知症が進むとニコニコ笑顔に、神様が最後にくれ









認知症は終わりじゃない生きる知恵と力は残っている
”認知症の人は、色々な意味で安全志向です
クルマに撥ねられるのを避けるだけではなく、誰にでも敬語を使うようになります
私は、元大臣だった人も診ていますが、最初のうちは「失礼な」と怒っていたのに、いまではみんなに敬語を使っています
やはり、敬語を使って接したほうが軋轢(あつれき)が生じにくいからでしょう
お財布が小銭だらけになるのも、安全志向だからです
たとえばコーラを買って「いくらだっけ?」となる
「昔は40円だったよな」と、ふと思ってもさすがに40円を出すわけにはいかないから千円札を出す
「大は小を兼ねる」という心感からの行動です
おそらく人間には、「バカにされないように」とか「安全にやろう」という発想があるのでしょう
認知症になっても、それは残っているのだと思います
以外かもしれませんが、認知症の人は一人暮らしもでいます
もちろん、できないことは増えていくのですが、できる能力も残されているからです
私は浴風会病院に勤めていたときに、月に2回ほど保健所に派遣され、一人暮らしの認知症の人に対応していました 「隣の家のおじいちゃんが徘徊している」とか「ゴミがたまって臭いがひどい」とかの苦情が近隣に寄せられると、私が往診に行き、診断をつけてどこかの施設に入れたり、入院させたりするわけです
その経験から学んだのは、人間は思っていた以上に強い、ということでした
たとえば「臭くてたまらない」という家に行くと、足の踏み場もないほど散らかっています
ほとんどがコンビニ弁当の空箱
おそらくずっとお風呂にも入っていないことがわかります
近所から苦情が出るほどですから、家の中はもっと臭い
しかし、そんな状況なのに、生きているわけです
毎日、五百円玉か千円札かを握ってコンビニに行き、お弁当を買って食べる
そうやって、お腹も壊さずに生きている
自販ができなくても、片づけができなくても、お風呂に入らなくても、生きている
人間はしぶとく、たくましいのです
認知症になったら何もできない、なんて決めてかかる必要はありません
最期まで生きる力、生き抜く知恵が備わっている”
人間はとても強いのです
長生きが大事なのか残りの人生が大事なのか
どちらが正解かは誰にもわからないのである
自分はどう生きるか、どう生きたいかのか
これまでの人生で何度も考えてきたでしょうけれど、、、
若い頃はえかきのつまは一切考えなかった
幸齢者(高齢者)になるとこの言葉の前に「いつまで元気でいられるかわからないけど」という前提条件がつく
ある日脳梗塞になったり認知症になったり、突然寝たきりになるリスクが高まる年代
だったら元気なうちに楽しもう
その方が免疫機能も上がり健康にも良いと和田医師の提案
寝たきりは終わりではないだからこそできることもある
いざそうなってしまったときにはそれに応じた楽しみ方があるそう
病気を心配しても始まらない
なるときにはなるのだから、なったらなったで「出たとこ勝負をすればいい」
80歳を過ぎた幸齢者なら、動けなくなったらどうしょうと考えると寂しくなるのでそういう日がやってくると腹をくくり、それまでは生きている日を大事にするほうが健康にもいいそう
老いや衰えを受け入れる、まだある機能で勝負する
残存機能を残すヒント
あ 歩き続けよう
歩かないと歩けなくなる
い イライラしたら深呼吸
水や美味しいものも効果的
う 運動は体がきつくない程度に
え エアコンつけて水を飲み、猛暑から命を守る
お おむつを恥じらない
か 噛めば噛むほどに体と脳はイキイキ
き 記憶力は年齢ではなく、使わないから落ちる
く 薬を見直そう 我慢して飲む必要はない クスリはリスク
け 血圧、血糖値は下げなくていい
こ 孤独は寂しいことではない 気楽な時間をたのしもう
さ サボること恥ではない 我慢して続けなくていい
し 自動車の運転免許は返納しなくていい
す 好きなことをする 嫌なことはしない
せ 性的な欲もあって当然 恥ずかしがらなくていい
そ 外に出よう 引籠ると脳が暗くなる
た 食べたいものは食べてよい 小太りくらいでちょうどいい
ち 「ちょっとづつ」 こまめにやるのがちょうどいい
つ つき合いを見直す 嫌な人とは付き合わない
て テレビを捨てよ、街に出よう
と 闘病より共病「在宅看取り」の選択もあり
な 「なんとかなるさ」は幸齢者の魔法の言葉
に 肉を食べよう、しかも安い赤身が良い
ぬ ぬるめの湯、浸かる時間は10分以内
ね 眠れなかったら寝なくていい
の 脳トレよりも、楽しいことが脳にいい
は 話したいことは遠慮せず話せば気分も晴れてくる
ひ 病院は「かかりつけ医」を決めておく
ふ 不良高年でいい いい人を演じると健康不良になる
へ 変節を恐れるな 朝令暮改は大いに結構
ほ ボケるのは、悪い事ばかりじゃない
ま 学びをやめたら年老いる 行動は学びの先生
み 見栄を張らない あるもので生きる ないものをあるように見せるのが見栄 80歳の壁を超えるにはないものはないと認めあるものを大事にしながら生きるのがコツ
む 無邪気になれるのは老いの特権 人生の達人ならではの生き方
め 面倒なことほどじつは面白い
も もっと光を 脳は光でご機嫌になる
や 役に立つことをする 自分の経験を生かせばよい
ゆ ゆっくりと今日を生きる 終わりは決めない
よ 欲望は長生きの源 枯れて生きるなんて百年早い
ら 楽天主義は幸齢者にこそ必要
り リラックスの呼吸で老い退治
る ル-ルは自分で決めていい
1-自分でできることはする
2-嫌なことは我慢しない したいことをする
れ レットイットビーで生きる Let it be あるがままに
いくら悔やんでも昨日は戻って来ない
明日のことは誰にもわからない 明日は明日の風が吹く
それが人生というものです その通りだと思うえかきのつま
自分の人生をあるがままに受け入れ、なにも恐れず、何も心配しない
したいことをして、食べたいものを食べ、会いたい人に会い、言いたいことを言う
そして口笛でも吹きながら(えかきのつまは口笛は吹けないのでどうしょう?)今日という日を気ままに生きていく
80歳を過ぎたら実行しょうというか若いころからそのように生きて来た
3-老化より朗化 これが愛される理由
二つのタイプの人がいるそう
ボケても愛される人と
ボケても疎nんじられる人
人間長生きし続ければやがてボケる
だったら愛されるボケを目指す
わ 笑う門には福来る
楽しいから笑うのではない、笑うから楽しいのだ~
子供のようにくだらない事にも夢中になったり、大笑いしたりなんでも楽しんでしまう能力

しあわせとは何かは人それぞれでしょうが、やっぱり楽しむ能力ではないでしょうか?
B型は人をしあわせにする~
小川(松ノ下)マリアイネス拝
