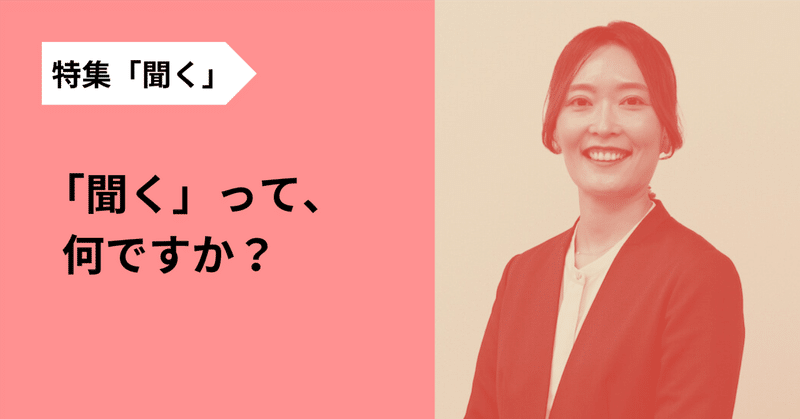
幸村カウンセラー、「聞く」って何ですか?
ソーシャルメディアでは誰も人の話を聞いていないんじゃないか。
そんな私、メザニン広報担当の個人的な問題意識から、8月は「聞く」をテーマに色々な人に話を聞いてみます。
「聞く」と「聴く」は行ったり来たりする
このインタビューを行うにあたって、事前に「8月のおすすめ読書記事」を共有させていただきました。いかがでしたか?
幸村:そうですね。カウンセリングで「きく」と言うと、傾聴の「聴」になるんですけれど、今回テーマになっている「聞く」も、実は「聴く」ことに含まれているのかなと思いました。
「聞く」と「聴く」は別々のものというよりも、行ったり来たりをしながら「話を聞く」という行為が行われている、そんな感覚があるなと思いました。
「聞く」と「聴く」を行ったり来たりしている、興味深いです。
幸村:「聞」を使った「聞く」には、知識を得るための情報収集というイメージを持っています。頭で状況や状態を理解する、そんな感じです。
一方で、カウンセリングの「聴く」になると、心なんですよね。心を傾けて聴く、そんな感じ。
例えば、ある人から「大学ではこういったものを研究していて、こんな勉強をしていました、楽しかったです」と言われたとき、それを「聞く」のであれば研究内容、勉強内容、楽しかった気持ちを情報として理解することになります。
でも、カウンセリングで話をされた時は、情報を情報として理解するだけじゃなくて大学生活というストーリーの中に私自身の身を置いて一緒に体験をするような感じがします。
それは、いわゆる「共感」のようなものでしょうか。
幸村:共感にも形だけの共感と、実感を持った共感があると思います。
頭だけで聞いていると、形だけの共感になりやすいかもしれません。
こういうことがあって嬉しかったんだという話をした時に、ただ「良かったね」と言われるのと、本当に心から一緒に喜んでくれるような実感を持った「良かったね」は違うと思います。
なるほど。例えば何かプレゼントを貰った人がいたとき、それは滅多にないために良い事だと評価・判断して「良かったね」と機械的に弾き出される感じと、もっとその人の事を思って心を寄せるような感じと、共感は2種類に分けられる。
幸村:そうですね。実感を持った共感という感じ。
伝わっているという実感を持たせられるか
幸村:旦那さんには普段から色々と話をするんですけれど、一方的に「うんうん、そうなんだ」と受け止めるだけじゃなくて、「自分はこう思うけれど、奈未子はこう思ったんだね」と確認しながら聞いてくれます。
そうすると、私も伝わっているんだって思えます。
逆に、何かしながら片手間に話を聞いていたり、理解できていないけれど頷いていると感じると、聞いてないな……と思ってしまいます笑
伝わっている感覚がすごく大切なんですね。
幸村:うん、大切ですね。もし分からなかった事があっても、「それはこういう事ですか?」って聞き返してくれる方が一生懸命聞こうとしてくれているのかなって思えますよね。
確かに。
幸村:あとは、これも実感という話につながってきますけれど、「私はそう思わない」とか「え、普通はこうじゃない?」っていう風に、相手の主観とか個人的な価値観と合わなかったとしても、それをきちんと話をしている私に投げ返してくれることによって噛み合っているというか、真剣に聞いているんだなと思うことができます。
分からない時は「分からない」、違うと思ったら「違う」と率直に言ってくれた時は、「なぜそう思ったのか」を通して、自分の気持ちや想いをもっと話せる気がして。
そうすると、お互いの「話す」「聞く」を通して理解がより深まっていって、最終的に伝わっているなという実感に辿りつく気がします。
聴いてもらえたという「実感」には、そこに至るまでのプロセスがすごく大事ということですか?
幸村:そういう意味では、情報を頭で理解する「聞く」の方も大事だと思います。たくさん聞いて、その上でストーリーに自分を置いてさらに聴いて。聞く側も、自分自身が実感を持てるまで聞くことがすごく大切だと思います。
自然体、心を開くこと、正直でいること
実感を持てるまで聞くには、どうすればいいんですか?
幸村:そう、そこなんですよ。自分のなかで凄く大切だなと思っていることが3つあります。自然体でいること、心を開いて聞くこと、あとは正直でいること。この3つです。
自然体でいないと聞けないんです。頭に入ってこなくなってしまうし、理解することもできなくなってしまうので。
心を開くというのは、何に関わってくるんですか?
幸村:相手の語っているストーリーに身を置いて、どんな感じだったんだろうと一緒に感じることです。これも、こちらが防衛的になっていたり、変に緊張していたり、先入観を持っているとできません。
そうやって自然体でいると、自然と心が開かれる感じがします。
心が開いていると、相手の体験を感じながら沸き起こる自分の心の感覚にも素直になれて、違和感に気付けたり、自分はそう思わないなって感じる時があります。
そして、その時に正直でいられれば「どうしてそう感じたんですか?」と相手に投げかけられるんですね。
私と相手の間にある違うもの、これがその人らしさなんです。
なるほど、違いがあるから個性が際立つというか、輪郭を持ってくるんですね。
幸村:そうです。その違いに気づくために、話を聞いている私の心が開かれている必要があります。だから3つは全部つながっています。
改めて整理をすると、「聞く」と「聴く」は別々のものだけれど、
だからこそカウンセリングでは「聞く」と「聴く」が行ったり来たりされる。
「きく」態度が違うと、当然そこから生まれる反応、いわゆる「共感」も質的に異なったものになる。幸村カウンセラーはそれを「形だけの共感」と「伝わっているという実感のある共感」という分類で説明してくれた。
私たちは普段、常に集中力全開で相手の話を聞いているわけではない。
だから、儀礼的な形だけの共感をよく使う。
個人的に非常に興味深かったのは、意見の相違はあっても別に良くて、むしろ違うことを確かめる過程が、話が伝わる実感につながっていくというところだ。
そうして確かめられた私とその人の違いによって、その人の個性が輪郭を持って現れる。
聞くことによってすれ違いが生まれたとしても、それは理解という道につながっている、そんな予感のするインタビューだった。
幸村 奈未子
公認心理師として、心理学講座講師、対面カウンセリング、電話相談、SNS相談等に従事し、様々な背景をお持ちの方のお悩みに寄り添ってきた。また、感受性が強く敏感な気質(HSP)の方へ向けて、心のケアのためのセミナーや、気持ちを分かち合う場を提供している。
インタビュー、文:メザニン広報室
今ならカウンセリングに使える3,000円相当のポイントをプレゼント中!
会員登録はこちら▼
