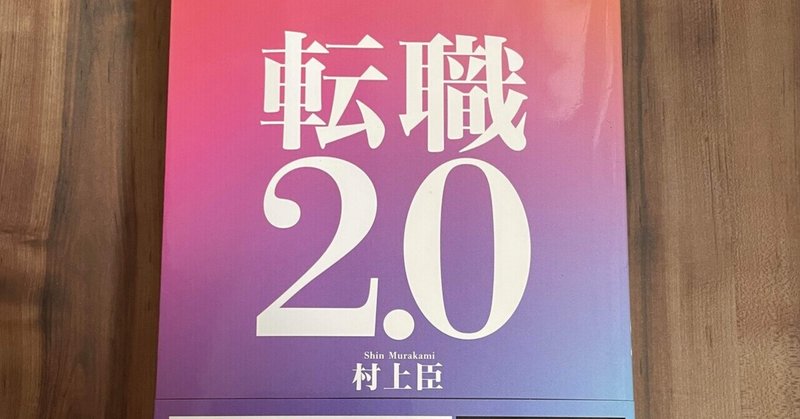
転職2.0も読んでみた
我慢して働く時代は終わった
自分が望むキャリアを手に入れやすい世の中になった
というテーマの本を手に取ってみた。
少し前に読ませてもらった " 年収300万円から脱出する「転職の技法」"
この投稿の冒頭で元々買う予定にしていた本があったと書いたが、その本も読んでみたいと思い結局のところ読ませてもらった。
今回紹介するのは
村上臣 著
転職2.0
日本人のキャリアの新・ルール
この本は「仕事を変えると給料や人間関係などの何かを犠牲にする」という転職への古いイメージをアップデートしつつ、今の時代にあった転職の攻略法が書かれている。
題名の転職2.0とは転職のOSをアップデートし新たな形の転職を実現させる意味合い。
かつての1度の転職で成功する考えから、今では自身のキャリアを選ぶための手段という認識に変わってきているようだ。
著者の村上さんは大学在学中に有限会社「電脳隊」を設立やヤフーに入社。そしてビジネス特化型ネットワークのLinkedIn(リンクトイン)日本代表に就任されていました。
本書の経歴にはここまで書かれておりまして最近の情報だと株式会社ポピンズ、株式会社ランサーズの取締役などをされているようです。
以下参考文献
私自身そろそろ転職したい願望が強くなってきたタイミングなので自分用に整理するつもりも兼ねて選んでみた。
それでは解説に移りましょう。
自分でキャリア形成していく時代
名の知れた大手企業、その会社で務めて年功序列で上がりつつ自分のキャリア形成を会社が決めてくれる。
大手企業なら文句はありつつ安定しているから我慢してでも働くべき!など
高度経済成長あたりから何の疑いもなく常識とされてきた考えだが言うまでもなく過去のものになろうとしている。いや既になっている。
それが終身雇用も幻想になり人口の減少に伴って労働者も減っているという暗い話に聞こえる。
それに自社が他社と合併し内容や環境が大きく変わるリスクすら存在する。
今まで信仰されてきた安定という保証は消えつつある。
逆を言えば労働者は仕事を選べる立場にもなっている。
企業の寿命が短くなるであろう未来を想定するならいつでも転職できる状態を意識する事はこの先の必須戦略と言ってもいいでしょう。
この先の章で書いていくが転職の正しい準備さえすれば希望の働き方、いや望み通りのキャリアを手にすることだって可能な世の中になった。
これからは「会社に就く」という認識から「自分が株式会社」という思考で人生形成していくという生き方になる。
自分の望む生き方、キャリアを転職という形で段階を踏みながら自己を高めていく、これこそがこの本の大々的なテーマである。
自分をタグ化する
この本で重要となる点のスタートステップが自分をタグ付けすること。
Twitterなどの投稿でカフェなど内容の分類に用いるハッシュタグを自身の証明として使うというわけだ。
そのランチが「どこの地域で」「店の名前」かを分類付けするのはSNSづけの現代人ならイメージしやすいかもしれない。
持っている経験、資格、個性を形にして自分を分類化しようというのが転職活動の基盤となる。
タグには
・ポジション(役割)
・スキル
・業種
・経験
・コンピテンシー(元から持ってる能力)
の5つでくくる事を書いている。
例えるなら
Aさん
・営業
・車種の知識が豊富
・自動車業界
・1ヶ月でノルマより10台成約を達成
・お客様の本音などある程度理解できる
ハッシュタグで言えば
#営業 #自動車知識 #車業界
#BtoC #ノルマ達成可能 #共感力
といった所だろうか。
Bさん
・コンサル
・データにめちゃ詳しい
・IT業界
・企業とも個人とも成約率高かった
・様々な人と連携が取れる
ハッシュタグだと
#コンサルタント #データ分析 #IT
#BtoB #BtoC #コミュニケーション力
みたいに自分の持っている能力を絞り出し明確化する事が大事となる。
本書の巻末にハッシュタグのリストが載っているので実際に見ることは推奨しておく。
この投稿作る際に一部参考にさせてもらったほどわかりやすく書かれておりました。
欲しいタグを取りにいき掛けあわせる
タグ化していくとこれが足りないというものに出会うこともあるので必要なタグ、わかりやすく言えばスキルを習得するというのも大切なこと。
例えば
Webライターをされている人で「海外向けに文章を作れるようになりたい」という願望があるなら、海外向けに記事を作成している会社に転職して英語の構成を覚えて自身の幅を増やす。
ハッシュタグだと
#ライター #ライティング #メディア
#サイト運営 #新規事業の創造 #継続力
#改善思考
とすれば、そこに転職を用いて #英語力 #文法 などを付け足していくイメージ。
企業相手に営業をする #BtoB が得意な人が一般消費者を相手に営業できる力を身につけたいなら #BtoC を習得できる会社に転職。
と例をあげたように自分のタグを増やし掛け合わせて希少性の高い人材になっていこうと言うのがこの章の狙いだ。
話を変えると、ポケモンは技を4種類までしか覚えれずタイプが多くて2種類のところを、我々はスキル技を際限なく習得できるポケモン以上の存在になれる。
言うならば 「炎タイプにも水タイプにも対応できて技を10種類くり出せる希少ポケモン」にもなれる!!!
転職というステージ変更を繰り返しながら自身の可能性を広げていく生き方がこの先の主流という結論に繋がるわけだ。
業界を固定し軸をズラす
タグ付けと同じくらい大切になるのが業界やポジションのどれかを残しつつもう片方を変更する生き方。
例えば「自動車業界で営業」をしている人なら、自動車業界という軸を残しつつ、営業から管理職に転身する。ようなイメージです。
エンジニアという職種を残しつつ「現地に行ってやるポジション」から「完全在宅で業務」というように片方を変えながらもう片方を変えるやり方でのステップアップが転職の基本ルールになるということです。
バスケの片足に軸足残しつつ方向を変える事を転職でも応用するイメージ。というのを要約動画でそのルール思い出した事は自白する(小声)
いきなり両方を変えるのはリスクがあるので極力控えた方がいいということだ。
シナジーで選ぶ
シナジーとは相乗効果を意味する単語。
「キャリア目標」と「会社事業」が合致しているかがこの先で重要となってくる。
わかりやすい例えかは置いといて
私がこの単語を覚えたキッカケが遊戯王だった。
「カードを墓地に送り他のモンスターを展開」と「カードが墓地に送られる度に相手にダメージ」みたいにカード同士が作用し合う際に使われる単語だ。
公式で使う言葉じゃなくユーザー内で使われるようになったというのがおそらく経緯だろうが。
遊戯王にはカードをまとめた「デッキ」というのがある。ここでは「企業」として例えよう。
そして「カード」にも属性や種族、能力がそれぞれある。ここでは「人」に例えよう。
そのデッキが「ドラゴン系を使って勝つ」のが目的なら、カードは「ドラゴンを場に呼び出せる」ようなものなどが必要になる。
デッキが目標、カードは目的を叶える手段とも取れる。
話を本題に戻すと。
企業が「これからアプリ開発を始める方針」
転職者が「アプリ開発のスキルを更に上げたい」
となるとお互いの願望が一致する。
まとめると自分の欲しいキャリア目標と相性のいい企業を狙う事こそが、有名企業を狙うよりもこの先とても重要になっていくということだ。
カルチャーフィットは特に重要
最後に重要なのが会社の文化(カルチャー)が自分に合う(フィット)か?
キャリア目標を叶えられる会社だとしても人間関係や人同士の空気が合わないのは自分も企業も損になる。
例えるなら温厚な人がゴリゴリな体育会系の会社に行けば地獄だろう。
本書の例え通りなら、アメーバブログやAbemaTVなどで有名な「サイバーエージェント」やフリーマーケットの王道「メルカリ」も特殊な雰囲気の会社の代表例になっている。
特殊な空気感や体育会系が馴染む人もいれば、耐えられない人もいるので、自分がどんな環境ならマッチできるかの大まかな想定が大事ということ。
見分ける方法としては
・企業のSNSを見て判断
・企業のクチコミも参考にする
・面接で社内の雰囲気を確認してみる
など書かれていた。
「転職を3.4回する人が増える」と例えられるこの先ではあるものの数年近くお世話になる所で空気感に馴染めないと地獄なことは予想つきやすいはず。
ちなみに私も過去に2社辞めている。
その両方がゴリゴリの体育会系だった。
自身の体験からカルチャーフィットの重要性は身に染みて理解できる。
自身のキャリア形成の明確化、それを叶える相乗効果、馴染みやすい環境の3つが転職においてとりあえず大切なこととなる。
ざっくりだが説明は以上。
もう少しキレイにまとめたかったが時間ギリギリで最低限のまとめになってしまった。
金曜に投稿予定ながらここ打ってる今まさに金曜に突入した深夜という。
始めに「転職したい願望が強くなった」といったように今の現状に満足できていない。
独立や副業がメインになりつつあり正社員信仰も崩壊しつつあるが、やはり正社員は通っておきたい願望なのは拭えない。
ダブルワークになるが私の現状も
・まわりが一回り上の人が大半の社内でどう打ち解ければいいか正直難しい。しかも自分が必要とされている実感が少なくとも私の主観だがない。
・もう1つが時々クレーマーや理不尽な状況に出くわしやすい店舗業。ちょうど人が増えてきたのでそろそろ私1人抜けても回るという実感すらある。
しかも転職に多いイメージの20代を来年で終えてしまうという焦りもある。
悲しいことに両方とも結果として誇れるものが何一つないまま30代目前という主観的に絶望しかない状態。
その中で読むと会社の転職への認識が変わっていたり今までのイメージをOSのごとくアップデートしてくれる、そんな1冊だった。
巻末のタグ通りに自己分析してみると
#店舗 #接客 #商品知識 #法人電話の対応
#共感力 #発想豊か
くらいしかない。。。
欲しいタグはザックリ思い浮かんだもので
#ライティング #テレワーカー #動画編集
#ネットの知識 #成果報酬 #英文作成
#ネットでのコミュニケーション力
くらいか
途中タグというより在宅いや旅先でも仕事できるようになりたい自分の願望だが。
私のキャリア形成としての目標は、時間に縛られず自分の考えを発信したり「周りにいいものをすすめたい」という価値観に沿った紹介(ちなみにこの投稿もすすめたい書籍としてカウント)ができる生活に持っていきたいと考えているのが投稿時点の願望だ。
今の自分に悲観になってはしまうが今の生活をこの瞬間すら脱却したくて仕方ないので転職イメージの今を知れたからこそ少し気分が楽になれた気がした。
本書には転職においてのネットワーク、望み通りのキャリアの手に入れ方など転職をポジティブにする助言がたくさん書かれていたのでオススメです。
転職するか悩んでいる方
自分の市場価値が知りたい方
単純に今の転職という認識がどういうものか気になった人にオススメです。
時計見たら3時突入してて焦った。
(投稿朝だけど)寝る。
追記
本書を知るキッカケとなったフェルミさんの動画も貼らせていただきます。
それと村上さんご本人が解説されている動画を見つけましたので追加で貼らせていただきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
