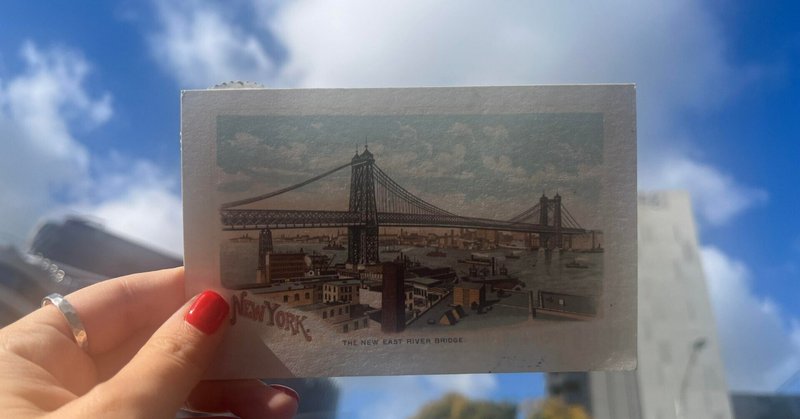
【社会人留学】まなびをつかもう~Week12~
こんばんは!(写真は、米国の大学院でがんばっているお友達から届いたポストカードです❤)
さて、今学期を「学び尽くした、、、!」という気分で締めくくり、これから約1か月に及ぶ、試験期間にはいります。(試験が終わり次第、Week11のPart2以降を更新していこうと思います。)
あっという間の3か月でしたが、たくさんの得難い学びを掴むことができました。正直にいうと、今期の履修科目は、前期と異なり、すべて職務経験に直結する科目だったため、実務的視点でみると、テーマの掘り下げ方やケースディスカッションが物足りないな、と思うことも度々ありましたが、そういうときこそ、教授や友人、日本にいるメンターや友人達とディスカッションをすることで、有意義な時間を過ごすことができました。学びを自らつかむこと、享受する力が大切だとあらためて体験的に理解しました。
今回はブリーフに、各科目につき一つ、ぱっと思い浮かんだ具体的な学びを記したいと思います。
HR Fundamentals: Adam's Equity Theory / Psychological Contract (心理的契約)
Adam's Equity Theoryとは、従業員が自分自身のインプット(例:努力)とアウトカム(例:報酬)を他の人々のそれと比較し、不均衡があると認識した場合、均衡を取り戻すために行動することを示唆しています。つまり、もし自分が不公平に扱われていると感じた場合、従業員は一生懸命働く意欲が低下するということです。Psychlogical Contractも似た概念で、自分の心理的契約が公平であると信じている従業員(つまり、与えた分だけ受け取っていると感じる)は、一般的に仕事や会社の大きな目標に対してより動機付けられ、コミットし、期待以上の成果を出す可能性が高くなります。一方で、心理的契約がどちらか一方によって違反または破られると、裏切りや憤り、そしてエンゲージメントの低下といった感情が生じ、生産性や士気に悪影響を与えることがあります。⇒ 授業を通して、耳にタコができるほど聞いた概念です。それほどにEquity(公平性)は、ジョブパフォーマンスに影響を及ぼす重要な要素ということです。実務においては、個人ごとに公平性に対する認識が異なるなか、人事やマネジメントは公平性をどう扱えば良いのか、難しい問いですね。

Managing Behaviours for Organisations: Mechanism of Job Performance
ためになる多くのフレームワークに触れましたが、下記のメカニズムがさまざまな課題を整理するのに非常に役立ちました。

International HR management: Expat's Adjustment
駐在員派遣において、その成否に最も影響を与えるのは、駐在員のAdjustment(適応)であり、会社が駐在員本人・家族にさまざまなベネフィットを付保するのは適応を促すためである。人事のさまざまなテーマにおいては、目指すべきゴールがJob performance(職務遂行)とされることが多いですが、駐在員派遣においては、適応がゴールになるというのが妙ですね。※ベネフィットに関して、駐在員が自ら志願する場合(Self-initiatedという)はその限りではない。教授(アメリカ人)に、「欧米のHRが、海外勤務手当といった日本の給与体系を見て、なぜそこまで手当する必要があるのかと驚かれるのはなぜ」と聞いたところ、「おそらく候補者が多くいるので、派遣者選びに困っていないからだろう」という回答でした

HR Consulting: "Empathy is important, but we are not a couselor."
教授がご自身のHRコンサルタントとしてのプロフェッショナリズム(哲学)を語ってくださったときに、心に響いた言葉です。教授は、私と同い年くらいの頃、企業内人事として働かれており、大規模リストラを経験されたそうです。辛い思いを抱えながらも、"At the end of the day, we are mitigating the risk for the organisation.(最終的には、組織に対するリスクを軽減しているのだ)"と考えていたとのこと。人事として会社と従業員の間に立つことの厳しさと、大義、自分の立ち位置を見失ってはいけないということを共有してくださいました。
今回も読んでくださり、ありがとうございました。
次回は約一か月後、試験が終わり次第、更新したいと思います。
みなさま、ご自愛くださいませ~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
