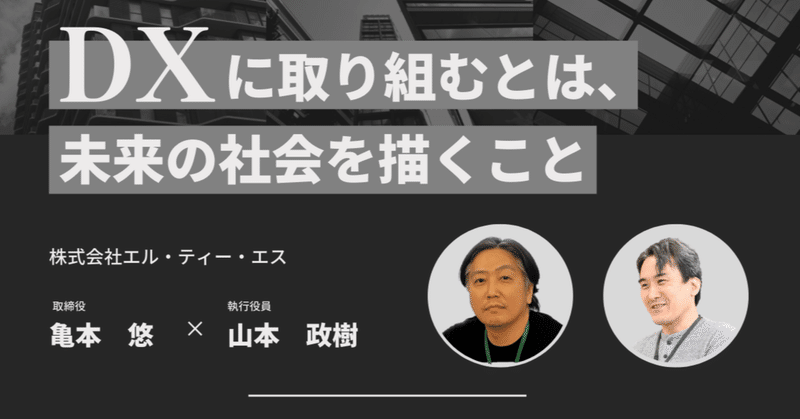
LTSが考えるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは?
LTSが考えるDXについて議論したことをまとめたコラム「DXに取り組むとは、未来の社会を描くこと」全四回を、LTSのオウンドメディアCLOVER Lightで公開しました。
今回はこのコラムを書いた背景や、LTSが「デジタル」「DX」をどう捉えてきたのか?を書いてみます。
DXコラムを書いた経緯
このコラムは「Forbes Japan」に掲載した以下の記事が元になっています。
こちらの記事も是非読んでいただきたいのですが、、
Forbesの取材後に「もう少しこのテーマで語ってみよう!」と、取締役の亀本悠と、執行役員の山本政樹が追加の対談をやってみたところ、面白い気付きが得られたので、あらためてコラムとしてまとめ直しました。
LTSにありがちなのですが文章を書くと長くなってしまい、、全体で約17,000字あります…。
ただ、読み始めると気付きもあり身近なエピソードもありで(いつもと比べると)読みやすい内容になっていると思いますので、少し時間のある時に読んで頂きたいです。
こちらから読めますので、気になる方は是非ご一読ください!
LTSのコラムは、組織の現場にいる若手~変革リーダー層(部課長クラス)に対する学びの共有やメッセージが多いのですが、今回は珍しく経営者への提言で締めています。LTS的な経営トップへのメッセージとは?という観点でもユニークな内容になっているのではないかと思います。
あらためて「DX」を振り返る
世の中に「DX(デジタル・トランスフォーメーション)」という言葉が出てきてから、すでに数年が経ちます。
「デジタル」は率直に言ってバズワードであり「それがデジタルであってもITであってもさほどの違いはないだろう」というのが、流行り始めた当初の感覚でした。
その状況から始まり、2019年以降には「DX」が言葉として一般化されました。経済産業省のDXレポートが出たのもこの時期です。
2019年頃になると「DXをやりたい」「DXについて講演してほしい」「〇〇ビジネスのDX」など、LTSへのお客様からの問い合わせや相談内容に「DX」が当然のように含まれるようになります。
「一つの独立した言葉」としてDXが定着した、と感じました。
ただ、定着しているのにも関わらず、語る人によって「DX」の定義がバラついている状況は変わっていないと感じています。
多くの人が使っているにも関わらず、ここまで異なるシーン・意味合いで使われている言葉というのも珍しいのではないでしょうか。
LTSがどのようにDXを語ってきたか
LTSはどのようにDXを語ってきたのか?思い返してみると、以下のような変遷で今回に至るのではないかと思います。
1.デジタルは目的ではなく手段
当初から今に至るまで、DXについてLTSが語る場合に使っている言葉がこの「デジタルは目的ではなく手段」です。デジタル化することやツール導入が目的のように語られる中で、あくまでデジタルは手段であり、目的は「お客様への提供価値を高めること」だろうと説明してきました。
2.デジタルは事象
最近になって「けっきょくデジタル化、DXはなんなのか?」という問いに対する回答として、企業のプロセスや価値提供手段がデジタル化する以前に「社会がデジタル化・デジタルツールが浸透している事象」そのものだ、と説明する機会が増えました。
今回の連載でも、最初に「事象としてのDX」の考え方を説明しています。
3.“DXの定義”にたった一つの解はない
方法・道具・目的など、ある意味都合よく解釈を拡張させていった「DX」は、それぞれの場面でそれぞれの意味を持っている、と今回のコラム1回目でまとめています。
4.デジタル化した社会に身を置き学ぶこと
そして、今回のコラムで提示したテーマ「DXに取り組むとは、未来の社会を描くこと」では「すでにデジタル化している社会があり、そこに身を置いてどう未来を感じ描けるか?」が大事だと語っています。
コラム4回目の最後のパートでは「デジタル時代における経営とはSF小説を描くこと」の見出しで、以下のように書いています。
SF作品が描いているのは技術の使い方ではありません。技術が進化した先に登場する社会の姿、人間の姿です。アイザック・アシモフは「もし技術が発達して、ロボットが知能を持ったら」という仮説から、いわゆる「ロボット三原則」を打ち立てました。今、世界ではAIの活用に対して法的なガイドラインを制定する動きが盛んです。アシモフが『われはロボット(I, Robot)』の中で、ロボット三原則を表現したのは1950年ですから、実に70年前に今の社会課題を先取りしていたわけです。
デジタル化した世界に身を置いて、自ら感じた感覚(さらに未来へ進めばこうなるはずだ)からサービスや製品、新しい世界を生み出す。
新たなデジタルビジネスが生まれる瞬間は、こんな気付きが元になっているかもしれません。
