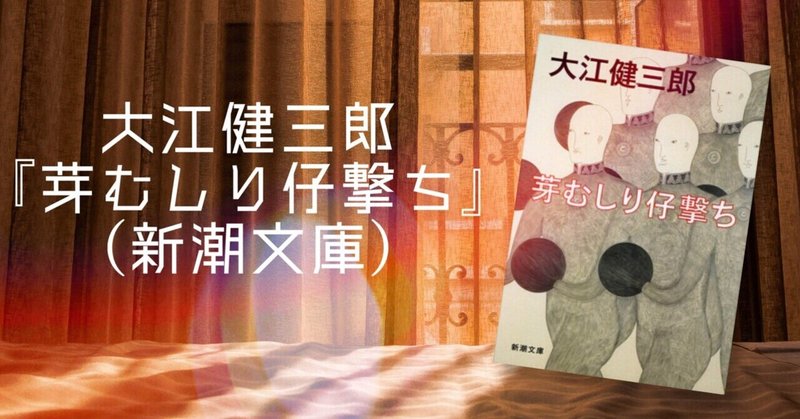
濃密な絶望、精巧な虚構―大江健三郎『芽むしり仔撃ち』
第二次世界大戦の末期、閉塞した時代状況の中、この物語が語られる舞台は疎開先の山村である。それも、ただの疎開ではない。親に見捨てられ、感化院(当時の不良少年が入れられた少年院のような場所)に入れられた身寄りのない囚人となった孤児たちの疎開である。人が死ぬのが物珍しくない時代、感化院の少年たちはほとんど孤児同然、そして孤児より非人間的に扱われざるを得ない。大江の語りは濃密に、丹念に絶望や死の匂いというものを織っていくような密度を持つ。
人殺しの時代だった。永い洪水のように戦争が集団的な狂気を、人間の情念の襞ひだ、躰のあらゆる隅ずみ、森、街路、空に氾濫させていた。僕らの収容されていた古めかしい煉瓦造りの建物、その中庭をさえ、突然空から降りてきた兵隊、飛行機の半透明な胴体の中で猥雑な形を尻につき出した若い金髪の兵隊があわてふためいた機銃掃射をしたり、朝早く作業のために整列して門を出ようとすると、悪意に満ちた有刺鉄線のからむ門の外側に餓死したばかりの女がよりかかっていて、たちまち引率の教官の鼻先へ倒れてきたりした。
疎開中、疎開先に到着以後、徹底的に孤児たちは痛めつけられ、異物として迫害される。脱走を試みた少年は「半殺し」にされる。村に着いて初めての仕事は、疫病で死んだ動物を埋めることであった。そしてその際も、村の子供は手厚く守られているのである。
やがて疫病のため村人が逃げ去ると、そこには語り手「僕」と「弟」、母を疫病で亡くした少女、村で迫害されていた朝鮮人の子「李」、予科練の脱走兵、そして感化院の子どもたち大勢が残される。そこでもぬけの殻となった村から、村人の食料を盗み、さながらユートピアを作り上げるが…という物語の大筋がある。
大江健三郎初期作は、通して語り手の内面描写の秀逸さ、その洞察の鋭さにおいて特徴づけられる。様々な死に面して、時に嗚咽し、時に恐慌しながら「僕」は爆発的な怒り、悲しみを綴る。それらは過不足なく、物語の進行を妨げ得ない範囲で最大限にダイナミックであると言える。精緻に絶望的な状況を構築し、大人たちが子供たちを監禁することで、子供たちの無垢さ、その燦然としたエネルギーがくっきりと現れ出る。
愛人たる少女、犬、無垢な少年たる弟の消失、それはすなわち、幼年期の喪失の姿そのものだ。母の愛、恋人との親愛、動物への愛、兄弟への愛から抜け出し、1人の人間として生きてゆかなければならないという人生における不可逆で決定的な遷移そのものも、ひとつのテーマを成す。
読んでいて面白かったのは、濃密な心理描写、血なまぐさい情景描写が相まった密度のなかで、ところどころに大江自身の回想ともとれる、幼少期の想念が織り交ぜられていることだ。
私事で恐縮なのだが、私は祖父を3歳で、祖母を6歳で亡くしたため、「死」について幼少の時分から永く、深く考えていることが多かった。夜眠る前に、此の世から永遠に消えることを想像するだけで、空恐ろしく、自らの想像の限界に触れながら精一杯恐怖し得た経験がある。大江の描写はまったく完全な姿で、それを思い出させるのだ。
僕は死について考え、胸をしめつけ喉をかわかせる感情、急激な内蔵の押しあいへしあいにおそわれた。それは僕の一種の持病だった。その感情、全身的な動揺が一度起ると眠りこんでしまうまで決してそれから逃れることはできないのだ。しかも昼間それを実感もって思い出すことはどうしてもできない。僕は冷たい汗に背や腿の皮膚を濡らしそれにひたりきり、頭までめりこんだ。《死》は僕にとって百年後の自分の不在、幾百年、限りなく遠い未来の自分の不在ということだった。
不定形で、不可避だがやがてやってくる「死」について、考え始めてしまう病理。夜になると襲い来る陰性感情を、こうも的確に抉り出してくる大江の手際、小説家としての手つきは、日本語で書かれた小説のうち随一と言って差支えないだろう。
最後に言っておきたいのは、新潮文庫版(令和五年刷、五三版)には、平野謙の解説がついているが、そこではこの物語の設定の非現実性が指摘されていることだ。これは非常に大切なことで、これが現実ベースで書かれた「虚構」であることを忘れてはならないという当たり前の事実に我々を引きもどす。逆に言えば、それほどにこの小説が迫真に出来事を提示し得ているということになるのだが…。
とまれ、我々はつねに批評するように読むべきで、読んだものを無条件で肯定し、擁護する白痴となるべきではない。特にこのようなすばらしく、耽溺に誘う小説にそうした解説が付してあることの幸運(新潮社の慧眼)は、ありがたい。
