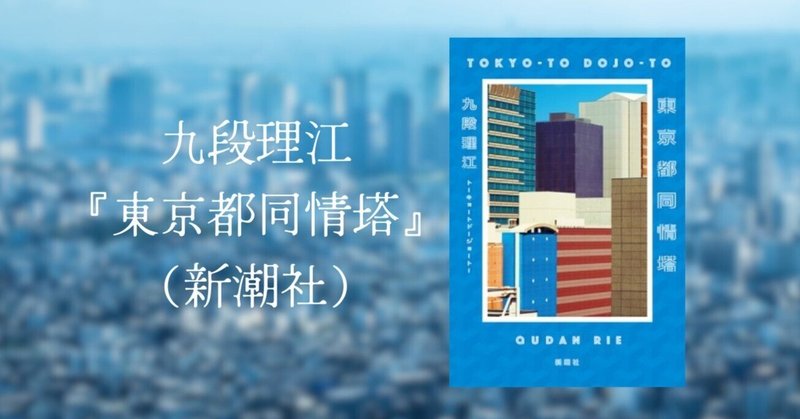
分断の時代に聳え立つ―九段理江『東京都同情塔』
概要
第170回芥川賞受賞作。ザハ・ハディドの圧倒的に美しい、東京五輪の競技場が、アンビルド(un-build)ではなく、出来上がってしまったifの世界にこの物語は始まる。そこでは新宿御苑に新たな塔が立つ。その塔は犯罪者を「同情されるべき人々」として厚遇する、斬新な価値観に基づく建築だった。「バベルの塔の再現」という字句から始まる『東京都同情塔』は、その塔を見据え、実際に設計・建築する女性建築家を主な語り手としている。バベルという涜神によって言語がばらばらになる、その現象と罪を近未来のIF東京に重ねている、巧みさは鮮烈なものだった。
生成AIとの距離
この物語のすばらしいところは、突拍子もないifの世界の思想、その設定状況を、読者の現代的実感に落とし込む形で提示して見せるところだ。そのために大いに用いられているのが、生成AIという存在だ。この作品の断片をそのままAIの文章が形成していることも芥川賞受賞の会見において話題となった。読書する人間、創作する人間がどこかで感じている生成AIの限界と、その欺瞞を文章の端々に置いている。
訊いてもいないことを勝手に説明し始めるマンスプレイニング気質が、彼の嫌いなところだ。スマートでポライトな体裁を取り繕うのが得意なのは、実際には致命的な文盲であるという欠点を隠すためなのだろう。いくら学習能力が高かろうと、AIには己の弱さに向き合う強さがない。無傷で言葉を盗むことに慣れきって、その無知を疑いもせず恥じもしない。人間が「差別」という語を使いこなすようになるまでに、どこの誰がどのような種類の苦痛を味わってきたかについて関心を払わない。好奇心を持つことができない。「知りたい」と欲望しない。
語り手の女性建築家がAIに文章を出力させるシーンにおいては、このような批判がAIに向けられる。人間の言語は、無数の傷の歴史の上に存立していること、その言葉の成立の歴史的・社会的重みを「無傷で」「盗む」と表現しえたのは、言葉に鋭敏な意識を向ける作家としての自恃でもある。もうよいかと思いつつも、もう一節、こんどは別の男性による発話を引く。AIに文章を作らせたらよいのではないかという提案への鋭い切り返しだ。
「・・・なんとなくだけれど、でも絶対に、『違う』って体が拒否してる。僕の中に住んでいる検閲者が、それは伝記じゃなくてただの文章だって言ってる。フォルムとテクスチャーがない、ただのクソ文、ファッキン・テキストだって」
AIの作る文章も、同情塔の内側の犯罪者の理想郷も、平板な言語の表面を弄ぶだけの、「フォルムとテクスチャーがない、ただのクソ文、ファッキン・テキスト」的世界なのだ。構造として、AIの世界(塔)と、外の世界は空間的にも言語的にも分断されているのだ。(この点は次章に後述する)
本作においてAIは効果的な仕掛けとして物語を駆動しているように思われる。思考のきっかけとなるような批判として使用されている。その存在において提起をする、特異な小説だ。その位置づけだけ見れば、まるで現代社会に突如異物として立ち現れた、生成AIそのもののようだ。皮肉にも。
涜神と贖罪
私自身の勝手な読みの筋だけ明かしておこう。
この物語は先だって言ったように、「バベルの塔の再現」である。バベルの塔は人間が天まで届く塔を建てようとし、人間たちが単一の言語であったためにこのような叛逆が起こった!と、神の怒りにふれ、言語が散逸し、混乱し、人間自体も離散するという創世記におけるひとつの「物語」の「再現」である。「東京都同情塔(シンパシータワートーキョー)」は、完成してしまった「バベル」であり、その存在によってまさに言語は分断され(塔の内側は、「幸福に生きる」ため、ネガティブな語彙を使ってはならない。)、建築家は罪を負うこととなる。それは、現実の人々に対する表層的な罪科ではなく、世界を分断したことによる神罰のようなものだ。
「大きな物語」の時代が終わり、断罪する神なき現代(大独り言時代)において、罪はもはや自らで認識するか、捨て去るかしかない。(あるいは、最終部で不条理な欲望をもつ「男」の不条理性が罰する者として位置づくかもしれない)。
それゆえに、彼女は表向きには建築を放棄する。そして、途方もない時間による大いなる破壊、そして「永遠」という持続を幻視する。その幻視によって再び建築家が夢見たのは、AIの言語領域の消滅、そして外界との融合である。この物語はそのような建築家の志向によって円環に閉じられる。
まだまだ文芸には拡張的な可能性が残されている。創世記のバベルの塔、生成AI、SNS、検閲、美学、ママ活、あまたの要素を活かしきるという気概のもと、書く人・読む人を駆り立てるような知的な、冷静な熱が文体に宿っている。完全に言語的に分断され、各々が好きなことを語るこの時代、状況だけ見ればわれわれは幾重にも罰されているようだ。この小説はそんな時代にうち立った記念碑的塔そのものだ。
