
介護支援専門員(ケアマネ)実務研修:事前レクチャーの巻
介護支援専門員、別名ケアマネジャー
今さらだけど、ゴレンジャーみたいでカッコいい✨

それはさておき、いよいよケアマネの実務研修の先駆けとしてPC操作のレクチャーが行われた。勝手に同期と呼んでいる合格者の一部の人とzoomにてご対面した。

我が県の今年の実務研修受講予定者は1000人弱
その中でパソコンの操作方法を説明してくれるレクチャーに参加するのは半数程度。
50人を1グループに分けたレクチャーを主催者側で行ってくれる。
これは強制ではなく、あくまで希望者のみなので参加人数も少なめ。とはいえ多くの参加者が自分と同じくPC操作と今後の研修に不安を持っていることにホッとする。
レクチャーに参加した際、これから始まる実務研修の内容について伺ったところ、前に上げていたnoteに書いた内容と若干違っていたので、念のため改めて書いておこうと思う。
探してはみたもののケアマネの実務研修について書いてある記事はわりと少ない。
もしもこれから試験を受けてみたいと考えている人の参考になれば、と良い人ぶって書いておく。
ただし、私の認識が間違っている可能性も存分にあるので要注意。
自己責任で読み進めて欲しい。
当然クレームは受け付けません。
なぜなら豆腐メンタルの持ち主だから。
クレーム体質の人はここで読み終えることを強く要望する。
大切なことは2回書いておく。
自己責任で読み進めて欲しい。
↑
過去にUPしているこの記事ではケアマネの実務試験について
『ケアマネジャーとしての仕事内容を学ぶ研修』という表現をしているが、実際のところはちょっとニュアンスが違う気がしてきた。
もちろん仕事内容も学ぶし実習もある。
ただ、それだけではなく、どうやら多人数のチームでのコミュニケーションの取りかたやグループでの話のまとめかた、ケアマネジャーの立ち位置や業務内容についての他人への伝えかたなど、理屈や机上では学べないことがメインのような気がしてきた。
そのレクチャーとはこんな流れだ。
「今後、研修が始まったら11日間宜しくお願いします」
今回のレクチャーを担当してくれた人が今後の実務研修も進行するようだ。
この人こそが我々の希望の光、頼みの綱であり中心的存在。
赤レンジャーである。

赤レンジャーは言っていた。
「パソコンが苦手な人も多いと思います。我々も集合研修のほうが正直やり易いです。でもこれはICT活用を促進する国からの指示です。たとえパソコンが苦手でも参加することが大切です」
ICTとは
情報通信技術や情報伝達技術を意味し、インターネットやスマートフォンなどの情報通信機器を利用して、デジタル化された情報を伝達したり、コミュニケーションを円滑化したりする技術を指します。
つまり
業務で使用する最低限のパソコン操作方法くらいは知っとけ! by国
仕方ないことだ。
ケアプランや支援の経過記録に限らず、聴き取りした内容や、各サービス事業者とのやり取り、市への提出物など様々な情報をパソコンに入力して書類を作成して、ネット上で各職種と共有する時代。
全ての関係者が同じ場所に一同に集まって会議するのはあちこちで支障が出る。

今後はデータのやり取りが主体で紙は使わなくなるだろうし、ネット会議も今となっては当たり前。そのほうが誰しも時間もお金も有効に使える。
何枚もの紙をコピーしてFAXして、訂正内容を印刷してFAXで返して、それを保存して。
なんてやってる場合か、ということだろう。

小学校でパソコンを教える時代なんだもん。何歳だろうがパソコンなんて使えて当たり前って思ってるのだ。
これは、バブルの頃に「どうせ1999年に世界滅亡するから」と言って、カラフルに染めた鳥の羽根で出来た扇子を振り回していた罰なのか。
どうしてくれよう、ノストラダムス。
この恨みは忘れまじ。
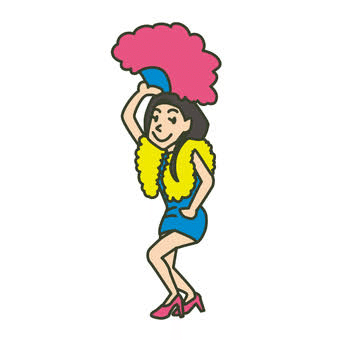
赤レンジャーは、ワンレン・ボディコン世代の我々を強制的に8名グループに分けて、超初歩的な課題を出してきた。
受験番号が若い順で振り分けられたグループ内メンバーは年齢も職業もパソコンの習熟度も様々。
全体zoomから、グループミーティングに移動させられてして、
一人ずつ自己紹介→共有ドキュメントを開く→開いた共有ドキュメントに各々が記入して書類作成→記入した共有ドキュメントを各自が名前を付けて保存する。
これが赤レンジャーのいう『超初歩的な課題』だ。
移動したグループチャットには、明らかにパソコンを操作することだけで目一杯なメンバーがいた。
クリックをタップと言っている。これはスマホは使えるけどパソコンは初心者🔰
自己紹介でも「パソコンが大の苦手で触るのも恐怖です」と言っていた。
初心者にとってのパソコンは高価なものであり、壊したらどうしよう、元に戻せないのではないか?と恐怖そのものだ。
私も含めて誰しもが通ってきた道。
初心者🔰さんはドキュメントをダウンロードするためのURLが表示されている[チャット画面]を開けずパニックだった。
グループ内の男性から説明を受けて、言われたとおりに操作をし、何とかチャット画面を開くと今度は[zoom画面]が無くなったと大騒ぎである。
「ドキュメント?何?それは。どこ?」
「チャットってどうするの?今、画面には皆さんの顔しか出てないの」
「あ、これかな?ここ押すの?青い線のやつ?」
「あぁ、これがドキュメントね」
「でも今度は皆さんの顔が見えない、どうすれば顔が見れるの?」
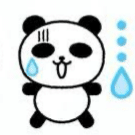
カオス
ある程度予想はしていた。
でもこれは予想していたよりも手強い。遥かに手強いぞ。
レクチャーの主催者側も閉口している。
パニック中の初心者🔰さんと説明する男性の二人を除いたグループ全員は無表情で黙り、そのやり取りを聞いている。
恐らく、ドキュメントが全画面で開いたことにより、zoom画面がドキュメントの裏に隠れてしまっているのだろう。

慌てている。
他の誰にも1ミリの発言を許さないほどずっと一人で間を置かずに喋っている。
「皆さんは見えてますか?私は皆さんの顔が見えません!」
いや、顔は別に見なくてもイイのよ。
言いたいけど言う隙を与えない。
「さっきまで皆さんの顔が見えたのに、見えないの」
「どうすればイイの?」
やべぇ
赤レンジャーに「各自が自分のパソコンに保存する所までやって下さい」と言われた課題は、当然終わらずにグループミーティングの時間が終了した。
( ゚д゚)ハッ!
そうか、これか!
これこそが本当の実務研修だったのか!
分かったぞ、つまりこういうことだ。
謎が解けた!

このように誰かがパニックに陥っている場合でも丁寧に分かりやすく、難解な課題をこなす方向に導けるよう、グループで助け合って答えを出す。
まさに、これこそが実務研修で身につけて欲しいスキルなのだ!
だって研修中に流れる動画の内容は難しすぎて理解不能。
動画に表示されている内容をただ読み上げているお姉さんは、時々読み間違えている。動画なのに?間違えたまま続行?撮り直さないの?実は、もしかして間違い探し?間違いを見つけられたかのテスト?そう思って最初の頃は読み間違いの箇所をメモしていたのは内緒だ。
20分前後の理解不能な異世界の言語による難しい講義動画を、何本も見続けて最後に小テスト。
ドキュメントに記録して名前をつけて保存→システムに格納。
苦行である。
お経を聞いているかの如く、話している意味が分からない。
この苦行を体験することに実務研修の意味があるのか?とさえ思っていた。
違うのだ。
こんな苦行を与えて無の心を知らしめることは本来の目的ではなく、きっと本質はこうだ。
この先、利用者それぞれが抱える難解なケア課題を協力して解決して行くにあたり、予想を超えるような出来事や、様々なパニック状況に陥っている人と関わっていかなければならない。
それを一つずつ、多職種が連携して、誰もが理解して納得するようなチームケアで困難を乗り越える。
これこそが、実務研修の目的!

お得意の勝手な解釈である。
動画の内容は大切なことで、難しい言葉も理解しなくてはいけないのは分かっている。でもそれだけでは無い気がした。
勘違いされると困るので念のため書いておくと、パソコンが苦手な受講者は何ひとつ悪くない。責めるつもりも毛頭ない。
それよりも頑張りがすごいし、私も同じ道を通ってきたのでパニックになる気持ちがよく分かる。
当然、そういう人のための操作方法のレクチャーだと思っていたから受講者になんの落ち度もない。みんなの顔を見たがっていた前出の初心者さん🔰はこの研修のためだけにパソコン教室にも通い始めたと言っていた。ガッツが素晴らしい👍
それよりも問題点を探すなら、ある程度のパソコン操作習熟度が必要なら、その程度をもう少し詳しく、早い段階で周知しておいたほうが良かった気がする。
あと、レクチャーの時間が足りなすぎる。
MOS資格持ち、Windows95からパソコンを使っている私ですらも、相当かけ足のレクチャーで、これ私大丈夫なのか?と焦った。
・実務研修はオンライン研修です
・事前にレクチャーやります
これだけでは油断してしまう。
レクチャーはやればOKではなく、理解してもらわないとやる意味がない。
我が県なら次からは改善してくれるはずである!
レクチャーに戻ろう。
レクチャー終了予定時刻が大幅に過ぎ、そろそろ終わりの雰囲気が流れたとき
「この実務研修の内容次第では、またもう一度実務研修を受けなければならない事態になり得ますか?」
赤レンジャーに質問がとんだ。

イイ質問!
誰もがそれききたかったはず!
赤レンジャーは丁寧に優しく説明した。
「入院など個人の事情で、研修を最後まで受講できなくなり未受講の部分を翌年受けるというかたはいます。ですが、講義中に眠っていたり席を立つ時間が長いなどの問題行動が無く、きちんと全部の受講を終えて、期日を守って提出した「課題の出来や内容」次第で受講完了にならないということは無いです」
「パソコンを上手に使えなくても、大丈夫です。グループで誰かが記録して、誰かが発言する。グループワークなのでそこはグループのメンバーで助け合って研修をすすめてください。パソコンの操作は研修中に少しずつ習得して慣れてください」
そう!これこそがレクチャーを受けた我々が一番心配していたことだ。
この答えで、少しだけ肩の荷が降りた。少しだけね。
久しぶりに言う。
さすが我が県である!

ちなみに
未受講になってしまった場合、翌年に限り無料で「未受講部分だけ」を受講することができる。
しかし、翌々年となると受講費を再度支払い、全講義を最初から受講しなくてはならないとのことだ。
(我が県のことで他県は不明)
カオスな集会レクチャーが終わり、次はオリエンテーション。
その前に、山のようにある事前課題という名の宿題をこなさねばならん。
やれるのか?
先はまだまだ長い。
いいなと思ったら応援しよう!

