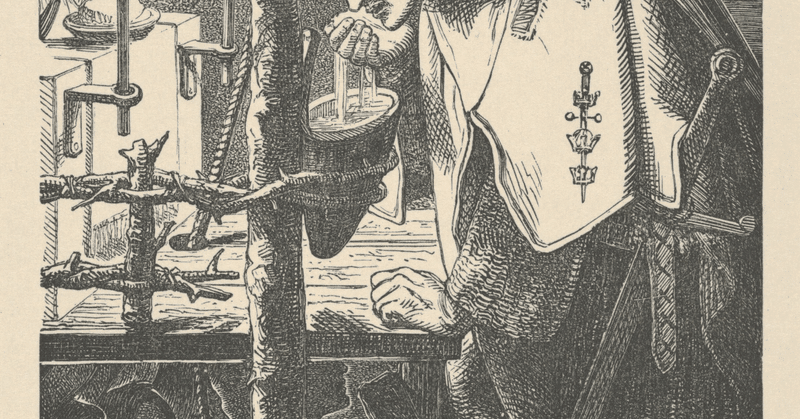
バカなカバと加速主義的司馬史観、日本子供銀行券と田中各駅停車もしくは敏腕経営者のケツバットあるいは寸止め海峡日本海、肋骨鎖骨暗黒啓蒙ヴィーナス頬杖桜草、亭主元気で箪笥にごんごん夢を語れば文春砲
六月二八日
強い酒を飲んで酔ふのは外道である。清酒や麦酒なら酔つてもそれ程の事はない。しかしお酒にしろ麦酒にしろ、飲めば矢張り酔ふ。酔ふのはいい心持だが、酔つてしまつた後はつまらない。飲んでゐて次第に酔つて来るその移り変はりが一番大切な味はひである。
午前六時。やたら蒸すんでエアコン作動させてます。いまから十二時間は起きていないと。43200秒と思えば大したことはない。43200000000マイクロ秒だと思えばもっと大したことはない。濃い目のブラックティー飲みまくればきっと大丈夫。中丈夫。小丈夫。ポムポム不倫、リラっ糞、苦労柳哲子。図書館は明日か明後日からか。つぎ何読もか。グレアム・ハーマンがやや気になっている。「オブジェクト指向存在論」とか胡散臭さ満点じゃないですか。オイラこういうの嫌いじゃないよ。トンデモ文学とかトンデモ思想も世には必要と思うのさ。すくなくとも「哲学」という業界では極端なものほど「正統」の座を占めやすい。たとえば「西洋哲学史」の巨人を挙げてみよう。プラトン、ヘーゲル、ニーチェ、キルケゴール、ショーペンハウエル、ベルクソン、ハイデガー、レヴィナスと、どいつもこいつも実によくぶっ飛んでる。誇大妄想やオカルティズムを内包していない人物を探すほうが難しい。でもそれでいいのさ。この宇宙自体がトンデモないシロモノなのだから。オッケーグーグル、さだまさしの名曲かけて。元気でいるか街になれたか友達できたか。おっけーぐーぐる、馬と猫と駱駝の睾丸を使ったおいしい料理教えて。俺はイエローでいまかなりブルー。ブルーアイズホワイトドラゴン。
川上未映子『乳と卵』(文藝春秋)を読む。
川上未映子の「著者近影」は女優的なナルシシズムが全開で、私はこういう女が少し苦手なんだけれども、彼女は作品はまあまあ好きなほう。彼女の書く言葉はよく跳ねている。地の文も地じゃない文もしゃきしゃきうねっている。とくに「関西弁」がいい。たぶん耳がいいのだ。小説書きはだいたい皆そうだ。文学の本質は「詩」なんだよ。僕は関西弁というか方言の多様された小説はおよそ嫌いなんだが、名調子快い文章であればときどき心を許す。
『乳と卵』は芥川賞作品(二〇〇八年)。とうじ学生だった私は文藝春秋(雑誌)を購読していて、この受賞作が掲載された号も確か買った(石原慎太郎による否定的な評を読んだ記憶がある)。でも最初の数頁で作品を読むのを止めてしまった。その文体に馴染めなかったのだろうと思う(ついでにいうと『abさんご』も途中で止めた)。当時の私は「文学作品」としてパッケージされた文章が概して苦手だったのです。私が文学に目覚めるのはそれから約三年後、埴谷雄高の『死霊』に出逢ってからだ。文学は「存在の革命」の一手段になりえることを私は彼に教わった。「なんでもあり」であることこそ文学の暗黒生命なのだ、と。いずれ埴谷論もやろうか。彼の主要な書き物をいっかい読み返してもみたい。埴谷に比べればたいていの日本作家は小物過ぎて真剣に論じる気になれない。
当たり障りのない「解説」風にいうなら、『乳と卵』には、のちの大作『夏物語』で展開される主題が凝縮されている。「性」ひいては「肉体」というのものの気味悪さや残酷さが、夏子、巻子、緑子の三人の女たちの「語り」を通して表出される。巻子の偏執的な豊胸手術願望は「女としての自我理想」の暴走にしか見えず、痛々しい。その痛々しさはきっと、「女であること」というより、「肉体的存在であること」に起因しているのだ。他者の眼につねにすでに開かれている不条理的肉塊であることに(ロクサーヌ・ゲイは『飢える私』のなかで自分の巨体を「檻」「犯罪現場」に喩えていた)。肉体を持って生きるということは、他者の品評的眼差しに死ぬまでさらされ続けるということ。この「耐えがたさ」を主題にした小説はやはり女性作家のほうが一等上手い。
巻子の娘・緑子の緘黙は、『死霊』の矢場徹吾の黙狂ほどには徹底したものではなく、そこが残念だった。あとなんだかんだ緑子は一人称語りのなかで母親をそうとうに気遣っていて、そこも残念だった。ところどころに目立つこうした「俗情との結託」は文学の「本来的自由」に対し抑圧的に機能してしまう。さいごのほうの、母娘が卵を頭で割りながら泣いたり叫んだりするところに至っては、日本映画の安い絶叫シーンみたいで興醒めだった。やはり狂気が決定的に不足している。もっと遠くにいかねば。遥か遠くへ。知らない
街を歩いてみたい。どこか遠くの街に行きたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
