
「生きづらさ」がマジョリティとなる時代にー熊谷晋一郎さんが語る当事者研究の可能性
食事をする、移動をする、働く、遊ぶ、語り合う。私たちが生きていく上で抱く欲求や願い、それを実現するための行動。それらが自分の思うままに叶えられないー「障害」があるというとき、その原因はどこにあるのだろうか。
かつては、障害の原因は本人の側にあるという「医学モデル」の考え方がスタンダードだった。しかし1980年代以降、「障害というものは、皮膚の内側にあるものではない、皮膚の外側にあるものだ」という「社会モデル」への認識の転換が起こる。
法律や福祉サービスの制定・改正、生活環境のバリアフリーやユニバーサルデザイン、身体を拡張するテクノロジーの開発と普及。先人たちの「当事者運動」の結果、さまざまな制度や社会環境の整備が進んでいった。
そして近年では、困りごとのある当事者が、医師や支援者ではなく、自分自身が主役となって困りごとの正体を研究する、「当事者研究」というムーブメントが広がりを見せている。
先人たちの挑戦が切り開いた地平と、現代社会特有の課題、そして未来。
私たちはどこから来て、どこへゆくのか。過去・現在・未来を結び、社会的マイノリティに関する「知」の共有と深化を目指すシリーズ講義「LITALICO研究所 OPEN LAB」が2019年7月よりスタートした。
第一回の講義では、「『障害のない社会』に向けた現在地と課題、そして」と題し、東京大学先端科学技術研究センター准教授で小児科医の熊谷晋一郎さんが登壇した。
熊谷さんは1977年山口県生まれ。生後間もなく脳性まひによって手足が不自由になり、以後車椅子で生活をしている。
熊谷さんの専門分野のひとつに、「当事者研究」がある。2001年、精神障害の当事者グループ「浦河べてるの家」で生まれた活動であり、『みんなの当事者研究』『当事者研究と専門知』『当事者研究をはじめよう』(熊谷晋一郎責任編集、雑誌「臨床心理学」)といった当事者研究にまつわる雑誌が3刊連続で発売されるなど、現在注目を集めている。
「当事者研究」とはどのようなものであり、どのような歴史のもとで始まり、どこへ向かっていくのか。誰もが「生きづらさ」を感じる現代において、当事者研究の持つ可能性はどこにあるのか。
過去と現在を結び、そして未来への展望を描く、熊谷さんの講義が始まった。

水と油が混ざりあう? 「当事者研究」の謎
障害や病気など困難のある当事者たちの活動には、日本では大きく二つの流れがある。
一つ目は、社会を変えることを目的とした「当事者運動」。日本では脳性まひ者を中心として、親元や施設から離れた生活を目指す「自立生活運動」が1970年ごろから活発に行われた。二つ目は、薬物やアルコール依存症者による「依存症自助グループ」だ。アメリカの誕生とほぼ同時期にその記述が確認されているほど、自助グループとしての歴史が長い。
この両者が合流し、精神障害当事者たちのグループ「べてるの家」で「当事者研究」がはじまった。
しかし当事者運動と、依存症自助グループの活動は、表面的には一見、「大切にしていることが正反対」だと熊谷さんは指摘する。
「水と油のような両者がなぜ混ざり、なぜ混ざらなければいけなかったのか。それが当事者研究の謎と魅力です」
日本の当事者運動の中心となった脳性まひ者たちは、水を飲むタイミングも、住む場所や人も自分で決められなかった。子どもを生みたいという思いも、「優生保護法」のもとで踏みにじられてきた。それに対するカウンターが当事者運動だった。
「当事者運動では、本人の意思や欲望を承認するのが大事なスタート地点なんです。自己決定や意思決定を大事にしてきた。どう生きたいのかは自分で決めるのだと」
力を奪われてきた当事者が、力を奪い返そうとする。だからこそ当事者運動は、自分の欲望や意思を承認し、自己決定を重んじてきた。
一方、依存症自助グループは異なる立場をとる。
「アルコールを飲みたい、薬を使いたいというのは、まさに意思や欲望です。依存症自助グループではこれを『手放す』という独特なスタート地点に立ちます。意思や欲望の存在を認めながらも、保留にするのです」
アルコール依存症の回復グループとして歴史のあるAA(アルコホーリクス・アノニマス Alchoholic Anonymous)では、12ステップと呼ばれる回復プログラムを使用する。最初のステップ1は「自分の意思ではどうにもならなかったことを認める」ことからはじまる。「アルコールを絶対に飲まない」と宣言すると、すぐに飲んでしまう。そうした逆説的な人間のあり方への洞察が、アルコール自助グループにはあった。
両者はグループの運営の方法も違う。当事者運動は社会変革を目的としているものだ。「われわれ」の声として意見をまとめ、社会に訴えかける必要がある。一方、依存症自助グループは、「言いっぱなし聞きっぱなし」のグループミーティングを行う。多様な声をひとつにまとめず、様々な声があることを重視した。熊谷さんは前者を「シンフォニー(語りの統合)」後者を「ポリフォニー(語りの陳列)」と名づけている。

当事者研究と「ドーナツ」
まさに、「水と油」の二つの当事者活動は、どのようにまとめられてきたのだろうか。熊谷さんはそのポイントとして「周縁化」を挙げた。
周縁化とはなにか。どのようなグループでも、そのグループを代表する中心メンバーがおり、そこから外れて排除されてしまいそうな位置に置かれている人々がいる。
当事者運動と依存症自助グループの中心にはどのような人がいたのか。
障害者自立生活運動の中心にいた一人として、新田勲(にった・いさお1940-2013)がいる。彼は重度の脳性まひで喋れないため、木の板の上で足先をはずませる「足文字」という方法で介助者とコミュニケーションをとりながらも、粘り強い行政との交渉で24時間の公的介護保障を生み出した運動家だ。
依存症グループの中心には、社会的な地位があるにも関わらず、「人生のある段階までうまくいっていたが、アルコールや薬物の魔力にとらわれて、すべてを失いかけてしまった」人たちがいた。グループができはじめた初期の段階では、戦争のトラウマがあり、PTSDを自己治療しようとしてアルコールや薬物の依存症になってしまった元軍人が多かった。
それぞれのグループの中心メンバーはずいぶん違っているが、どちらも中心にいる人たちにカスタマイズをされる形で、グループはその性質を洗練させていく。
では、それぞれのグループで「周縁化」されたのはどんな人だったのだろうか。
当事者運動のグループにおいて周縁化されたのは、精神障害や発達障害のある人、身体の痛みだけが問題であるような人など、「見えにくい障害」のある人たちだった。
「新田勲さんや私は、見るだけで障害者だとわかります。通勤の時に満員電車に乗ると、月に一度は舌打ちや、唾を吐きかけられるような露骨な差別に直面する。一方で、見えやすい障害を持っていると、『表現コスト』が節約できる面もある。例えば、私の手が曲がっていてマイクを持ちづらいことが分かるので、スタッフの方が私のかわりに持ってくれる。自分に必要な支援を、わざわざPowerPointでプレゼンしなくてもいい」

(この日の講義では、会場のマイクスタンドに不具合が生じ、スタッフが交代しながらマイクを支えて対応した)
しかし見えにくい障害のある人は、自分から表現をしないと支援が得られないことがほとんどだ。周囲から常に「本当なのか?」と疑われ、「甘えているだけ」「もっと努力できる」と言われ続ける。さらに、本人さえも自分の障害に気づけない場合もあり、自分を責めるなど、混乱の中に居続けることになる。当事者運動に参加したくても、そもそもどのような社会的ニーズを訴えたらいいのかがわからない。
「どこまでが努力でどうにかなり、どこからが仕方ないのか。『見えにくい障害』を持つ人たちは、運動をする手前で自分たちを『研究』する必要がありました」
一方で、依存症自助グループで周縁化されたのは、依存症以外にも問題を抱えている人々だった。
「言いっぱなし、聞きっぱなし」の依存症グループの手法では、「外部の問題には意見を持たない」ことが重視されてきた。依存症はもちつつも、ある程度は社会的資源に恵まれた人たちが中心にいたため、依存症から回復して元の社会に戻ることが目指されたからだ。
しかし現在では、戦争によるPTSDは減り、貧困、家庭内暴力やいじめの被害者、重複的な障害などが依存症のリスクになっている。依存症から回復してもなお、たくさんのリスクが残る人々が増えた。
「世の中から差別されている人たちは、自分たちが置かれている状況をグループの外に発信しないと生き延びられない。女性で依存症になった方の背景に女性差別があるのであれば、グループの中で分かち合いができても、社会に出ると苦しくて、また依存症に戻ってしまう」
当事者研究は自助グループとは違い、公開性があるのが特徴だ。「研究」であるため、学会発表のように他者に向けて研究した内容を発表する。閉じたグループでお互いのつらさを分かち合うだけではなく、広く一般に向けてプレゼンテーションすることによって「世の中の差別や偏見を、自分の生活圏内においてじわじわと減らす効果」が期待できる。
「ドーナツの場所から生まれるのが当事者研究」と熊谷さんは話す。
どんなグループでも、中心があり、そこから外れる人たちが生まれ、周縁化されている当事者から当事者研究がはじまる。そして当事者研究が成熟すると、初期の担い手であった当事者たちがグループの中心となっていく。するとまたそのグループで周縁化されたドーナツの場所にいる人たちが、次の当事者研究の担い手になっていく――

(文字起こしアプリ「UDトーク」を利用し、聴覚障害や難聴などがあり会話が聞き取りにくい人のために、発言内容を文字起こしする様子)
障害者支援の「制度化」の功罪
次に、テーマとしてあがったのは「制度化」だ。
「制度化」とは文字通り、あるサービスが制度に組み込まれることで、法律や制度の文言として書き加えられたり、補助金が下りたり、グループが法人化したりすることを指す。
それまで当事者たちが自費で集まり、ボランティアや寄付金を活用し、自転車操業でなんとかやってきた活動も、制度化が進めば、補助金が下りて運営がスムーズになり、スタッフの雇用も可能になる。活動も持続可能なものになっていく。
熊谷さんは自身の生活を振り返りながらこう話す。
「2003年に身体障害者への支援費制度ができ、ようやく介助者を探すのに苦労しなくなりました。それ以前は、私のような1日24時間介護が必要な障害者は、自らサンドイッチマンになって街頭でビラを配り、ローラー作戦で介助者を自力で集めないといけなかった。200人ほどの協力者を集めないと、シフトが組めなかったんです。でも、今は介助者を集める役を事業所が担ってくれるようになりました。もちろん今でも大変なのですが、当時ほどつらいものでは無くなった。介助者の給料も、保障されるようになりました」

当事者運動の歴史は、まさに制度化の歴史でもある。依存症自助グループにおいてもグループが法人格をとるなど、制度化は右肩上がりに進んでいる。
ただ、制度化にはデメリットもある。
まずは、メンバーの多様性が増えることだ。「多様性」は、一般的には肯定的に捉えられるが、団体運営の面では困難さが増す。かつては志をともにしてきて、似たような経験をしてきたメンバーたちが、連帯してグループを運営してきた。しかし制度化されると、行政から当事者を紹介されたり、依頼に応えたりすることになる。理念や経験を共有できておらず、そもそも本人にまだモチベーションがない場合、これまでのグループのノウハウでは対応できなくなってしまう。
依存症自助グループでは「12ステップ」プログラムにうまくなじめない当事者も登場した。あるいは、障害者運動の歴史をまったく知らない障害者たちが、介助者を得るためだけにグループに入ってくる。その結果、従来のプログラムでは対応できなくなっていく。
さらに、制度化の波の中でメンバーの多様性が増すことで、「発達障害」の概念が濫用されるようになってきてていると熊谷さんは指摘する。
「例えば、新しい仲間にこれまでの依存症自助団体のプログラムが通用しなかったら、『あの人は、発達障害なんじゃないか』と言われてしまう。専門家だけではなく、当事者同士でなじめないメンバーのことを『発達障害』として解釈するような状況が散見されます。
発達障害はまだ未熟な概念です。ひとつの教室になじめない子がいても、担任が変わったりクラスの秩序が変わると、その子は翌年から馴染めるようになる。そうしたことは、現場ではよく起きます。でもそうした子を『発達障害』と呼んでしまう。ある秩序に馴染めない人のことをラベリングするような概念になっていないか」
次に「コンプライアンス」(法令遵守)の問題がある。行政から補助金が下りると、活動にコンプライアンスが求められる。しかし今まで練り上げてきた回復のテクニックは、必ずしも法律と相性がいいわけではない。例えば「ダメ、ゼッタイ」の厳罰主義では依存症が回復しない。むしろ依存症自助グループでは、違法な物質を使いながらも生きのびることが、回復のある段階においては必要な場合もある。障害者運動においては、これまで法律の問題点を指摘し続けてきた歴史がある。それでも、補助金が出ているため行政に批判的なスタンスをとるのが難しくなってしまい、従来の理念やプログラムが換骨奪胎されてしまう。
制度化の功績はある。しかし、プログラムが効かない新しいメンバーができる上に、プログラム自体が骨抜きにされてしまう。制度化により、当事者活動は二つのプレッシャーにさらされているのだ。
このような制度化のデメリットに対抗するためにはどうしたらいいのか。
メンバーの多様性に対しては「クロスディサビリティ」を、行政への対応としては「ロビイング」と「アドボケイト」が有効だと熊谷さんは提案する。
「クロスディサビリティは、障害の種類を超えて活動すること。自分の障害だけではなく、身体障害の人も依存症の人もお互いの歴史や理念から学ぶ。障害種別に縦割りになっているところに、クロスディサビリティの輪をつくる。
行政からお金をもらっても、制度を変えていくためのロビイングやアドボケイトは行う。例えば、依存症からの回復のためには厳罰主義はダメなのだと行政や人々に教育し続ける必要があります」
そして、このクロスディサビリティと、周縁化は密接に関係している。
「クロスディサビリティは、グループAとグループBとの橋渡しをすることです。それが可能なのは、周縁にいる人です。例えば、脳性まひでアルコール依存の人は、障害者運動と依存症グループの両方が必要ですが、どちらのグループからも周縁化されます。彼らこそが、クロスディサビリティの最先端に位置しているのです」
そして、周縁者が主役になるノウハウこそが当事者研究なのだという。周縁者が語りを必要としていること、クロスアビリティの推進、この両方に当事者研究は取り組むことができる可能性を持っている。
(制度化については、熊谷晋一郎 編集『当事者研究と専門知(臨床心理学増刊 第10号)』にて詳しく触れられている)
「妄想」と「現実」の二階建て
では、当事者研究とはどのようなものなのだろうか。
べてるの家で生まれた当事者研究は、幻覚や妄想を持ちながら生きていく当事者が、支援者にサポートされながら生み出したひとつの方法だ。
統合失調症の特徴のひとつに妄想がある。「妄想」とは、「多数派とは異なる信念体系を持っていること」だと熊谷さんは定義する。それまでの精神医療において、この「妄想」は、どんなに説得しても変わらないものだと信じられてきた。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんのそれぞれがこのような信念を持っているとしよう。
・Aさん「UFOに追われている」
・Bさん「FBIに追われている」
・Cさん「暗殺集団に追われている」
べてるの家が当事者研究を実践する中で分かったのは、「人の妄想は妄想だとわかる」ということだった。つまり、それぞれがこう考えるようになる。
・Aさん「UFOは真実だけど、FBIや暗殺集団は違うのでは?」
・Bさん「FBIは真実だけど、UFOや暗殺集団は違うのでは?」
・Cさん「暗殺集団は真実だけど、UFOやFBIは違うのでは?」
この3者でコミュニケーションをとると、「他の2人には共有されていないということは、私の信じて疑わない感覚も妄想なのではないか」と考え、自分が妄想を持っていることに気がつく。
「支援者が一対一で説得するよりも、多くの人にとっての現実をただ否定せずに並べた方が、『えっ、そうなのかな』と思う。この事実は、数の力の再発見でもあります」
よく知っている人に「あなた素敵ね」と言われても信じられないが、通りすがりの人数名に「あなた素敵ね」と言われると、「私って素敵なのかな」と思える。戦略的に嘘をつくかもしれない専門知のある支援者よりも、特に信頼をしておらず距離のある人が、数名で同じことをいう方が、信憑性が高くなることも多い。
当事者研究によって、「私が信じているのは多数決で妄想らしい」という気づきが生まれた。さらに、「つまり、合意してもらえた範囲が現実なのだ」と考えることになる。Aさん、Bさん、Cさんの中で、「妄想」と「(最大公約数的な)現実」の二つのレイヤーが生まれる。
しかし、3人は「現実」のレイヤーでのみつながっているのではない。「妄想」のレイヤーにおいても、「○○に追われている」という共通点が見つかり、深い共感が生まれる。この共感は、レイヤーが2つに分離し、妄想のレイヤーを現実のレイヤーが客観視できるようになるための、重要な前提条件だ。UFO、FBI、暗殺集団、といった○○に代入される中身が違っていても、ストーリーの骨格や経験は共通している。こうしたエピソードや出来事の骨格を、熊谷さんは「スクリプト」と表現する。否定された妄想は固くなり、スクリプトのレベルで共感され、客観化された妄想は、柔らかく、対話や変化が可能な何かになる。
「小説を読んだり、映画を見て共感したり、感動したりするのは、スクリプトに共感しているからです。まったく同じ体験をした人はいない。にもかかわらず私たちはスクリプトのレベルで共感しあっている。当事者研究によって、『○○に追われている』というスクリプト部分の共感を得ることができるのです」
「現実」のレイヤーでは、ハンナ・アーレントのいう「現れの空間」(space of appearance)のように、異なった人同士が、それぞれの異なりを表現しあっている中で、話し合い、合意してもらった範囲で「現実」が立ち現われてくる。
「妄想」と「現実」、この二つの信念の二階建て構造を、熊谷さんは政治哲学者のリチャード・ローティの言葉をかり、「アイロニー」と呼ぶ。ローティは、多様化した価値観を持つ人が乱立する社会の中で、それでも共存する切り札が「アイロニー」だと考えた。
自分の信念体系を「もしかしたら思い込みかもしれない」と思うレイヤーがなければ、異なる人との共存はできない。べてるの家の当事者研究では、ローティの言う「アイロニー」と非常に近しい状態が生まれている。
「さぁ、ここまで来ると、一体誰が妄想を持っていたといえるでしょうか」
と熊谷さんは会場に問いかける。

「『統合失調症の人は、妄想を変えられない』という『妄想』をもっていたのは、精神科医の方だったのかもしれません。だから薬を大量に投与し、間違った方法でその妄想を消そうと強迫観念に駆られていた。そして、一般市民も『妄想を持っている人は危ない』のだという『妄想』を持っていて、過度に恐れていました。それらの妄想によって、排除することを正当化してきた。
「自分が病気であることの認識を『病識』と言います。これまで『病識』を持っていないと思われていたのは統合失調症の人々でしたが、実は精神科医も、一般市民も、自分の妄想について『病識』を持っていなかった。誰でもうっかりすると、アイロニーを失い、妄想にとらわれてしまう。
つまり、当事者研究における『当事者』は、障害を持った本人だけではありません。精神科医も、一般市民も、すぐに妄想にとらわれてしまう、脆弱な存在としての『当事者』は普遍的なカテゴリーなのです」
どんな当事者グループでも必ず信念体系を持っている。例えば、一昔前の依存症自助グループであれば「薬物やアルコールを完全に辞めなければ回復ではない」とする「スーパークリーン幻想」があった。
グループがあればグループがとらわれている信念体系があり、この信念体系から外れる契機やチャンスも、周縁でこそ起こりうる。周縁はアイロニーが起きやすい場所でもある。
「リカバリー・イズ・ディスカバリー」
自分の信念体系を疑ってかかることができる、「アイロニー」こそが研究者にとって必要な態度であり、「現れの空間」を成立させる条件は、研究者になる条件でもある。だからこそ、「当事者研究」は「研究」の言葉を使う。
さらに当事者研究は、本人たちが生きやすくなるための方法でもある。それを端的に表現した、「リカバリー・イズ・ディスカバリー」(「回復とは発見である」)という標語がある。今までは発見を研究者が、回復は医療機関や自助グループが担ってきた。しかしこれら2つは別のものではなく、イコールで繋がっているのだと考える。
では、リカバリーとディスカバリーはどちらが目的で、どちらが手段なのだろうか。
当事者研究が広まると、「新しい支援法」として注目されることが増えてきた。これは、リカバリーが目的で、ディスカバリーを手段とみなした考え方だ。熊谷さんはその点に批判的だ。
「当事者研究の究極的な目標はディスカバリーにあって、リカバリーは副産物でしかない。リカバリーを狙うと、リカバリーしない。ディスカバリーを目的に設定したときに、リカバリーが最大化するんです」
あくまで「発見」を目指す。それが、当事者研究の中の「知恵」なのだという。これは「回復」を目指す依存症自助グループとも、「問題解決」を目指して社会に問題的する当事者運動とも異なっている。二つの当事者活動の潮流が混ざりあいながら、当事者研究に流れてきた独自の知恵は、言葉を持たなかった人々が言葉を発見するための力強い味方だ。

理想と現実、言葉と仲間
質疑応答の時間になり、会場からはいくつか質問が寄せられた。
質問1:どうして自助グループは声をまとめようとしないのでしょうか。もう一度ご説明ください。
熊谷:依存症の自助グループでは「言いっぱなし、聞きっぱなし」が重視されます。それは、依存症の背景に、少なからず暴力被害の問題があるからです。家庭内での虐待、学校内や職場でのいじめ、戦争のような国家の暴力――様々な暴力が依存症に影響しうるものです。
特に身近な人から幼少期に被害を受けると、大きな影響を受けます。身近な人に心を開いても、殴られたり、ののしられたりした経験があると、「身近な人に頼ってはいけない」「頼るともっとひどい目にあう」と学んでしまう。身近な人に依存できないと、頼れるものは、消去法で限られてきます。身近な物質に依存するか、自分の能力に依存するのか、遠くのカリスマに依存するのかしかない。
そうした人が依存症グループで話をして、次の人に「わかる」と共感されたとする。そうすると「ふざけるな、何がわかるんだ」と感じます。これまで長年、誰からも理解されて来なかったのに、ちょっと喋っただけで「わかる」と言われることに違和感があるからです。逆に批判されると「正直な話をしても、嫌な思いをする」となじみ深い感慨に包まれ、やはりそのグループには行かなくなってしまう。
ではどのような場が安全なのか。その中で編み出された手法が「言いっぱなし、聞きっぱなし」でした。喋る‐批判する、喋る‐共感するといったように、語りと語りとを安易に連結させない。自分の語りを長年相手の顔色を見ながら調整してきた人にとって、リアクションが発生することほど怖いことはありません。だから分断して並べる。質問したり、批判するのは合意形成を急いでいる状況で、意見をまとめようとする振る舞いでもあります。それを断念するところからスタートしているのが、依存症自助グループなのです。
このような手法は従来の「対話」とは異なるように感じるかもしれません。しかし、他人から受け入れられないことに恐怖心を感じている人にとっては、安全な条件なのです。並んだだけの語りの中にも、大きなヒントがあります。「言いっぱなし」「聞きっぱなし」の空間の中ではじめて、自分のことを正直に話すことに集中でき、人の話を聞くことに集中できる。その空間の中で、回復という現象が起きてきました。
今はちょっとした対話ブームですが、対話には様々なデザインがあります。どのような傷つきを抱えた人なのかによって、安全な対話のデザインが変わってくるのです。
質問2:リカバリーとディスカバリーの中で、なぜディスカバリーを重視するのか、その点について再度お聞きしたい。
熊谷:リカバリーには危うい面もあります。なにをもって「リカバリー」なのかは、社会や本人の価値観に支配されてしまうからです。例えば、フルタイムで働き、家族を養い、子どもがすくすくと育つ状態を「リカバリー」としてしまうことはできますが、それだけで依存症になってしまいそうです。
ある時、依存症のワークショップで、子育てをテーマに講演を頼まれました。テーマは「しつけと暴力の境界線がわからない」「子どものわがままにどう接していいのかわからない」というものでした。そこで私は「お預け期間をどう生き延びるのか」というテーマに設定しなおしました。
「お預け期間」とは、理想と現実が一致しない期間のことです。「おもちゃを買ってほしい」理想と、「おもちゃを買ってくれない」現実が一致しない。実はその時同時に、親にとっても「お預け期間」だといえます。「良い親になりたい」理想と、ついつい怒って「良い親になれない」現実がある。
依存症というのはまさにこの「お預け期間」をどう受け入れるのかという問題です。「お酒を飲みたい」理想と、「飲めない」現実がある。「飲まない」理想と、「飲んでしまう」現実がある。だから私は、「お預け期間についての答えは、もう皆さんの中に眠っています。私は答えを知りません」と会場に問いを投げ返しました。
話し合いの中で、お預け期間を生き延びる方法として2つの意見が出てきました。
(1)現実を理想まで引き上げる。(頑張る)
(2)理想を現実まで引き下ろす。(諦める)
この2つを挙げたのは、依存症自助グループにつながって間もないビギナーたちです。すると、依存症グループに長くいる人が「二つとも、依存症だ」と言いました。「依存症から回復するためには、理想と現実の一致を諦める。理想を諦めるのではなく、現実と一致させることを諦める。そして、その理想と現実の間に空いた隙間を「言葉」と「仲間」で埋めます」と。
理想と現実の間にあいた隙間を「言葉」と「仲間」で埋める。これはつまり「愚痴を吐く」ことです。こうして3つ目の意見が出てきました。
(3)理想と現実の一致しない状況に対して、愚痴を吐き、その苦しさを分かち合う仲間を持つ。
依存症になっていない人はこっそり愚痴を吐き続けている。愚痴を潔くないと思っていると危ないのです。
リカバリーを目指すのは、回復という理想に現実を近づけようとしているため、まさに依存症的です。一方で、現実を知り、分かち合う「発見」の作業は、愚痴に近い。等身大の語りをお互いに交わして行く中で、発見が起きます。しかし、「発見を狙う」ことが目的になると、また依存症になりやすいので注意が必要です。
「当事者」とは誰か?

次に、本会主催の鈴木悠平から質問があがった。
鈴木:周縁にいる人たちが橋渡しをする「クロスディサビリティ」が重要なキーワードになっていますが、2つも3つも当事者性を持ち合わせている人は全体の中では少人数です。橋渡しや連帯の担い手を求めていくのは難しいことではないでしょうか。
熊谷:「求める」というと、荷が重いことを要求しているような感じになるので、「勝手に起きている」と思ってほしいです。面白い言葉がそこから生まれてくる現状がすでにある。これまで言葉がなかった人たちの経験から、言葉が生み出されてきて、当事者研究がすごく豊かなものになっていきました。
その人たちが運動的な責任を負っているわけではなく、正直に自分の経験を話して、発信しているだけです。社会を変えるために行っているのではなく、正直になっただけで社会が変わってしまうことが起き始めています。
リカバリーとディスカバリーの関係性と似ているかもしれません。社会を変えようと発言するのではなく、正直に自分の経験を語ると、その副産物としてじわじわと社会が変わっていく。そこに蓄積されていくのは語彙です。今まで光が当たらなかった経験に言葉が与えられると、それが様々な場所で引用されはじめます。当事者研究のような周縁から生まれた言葉が、グループの中心でも使われるようになっています。
鈴木:自発的な連帯や発見が起こりやすいような場所や文化の条件としてどのような要素があるのでしょうか。
熊谷:アイロニーやスクリプト的な共感、言いっぱなし、聞きっぱなしのような当事者たちが蓄積してきた様々な技法と態度がすでに存在しています。
障害分野に限らず、企業の中や学校で当事者研究を持ち込むとどのようなことが起こるのか。例えば周縁化や制度化の話は、障害分野に関わらず、行き詰まりを感じている組織のあらゆる場面で起きています。私としては、様々な場所に根付くのではないかと思いつつも、あまり張り切らないようにしています。
鈴木:では、「当事者」とは誰なのでしょうか。診断のつく障害や病気がない方とも、共通の困難を持って集まり研究をすることができるのではないかと思う一方で、「つらいのはみんな同じだよ」とぼやけてしまうこともある。今は「生きづらさ」という言葉を、障害疾患がない方でも広く使うようになってきました。
熊谷:障害には「医学モデル」と「社会モデル」の二つの考え方があります。医学モデルは、本人の身体の特徴で障害を定義します。足が動かないから、目が見えないから障害者だと考える。一方で社会モデルは、本人と社会との間に障害があると考えます。置かれた社会の状況によって、障害者になる場合とならない場合がある。現在、障害については「社会モデル」で考えるのがスタンダードです。
例えば、粛々とマニュアルにそって労働をやり続けていた製造業が中心の時代では、コミュニケーションをとらずにコツコツこだわりを持って労働をするのは、むしろ「健常者の鏡」でした。しかし、そうした仕事が機械化し、あるいは海外に移転してしまったことで、機械ではできない労働をこなす人々が「健常者」と呼ばれ、コミュニケーションが苦手な人たちが「自閉症」だと診断されることが増えてきました。
かつては「理想の健常者」だった人が、社会の側が変化した結果、「障害者」と呼ばれるようになる。社会の側が急速に変化しているので、昨日までは障害者じゃなかった人が、自分も気が付かないうちに潜在的な障害者になっている。自分の身体は変化していないのに、社会の変化によってミスマッチを起こしはじめている。これは「見えにくい障害」と同じ状況です。
そうなると、なぜだか分からないがうまく行かない。ストレスがたまる。そうした時に、自分を責めるかもしれないし、誰かが自分の足を引っ張っているのだと、犯人捜しをしてしまうかもしれない。そうした犯人捜しの思考パターンは政治利用されることもあります。
障害者が特権を持っているだとか、社会的に弱い立場に置かれている人が私たちの邪魔をしているだとか、排外主義的な言説で自分のしんどさを説明しようとするけれど、当然ながらうまく説明できません。本来ならば、社会の変化に原因があるのに、その情報にアクセスできずに、間違ったものを原因だと捉えてしまう。このような現象が世界的に起こっているのです。
そうした意味で、今は最大のピンチであるとともに、チャンスでもあります。相当な人が今”障害者”になっている。そこに気づけば連帯の道はあるのではないか。
見えにくい障害を持つ人たちは、当事者研究を行う中で、より説明力の高いものに自分の困難の帰属先を変更しています。今、同様のことをやらないといけないのはマジョリティかもしれません。自分の名づけづらいしんどさを、当事者研究によって見える化し、帰属先を慎重に選ぶ。現在、見えにくい障害の最先端にいるのはマジョリティかもしれません。
ただ、難しいのは、当事者研究は強要するものではないことです。「お前は研究者になれ」と言われて研究者になる人があまりいないように、自分自身で気がついて興味を持った時に取り組みはじめるしかない。だからマジョリティも「現われの場」としての「研究」の場に、もっと身を置けるようになったらいいなと思っています。
おわりに
「ドーナツの場所から生まれるのが当事者研究」
熊谷さんがそう話していたのが印象的だった。
当事者研究は周縁から生まれ続けていく。語りを必要としている周縁者のニーズに応えるだけではなく、制度化によりクロスディサビリティが求められて行く中でも、当事者研究は有効な役割を担っていくだろう。
そして社会の急速な変化によって、自分自身はマジョリティだという感覚を持っていても、身体は変化しなくても、潜在的な障害者として「生きづらさ」を感じる人が増えていく。多くの人が、「見えにくい障害」を抱える人と同じ状況におかれ、自分の「生きづらさ」を言語化する重要性が高まっていく。仮に社会との間に「生きづらさ」を感じなくとも、年を重ねていけば、誰しも障害者にならざるを得ない。
「周縁」はマジョリティーの側に移ってきており、マジョリティーこそが当事者研究の最先端にいるのだ。当事者運動が蓄積してきた語彙と知恵が、誰にとっても心強い武器になっていくだろう。

-----------------------------------------------------------------------------
レポート執筆: 山本ぽてと
1991年沖縄県生まれ。早稲田大学卒業後、株式会社シノドスに入社。退社後、フリーライターとして活動中。
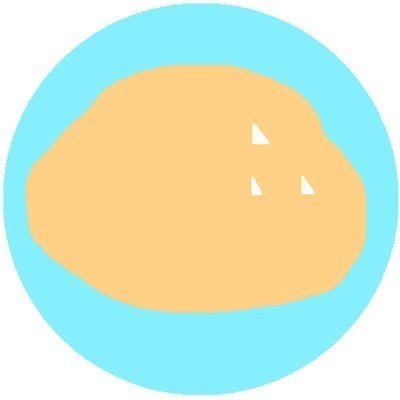
写真撮影: たかはしじゅんいち
1989年より19年間のNY生活より戻り、現在東京を拠点に活動。ポートレイトを中心に、ファッションから職人まで、雑誌、広告、音楽、Webまで分野を問わない。今までトヨタ、YAMAHA, J&J, NHK, reebok, Sony, NISSAINなどの広告撮影。現在Revalue Nippon中田英寿氏の日本の旅に同行撮影中。著名人 - Robert De Niro, Jennifer Lopez, Baby Face, Maxwell, AI, ワダエミ, Verbal, 中村勘三、中村獅童、東方神起、伊勢谷友介など。2009年 newsweek誌が選ぶ世界で尊敬される日本人100人に選ばれる
執筆協力: 雨田泰
同講義のダイジェスト動画はこちら(一般公開)
配信・録画・動画編集: 有限会社スーパーダイス
LITALICO研究所OPEN LABについてもっと知りたい方へ
「LITALICO研究所 OPEN LAB」は、社会的マイノリティに関する「知」の共有と深化を目的とした、未来構想プログラムです。
さまざまな分野で活躍する当事者・専門家・起業家の方々を講師としてお招きし、社会的マイノリティ領域の歴史や課題、解決策、そして未来のビジョンを探求します。2019年7月〜2020年3月まで、毎月一回、全9回のシリーズ講義を実施します。
詳しくはこちらの特設サイトをご覧いただき、気になる講義にぜひご参加ください。
OPEN LABの知は、自分たちが生きる今と未来をより善いものにしていこうと願う、すべての市民のためのものでありたいと思います。
障害や病気のある当事者の方、経済的に困難な方や遠方におられる方も含め、あらゆる人にオープンな知のコミュニティとなるよう、以下のような情報保障や合理的配慮を、すべての講義において実施します。

・講演会場での合理的配慮(ライブ文字起こしや休憩スペースの確保)
・経済的に困難な方へのスカラーシップ制度
・オンライン受講制度
・レポート記事・レポート動画の無料公開
・レポート記事の英文翻訳
次回11月27(水)第5回講義のお知らせ
眼差しだけで音楽を奏で、映像を立ち上がらせる。
やがて失われていく「肉声」を、AIによって記憶・合成し、自分の「こえ」として残していく。そこに実在しないはずのものの「さわり心地」を表現する。
テクノロジーには、人間の身体を拡張し、「コミュニケーション」のあり方そのものを変容させる可能性を秘めています。
今まで想像できなかったようなワクワクする未来をかたちにしている、二人の実践者をお招きします。
ゲストは、武藤将胤さん(WITH ALS 代表理事 / コミュニケーションクリエイター/EYE VDJ)、南澤孝太さん(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD) 教授)です。
チケット販売サイトPeatixよりチケットをお求めください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
